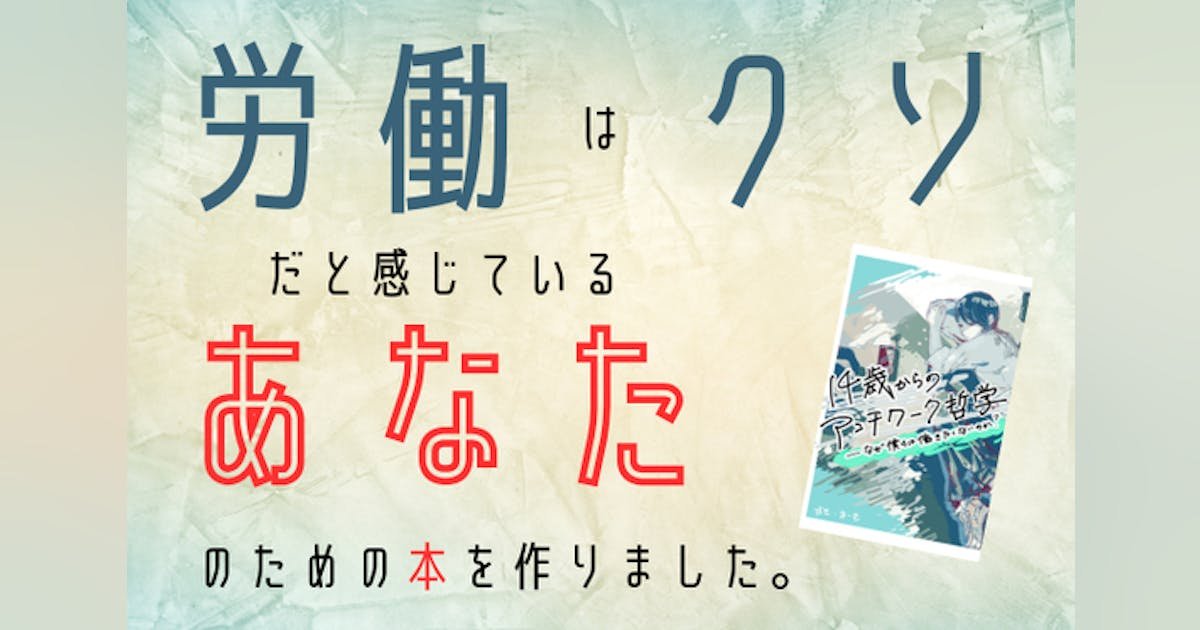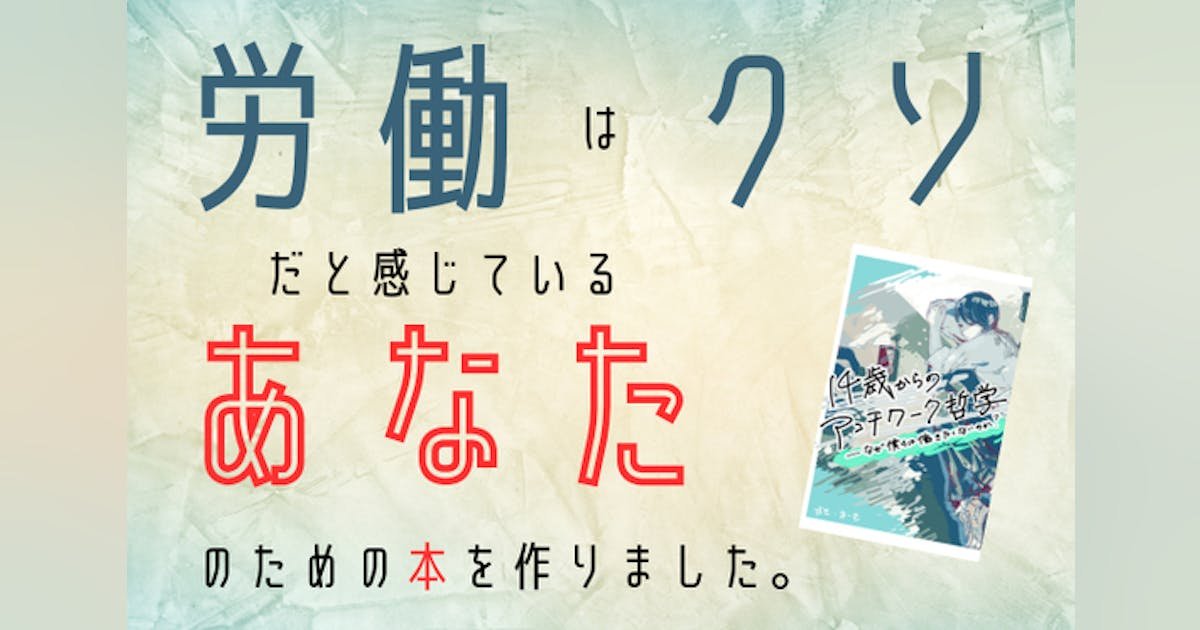クラウドファンディングについて語らせてくれ【出版社をつくろう19】
ふだんは金稼ぎのための営業活動を蔑む僕が、昨日からクラウドファンディングをはじめた。いろんな葛藤があったのだけれど、とりあえずはじめてみたのだ。
詳しい経緯はこのページに書いてある。しかし、これはあくまで「CAMPFIRE」っぽく書いた経緯だ。嘘はない。が、ちょっと殺菌されている気がする。こっちにはもうちょっと本音を書こう。
■なぜクラウドファンディングをやるのか?
理由1.ネット通販&予約販売として
そもそも僕は書店に本を並べることを目的に、出版社を立ち上げることにした。はじめはネットは選択肢から外すつもりだった。
しかし、いまや50人規模になったコミュニティではいろんな意見をいただいた。「興味を持ってくれた人が買えないのでは?」という至極まっとうな意見だ。
僕は工数削減のためにネットを除外しようとしていたが、別によくよく考えれば大した手間にもならないことに気づいた。詰めて貼って送る。以上。メール便ならポストに放り込むだけだ。なら、興味がある人に届かせないのはもったいない、そう思った。
「じゃあ普通にネットショップを開けばいいじゃん?」という話になるのだけれど、それはそれで準備は進めている(BASEで)。

とはいえ、モノができるまではまだ時間がかかる。なんといっても印刷会社すら決まっていないのだし。この段階でプロモーションをかけまくったところで、「なんや、できてないんかいw」となって次の日には忘れ去られるほかない。だからといって、できてからネット上でプロモーションを展開するとなると、それも遅すぎる。
ちょうどいいシステムがクラウドファンディングであった。早すぎる告知から興味を持続してもらうシステムとして、クラウドファンディングという仕組みは使えると思ったのだ。要するに予約販売的な使い方である。
理由2.発送の予行演習として
発送システムを準備し練習する準備期間としてもクラファンは使えると思った。僕はネットショップの経験がない素人である。いきなりネットショップを開いて注文がはいったときに、ばたばたと手間取って発送まで1週間もかかったとしよう。評判はがた落ちである。そのような事態を阻止しようとすれば「こっちの業者で発送したほうがいいかも?」「こうやって梱包したほうがいいかも?」などとじっくり試行錯誤する時間もなく、ただ業務に忙殺される可能性が高い。
ところがクラファンなら発送までタイムラグがあるのが当たり前だし、多少の試行錯誤の猶予が生まれる。予行演習としてクラファンは使えそうだと思ったのだ。
理由3.書店への営業ツールとして
色んな人に話を聞いていると、僕がやろうとする書店への直営業はむずかしく、どこの馬の骨とも知れない男には門戸を開いてくれないのが常らしい。僕はそれをこじ開ける策を多少練ってはいる。
(かなりクラファンの話からは脱線するが)計画はこうだ。まずは書店ではないが書店も扱っているタイプの小売店・雑貨店などに営業をかける。無料で何冊か卸し、ポップをつけて並べてもらう(売れ行きがよければ有料で仕入れてもらう)。多少いぶかしがられる可能性はあるものの、無料で卸すのであればこれくらいのことをしてくれるのではないかと予想している。
まずはこのシチュエーションをつくっていく。店頭に平積みされていることや、実際にお客さんに売れたとなれば、それは1つの実績になる。そして、実績は書店への営業ツールになる。
はじめから書店に無料配布をしてもいい。それもやろうとは思っている。だが僕は書店以外からのアプローチを重視しようと思う。
半分は「書店以外からやったらどうなるか?」という実験精神である。そしてもう半分は書店、出版業界に対する当てこすりである。
日本の出版業界はとにかく儲からない構造になっている。委託販売という仕組みのせいで、売れない本は書店から返品されるし、取次会社を通じた販売は入金が6~8ヵ月先まで待たされる。おまけに入金されてからも返品のリスクがある(つまり赤字伝票を切る必要がある)というわけのわからない仕組みである。
現状「そうでもしなければ誰が買うのかわからない弱小出版社の本を置けない」という理由でこの仕組みは正当化されている。一理なくはない。だが、新興出版社が儲からないという現状は、明らかにおかしい。本という人間が必要とするものをつくっている人たちが儲からないのは経済システムとして不合理なのだ(僕はそもそもその経済システム自体を破壊しようとしているわけだが)。
だが、僕は思った。「お試し無料配布なら、弱小出版社の本にもチャンスを与えることができるんじゃないか」と。そしてそれが成功すれば、現在の書籍流通システムを正当化するロジックを崩壊させることができるのではないかと。だから僕は最初の1000冊くらいは、ぜんぶ無料で小売店に配ろうと思っている。そんなリスクを取るべきではないという反論もあるだろう。だが、正当な手順でやっても8ヵ月も入金を待たされ、返品されて赤字伝票を切るリスクがあるのだ。どうせリスクをとるならまだ無料で配っている方が気持ちがいい。
・・・というわけで、脱線が長くなったが、無料配布キャンペーンと並行して、実績をつくるために始めたのがクラウドファンディングである。要するに「クラウドファンディングで○円を集めた本!」みたいな営業をかけたいのだ。
書店以外からアプローチをはじめるとはいえ、やっぱり多くの人に届けて革命を起こすという目的のためには書店には並べたい。それも大型書店にコーナーを設けて平積みしたい。
なら、無料で5冊というレベルではなく、何十冊と置いてもらわなければならないのだ。そのために「これは売れる本だ」という説得力はいくらあってもありすぎることはない。
理由4.どう伝えればどう届くのか、テストしたかった
CAMPFIREは、重要な個所を除けば、掲載中の修正が可能だ。僕はどんな言葉ならこの本に興味を持ってくれる人が増えるのか、テストしたかった。それは書店のポップ、営業、ネットプロモーションにおいて、必要なデータなのだ。

正直この画像は、クラファンユーザ―に受ける社会貢献感が薄く、弱者男性の妬み嫉み感が強い気もする。なので、「労働はクソだし寝そべって生きようぜ!ウェイ!」みたいな思想と勘違いされるリスクが高そうだ。とはいえ、アンチワーク哲学を一言で表現できるキャッチコピーのようなものが存在するなら、僕はわざわざ本を書いたりしない。つまり、キャッチコピーはこの本を部分的に切り取らざるを得ず、それは常に誤解を生む。問題は「どんな誤解をした人ならこの本を読んでくれるか?」だ。それを確かめるにはテストするしかない。
なので僕はこのトップ画像をちょくちょく変えていこうと思っている。
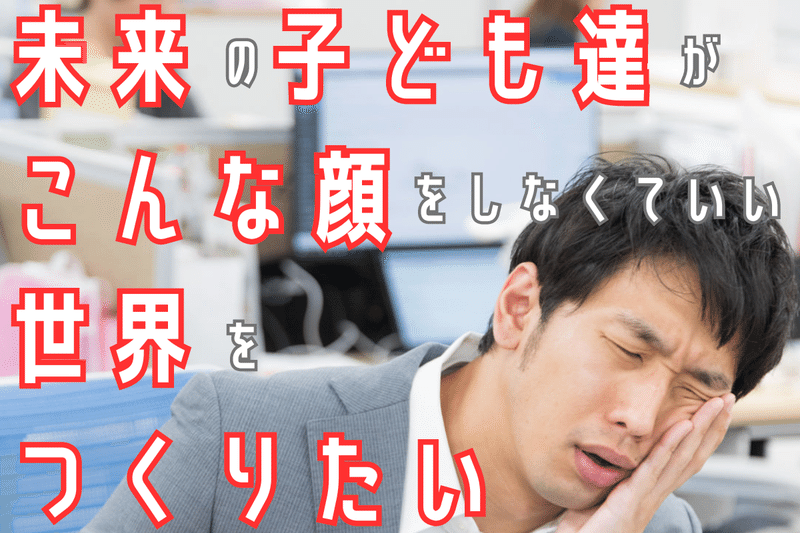
理由5.お金と支援を集めたかった
1000冊を無料で配るくらいのことはできる。だから別にクラファンをしなくてもよかった。でも、支援したいと思ってくれる人がいるのであれば、支援してもらいたかった。このプロジェクトは大きくなれば大きくなるほどいい。巻き込める人は巻き込みたいのだ。
ここに葛藤がないではない。僕は常々指摘しているようにお金は命令のツールであり、それに執着することによる弊害は大きいと考えている。利潤追求動機が社会や環境を破壊してきたことは、斉藤幸平のような人たちが口酸っぱく伝えてきたとおりである(もちろん恩恵もあったわけだが)。
まとも書房は利潤を目的としたプロジェクトではない。しかし、持続させるには一定の利潤が必要である。深淵を覗いていると深淵に覗かれているような気持ちだ。社会に対する革命を志していながらも、ついつい利潤追求の方を目的化してしまう。そんな瞬間がもうすでに何度かあったし、これからも体験することだろう。
だから今ふと思ったのだけれど、会社を立てた後は、会計をフルオープンにしようかと思う。なんかこっそり着服するようなことになるのも、僕は耐えられない。いろいろリスクはあると思う。だが、可能な限りオープンにしよう。そして、僕は何度も書いてきたが、余剰利益が出てしまったら、かかわってくれた人たちを全員呼んで一晩ですべてを使い切る饗宴を開きたい。
イメージはこんな感じである。子どももつれて、楽器できる人は演奏もやって、料理つくりたい人はバーベキューセットを持ち込んで、といった具合だ。
結局それをやるために金儲けしてしまったら本末転倒なわけだが、まぁいい。おそらく僕はこの葛藤とはしばらく付き合い続けなければならない。無理やり正当化するよりも、矛盾の存在を受け入れていこうと思う。
いつの日か、労働なき世界が実現したなら、僕の矛盾はきれいさっぱり解消され、また別の矛盾を抱えて生きていくことになるだろう。人間が完全に理路整然とした存在として生きることは、これまでもこれからも一度もなかった(理路整然と生きているつもりになっている人は大勢いるが)。
矛盾が解消されようがされまいが、僕たちは生きていく。あれもこれも引き受けて、生きていこうと思う。
まとめ
というわけで、そんなこんなでクラファンをはじめたのである。純な動機も不純な動機も入り混じったクラファンである。
1番高いプランでも3万円です! ブレンディのインスタントコーヒー換算で約4285杯分の金額です(当社調べ)! 労働のない世界を未来の子どもたちに残すために、4285杯のコーヒーを我慢して1回ご支援してみてはいかがでしょうか? https://t.co/ZOHTX2t9bJ
— まとも書房/哲学者ホモ・ネーモ (@NEMO_YOKAISM) March 8, 2024
「上手くいかなくてもいい」という気持ちで始めたものの、結構頑張って作り込んだので、上手くいってほしい気持ちが強くなってきた。これがグロウスパッションというやつであり、ブルシット・ジョブを正当化する心理なのだと感じつつも、上手くいってほしいと願ってしまうのだよ。
1回でもサポートしてくれれば「ホモ・ネーモはワシが育てた」って言っていいよ!