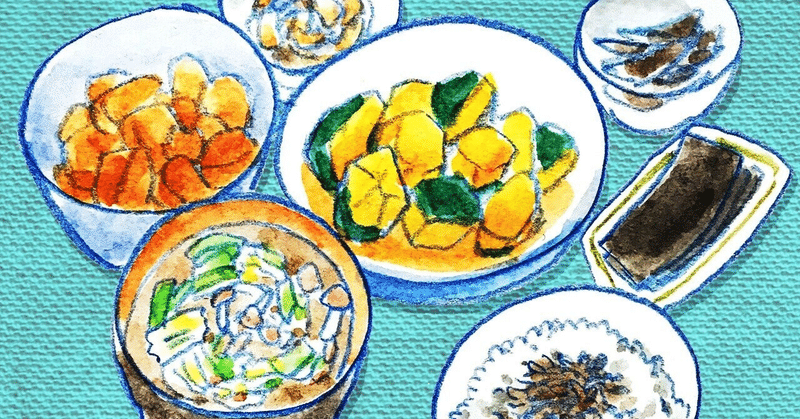
読んだ:「おふくろの味」幻想 誰が郷愁の味を作ったのか
すごかった、好きなジャンルで期待通りの本で最終章は三十時間のRPGのラスボス戦のようなカタルシスと未来への希望を感じるエンディングすらありました。
タイトル通り「おふくろの味」ってなに? というやつ。
そもそも「おふくろ」って言葉、何? 誰が「おふくろ」っていってるの? という言葉の定義から入る一章、ここから引き込まれます。
初出は五百年前で、そのころは武士が上司?の母親に対して「御袋殿」と呼んでいたのがはじまりだとか…… ふくろ! ふくろってそういう!? ゴブリンスレイヤーでいうところの「孕み袋」と同じニュアンスの!?
これ知っちゃうともう「おふくろ」って言葉自体もう使えねえな……となりますね……
全部の章が「うわーーそうなんだおもしろーー」で進みます。
そもそも「おふくろの味」というのが有り難がられるようになったのは高度成長期で田舎から上京してきた男達の美化が始まりだとか(それを補強するような歌謡曲もたくさんあった)、だから「おふくろ」は男らしい呼称として定着した、とか。
人類史において「母親」が料理をするようになったのはここ6、70年程度のことだとか。
それまでは「食事」は家族で作るものであったとか。
高度成長期に人口が都会に集まることにより核家族の第一世代とでもいうものが出現し、しかしその家庭の母親たちは突然新しい生活様式での調理担当にされたし理想の生活として海外ドラマ(奥様は魔女、とか)が流れ込みその憧れをそのまま再現しようとしたり逆に「地方」サイドでは郷土料理を保存する動きとしてふるさとの味戦略が起こったりとか。
けっこう自分の実感としてもわかってくるとこがあるんですよね。うちの母親ってあまり料理が得意でなかったと大人になってから思い返してたんですが、まさにこの本が言うところの「母親から炊事を学ぶこともなく、かつ調理家電がたくさんはいってきた第一世代」の二十代そこそこの人だったわけで。かつ当時はインターネットもないんだから、テレビドラマや料理本、料理番組をよりどころにするしかなかったんだろな。
本書は「おふくろの味」とタイトルにつけられた本がいつ現れ、いつごろから使われなくなっていったのか? というのも重要な軸として参照しています。
で、このへんの新しい生活様式への憧れとしてなりたってきたあれこれに、女性誌、赤文字系雑誌も手を貸してきた流れなどが記されます。
赤文字雑誌、cancamとかですね。二十年前? くらいって、あのへんの雑誌、コスメだファッションだってやりながらも「でも最終目標は専業主婦」だったので、「結婚できるスキル」として「おふくろの味」特集を何度か組んでたんですって。へーーーー。そういや「作ってあげたい彼ごはん」なんて本もありましたね。家事スキルが高くて嫁に適した存在である、というプレゼンに使われてたんですね、おふくろの味っぽい献立。
まだまだ「そうなんだーー」があるんですけど、本の内容を要約して語り直すのは本意ではないんで「うわおもしろ!」と思ったところをかいつまみます。
いろんな戦略や思惑でぐっちゃぐちゃになってしまった「呪い」とも言える「母親が料理すべき」の呪いを打ち破った存在として現れた小林カツ代、そして栗原はるみの存在、この本だと近代の英雄みたいに描写されてます。すごい、カツ代もはるみもすごい……! 坂本龍馬!!(?)
そして最新の概念とも言える土井善晴にも触れてます。ええ、一汁一菜の。
ただこの本で知ったんですが土井先生の父親ってまさに「おふくろの味」というタイトルのヒット作を飛ばしてその幻想の定着を行った人物の一人(もう一人は辻勲)でもあったようで、土井先生だけでなく今活躍しているに世代目家庭料理家の話もラストに詰まってて、なんかもうこれ歴史書じゃん……ってなりました。すげえ……歴史だ…… あと個人的に好きな魚柄仁之助も出てきてちょっとうれしかった。
ところでこの本で「コンフォートフード」という言葉を知りました。「おふくろの味」はまさにこれらしいです。(なお本書でも言及されてますが、最近は「おばあちゃんの味」に変化しているし、まさにそういうテレビ番組もNHKにある)
コンフォート・フード (Comfort food) は、食べた者に郷愁あるいはなにがしかの感傷(幸福感や安心感であったり、特別な価値または意味)を呼び起こす食品を指し[1]、高カロリー、高炭水化物、あるいは調理が簡単といった要素で特徴づけられることもある[2]。食べたときに感じる郷愁は、個人に特有のものである場合もあれば、文化に特有である場合もある[3]。コンフォート・フードは、日本語の「おふくろの味」や「懐かしの味」、「郷土料理」または「家庭料理」、あるいは「ソウルフード」の概念を含む言葉である。
これ、かつては「もうやすやすとは帰れない故郷」、あるいは「理想の母親が作る献立」だったわけですね。
で、コンフォートフードかあ……自分はどういうものかなあ、母親の料理ではないしなあ……と思ってたところに、あ、これか? というのがTwitterで流れてきました。
疲れすぎて何もかもがどうでもよくなったアラサー社畜の夜ご飯はこれです(MOWの抹茶味) pic.twitter.com/XrNAZPu6CW
— オタ美 (@debu_tarou) June 8, 2023
これ。小学生時代に作ったお菓子にだいたい入ってた、カラースプレー、アラザン、アンゼリカ。このへんが私にとっての「懐かしくて生育時代を感じる安心する味」かもしれない。やはりもう一度読み返すか、わかったさんシリーズを……
あと、これ……

「あのころのマック」って、これ、30代40代にとっては肉じゃがなんかよりよっぽど「あのころ」に浸れる、いわゆる「おふくろの味」とかつて言われていたものの位置にあるものなのでは……?
というかマックにはなんだかたまに行きたくなってしまうけどモスにはそういう感覚にはならないって、まさにそういう、高度成長期に上京してきた男性が「おふくろの味」を売りにしていた居酒屋やら小料理屋やらに通ってしまっていたのと、同じものなのでは……
本書では「トポフィリア」という概念も説明されます。場所愛、とでも言う感覚。
「場所」に愛着を持つことができる、というのが人類の大きな特徴の一つだそうです。この「場所」って緯度経度の示す位置ではなく、空間とか、概念とか、そういうかんじです。「国家」とか「学校」とか。そういう空間的な連帯感で、脳では150人が限界だった「仲間意識」を数千、数万に広げることに成功した、という。
「おふくろの味」は、このトポフィリアでいうところの「理想の故郷」「理想の家庭」の中で供されてる食事としての意味合いがある、みたいなことが綴られていました。それを食べることでそこにいたことを思い出す、いるような気分になる。
で、ぴんときましたね。
それってオタクが作中再現レシピ作ったりコラボカフェ行ったりするやつじゃん! て。
なるほど「おふくろの味」は「理想の故郷コラボカフェ」のメニュー! なるほどなるほどね!!
雑な結論はともかくとして、本書はすごく楽しいドキュメンタリーでした。興味持ったらぜひよんでみてほしいです、全然省略したけどおもしろい資料やエピソードがたくさんつまってるので。
サポートいただいたお金は本代になります! たのしい本いっぱいよむぞ
