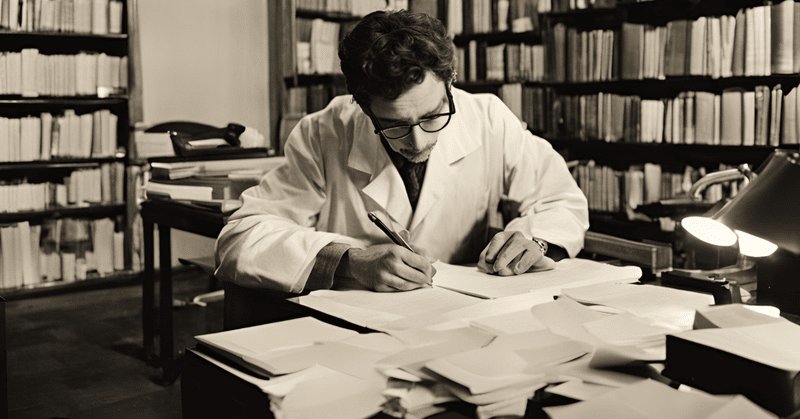
読書㉑ 知識をいかに保存し、わかりやすく伝えるか
先日、私は「記憶」に関する事業を行うスタートアップ経営者と話す機会がありました。
最初の印象は、暗記が得意になるくらいのものなのかと思っていたものの、ビジネスパーソンが取引先の人の顔と名前を覚えることができないという課題に対するtoBのソリューションや、年長者が記憶力や認知力が低下してしまうということに対する人類未踏領域のソリューションなど、かなりの可能性を秘めているのではないかと考えが変わりました。
自分を省みると、私は記憶から知識を取り出し、その知識を情報にして、伝えることで生活の糧を得ているわけです。
記憶そのものの精度の向上が進んでいくと、情報化し、わかりやすく伝えることが上手な人の価値がより高まるのではないかと感じました。
そこで、今回は「わかりやすく伝える」能力を高めることを目的として、私たちはどう知識を保存し、活用するべきなのかについて、参考になった本を元に考えをまとめます。
わかりやすさとは
誰かから説明を聞いている場面で、「ああそうだったんだ」と思うことがあります。このような状態はどんな要素によって生み出されるのでしょうか。それは、自分がわかり、相手がわかるという、以下要素の時系列をたどります。
「わかる」こと
自分の頭の中に以前から存在していた断片的な知識がひとつにつながったとき。
断片的な知識が、あるルールのもとにきれいに並べられたとき。
断片的な知識が、いくつかのグループに分けられたとき。
こんなときが、「わかる」瞬間です。
つまり、つながることが、わかるということです。
相手に「わかった」と思わせること
相手に話がつながったという思いをさせることができれば、「わかりやすい説明を受けた」と評価されます。
それは「知識」そのものへの評価ではなく、あなたの実力に対しての評価なのです。
つまり、あなたが持つ断片的な知識をつなげ、そのつながりを説明することで相手が持つ断片的な知識もまたつなげたとき、相手は「わかった」と思うのです。
わかりやすく伝えるためには予習が必要である
学校の勉強において、学生は授業で教わる内容がわかるように予習をします。
同様に、伝えることためにも予習が必要です。
この予習の精度こそ、「わかりやすく伝える能力」に直結します。
予習は大きく2本の柱があります。
自分は何がわからないかを知る
ひとつめは、「自分が何がわからないのかを知る」ことです。
人に何か伝えるするとき、無駄なことを言ったり、動揺したりするのは、実は「わからないから」なのです。
「自分が何がわからないのか」に気がつかないまま説明してしまうことは意外と多いものです。
それは、断片的な知識を持っているだけの時点で、自分は「わかっている」と過信してしまうからです。
「わからないことをわかる」方法は、実際に誰かに説明してみることです。
声に出して話してみることで、自分に何が足りないかわかってくるのです。
自分はまだわかっていないという謙虚な気持ちを持てる人ほど、わかりやすく伝えられる条件を備えているのです。
フロー情報とストック情報を使い分ける
もうひとつの柱は、フロー情報とストック情報を使い分けることです。これは、どう知識を保存するべきなのかという観点に通じると思っています。
私たちは普段、フローの情報を追っています。フローとは文字通り流れていくものです。ニュースメディアや会話のなかで日々新たに伝えられ、すぐに消えていく情報です。
一方、ストックとは本や議事録などの形で保存されているものです。
毎日の生活にはフローの情報があふれています。わかりやすく説明できるようになるためには、ただ情報を追いかけるだけでなく、「この情報について、自分が理解できない点」を常に見つけるようにするのです。
ここでまた「自分は何がわからないのか」を自問自答するのです。
フロー情報で自分がわからない部分を見つけ、ストック情報で勉強する。これを繰り返していくうちに、自分の記憶のなかのストック情報が厚く重なっていき、つながりやすく「わかりやすい説明」の素となるのです。
まとめ
これまでは、「物知り」な人の価値が高かったわけですが、これからは「説明が上手」な人の価値がより高まると思っています。
それは人々の「記憶力」、すなわち「保有する知識の量」の差が、どんどん縮まっていくからです。
だからこそ、記憶から知識を取り出して、どのような使い方をするのかについて、これまで以上に勉強をするべきなのです。
この文章もまだわかりにくい点が多いと思います。
「わかりやすさ」とは追いかけ続けるものですね。
今回の本
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
