
コロナ渦における〝自由〟な音楽のゆくえ
本稿は慶應義塾大学アート・センター主催のシンポジウム『文化と集団のアーバン・リサーチ──いま、都市のコミュニティはどうなっているか?』での自分の発表「コロナ渦における〝自由〟な音楽のゆくえ」を事後的にまとめたものです。
シンポジウム全体の目的や趣旨に関しては、事後的にまとめられた冊子の巻頭言を参考にして頂きたいです。
新型コロナウイルスによって対面での交流やイベントの実施に生じた制限は、生活や仕事のみならず、文化的実践の領域にも及んでいる。こうした状況下でとりわけ大きな打撃を受けているのは、趣味の共同体や小規模なシーンだ。短期的には成果が見えづらく、基盤が脆弱で維持が難しい。コロナ禍によって、活動に制限が出てしまうだけでなく、そうした苦境自体が可視化されづらくなってしまった。たとえオンラインで問題なく活動できるように見えても、シーンを支える上で不可欠な熱量や献身をうまく調達できなくなり、本来ならばもっと伸びていたはずの新興ジャンルが停滞してしまうケースも見られた。
コロナ禍でさらに勢いをつけることになったサブスクリプションや各種配信サービスなどの「プラットフォーム」は、そうした停滞を打開しコンテンツを大きく伸長させる可能性を秘めていると同時に、ニーズへの過剰な同一化やバズコンテンツによる「勝者総取り」を促し、シーンを硬直化させてしまう側面もある。
だからこそ、小さなシーンをプラットフォームに回収させることなくどのように維持・発展させていけばよいのかという問いは、コロナ以降なおさら切実なテーマになっている。結局、そうした熱量に支えられた草の根の動きからしか、文化は生まれないように思うからだ。有事の際に、短期的な解が求められるのはある程度仕方のないことかもしれないが、未来につながる別の選択肢をなんとか確保することも、また必要なことなのではないか。
そんな問題意識から、今回はさまざまな分野にまたがる6名の登壇者を呼び、コロナ禍以降の実践やリサーチについて話を伺った。今足りていないのは、個々の実践から得られた学びや知見を共有し、より公共的で普遍的な文脈から語り直すような時間だ。本イベントの目的は、その端緒をひらくことにある。
当日の様子は下記の動画で確認できます。自分の発表以外にも他の登壇者の方々とのディスカッションもありますので、お時間ある方は是非。
読むのが面倒な人は、僕らの定期的に更新してるPodcast「ポコラヂ」でも同じ内容について喋っていますので、そちらをどうぞ。
自分が登壇したのはセッション2の「リモート・アーバン・リサーチ──今、リアルの空気を捉えるには」です。概要は以下。
コロナ禍で「現場」に足を運べなくなったことで、それぞれの国や地域におけるリアリティの把握は著しく困難になってしまっている。しかし一方で、各種配信サービスやSNSなどのプラットフォームを通じて、他国発のコンテンツにふれる機会はむしろ増加している。直接的な往来や交流が減ったままプラットフォーム上の接点だけが増えていくことで、他国のシーンはおろか、自国のリアリティさえも掴みがたくなりつつある。コロナ禍の閉塞感とも切り離しがたいその見通しの悪さを解消するには、大味な見立てではなく個別具体的なケーススタディの共有が必要ではないか。本セッションでは、コロナ禍における各国のカルチャーの現状や、他国の現場のリアリティを探る方法について議論する。韓国についてはK -POPグループのアートディレクションも手掛けるデザイナーのErinam氏、中国については『中国新世代 チャイナ・ニュージェネレーション』の著者・小山ひとみ氏、日本についてはZ世代の支持も厚いラッパー・Tohjiのマネジメントを手掛けるCANTEEN代表・遠山啓一氏に発表してもらう。3名の語る事例を通じて、現代のユースカルチャーを規定するプラットフォームの重要性と、それに対する各国ごとの態度の違いを立体的に検討する。
コロナ渦における『自由』な音楽のゆくえ
TohjiやLoota、Ralphなどラッパーを中心に十数組のアーティストをマネジメントする会社・CANTEENを経営している遠山です。僕はライターやリサーチャーではないので、少し他のお二方とは角度の違う話になるかもしれません。とはいえ、戦略を立てる上でシーンの俯瞰は必須ですし、扱っているアーティストの傾向もあって国外の動向も把握するようにしているので、問題意識は共通しているかなと思います。
「こんな風に聴いて欲しい」が伝わらなくなった
今回のキーワードは、ざっくり言うと「自由と身体化」です。音楽業界の外から見ていても中にいても1番大きい問題というのは、現場がなくなったとかライブができないということだと思うんですけれども、現場がなくなった意味とは何なんだろうという問いを、解像度を上げて掘り下げられればと思います。
僕たちのチームでは、「音楽が身体化される場所」を「パーティ(=現場)」として定義しています。いわゆるイベントとしてのパーティだけでなく、たとえば仲間とのドライブで音楽をかけてみんなで大歌唱する、みたいなものも「パーティ」に含みます。飲み会の後にカラオケに行って「この曲あったよね」とか言いながらみんなで歌うのも「パーティ」ですし、普通にクラブで踊るのも「パーティ」、いわゆるショーケースでハンズアップするのも「パーティ」です。
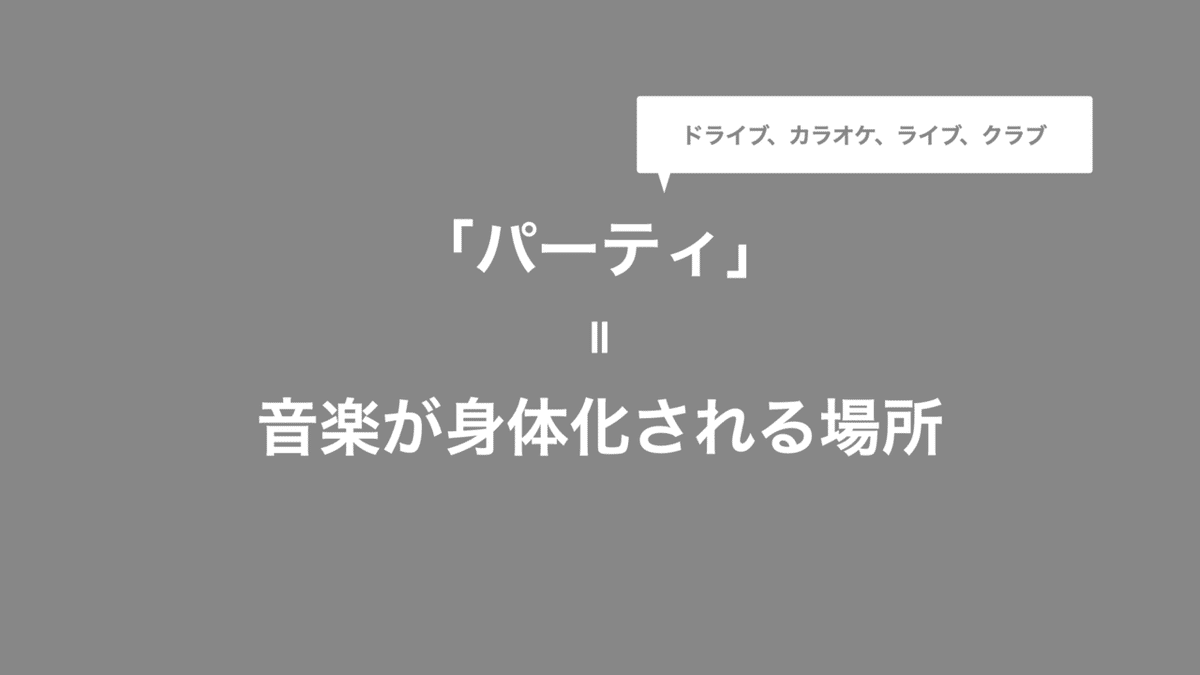

そのことに自覚的でないと、音楽はただの音源データにすぎないわけです。今回のトークテーマとして、「コロナによって現場の空気が掴めなくなった」という話がありましたが、コロナ渦においてはそもそもこうしたパーティの機会が奪われてしまっている。それに対してどんな対処をしてきたかを、事例をもとに話していきたいなと思います。
具体的に言えば、現場がないというのは、リスナーとコミュニケーションがとれないということだと思うんですね。もちろんオンラインでできるコミュニケーションもあるけど、身体性を重視するタイプの音楽については、オンラインだと体感的には2割ぐらいに強度が薄まる印象です。
そもそも音楽の作られ方をとってみても、最終的にはボーカルブースで録音したり、家でひとりで機材を使って作曲したりするだけかもしれないけど、そこに至るまでの過程では友達との時間だったり、身体が生み出すノリ、グルーヴみたいなのがあったりします。何かしらの身体的な経験や情動があって、それが音楽へと変わっていく。そのように作られた音楽は、聴かれるタイミングでも身体性を伴うと思うんですね。逆に言うと、それがない場合は本当にただ流行として消費されていってしまう。「誰が次に来るか?」にばかり関心が集まり、そのサイクルはかなり速くなっている。これは日本に限らず、アメリカでもどこでもそうだと思います。

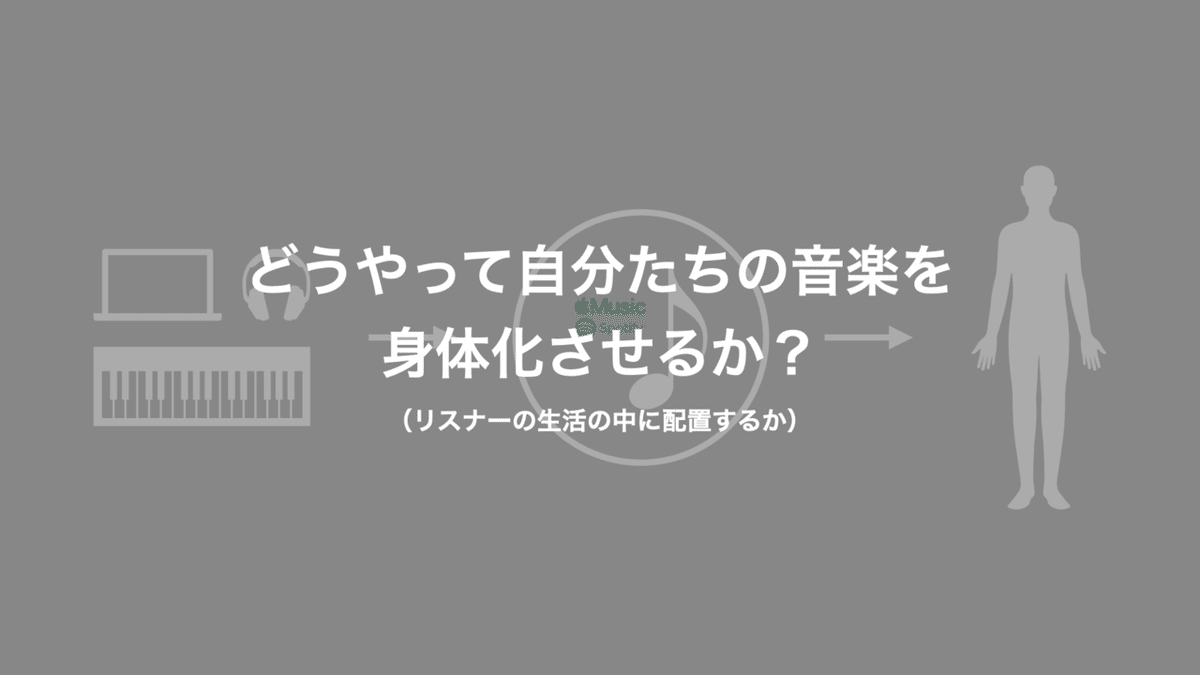
コンテンツをリスナーの生活の中にどんな風に配置するかを考えないと、ずっと聴かれる音楽は作れないし、良い付き合い方をしてもらえない。ここがコロナでだいぶ難化した部分だと思っています。たとえば以前なら、ライブを行って音楽を「経験」してもらったり、ライブ後にファンと一緒にフロアで踊ったりして、「自分たちがどんな風に音楽を聴いて欲しいか」を態度で表現することができたと思います。もちろんコロナ禍でもMVやライブ配信等の手段はあるけど、やっぱりコミュニケーションとしての質は異なります。
プラットフォーム上でいかに作品を身体化するか

具体的に、自分たちがどういう方法をとったかをシェアします。まずひとつめですが、TikTokで「#gokuvibeschallenge」というハッシュタグ企画をやりました。先ほどクラブでのノリ・バイブスの共有の話をしましたが、今はライブができないので、新曲を出してもその曲で実際に踊っている様子を再帰化できない。曲をしっかり身体化させるにはその曲で踊っている人たちのコミュニティを可視化することが大事なので、面白い動きとかを見せやすいTikTokを使って、ファンの人たちにも踊って投稿してもらえるようにしました。現場の代わりにプラットフォーム上で身体を通じたコミュニケーションができないかということでやってみたものです。

あとはVlogを出しています。これは作品が生まれる背景や、環境、生活を、同じ場に居ない人に届けるためのコンテンツだと定義しています。自分たちがどういうものを好んでいて、何を思って作品を作っているのかについて、言葉というよりも生活の雰囲気を見せることで伝えたいという意図です。自然体で出しているように見えますが、実際は精密に作り込んでいます。

あと今回はスライドに入れていませんが、Tohjiが元ハウスメイトとやってる「シャイニングラジオ」というPodcastなんかもそうですが、コアなファンに向けたコンテンツでは、作品に至るまでのプロセスや込めた思いを裏話的に直接話すのではなく、とにかく生活や好みを見せて共有することが大事だと思っています。初見のファンとコアなファンとでそれぞれ受け取って欲しい情報がが全く違う、現場で細かいニュアンスを届けられない分、どのメディアで誰に何を届けるかということに一層敏感にならないとうまくコミュニケーションが機能しないという実感があります。
自由のための音楽をつくるには

自分たちの実践の話が続いたので、参考資料を紹介しつつ補助線を引きたいと思います。福井一喜『自由の地域差:ネット社会の自由と束縛の地理学』という本が、今の状況を捉える上で大変参考になりました。ざっくりと整理すると、インターネットやSNSが出てきて情報流通が柔軟になると、人々の間で「消極的自由」が生じます。要するに、どこに住んでいても地域性に縛られずにいろんなコンテンツや情報に触れられるということですね。ただ、そうなると代わりに「広域な空間スケールにおける束縛」が生じます。

具体的には旅館の事例などが紹介されていて、要するに旅行系ポータルサイト活用によって既存の旅館組合からは自由になれるものの、今度はポータルサイトのアルゴリズムに従わざるを得ないという別の「束縛」が生じるということです。競争の側も地域に縛られなくなるので、下手をするともっと過酷な競争や不自由が生じてしまうかもしれないと。そこから次の段階に行くには、地域という制約を再編成することで「積極的自由」を獲得しなければならない。旅館組合を若返らせるとか、地域ならではの体験価値を見つけるとかそういったことです。

この積極的自由の段階に至る契機であるローカルな束縛には、身体性をともなった現場の交流が不可欠という内容なんですが、その機会がこのコロナ禍で奪われてしまったと考えています。その結果、「広域な空間スケールにおける束縛」を前提とした企画やコンテンツしか生まれなくなりつつある、と整理することができます。特定のプラットフォームのレコメンドで流れてきやすい長さや曲調、アテンションを稼ぎやすいフックや歌詞など、その特徴はいくつか挙げられます。受け手が「エモい」と呟きたくなるような質感だったり、TikTok向けの手や上半身の動きを楽しめるような振り付けが流行したり。
これを好みの問題に還元することもできますが、それはアーティストに寄り添う立場の人間としては無責任だと考えています。それは最初の方で述べたように、やはり音楽を消費ではなく生活の中で体験してもらったり、リスナーが自分の体験や価値観とその作品を紐付けたりすることで、初めて音楽やコンテンツは価値を生み出すと思うからです。そうした身体的な、ローカルな束縛を再編成することでしか、本質的には自由になれない。つまりこれはコンテンツ産業の問題という以上に、今生きている人々の自由をめぐる問題なんだと思うんですね。

先ほどの本の孫引きになってしまうんですが、グレイ『自由論の系譜』に書かれている次の一文にはその意味でとても惹かれました。「ある人間が自由であるのは、かれが自らの生に責任を負い、自らの環境の主人であり、そして自らなそうと決めたことをなすことができる時だけである」。現実を前に踏ん張っている人間を後押ししてくれるようなカルチャーがやっぱり僕は好きですし、この状況下で本来求められるカルチャーもそういうものなんじゃないかと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
