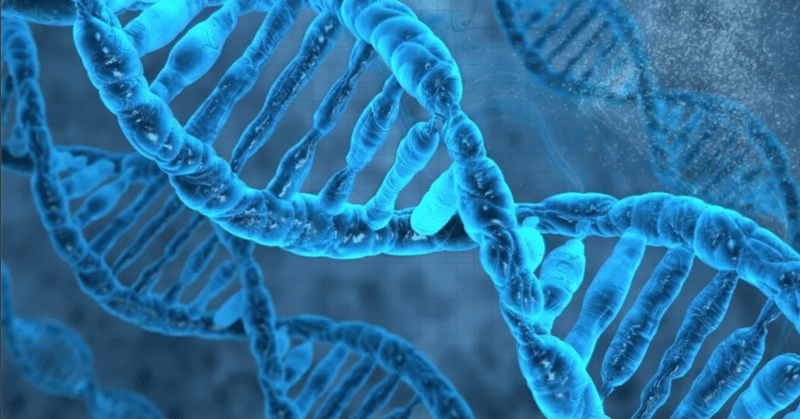
若返り(Rejuvenation)
主な登場人物
荒井美智子(七十一歳)
資産家で、遺伝子操作で若返る。見た目は二十代前半。しかし、近所で美智子を最近見たことがないと噂になり、警官が美智子の家に来る。
松木雄二(四十三歳)
警視庁西田園調布警察署捜査一課主任。優秀な警察官であるが、どこか間の抜けたところも持ち合わせている。
西沢刑事
警視庁西田園調布警察署捜査一課刑事。松木の部下で、松木を先輩と呼んでいる。
門脇正之(五十七歳)
医師で帝産医科大学の教授。彼の遺伝子操作で荒井美智子を若返らす事に成功するが、アメリカの大学に招聘された後に失踪したため美智子の無罪を証明する事ができない。
日下部雄太(三十一歳)
警視庁西田園調布警察署鑑識課員。
解 説
遺伝子治療で若返ったのはいいが、若返る前の自分が失踪したと思われ、殺人の疑惑を掛けられ殺人立件の登竜門となっている死体遺棄容疑で逮捕されてしまう。彼女の無実を証明できるのは、遺伝子治療を施した医師のみ。
1.発端(おばちゃんの思い込みは、恐ろしい)
おばちゃんは、不思議な生き物である。が、我々警察にとって、貴重な存在でもある。何故なら、 おばちゃんの井戸端会議で話題にのぼる近所の噂話がたまにではあるが、極たまにではあるが、事件を解決に導くきっかけや事件を発覚させることがあるからだ。
今回の奇っ怪千万な事件を最初に察知したのは、他ならぬおばちゃんの勘ぐりからであった。その日は、九月の中旬初秋の晴れ渡った休日であった。空は晴れ渡っており秋晴れが相応しい日だった。
「おまわりさん」
西田園調布警察署管内の田園公園前交番に、一人のおばちゃん、失礼、五十代とおぼしき小柄でふくよかなご婦人が現れた。応対に出た巡査の近藤良樹は、顔見知りの女性に嫌な予感を感じた。
「なんだ、君塚さん。どうしました?」
近藤巡査は、平静を装い尋ねた。が、今日は、何時間付き合わなければならないのか…? と、覚悟した。まだ午前の十時過ぎだ。また長い一日になりそうだ。
「それが、おかしいの」
ほら来た。主語がない。何がおかしいのか、判然としない漠然とした話の始まりだ。近藤は、事件がない限り仕方なく付き合うしかない。
「荒井のおばあちゃん、知ってるでしょ」
「豪邸に一人住まいの、上品な方ですね」
近藤は、念のために尋ねた。
「そうなの。半月ほど前から見かけないのよね」
「そうですか…。でもあまり外出はしないようですし、長期の旅行に良く行かれるとか。今回も旅行では?」
近藤は、話を合わす。さりげな~く、荒井が良く旅行に行くということを君塚に印象付けようとした。
「でも、出掛ける所を見てないし…」
やっぱり、失敗した・・・。あんたは、荒井のおばあちゃんのストーカーか! と、突っ込みを入れたいのをグッと我慢した。
「それに、半月ぐらい前に、若い、そうね、二十歳そこそこのけっこう美人が、多くの荷物を持って、荒井さんのお屋敷に入って行くところを見たのよ」
やはり、ストーカーか? 少なくとも人のプライバシーにずかずかと入っていく典型的なおばちゃんだ。と、思いながらも、「親戚の誰かが、留守番でもしているのではないですか?」と近藤は、言ってみた。
「そう言えば、前に見せてもらった若い頃の写真に似ている気もするけど…」
「でしょ。でしょ。気の回しすぎですよ」
近藤は、すかさず結論に持っていこうとした。
「でも、荷物は、スーツケースじゃなくて、海外有名ブランドの袋や箱だったの。まるで、荒井さんのお金を盗んで使っているみたいに…」
君塚は、それでも食い下がった。さすが伊達におばちゃんをやっている訳ではない。手強い! 本題を話し始めた。やっと本題にたどり着いたのだ。今までの会話は、いったい何だったのだろうか?
それでも君塚は、勝手に犯罪に巻き込まれていると決めつけているようだ。が、警察に話しても、まともに取り合ってはくれないことも知っている。それに、違った場合の事を考えると、問題になる。世間からバッシングを受ける可能性すらあるのだ。自信が揺らぐから、自分を巻き込むつもりのようだ。しかし、おばちゃん独特の感と興味本意は、思い込みに昇華して結果揺るぎない自信となるのだ。
「分かりました。一回様子を見に行きます」
行けばいいんだろ。行けば…。という言葉を、近藤はグッとこらえた。「でも、私も暇じゃないから…」
付いて来る積もりだな…。近藤の一瞬の顔色を察知したのか君塚は、「だって、私にも責任せあるし、気になるじゃない」と、今度は、言い訳と正当性を主張した。おばちゃんには敵わない。
「いつなら、ご都合がいいでしょうか?」
「そうね。今日なら、二時から空いているから…。善は急げと言うでしょ」
君塚は、少し考える振りをした。
最初から、今日連れていくつもりだったんだな! 近藤は、頭のなかで白旗を掲げた。おばちゃんには、勝てっこない!!!
「じゃあ、午後二時に来るから、空けておいて」
君塚は言い残すと、近藤の返事を待たずに帰っていった。
その日の午後二時半過ぎに、君塚は約束より遅れてやってきた。
「娘もとっくに成人しているのに、私が昼ごはん作って大変だったのよ。隣の奥さんも来るし、忙しかったし~」
約束の時間に、来れるはずはない! と、言いたげだ。おばちゃんは、謝罪はしない。遅れた言い訳を、正当化する。
近藤は、交番の同僚の同情を全身に受けて君塚に従うように荒井の豪邸に歩いて向かった。歩いて数分の距離である。それにしても、豪邸だらけだ。
近藤は、いつも思う。荒井邸に行くまでの道のりは、さすが田園調布だけのことはある。しかし君塚は話し続けていた。荒井美智子のことではなく、自分の愚痴である。近藤は、仕方なしに相槌を打つしかない。数分すると、荒井の豪邸に着いた。田園調布でも、一際立派な豪邸だ。
応対に出たのは、君塚が言っていたように二十歳そこそこの若い女性だった。女性は、スラットした美人だ。女性は君塚の顔を見ると少し驚いた顔になった後に、一瞬君塚を睨みつけた。が、厄介な事になりそうな困惑した顔のまま、すぐさま近藤に顔を向けなおして、「何かあったのですか?」と、心細いようなおどおどした声で尋ねた。
それも、そうだろう。留守番に来ているはずの若い女性の元に、いきなり警官が訪れたのだ。もっとも、警官が事前に電話してくる事の方が稀である。事件があったのか、心配なのだろう。
「こちらは君塚さんといって、ご近所の方です」
近藤は君塚に不審な顔を向けたと思って、仕方なく紹介した。のこのこ付いてくるから、不審に思われたじゃないか! と、思ったが、のこのこ付いてきたのは、自分の方であることに彼は気が付いていない。
「荒井美智子さんのお宅ですよね」
近藤は、若い女性に尋ねた。しかし、美しい。こんな美しい女性が犯罪を犯す筈はない。と、思ったが、思い込み以外の何物でもないことに気づいていない。
「はい。そうですが…」
女性は、困惑気味に答えた。
「このところ美智子さんを見かけないとある女性から申し出があったので、確認のため来ただけです」
近藤の説明に女性は、一瞬だけ君塚を睨みつけた。やはり、あなたなのね。君塚が、そのある女性だと誰でも理解できるような近藤の説明だ。
「伯母なら、海外旅行に行ってますよ。一ヶ月の予定なので、十月の初めごろには帰ってきます。留守番がてら遊びに来ているのです。伯母ったら、お手伝いさんをそのままお願いするからお嬢様気分が味わえるからと言ったのです。でも、自由を満喫したいので断りました。こんな豪邸で、ゆったりと暮らせるのですから」
女性は、近藤に向かって告げた。
「姪御さんですか」
近藤は納得したがちらっと君塚を見ると、彼女は疑りぶかい顔のようだ。「念のために、お名前をお聞かせいただけますか?」と、尋ねていた。
「はあ…」
女性は一瞬不審な顔になりながらも、「高橋・・・、高橋優香と申します。母の姉が、荒井美智子です」と、答えた。
「そうですよね。よく海外に行かれるそうですから…」
近藤は、納得した。が、君塚は、疑りぶかい顔をしていた。それでも、何も発言しなかった。納得してくれたのだろう。「お忙しいところ、失礼しました」近藤は、女性、いや高橋優香に頭を下げると君塚を伴って辞去した。
「どうです? 納得してくれましたよね」
荒井美智子の屋敷から少し離れると、近藤は君塚に尋ねた。
「やはり、おかしいわね」
君塚は、納得していない模様。
「何故です?」
「だって、あの人私を見て驚いたような顔をしたのよ」
そりゃ驚くでしょ。警官と一緒に知らない女性が、いや、おばちゃんが一緒にいるんですから…。という言葉を近藤は呑みこんで、「だから、何だと言うのですか?」と、分らない振りをした。
「あれは、初対面で私を見た顔じゃないわね。前から知っていたような…」
おばちゃんの推理力は凄い! いや、思い込みは脱帽に値する。「きっと、私のことも事前に調べたに違いないわ。きっと、美智子さんは、あの女に殺されてどこかに埋められたのよ。不審に思った私は、きっと口封じされるんだ」と、言ってから泣き崩れた。が、きっとが多い。
やれやれ、ミステリーの見過ぎか? 思い込みもここまで来ると尊敬に値する。近藤は、「考えすぎですよ」と、言った。
「私が、殺されてからでは遅いのよ」
君塚は、近藤に食って掛かった。泣き崩れた同一人物とは思えない豹変振りだ。
「そんな…」
近藤は、辺りに人がいない事でほっとした。誰かいれば、誤解されかねない。
「そうだ。あんたも、警察の端くれでしょ。刑事に知り合いはいるわよね」
君塚は、今度は詰問口調で近藤を睨みつけた。
「はあ、もちろんいますが…」
近藤は、困惑した。しかし警察の端くれとは、失礼な! と、言いたいところをぐっとこらえて、「どうしたいんですか?」と、尋ねるしかなかった。
「事実を伝えて、捜査してもらって」
君塚は、命令口調だ。
「松木さん、お忙しいところすいません」
近藤は、交番に戻るとすぐに知り合いの警視庁西田園調布警察署捜査一課主任である松木雄二警部補に連絡をした。当然、君塚の監視の下での連絡である。君塚は、近藤を睨みつけていた。
「一応、おかしなことがありまして、お知らせした方が言いかと…」
近藤は、君塚に促されて、掻い摘んで今までの経緯を話し始めた。
「分った。今日は事件もないから、今から行く」
電話で経緯を知った松木は、早速行く事にした。
「ちょっと、出かけてきます」
松木は原田係長に告げると、そのまま出て行こうとした。
「松木、どこへ行く?」
原田は、またか…、と思ったが、一応尋ねる事にした。
「ちょっと気になることがあるので、念のため確認しに行くだけです」
松木の答えに原田は、「のめり込むなよ」と、釘をさした。が、無駄な事も分っていた。
2.疑惑(おばちゃんの思い込みと刑事の思い込みが一致する?)
松木は、歩いて十分ほどして交番にやってきた。
「松木刑事」
近藤は、地獄で仏のような顔で松木を出迎えた。
「よかった。刑事さんですよね」
君塚は、ほっとした顔になった。が、「私の命が、助けてください」と、必死な形相になった。まともな日本語になっていないのも、おばちゃんの特徴である。『私の命を、救ってください』もしくは、『私を、助けてください』百歩譲っても、『私の命を、助けてください』だろうが…。思い込みが、激しいとはいえ、本人にとっては生きるか死ぬかの瀬戸際である。言葉もおかしくなるのかもしれない。
「それは、只事じゃないですね」
松木は、呟くように言ってから、「順を追って、教えてくれますか」と、君塚に向かって冷静な口調になった。
君塚の、取り留めのない、掴みどころのない、主語のない話が始まった。要約すると、荒井美智子を半月ほど見かけない。若い女性が、姪だと称して屋敷に住みついている。今日訪れたら、初対面なのに自分を見て驚いた顔をした。荒井美智子はその女に殺されて、若い女が財産を独り占めしているに違いない。それを知った自分が、命を狙われているという事だった。誰が考えても、根拠のない思い込みだけの話である。それを、三十分もかけて話したのだ。
「話は、良く分りました」
松木は一通り話を聞き終わると、「では、お手伝いさんに事情を聞く事にしましょう。でも、お手伝いさんの住所は分らないでしょうね」と、君塚に尋ねた。
「いえ、知っています」
君塚の答えに近藤は、知っているんかい!? と、呆れた。
「だって、買い物などでよく顔を合わせているうちに知り合いになったの」
流石、おばちゃんである。近藤は、開いた口が塞がらない。「でも、何でお手伝いさんの所へ行くの?」と、興味を持ったようだ。
「何、本人は不在で姪と名乗る若い女性は、さっき事情を聞いたではないですか。あと、何か知っているとすれば、お手伝いさんだけになるからです」
松木の話は、理路整然としていた。一応? 刑事だけのことはある。松木は近藤だけを伴って、君塚に教えてもらった住所に向かった。刑事の感から、君塚を連れて行くと面倒になると考えたからだ。
「松木、何調べてる?」
上司の原田係長は、夕方戻ってきた松木の態度におかしなものを感じて尋ねた。松木の独断専行は、今に始まった事ではない。「また、事件を作りたいのか!?」と詰問する。松木は少しの疑惑があれば、事件だと署を巻き込んで大騒ぎする。結果大山鳴動して鼠一匹…? になる。一度だけ、事件を早めに察知して解決に導いた事がある。が、一度だけ…。一度だけの成功体験が、独断専行の正当性なのだ。
松木は、「そんなあ…、おかしな事が起きているようなんです」と、原田に訴えた。
原田は、一応話だけは聞くことにした。後がわずらわしいからだ。松木は、根に持つタイプだ。万が一、万にひとつ。あるとは思えないが、本当の事件ならまずいからでもある。他の署員は、興味を示さない。またか…、だからだ。興味を示す一握りの署員は、今度はどんなこじつけや思い込みなのかに興味を示すに過ぎない。良く言えば孤高、一般的には浮いている。悪く言えば、役立たず! になる。
会議室で松木は、今までのいきさつをかいつまんで報告した。
原田は腕組みをして、少し考えていた。「だから、おかしいのか?」と、複雑な顔になった。
「はい。七十過ぎの老婆が、半月前から行方不明です」
「ちょっと、大袈裟じゃないのか?」
「いえ。根拠はあります」
松木は、自信ある態度になって、「通いのお手伝いさんに尋ねたら、『今検査入院しているの。退院したら、その足で当分の間海外旅行する。お給料は全額支払うから、ゆっくりしてちょうだい』と、電話で告げられたそうです。お手伝いさんは、『お留守番は?』と、聞いたそうです。荒井美智子さんが海外旅行に行くときは、お手伝いさんがいつも留守番していたそうです。『姪が、留守番がてら遊びに来るからだいじょうぶ』と、言ったそうです。給料は、全額振り込まれていたそうです」と、説明した。
「そのどこがおかしい?」
訝る原田。「別に、何の疑惑もないじゃないか」と、呆れた。
「では順を追って、疑惑を説明します」
松木は、もったいぶった言い方をすると、「何故、お手伝いさんに、直接話さなかったのでしょうか?」と言ってから、原田に答えを求めるような顔で見つめた。
「忙しかったんだろ」
原田は、ぶっきらぼうに答えた。早く終わらせたくなった。こいつに付き合っていたら、何時帰る事ができるかも分からない。それに、何でも事件にしそうだ。
「そうかも知れません。が、荒井さんは、今まで必ず直接話していたようです」
松木の、思い込みの推理が始まった。「二つ目。何故、姪が来るのに、お手伝いさんは不要なんでしょうか?」と言ってから、また原田を見つめた。
「何で、お手伝いさんが必要なんだ?」
原田は、逆に尋ねた。
「資産家ですよ。姪が来るんですよ。お手伝いさんがいた方が、姪も楽ですよ。ちゃんと給料を払ってるんですから…」
原田は、それじゃ留守番の意味がない。お手伝いさんがいること自体鬱陶しいかもしれない。自由を満喫したいだけじゃないか? どこがおかしいのか? という反論を呆れて言えなくなった。事件がない日は、早く帰りたい。近藤の問いに、姪が答えたのと同じ内容だ。
「四つ目…」
「三つ目だぞ!」
流石に原田は、松木の間違いを指摘した。少しでも疑惑を盛って、捜査の正当性をアピールするつもりだ。
「失礼しました」松木は、少したじろいだものの、「三つ目…」と言いかけて、「もういい!」という原田の言葉に遮られた。今いいところだったのに…。
「分かった。捜査を許可する。但し、慎重にな。逐一私に報告しろ」
原田は、仕方なしに許可した。今までのように、途中で白旗を上げるに違いない。本人が諦めるまでやらすしかない。
上司のお墨付き? を貰った松木は、次の日の朝荒井の取引銀行に向かった。今回巻き込まれるのは、いや人身御供は? 失礼、行動を共にするのは、大学の後輩で直属の部下である西沢良樹刑事だ。
「念のためです」
応対に出た支店長の疑念に対しての、模範解答。しかし支店長は、念のためとは思っていない。警察の常套手段だと分っているからだ。
「分かりました。しかし指静脈認証されてますから、パスワードが判っても指を静脈認証装置にかざさない限り他人が預金をおろすことは不可能です」
支店長は、胸を張って答えた。いるんだよな。警察にも、何も知らないやつが…。と、思いながらも。
「指静脈認証? そうなんですか?」
松木は、知らない。松木は、自分の指を不思議そうな顔で眺めた。西沢は思う。よくこれで刑事が務まっているものだと。
「指静脈は、指紋のように個人ごとに違います」
支店長は、松木のために説明した。が、こんな事も知らないのか? と、呆れ顔だ。
「歳をとってもですか?」
またしても松木は、あさっての質問。
「もちろん。まあ、指静脈認証がないATMなら、可能ですが…」
「そこだ!」
松木は、支店長の言葉に気色ばむ。
支店長の好意で、いや、松木のごり押しで、過去半月間の荒井美智子の預金引き出しの日時とATMの場所を教えてもらったが、荒井美智子は海外に出かけるという次の日だけしかATMを利用していなかった。荒井美智子は、指静脈認証が導入されてからいつも同じ静脈認証がある端末からお金を引き出していた。もっとも、限度額は、資産家だということか一回二百万までである。その日は、限度額いっぱいの二百万円を引き出していた。
「防犯カメラの映像を見せていただけますか?」
松木は、それでも引き下がらない。西沢は、松木の執念に脱帽するしかない。が、やはりお門違いのような気がした。支店長は、CDに防犯カメラの映像をコピーして応接室の一つを提供してくれた。さすがに、支店とはいえシティー銀行の田園調布支店だ。応接間は広くテーブルやソファーも立派だ。
「何か細工しているに違いない。例えば、美智子さんの指を切ってATMにかざすとか・・・」
松木は、防犯カメラを見る前から決めつけていた。
西沢は、松木の態度を見て何も反論できない。確か死体の指静脈認証は、不可能だと記憶していた。やはり、松木は無知で短絡的な人間なのだろうか?
「どこもおかしなところはありませんよ」
松木と一緒に防犯カメラの映像を見ていた西沢は、指摘した。自分の指を静脈認証装置にかざしている。
「つばの広い帽子を、被っている。怪しい」
松木は、疑惑を持った。いや、無理やり思い込みで疑惑を持っているような言い方である。まだ初秋とはいえ九月で、紫外線は強いはずだ。帽子を被っていてどこがおかしい? と、西沢は思う。
「西沢! ストップ!」
松木の声に弾かれるように西沢は、一時停止ボタンを押した。
「そら見ろ! やはり、おかしい」
松木は、得意満面な顔になった。
「どこがおかしいのですか?」
西沢は、松井の真意が分らない。
「目の辺りが映っているだろ」
「それが、何か?」
西沢は、松木に振り向いて尋ねた。「目の辺りしか見えてないじゃないですか」と、反論した。
「良く見てみろ! 目に皺がない。七十過ぎの老婆には、どうしても見えないじゃないか?」
西沢は言われたままに、ディスプレーを注意深く見た。「そう言えば、皺がありませんね」と、答えるしかない。「しかし、防犯カメラの映像ですよ。断定するのは、早いと思います」と、慎重である。
松木は、防犯カメラの映像を借りる事に成功した。署に持ち帰って、鑑識の日下部に調べさせる事にした。
松木と西沢は、数日後の午後二時過ぎに荒井美智子の屋敷に高橋優香を訪ねた。松木の執念? いや、単なる思い込みにより、持ち帰った防犯カメラのCDを鑑識課の日下部に分析させた。分析結果は、七十代の女性ではない可能性が高いということだった。顔の一部しか映っていないため、それ以上の事は判明しなかった。荒井美智子の海外渡航の記録により、荒井美智子は海外に出ていないことも判明した。原田係長は、「良くやった」と、上機嫌になった。が、思い込みがずばり当たったのは、奇跡に近かった。そこで、任意同行を求める事になった。
高橋優香は、在宅していた。応対に出た彼女は、うんざりしたような顔で、「今度は、何ですか?」と、尋ねた。
「荒井美智子さんが、行方不明です。そこで、少し事情をお聞きしたいのですが、署までご同行いただけますか」
西沢は、そう切り出した。
「そんな…、行方不明なんかではありません」
高橋は、否定した。が、困惑しているようでもある。
「事情を伺うだけです。お手間は、とらせません。それに、普通ならこんな機会滅多にないことです。社会見学だと思って結構です」
西沢は、松木の言い方が気になった。頭がいいのか? 単なる方便で言っているのか? アホなのか? 西沢は思う。やっぱりアホなのだ、と。それでも、たまに鋭い捜査をするから不思議だ。
3.被疑者(社会見学のはずが…)
「どうですか? これが取調室です。めったに入れませんよ」
松木は、取調室を自慢したあとに、「どうぞ」と、窓側の席を勧めた。
「テレビと違って、狭いのね」
高橋は、取調室を見回しながら少しがっかりしたようだ。しかし、窓にはちゃんと鉄格子がはまっている。が、あることに気が付いて、「マジックミラーの入った鏡はないんですか?」と、松木に尋ねた。
「そんなもん、ありません。まあ、最近取り調べの可視化で、検討はしていますが…」
松木は、高橋のために説明した。が、「みんな、そう思っているんですよね。あれは、ドラマの世界。そんなスペースは、ありません。経費的にも余裕がないんです」と、愚痴り始めた。
「先輩」
西沢は、松木を促した。この調子では、説明だけで日が暮れそうだ。
「そうでした。ちゃっちゃとやって、ちゃっちゃと終わらせましょう」
松木は、手で高橋に座るように促した。高橋は、言われたとおり窓側の席に座った。
松木は、高橋に対峙する格好でドアを背に座った。西沢は、隅に置いてある机に座りパソコンを立ち上げた。
「では、早速本題に入ります」
「はい」
高橋は、素直に答えた。が、何処となくぎこちない。取調室で、改めて刑事と対峙すると流石に緊張するのだろう。
「あなたは、本当に荒井美智子さんの姪ごさんですね」
松木は、念を押した。
「そうです」
「では、住所を教えて下さい」
「住所は、愛知県名古屋市○○区名城…、三丁目だったような…。四丁目かも、…」
「あなたの住所ですよ」
松木は、呆れた。
「だから、長いこと会っていないし、忘れることもあるでしょ。それに引っ越ししたかも知れないじゃないですか!」
彼女は、少し興奮してきた。しめた! 松木は、彼女の失言に、少なくとも荒井美智子の姪ではないと確信した。では、この女は一体誰なんだ。
「あなたは、荒井美智子さんの姪ごさんではありませんね!」
松木は、女を睨み付けながら凄んで見せた。明らかに女の動揺した顔が見て取れた。「一体誰なんですか? 荒井美智子さんは、今どこなんですか!?」と、畳み掛けて尋ねる。勝った。松木は、これで自分がこれから主導権を握れる。と、ほっとした。
「仕方ないですね」
女は、観念したようだ。きっと白状するに違いない。良くて監禁、最悪の事も考えなければならない。松木の無言の問いかけに、女は、「荒井美智子は、私です。だから、姪の住所が裏覚えだったのです」と、松木に告げた。
「何だ、そうだったんですか…。なら最初から言ってくれれば、こんなことにはならなかったんですよ」
「松木先輩!」
松木と同席している西沢刑事は、咳払いした。
「何かおかしいか?」
松木は、怪訝な顔になり尋ねた。
「荒井美智子さんは、七十を過ぎたおばあさんですよ」
「だから何だ!?」
松木は、西沢の指摘が理解できないようで、「荒井さんに失礼だろうが、美魔女を知らないのか? どんな老いぼれでも、整形手術という方法だってあるんだぞ!」と、逆に西沢に食って掛かった。
「老いぼれで、悪かったですね」
女は、松木の失言を見逃さず冷ややかな顔で松木を睨み付けた。
「いやあ、言葉の綾ですよ。あや…」
松木は、咄嗟に取り繕った。
「遺伝子操作と言うようですね。その遺伝子操作で、若返ったのです」
女は、きっぱりと言った。
「そうですか…」
松木は、女の発言を否定はしなかった。「誰に、若返らせてもらったのですか?」と、真面目な顔で尋ねた。
「先輩!」
西沢は、呆れながらもこのおかしな取り調べを元に戻そうとした。
「判っているさ」
松木は西沢に向かって言ってから、西沢の耳元で小声になり、「相手の術中に嵌まったことにして、取り調べをしょうとしただけじゃないか」と、取り繕った。西沢には、分かっていた。さっきまで、女の言っていたことを信じきっていた松木を…。あれは、いったい誰だったのか?
「帝産医大の門脇先生です。本当のことだから、仕方ないじゃないですか。私だって五十年前は、こんなに美人だったのですよ」
女は、鼻高々だ。美しさを強調するように微笑んだ顔を松木に見せた。
「美人なのは、認めます」
認めるんかい! 西沢の無言の突っ込みが、顔に現れた。が、西沢美智子の五十年前は、美人だったのだろうぐらいの察しは、西沢にもついた。納得せざるを得なかった。
「初めての任意同行ということで、今日はこれぐらいで勘弁してやる。いや勘弁しますが、今度はちゃんと証拠を持って伺います」
松木は、あっさりと高橋を帰すことにした。が、自信はあるようだった。帰り際に、「旅行や外泊するときは、必ず私の携帯に連絡してください」と、念を押して名刺を渡すと女を帰した。
捜査は、暗礁に乗り上げた。決定的な決め手に欠き、確たる証拠もない。遺伝子操作をしたと言われる医師もアメリカに出張しており、問い合わせても不在だった。本人の携帯にも繋がらない。採取した指紋やDNAも本人のものと断定された。しかし、半月間荒井美智子のお屋敷に滞在していた女にとって、本人に成りすます事は、容易に考えられた。それだけなら、重要参考人として逮捕する事もできるのだが、前から銀行に登録している指紋と指静脈は女と一致した。さらに、荒井美智子と女の顔認証でも九十八%本人と判断された。それでも、プライバシーのため、証拠がなければ公表すら出来ない。
事情聴取した次の日に、松木と西沢の二人は帝産医大まで赴いて、事情聴取した。若返りの事実は不明だった。病院関係者に、「そんな荒唐無稽な…」と、鼻で笑われてしまった。が、検査入院の事実だけは判明した。
八月の最終の一週間だった。防犯カメラの映像を取り寄せた松木は、おかしなことに気が付いた。検査入院した日の防犯カメラには荒井美智子の姿が映っていた。退院した日には、荒井美智子は映っていなかった。驚いた事に、荒井美智子と言い張っている女の姿が退院したという日に映っていた。手に持っていたバックは入院時と同じもののようだった。
「まさか? 本当に、一週間ほどで、若返った?」
松木は、自席でパソコンを眺めながら頭を抱えて呟いた。
「そんな…。そんなバカな話はありません」
西沢は、隣の席から言下に否定した。今度は、信じるんかい!? と、突っ込みを入れたくなった。いったいどっちなんだ?
「他には、考えられないじゃないか」
松木は、そう言ってもう一度頭を抱える。
「裏口から、出入りしたとか…」
「そうか…。そうだったのか」
松木は、隣の部下に向かって向き直ると、「帝産大学病院もぐるに違いない」と、叫ぶような大声を出した。
それは、ないだろう。と、西沢は思う。病院が荒井美智子を、荒井美智子と言い張っている女と一緒になって殺す訳がない。「裏口から出たとかは、考えないんですか?」と、松木の考えを正そうとした。しかし、松木の思い込みを覆す事は出来なかった。あらゆる出入り口からの防犯カメラにも映っていなかったからだ。それでも、「一階のまどからだって夜中なら出ることも出来ます。近隣の防犯反カメラに映っているかも知れませんよ」との指摘にも、松木は耳を貸さなかった。
4.発覚(不本意な取調べに対する、荒井美智子? の反撃)
どこで嗅ぎ付けたのか、週刊誌記者も執拗に食い下がってきた。たまたま記者が、松木の事情聴取した荒井美智子と言い張る女が取調室から出たところに出くわした。記者の勘から後をつけたことがきっかけだった。偶然? 君塚に会って事情を聞いた。結果は、見えていた。
荒井美智子と言い張る女性は、知り合いのテレビ関係者に真実? を突きつけた。最初は驚いた関係者も、荒井美智子と言い張る女がATMの指静脈認証システムに指をかざして預金を引き出す様子を見て信じないわけにはいかなかった。カメラは、その光景を映し出していた。
他にも言葉遣いも以前と変わらないし、知り合いのスタッフの名前を覚えていたからだ。会話も自然に成立し、顔を見なければ声も同じで若返ったことを信じるしかなかった。テレビ関係者を驚かせた事実がもう一つあった。現在アメリカで若返りの手術が行われており、一週間ほど経ったときに大々的に報道されるとの事だった。
関係者と打ち合わせの結果、数日後に録画だけすることにした。ある情報番組の収録で、荒井美智子と言い張る女性を匿名のA子として登場させることにした。
「A子さんは、本当に若返られたのですか?」
インタビューしているレポーターも半信半疑だ。無理もない。お約束どおり匿名のA子は、すりガラス越しにテレビに出演した。声も変えていた。
「はい」
「あなたの主張によれば、ある大学病院の遺伝子操作で若返られたという事ですが…。事実ですか?」
「はい。最初は信じられなかったのですが、実際に手術を受けたら、五十歳も若くなる事ができました。一週間入院しただけで、こんなに若くなったのです」
A子は、自分の若さをアピールした。が、「しかし、これから十年程で、もとの年齢に戻るそうです」と、少し残念そうだ。
「どのような経緯で、若返ろうとされたのですか?」
聞くまでもないが、視聴者全員の疑問だろう。
「若返れば、何でもできます。若返りたくない人が、世の中にいますか」
A子は、逆にインタビュアーに尋ねた。当然の答えだ。
「下世話な話ですが、費用はどれくらい掛かったのでしょうか」
これも、知りたいところだ。
「詳しい金額はお教えできませんが、億に近い額です」
スタジオから、どよめきが起きる。一般視聴者はスタジオにはいない。それでも、あまりの驚きに思わずカメラマンやスタッフたちが上げたどよめきだった。
「執刀医は、あなたの主治医の方ですね」
「はい。K先生は、遺伝子の研究をされていました。ある時私が、若返る事は可能ですか? と、冗談混じりでバカな質問をしたことがあります」
「で、K先生は、どう返事されたのですか」
「できるとも。と、仰いました」
「で、若返ったわけですか」
「はい」
「若返って、どんな気分ですか」
「世の中の人には、奇異な目で見られるでしょう。近所の人には、いずれ分かることです」
荒井美智子は、君塚の顔を思い浮かべながら答えた。いるんだよね。口さがないおばちゃんが…。荒井は少し間を開けてから、「しかし、青春を謳歌できるのです。青春をやり直せるのです。やりたいことが、若い時と同じようにできるのです。言いたい人には、言わせておけばいい。これは、私個人の問題です」と、まっすぐにインタビュアーに向かって言った。磨りガラスを通しても、荒井の覚悟が伝わってくるようだ。
「良いことばかりでは、ないようですね」
「はい。これから人の五・六倍のペースで歳をとるそうです。十年後には元の年齢になりますし、その時の健康状態は保証しないとのことでした」
「今回、何故テレビ出演しようとしたのですか?」
A子は、少し逡巡したのか間を開けてから、「直接の原因は、警察に本人じゃないと疑われたからです」
「無理もないかも知れませんね」
インタビュアーの発言も、当然だ。若返るなど、SFかファンタジーの世界だからだ。それでもインタビュアーは、信じないわけにはいかない。
収録した番組は、近いうちに若返りのニュースが流れた時に放送されることになった。荒井美智子が万一逮捕された時にも放送することになった。言わば、保険の意味もある。
そんな事が起きていたのを、松木たちは知らない。
いずれにしても、荒井美智子が奇異な目で見られることに変わりはないのだ。それでも、若くなることは魅力である。
次の日の電車の中刷りには、週間新報の『資産家の七十代の女性が、行方不明。お屋敷には、姪と言い張る若い女がいた』とあった。悪意に満ちたタイトルであるものの、記者が疑うのも無理はない話しだ。
「もう一度、明日任意で取り調べるぞ」
週間新報の中吊り広告が出たその日松木は、閉塞感を払拭するように自分にも言い聞かせた。しかし、荒井美智子と言い張る女の犯行を裏付ける証拠がない。任意で取り調べるしかないのだ。
次の日に、松木は任意で取り調べる事にした。女も、素直に同意して前に入った取調室で聴取される事になった。覚悟ができているのか? それとも警察をバカにしているのか西沢にも判断が付かなかった。
「いいかね。君には、死体遺棄の容疑が掛かっているんだ」
松木は、被疑者となった荒井美智子と言い張る二十代前半とみられる女と取調室で対峙していた。松木の後ろには、部下の西沢がパソコンを操作して取調べ内容を入力している。
「私は、荒井美智子本人だと何回も言っています」
女は、逆に松木を睨みつけた。
「ほう。遺伝子操作で、若返ったと言い張るんだな」
「言い張るも何も、若返ったのは事実です」
女も、負けてはいない。
「死体遺棄といえば、殺人の登竜門だ。本当の荒井さんが発見されれば、君の犯罪が明るみに出るんだ」
松木は、女が新井を殺してどこかに遺棄したと決め付けていた。
「登竜門…、ですか?」
女は、少し間を置いてから、「この場合は、登竜門はそぐわない気がしますが…」と、不服そうな顔になった。
「そんな事はどうでもいい。少し考えれば・・・、いや、考えるまでもない。そうだろ! いくら医療や科学が発達したといっても、七十過ぎの老人を二十代に若返らす事などできるはずはない。どうしたら、子供でも分るような嘘をつくのだ!?」
「子供なら、科学の進歩に敏感ですし、大人と違って想像力も豊です」
女は、すかさず反撃!
「あのなあ、言葉の綾だよ。綾。私は、現実を言っているんだ。荒唐無稽な嘘をついてもすぐにばれるだけだ」
松木は女の言い訳に間髪入れず反論したが、どこか取り繕っているような言い方でもあった。
「荒唐無稽とは、心外ですね。私は、すぐに分るような嘘は付きません。もっと分らない嘘を付くと思いませんか? 例えば、荒井さんの隠し子だとか、遠い親戚だとか…」
「だから、本人だと言いたいのか?」
松木は、呆れ顔だ。
「そうです。私の顔を見れば、五十年ほど前の顔と同じだと分るはずです」
「そうなんだ。最新の顔認証システムでも、98.7%の確立で本人だという結果が出た。指紋や指静脈、も銀行に登録されている指紋や指静脈と一致した。DNAも一致した」
松木は、真実を告げるしかなかった。言ってから頭を抱えた。
「そうでしょ。そうでしょ。だから、本人なのです」
女は、初めて笑顔を見せた。
「しかし、同じ家に住んでいたあんたなら、どうにでも出来るじゃないか。隠し子だとしても、親を殺した可能性だってあるんだ」
「それは…」
女は、言葉に詰まった。
「本物の荒井美智子さんはどこにいるんだ? 生きているのか死んでいるのか? それに、君はいったい誰なんだ?」
松木は、これで勝負あったと思った。
「あと、一週間待ってください。一週間経てば、証拠をお見せできます」
女は、おかしなことを言った。
「何故、一週間なんだ?」
松木は、キョトンとした顔になった。
「それは、黙秘します」
女は、押し黙った。
それから女は黙秘を続けた。松木は、止むを得ず女を帰すことにした。一週間後に、また任意同行を求めた。女の一週間という言葉に仕方なく待つことにしたのだ。
『凄いニュースがアメリカから飛び込んできました。遺伝子操作により、最高五十歳ほど若返ることが可能になりました』
「何だ、若返えられるのか…」
明日荒井と言い張る女の任意同行を考えていた松木は、署にあるテレビをつけていた。明日が、一週間の期限だからだ。世間の動向に敏感でなければ、刑事は勤まらない。それに、関係ないような事件やニュースが捜査している事件を解決に導くこともあるからだ。が、それは言い訳に過ぎず本音は、ニュース以外見られないからだ。
捜査対象者がテレビ関係者でない以上、ドラマやお笑い番組を見るわけにはいかない。松木は、若返ることが、出来るようになったとは…。と医学の進歩に驚いていた。若返り?
『なんと、若返りの方法を開発したのが日本の医師の、門脇正之氏だということです』
MCの発言に、『それは、素晴らしい。医学は、そこまで進歩したんですね』と、コメンテーターがしみじみと発言した。
『それが、そうでもないようです。若返りは、一時的なことで、一年に五倍ほど歳をとり十年もすると元の年齢に戻るそうです』
『それでも、十年間はいまよりいろんな事が出来るじゃないですか…』
番組はまだ続いていたが松木は、門脇正之という人物に引っ掛かった、どこかで聞いた名前だ。
若返りの事実がテレビのニュースで報道されると、西田園調布警察署は大騒ぎになった。その翌日松木が女の任意同行を考えていた日の情報番組で、女が、匿名のA子として登場したから騒動は、署だけではなく警視庁全体に及んだ。情報番組の中で、刑事が任意ではあるが事情聴取を行った事実を告げたからだ。
松木は、門脇医師が日本に戻るのを待って事情を聞くことにした。が、松木に対する署内の風当たりは厳しい。
「だって、誰でもおかしいと思うじゃないですか!」
原田係長の厳しい顔に対して、精一杯の反論…。いや、言い訳…。あくまで結果論だが…。松木が首を突っ込まなければ、何事もなく医学の進歩に驚きを与えたに過ぎないのだ。いずれにしても荒井美智子は、好奇の目で見られたことは確かだろう。匿名と名を伏せてもマスコミは嗅ぎ付け、荒井美智子の名は世間に知れ渡ったに違いない。結果世間からマスコミはバッシングされる。
松木が首を突っ込んだお陰でマスコミは、かえって荒井美智子のプライベートを守る結果となった。警察が必要以上に捜査をしたということで、警察がマスコミからバッシングを受けたのだ。何という皮肉な結果だろう。
「まあ、仕方ない。と、言いたいところだが…、苦情の電話やメールそれに新聞それに週刊紙まで警察へのバッシングが酷い」
原田係長は、ため息をついた。当然松木は始末書を書かされることとなった。始末書で済んだのは、若返りというとんでもない事実を病院が明かさなかったためである。なぜか? アメリカからのニュースが出るまで、事実を公にしないと決めていたからであった。徐々にではあるが、警察へのバッシングも少しずつ少なくなっていった。
門脇医師がアメリカで行っていたことは、荒井美智子と同じ若返りの手術であった。若返りの手術を受けた人物はプライバシーの保護のため明かされなかったが、アメリカ在住の七十七歳の日本人男性とだけ報道された。
今や荒井美智子は、時の人となった。
更に、一ヶ月後の十一月に衝撃的な事実が明かされる。荒井美智子と、アメリカで若返りの手術を受けた男性が結婚するというのである。二人は若いときに恋愛していたが、結婚を両家に反対され叶わなかった。そんな時代だったのだ。ようやく五十年後に、想いが叶ったのだ。さらに、子孫を残すための若返りでもあった。
「七十七歳の新郎に、七十一歳の新婦。どう考えても、現実的じゃないな」
結婚式の招待状を受け取った松木は、自席から隣の西沢に言った。
「最近では、珍しい事ではありませんよ」
西沢は、自分にも来た招待状を複雑な顔で見ながら答えた。
「そうじゃない。どう見ても、俺より若いじゃないか」
招待状に添えられていた二人の写真を、松木は複雑な顔で眺めた。
「そっち?」
西沢は、それ以上何も言えなかった。
「七十一歳で妊娠したら? ギネスに載るのかな?」
「さあ? 二人の場合肉体的には、二十代のようですが…」
西沢も、困惑ぎみで答える。
「そうか、若返った人間で、世界で初めての妊娠出産になる。凄いぞ!」
松木は、単純に喜んでいた。
そんなことはどうでもいいことだと、西沢は思う。今後松木が、思い込みや独断専行しない事を祈るしかない。が、無理だろう。
「しかし、何で我々を結婚式に招待する気になったのでしょうか」
西沢は、困惑気味である。が、「当て付けか? 嫌味ではないでしょうか」と、言ってみた。
「さあな」
松木は、そんな事は気にしていないのか、「こんな珍しい結婚式に招待されただけでも、凄いじゃないか」と、無邪気に喜んでいた。
「…」
西沢は、呆れ果てて何も言えない。
「しかしなあ」
松木は腕を組んで、思案顔になった。
「どうしました?」
西沢は、珍しく考え事をしている松木に尋ねた。
「簡単に若返りができるようになったら、パスポートや免許証はどうする?」
松木は、真剣に考えていた。西沢は思う。あんたの心配することじゃない。
「もし、結婚相談所に嘘の年齢で登録したら、俺は婆さんと結婚するはめになる」
結婚相談所に、登録してるんかい? という突っ込みを西沢は、咄嗟に封印した。
「でも、若返るには相当な額が必要になる。金持ちだ。なら、若いうちは楽しんで、相手が年取ったら、がっぽり慰謝料を踏んだ食ってやる」
西沢は、思う。やはり先輩はバカなのだと。先輩は金持ちと結婚するつもりのようだが、無理だろう。未だに独身ということは、やはり何処かに問題があるのだろう。思い込みが激しいだけ? それに、自分本意? いや、問題だらけなのだと…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
