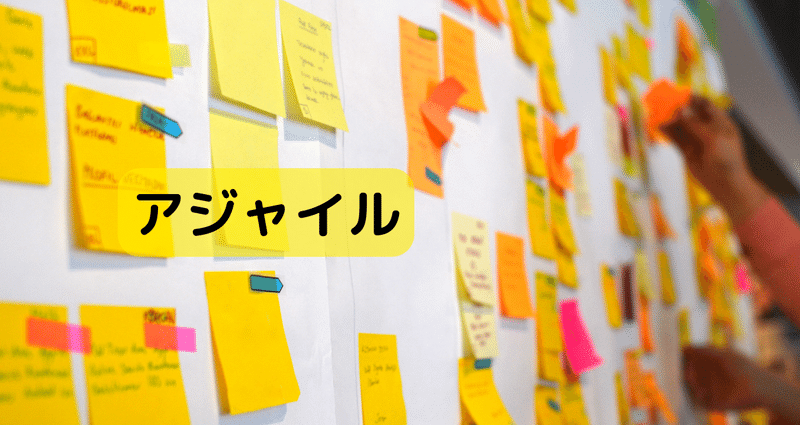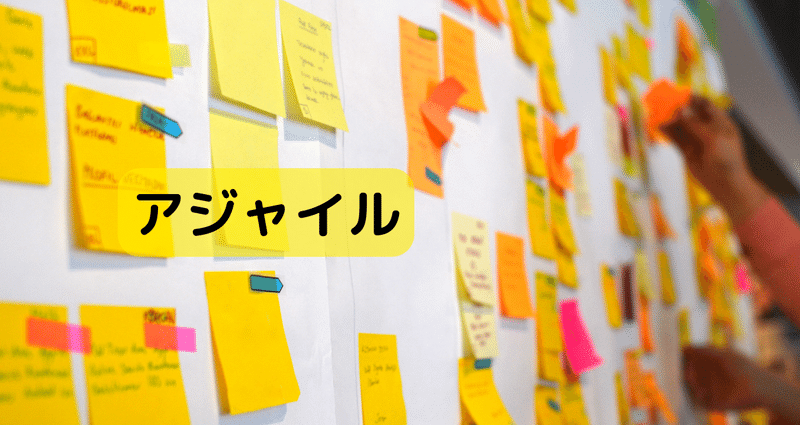【アジャイル】組織アジャイルの「組織」とはどういう括りだろうか?
「組織」の解釈でたまに混乱します。
組織アジャイルの対象範囲は?シンアジャイルのコミュニティの中で私は「組織アジャイル」の分科会チームに入っています。目的は開発・非開発に関わらず、組織でアジャイルな動き方や価値感、マインドセットを取り入れて、変化に富む不確実な時代に乗り切れる強い組織・学ぶ組織を作っていこう、そのためにはどういう活動をコミュニティの中でやっていくべきかを考えて実行していくというのが大枠の目的です。
この時の「組織」という対象は、確かチームとして明確にした記