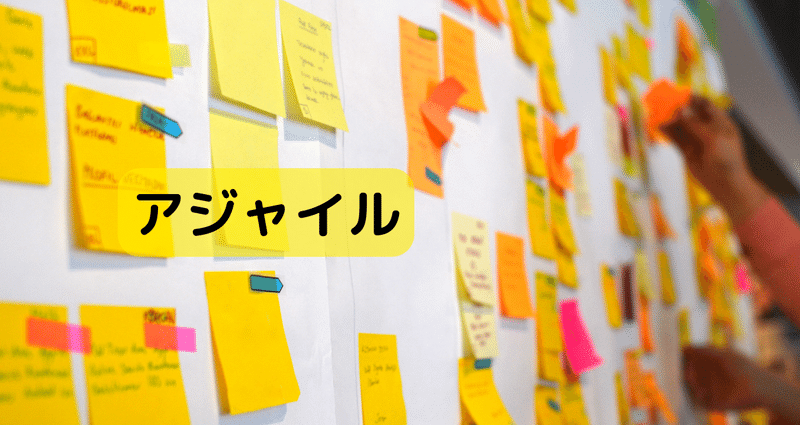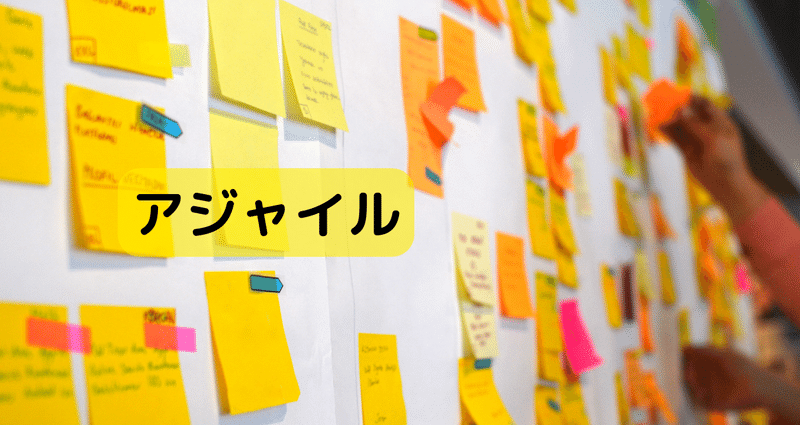【仕事・アジャイル】「むきなおる」勇気
なかなか決められた目標や計画は変えられないものです。
見込みの薄いプロジェクト私の部署で支援していたプロジェクトがあったのですが、色々と仮説構築検証をしてニーズはありそうだったのですが、より安価な代替品もあり、またその領域を実際シェアが取れたとしてもかなり事業規模が小さいことがわかったため、コストやパワーをかけてもあまり筋が良くないという見解になりました。
実際のプロジェクトの担当者もその内容には納得し、検討をクローズする方向で調整をしていたようですが、その担当者の直属の