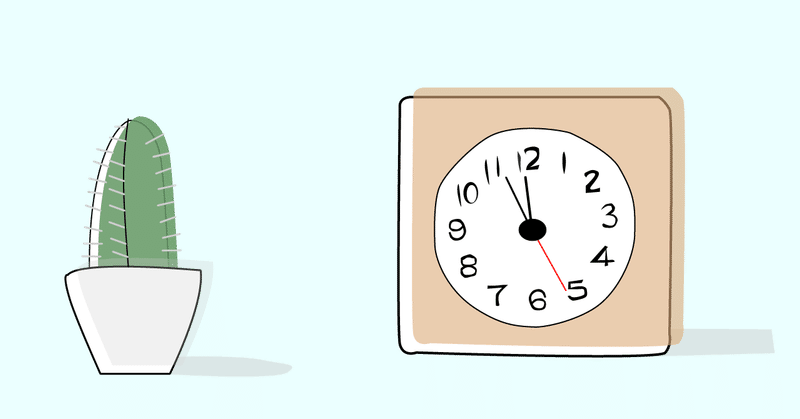
「話が長い人」の研究 〜自分は大丈夫?〜
ああ、この人もそうだった… と絶望する瞬間。それは、会話を始めて、8割、9割を、相手の話を聞いてなきゃいけないと悟った時。つらい。かといって、対抗して自分もたくさん話をしようとは思わない。多くの場合こういう人々は相手の話にほとんど興味がなく、こちらがいくら話をしても、それに共感することなくすぐに自分の話に転換してしまうからだ。こちらの渾身の意見にも全く反応がなく、綺麗にスルーされることもある。そして急いで自分の話を嬉々として再開してしまう。徒労感が尋常じゃない…
では、彼らはなぜ話が長いのか? 長年の個人的な研究の結果、いくつかの類型に分けられると思う。(もちろん、複合型でこじらせている場合もあるが)
単純にバランス感覚が悪い人
天然型。といっても、話が長い人の大半は天然だ。意識的に戦略的に、会話の9割もしゃべろうとするのは詐欺師か何かの類くらいだろう。こういう天然でバランスの取れていない人は、得てして自分を客観視できていない。だから相手との関係も、なかなか客観的に見られない。たとえずっと自分がしゃべり続けていても、それに何の疑問も違和感も持たず、それが自分の中ではごく自然に映っているのだ。だから、たとえ話が長すぎることを指摘したとしても、全くピンとこない。
全体の組み立てができない人
常に話があっちへ行き、こっちへ行き、あらぬ方向にどんどん展開していく。内容の重要度も区別がないので、どうでもいいエピソードが延々と続く。これとは別の例で、一部の優秀な起業家タイプ等には、敢えて話を多様に展開させる人はいる。でもそれは相手の反応を見ながら、常に最適なトピックを探っているから。そういうタイプとはもちろん全く違い、単に、思いついたことを脳から声へと単純にスライドさせてしまう人のことだ。
会話の空白を極度に恐れる人
コミュニケーションには、ある程度の余白が必要である。それがないと、話のテンポばかりが上がって会話の内容が深まらない。この隙間があるからこそ、次にどちらか何を話すべきかという、阿吽の呼吸での判断、アイコンタクトでの合意、場の切り替えができる。会話の共同作業といえる。しかしこれができない人は、まるで何かをしゃべり続けることが義務かのように、無駄に焦って、いつも食い気味にトピックを上乗せしてくる。相手にしゃべらせる隙を全く与えない。忙しくて仕方がない。
自己陶酔しがちな人
最高やっかいなタイプである。四天王最強である。これに出会ってしまったら、もうどうしようもない。こういう人はなぜか、自分の話はとても人にありがたく思われるはずと信じて疑わない。だから、空気も読まず、相手の顔色さえ見ず、得意満面で自説を延々と展開する。それが、相手にとっても幸せな時間だと思ってしまっているのだ。そして、これがまたアレなのだが、このタイプの人の話は、経験上8割以上はどうでもいい。なので1時間のアポイントの予定だった場合、その煉獄の苦しみから脱出するため、いかに打ち合わせを早く切り上げるか、という作戦を画策することになるのである。
こうは書きながらも、自分も、まれに興に乗ってちょっとしゃべり過ぎてしまったと反省することもある。いま書いた文章を読み直して、強く自戒するのであった。
///
ツイッターでも、できるだけ有益なことを毎日発信してます。ぜひフォローをよろしくお願い致します 🙇🏻♂️
経営者やこれからの若いリーダーへ、メンターとしていつも助言していること。
— 松本淳|アースメディア代表|メンター (@Jn_Matsumoto) May 24, 2020
・人生の目指すべき方向を知る
・自分の知らない強みに気づく
・弱みはユニークさと考える
・失敗の痛みを自信に転換する
・自分の感性と直観を信じる
僕自身のこれまでの失敗も伝え、成長の糧にしてほしいと思ってます。
経営者、若手リーダー向けのメンターとしても活動しております。課題をクリアにし、前向きに進みたい方の背中を押す伴走型サポートです。ぜひご気軽にお問い合わせください、お話できることを楽しみにしております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
