
潜水艦は海に漂う子供に機銃掃射した!
生存者と住民が語る「小笠原丸」の悲劇
吉村先生は『烏の浜』の執筆経緯について、「小笠原丸」の沈没ー「烏の浜」(「月間ダン」昭和54年4・5号初出、随筆集『万年筆の旅 作家のノートⅡ』昭和61年8月文春文庫に収録)で詳しく書いています。

まず、「小笠原丸」がどのような船であったのか、また、いかなる事情で樺太から避難民を乗せることになったのか、さらに潜水艦に襲われた折の状況はどのようなものであったか、を知ることから手をつけた。
私は、船舶名簿をひるがえし、「小笠原丸」が逓信省(ていしんしょう:かつて日本に存在した郵便や通信を管轄する中央官庁)所属の海底線敷設布設船(かいていせんふせつせん:海底ケーブルの敷設・修理・回収を行う船)であることを知った。
海底に電線をしく船であるなら、現在(昭和54年)では日本電信電話公社(現NTT)の仕事に属すはずで、私は、電電公社に勤務する友人に電話をかけてみた。
吉村先生は友人の協力により、「小笠原丸」の乗組員であった山口智男、大崎邦雄、高見沢淳夫の三氏から話を聞くことができました。
「小笠原丸」は、明治39年三菱造船所で建造された1,397総トンの船であった。多くの海底電線布設に活躍し、太平洋戦争勃発後は海軍の要請を受けて作業をつづけ、乗員はすべて軍属になっていた。
昭和20年4月上旬、「小笠原丸」は横浜港を出港、途中、敵潜水艦の魚雷攻撃を辛うじて避け、函館港に入港した。当時、北海道、樺太間の海底電線は不通で、また青森、函館間の電線にも障害があるなどみじめな状態で、その再開、修復工事のため派遣されたのである。
ただちに作業がはじめられ、8月上旬までに北海道、樺太を連絡する女麗(めれ)、猿払(さるふつ)間のケーブル3本の修理を終えた。そして、利尻島方面の作業にかかる準備のため稚内に入港していた時、終戦を告げる天皇のラジオ放送をきいた。
「小笠原丸」では翠川(みどりかわ)信遠船長を中心に幹部が今後の対策を練っていたが、樺太の豊原(とよはら)にある逓信局の局長から、樺太在住の逓信省関係者の家族の引揚げに従事して欲しいとの要請があった。
この様に「小笠原丸」の翠川船長は「逓信省関係者の家族」だけを乗せるはずでしたが、大泊は避難民であふれかえり、大混乱となったため、可能な限り乗船させたのでした。
吉村先生は「小笠原丸」が潜水艦に攻撃された状況を、大崎さんから聞き取り、つぎのとおりメモしていました。
(注)先生は「カタカナ」で書いていますが、読みにくいので「ひらがな」にしました。
終戦になったので、米軍から、航行中の船舶は灯火を灯すよう指令があった。「小笠原丸」も、電光を煌々(こうこう)とともした。戦時中、灯火管制下で航行することになれたので、変な気持ちだった。
また、逓信省から伝えられた特殊の無線信号音も発信しつづけていた。戦時中は、そのようなことをしたら、たちまち敵潜水艦に察知され、攻撃される。戦争は、本当に終わったのだ、と思って、安心だった。
この状況では、船が攻撃されるとは、誰も考えなかったのでしょうね。
しかし、悲劇は起きてしまいました。
山口さんは、次の様に語りました。
午前4時の当直であったので、15分前に起き、船橋に上った。海上は暗く、霧が流れていた。海図を見ると、留萌沖であった。
午前4時20分頃、水中聴音器についていたも元海軍警備隊員が、突然、
「魚雷音」
と、叫んだ。
魚雷音が右舷方向から接近してくると言うので、一等運転士田中高次が、
「面舵、一杯」
と、命じた。
魚雷音が接近したが、通過した。
私は、田中一等運転士の命令で船長室に走った。ベッドから起きた船長は、
「おかしいな、すぐ行く」
と、首をかしげた。
私は、船橋へ引き返した。その直後、警備員が、再び、
「魚雷音」
と、叫んだ。
と同時に、魚雷の命中する大音響がし、私たちはその衝撃で倒れた。
船尾の右舷に、火柱と水柱が上っていた。
船は、あっという間に沈没してしまいました。
山口さんら、乗員のほとんどは甲板や船橋にいたので、海に投げ出されたり、自ら飛び込むことができて、助かりました。
しかし、避難民たちのほとんどは、雨を避けて船内にいたので、船内にとじこめられたまま、海中に沈んでしまったのです。
大崎さんも、海に投げ出されてからの話をしてくれました。
船の沈没時に気を失った。気づいてみると、ボートデッキの木のタラップに、しがみついていた。
肩にのしかかる者がいた。30歳くらいの女だった。二人の重みで、タラップが沈みはじめた。私は、女の手を離させ、タラップの端につかまらせた。寒かった。
女は、
「子供をはなしてしまった、子供を・・・・・・」
と震え声で言っていた。
一人の老人が、浮かんでいる行李(こうり)に這い上がろうとし、行李がまわっている。やがて、行李の動きがとまると、老人の姿も消えていた。
潜水艦からの曳光弾銃撃
その後大崎さんは、海面に浮上した潜水艦が「曳光弾(えいこうだん)」で海面に向けて機銃掃射しているのを目撃しました。
「曳光弾」とは、発光して、弾道がわかるようにした弾丸のことです。
小説『烏の浜』では「小笠原丸」が「浮上した潜水艦が海面を機銃掃射していた」と記載はありますが、それにより「死亡した者がいた」とは書かれてはいません。
目撃した大崎さんも、機銃で撃たれた人は見ていません。
しかし、吉村先生の随筆から9年後に北海道新聞社が発刊した「慟哭の海 ー樺太引き揚げ三船遭難の記録ー」では、
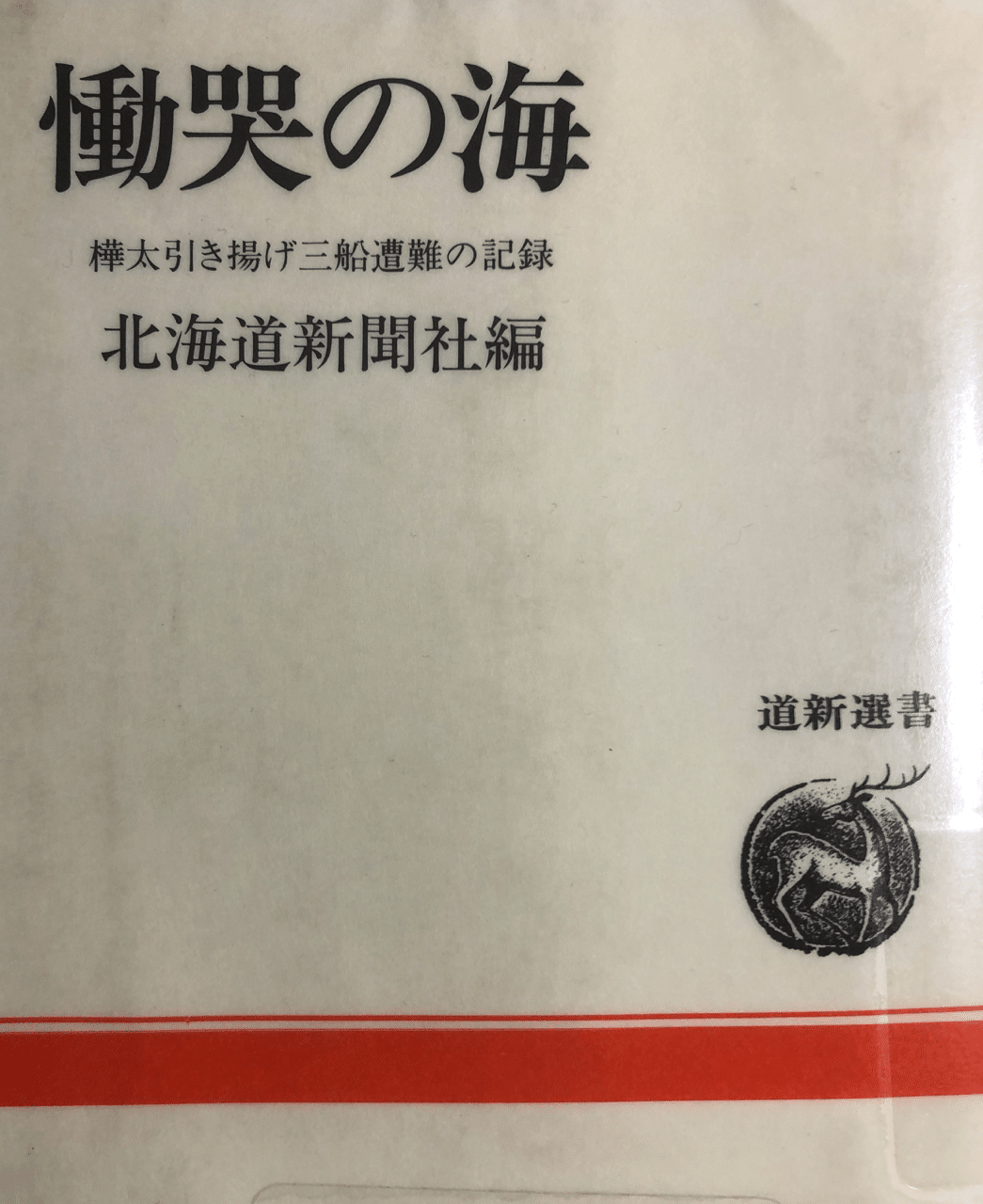
死体は増毛から来た消防車に積まれて運ばれていった。機銃で頭を割られた10歳くらいの少年の死体も混じっていた。一体、沖では何が起こったのか、漁民たちはおののくばかりだった。
との記載がありました。
潜水艦は兵士でもなく、武器を持って抵抗しているわけでもなく、溺れて恐怖のどん底にいる小さな子供さえも、威嚇射撃ではなく、正確に命中させるための「曳光弾」を使って、更なる恐怖を与えて殺戮したのでした。
この非道な潜水艦は、さらに2隻の船にも襲いかかります。
次回詳しく報告します。
吉村先生は、遭難者を「シナ人(中国人)が攻めてきた」と間違えて、大別刈がパニックになったことを、住民から聞き取っていました。
「小笠原丸」の沈没位置は、大別刈沖カムイト岬東方約四海里(16㎞)であった。
大別刈は、現在増毛町に併合されている小村落で、私は調査のため二度訪れた。第二回目の折には食料品店の櫛引キヨさんという六十年輩の人に会い、回想を録音したが、その取材を中心に、事件当時の大別刈の模様を記してみる。
「小笠原丸」が雷撃をうけたのは午前4時20分頃で、夜は明けていなかった。
「ヨンズ(4時)少し過ぎだったかね、ガチーンと沖の方から物凄い音がしたの」
キヨさんは当時を思い出すような眼をして言った。
キヨさんの夫ははね起き、いかぶしそうな表情をして浜に出て行った。
キヨさんも起き、朝食の支度にとりかかった。そして、味噌汁に豆腐を入れようと思い、長女に籠(カゴ)を持たせて買いにやらせた。が、長女はすぐに戻ってくると、
「母さん、大変だ。沖からボートが近づいてきている」
と、叫んだ。
キヨさんは、驚いて外に飛び出した。夜が白々と明けはじめていた。
「そこに岩が見えてるでしょう。その上手(かみて)あたりに、ボートが流れているの見えてったの」
海岸から数百メートル離れた海面に、大きな岩が突き出ていた。
やがて、夫が、駆けもどり、
「家から出るな」
と、きびしい口調で言った。
「そのうちに、浜からみんなが、ワーッワーッと泣いてきたんだわ。シナ人(中国人)が攻めてきたというの」
この事情は、誤解から生じた。
救命ボートが浜につくと、一人の老漁師が不安そうな眼で家並みの間から浜に近づいた。沖で雷撃の轟音(ごうおん)についで機銃掃射の音が連続的にしたのを耳にした村の者たちは、浜についたボートに強い警戒心をいだいたのだ。
ボートからおりた乗員の一人が、
「私たちは小笠原丸の乗員で、避難民をのせて航行していたが、潜水艦の魚雷攻撃をうけて船は沈没した。沖に生存者がいるから救助の船を出して欲しい」
と、訴えた。
老漁師は無言でうなずくと、村落の中に消えたが、それきりだれも出てこない。
漁師は乗員の言葉をききまちがえたのである。乗員は寒さで口がこわばり、言葉がきわめて不明瞭であった。それに、長崎生まれなので訛が漁師にはひどく奇妙なものに感じられた。
漁師は「小笠原丸」という言葉を耳にして小笠原島と考え、「避難民」を「シナ民」ときいた。そのため漁師は、ボートに乗った者たちを「小笠原島からきたシナ人」と受けとったのである。
キヨさんからは、救助の状況も聞きくことができました。
婦人会の人たちは、浜に行って火を起し、ボートに乗っていた者たちに暖をとらせたり、水を吐かせたりした。さらに着物を持ち寄って着せ、飯も食べさせた。
救助に向かった漁船は、竹筏(たけいかだ)にしがみつく11人の乗員を収容し、さらに伝馬船(でんません:木製の小舟)にまたがって半ば意識を失っていた少年を救い上げ、浜に連れてきた。
一人の女は子供を失って半狂乱になっていた。
「沖を見ながら泣いて、泣いてね。まじ、すごいことだったの」
キヨさんは、眼をうるませて言った。

別刈の海岸から大別刈方面に向けて撮影
「事実を追求する小説」が「事実」と違う!
この子供を失った女の人について、前回私が、お伝えしていなかったことがあります。
それは彼女が「妊娠」していたことです。
そして、「出産」について、小説と事実では違いがあるのです。
では、小説の一部です。
生存者たちは、増毛病院で流産した山口幸子という婦人をのぞいては、一人残らず健康を回復した。
幸子は、布設主任大崎邦雄の肩にしがみついて死をまぬがれたのだが、見失った二人の子供のうち3歳になる久美子という女児が沈没日に遺体となって発見された。
が、病院側では衰弱の激しい幸子を気づかって、そのこと関してはなにも伝えなかった。
<中略>
やがて回復した幸子は、退院日に突然のように一個の骨壺を渡され顔色を変えた。
彼女は二人の子供の死を覚悟していたようだったが、一人が遺体として収容され、他の一人が未収容であることを知らされ顔をおおった。
彼女は、骨壺を抱きしめ声をあげて泣いた。町の人たちは、声をかけることもできず激しく肩を波打たせる幸子の姿を見つめていた。
小説発表から7年後に書かれた随筆集『万年筆の旅 作家のノートⅡ』でも
山口幸子さんは妊娠していたが、病院に収容された夜、流産した。町役場の吏員は、山口さんの体を案じ、二人の子供が無事に救助されたと偽っていた。
<中略>
山口さんは、体も回復して退院した。
役場の吏員は二人の子供を救助したと伝えたのは偽りで、二人の子供は1人が行方不明、一人が事件の翌々日に遺体となって発見されたことを告げた。
発見された遺体は長女久美子さん3歳のもので、すでに焼骨されていた。
山口さんは、久美子さんの遺骨をおさめた壺を抱きしめて号泣し、吏員をはじめ町の人たちは涙を流して山口さんの姿を見つめていた。
と、やはり「流産した」と書いています。
しかし、北海道新聞社が発刊した「慟哭の海 ー樺太引き揚げ三船遭難の記録ー」では、山口さんについて
デッキ(船の甲板)の下には他にも大勢の引き揚げ者が肩を寄せ合っていた。そのなかには臨月の大きな腹をした山口幸子もいた。幸子は六つになる長男の英樹、三つの長女、久美子の二人を抱えて、郷里の宮崎県に引き揚げる途中だった。夫の忠春は豊原逓信局に勤務していた。
逓信関係者の家族には、乗員の居室などが提供されていたが、幸子はそんな申し出をしなかったらしい。雨しずくのたれるデッキの下で二人の子供を寝かしつけていた。小笠原丸が撃沈されたとき、このデッキの下にいた何人かが、海にほうり出され助かることになる。
<中略>
生存者は増毛町内の白毫寺、願王寺、潤澄寺、天真寺に収容され、容体の重い4人は増毛町立病院に収容された。そのなかに身重の山口幸子もいた。増毛病院で看護婦をしていた岩田照子はいまもその時の光景をありありと覚えている。
一週間後、元気を取り戻した幸子は出産のため退院した。町民の好意で世話してもらった町内の置屋、松島検番(けんばん:芸者屋の取締りなどをする事務所)の一室で幸子は男児を出産した。ひと月後、郷里宮城県に引き揚げる幸子の右手には赤ん坊が、左手には久美子のちっぽけな骨箱が抱かれていた。
と、書かれているのです(゚д゚)!
新聞社が病院の看護婦さんの証言として、「男の子を出産した」と書いているので、間違いないはずです。
徹底的に「事実」を追求する吉村先生が、「事実を曲げて小説にする」ことは考えられないので、取材時に証言した方が間違って「流産した」と言ったのだと思います。
でも、連れていた子供二人を亡くし、悲しみに打ちひしがれるなかで、唯一の希望ができたのなら、吉村先生も安心したことでしょう。
翠川船長は自ら波間に消えた?
「小笠原丸」の翠川船長は、多くの避難民が船と共に海中に沈み、波間に漂う者は機銃を浴びる凄惨な状況になってしまったためか、
『船長として生きのびて上陸することはできない』
と周囲の部下にいい、うずまく波間に消えたと生存者の証言が増毛町の記録にあったと、「樺太終戦史」 (昭和46年3月刊行樺太終戦史刊行会)に記載されています。
救命ボートに避難民と乗組員が一人でも多く乗せたい、という気持ちがあったのではないでしょうか。
あと数時間で小樽港に着くはずだったはずが、まさかこのような悲劇になってしまうとは。
本当に無念の極みであったと思います。
その翠川船長をはじめとする遭難者の慰霊祭を、増毛町は毎年行っています。
毎年7月22日に慰霊祭をおこなう増毛町

写真は先月22日、増毛町暑寒沢墓地「小笠原丸殉難者慰霊碑前」でおこなわれた慰霊祭の様子です。
町役場、NTT、遺族の方々が出席していました。
75年目となる慰霊祭は、コロナの影響もあってか出席者は少なく、用意されたイスに余裕がありました。
残念ではありますが、この状況下でも慰霊祭をおこなった増毛町の方々に感謝いたします。
今回は「小笠原丸」について報告しました。
次回は、あと2隻について調査報告いたします。(`・ω・´)ゞ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
