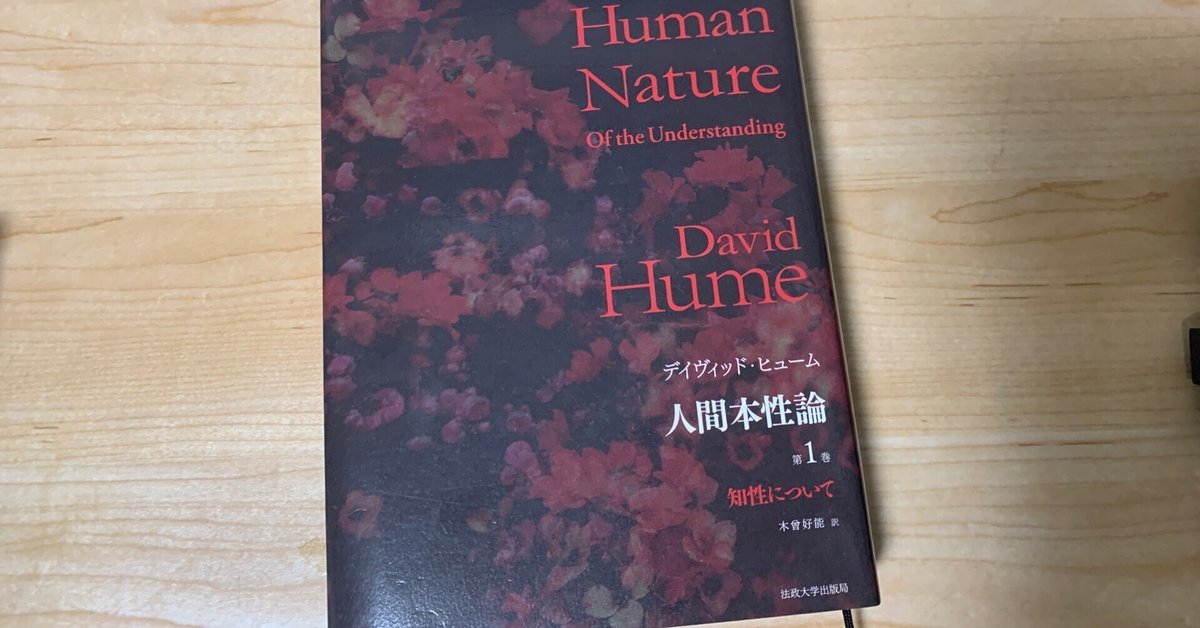
見えないものは無限に類似する~ヒュームの方法と普遍性の虚構
ヒューム『人間本性論』において、通常見過ごされがちだが体系全体にとって重要な示唆を含みうる箇所を取り上げる。西洋近世における経験論哲学が頂点を極めた本書(第1巻)のうち、第4部第3節「古代の哲学について」でのアリストテレス-スコラ的な実体概念への批判の箇所である。
すべては、われわれが対象を見る見方に依存する。われわれは、物体の感覚されない(気づかれない)変化をたどるときは、物体がすべて同じ実体あるいは本質をもつと想定する。物体の感覚される相違を考察するときには、各物体に、異なる実体と本質を帰するのである。そして、われわれは、対象を考察するこれらの方法の両方をみずからに許すために、すべての物体が実体と実体的形相とを同時にもつと想定するのである。
以下、本書(T)引用/参照箇所はビーチャム版の(巻.部.節.段落番号)を付す
この箇所は直接には、中世のアリストテレス-スコラ学的な実体と実体的形相の対概念を、虚偽の観念であると糾弾するものである。実体すなわち根源的な質料と、それを種的な本質を持つ特殊な在り方に規定する実体的形相という有名な対概念は、個体的対象が学説上の整合性を保つために導入された無内容の観念であると論証されている。こう批判しながらも、その批判自体を「でもそう考えるのもしょうがないよね、精神がそのように虚構してしまう自然的傾向と観念の間の引力があるわけだし!」と自らの体系への糧としていく方法それ自体が、ヒューム哲学全体に通底している包摂の力の凄みであるのだ。
さて、「人間精神は、見えない範囲にはすべて等しい本質を帰す」というこの主張が見据えている範囲は広大であり、卓越した洞察であったというのを語りたい。なお哲学史的考証は一切無し。
類似性による同一化の"見做し"
ことは「類似性」に関わる。これはヒューム知識論における中核概念であり、観念間の7つの哲学的関係における第一の関係[T1.1.5.3]であり、かつまた同時に自然的関係としての観念連合の3原理のひとつに数え上げられている[T1.1.4.1]。要は、反省的な考察にとってであれ人間本性に根ざす自然な傾向に見なしに沿ってであれ、ある観念と別のある観念が類似している(と看取する)ことが知識の絶対的基盤というわけだ。
そして、引用の箇所でもこの類似性が大いに影響力を振るう。ある対象の「変化」とは、類似性の破れである。とある"一つの対象"について精神に現れる知覚像が、いっときの知覚の中断の後に大きく変わってしまった場合、双方の知覚は類似性を持たず、それを"一つの対象"と呼ぶ根拠はもはやない。
しかし、それでもなお人間は、虚構してしまうのである。”一つの対象”と呼びうる一群の知覚が、様々な中断を超えて整合性を保つ場合[T1.4.2.19]、そして諸部分が同じ協働関係、同じ因果関係によって調律されている場合[T1.4.6.12]、それは"一つの対象"として物質界に実在すると見做される。これは数的に一である個物の固体化原理であるとともに、種的に一である"種"の定義においても同様である、とヒュームはこの箇所で考えている。ウシ1,ウシ2,….という各ウシ個体の間に我々が類似性を見るとき、それは「ウシ」種として同一の本性を持つものと捉えられ、他方では「ブタ」種にもまた別の本性が存する、という具合である。
知覚外での同一化の"見做し"
精神のこの原理に立脚したとき、問題は知覚に現れてこない部分である。このウシはどうやって"存在"しているのか?この"存在"の本性は?あるいは、「ウシ」種の本性はいかにして生じたのか?等々。
"存在"を例に取ろう。近世以前の哲学においては、あらゆる個別的な質料(=物質の素材)はある根源的な第一質料に基づいていると想定される。第一質料はあらゆる物理的存在者の存在を潜在的に支える"存在そのもの"として、第一原因としての神がそこに付与する形相とともに各々の存在者として成立している。火、水、土、空気といった四大元素が考えられるときでさえ、その各々は未分化な唯一の実体としての第一質料に"与っている"、と。当然ながら、こうした思索は感覚的印象に起源を持たない。知覚に決して現れない事柄についての普遍的な原理が、知覚的に検証不可能な形式で定義されている。
ここで注目すべきは、ただ一つの普遍的な根拠、絶対原因、唯一実体、etcが立てられてきた事実である。物理的な実在性以外においても、哲学史においては常に、統合的で単一的な原理が要請されてきた。
引用箇所でのヒュームの真の洞察とは、このように考えてしまう傾向が人間精神において類似しており、それ自体をひとつの精神の原理として立てることができるという点である。知覚可能なものどもと属性については相異なる形相が「種」として分化されていくが、知覚不可能な領域においては人間精神は単一的・同一的なものを好む。先に述べた"一つの対象"の固体化原理とここでの精神の動きは、いわばコインの裏表である。知覚できる類似性-相違は形相の分化(≒種的な固体化)の認識へと進むが、知覚できないものには無限の類似性を当てはめてしまう、と読み替えても許されるだろう。
ここから後世の科学的認識論なども経由しながら、森羅万象のカテゴリー的把握の発生論的な説明が為しうるかもしれない。ちなみに、『人性論 第1巻』第3部12~13節で論じられる蓋然的推論も、その逐次性と階層的発展性において上記と非常に似た認識の過程的性格を宿している。またどこかで論じるかもしれない。
学的認識"としての"虚構
歴史上の各々の哲学者たちの学説の間の類似性が意識されていることは推測するに容易い。引用箇所の次の節「当代の哲学について」で繰り広げられるロック批判も、彼の第一次性質が含む普遍的実在の概念が結局は空虚な観念であると示して終わっている。
神、物自体、絶対精神、記号論理、地平、無意識、そして一なる人間精神を特定の様式が"表出"しているとする構造主義まで含め、大半の学説がある種の普遍的一元論的構造を有している。またこれは原子論的唯物論にも妥当する。
主体が真理を直観する学派であれ客体に含まれる真理を抽象する学派であれ、古代ギリシアから近代まで連綿と続いた「普遍的/絶対的な真理への還元」という作業が堂々巡りの消耗戦であったと剔抉できるには、我々はアルチュセールやドゥルーズ、デリダの登場を待たなければならなかった。
しかしひょっとすると、ヒュームは18世紀のイギリスでただ一人、そのことに気づいていたのかもしれない。今では十分に理解されているように、この哲学者の経験論は単なるステレオタイプな知性への懐疑論ではない。その在処を巡って主体と客体との間をさまよい続ける"不可視の真理"という亡霊が人間精神に内在するバグに他ならないと引用箇所で喝破した功績は、もっと広く認められても良さそうに思えるのだが。
真理としての「穏健な懐疑」
人間理性の限界を超えた探求を決して望まず、それでいて現代心理学の始祖足りうる壮大な認識論の体系を構築したヒュームが、その理論的部分と相即的である探求方法を採っていたことは注目に値する。彼が「穏健な懐疑」と呼ぶのは、長い論証の緊張と矛盾を避けて精神が休らうところに思惟も休らうという在り方である。『人間本性論』の中でも、幾分抑制された筆致ではあるが数回にわたって「哲学という方法も自然本性の導きに従うべし」と提案している。バグをバグとして理解し、そのうち自然本性に端を発するものについては探求に境界線を引く。
哲学者としては、知覚に直接与えられているものに留まり、根源的な実体の仮構から身を引くこと。しかし日常的感覚としては、知覚に与えられているものが同時に根源的な実体の思いなしへと至りついてしまうことを良しとすること。これはヒュームにとって方法であると同時に人間本性がそれ以外ではありえない"真理"でもあった。普遍的・同一的という概念規定から徹底して距離を置いた彼にとって、起源不明の「自然」にどこまでも身を委ねることのみが唯一認めることの可能な"原則"だったのである。
のちに「存在とは差異である」と語り出すことになるドゥルーズが、まずヒューム哲学の読解からその思索を開始したことは、またひとつの留意すべき事実である。
頂いたサポートは、今後紹介する本の購入代金と、記事作成のやる気のガソリンとして使わせていただきます。
