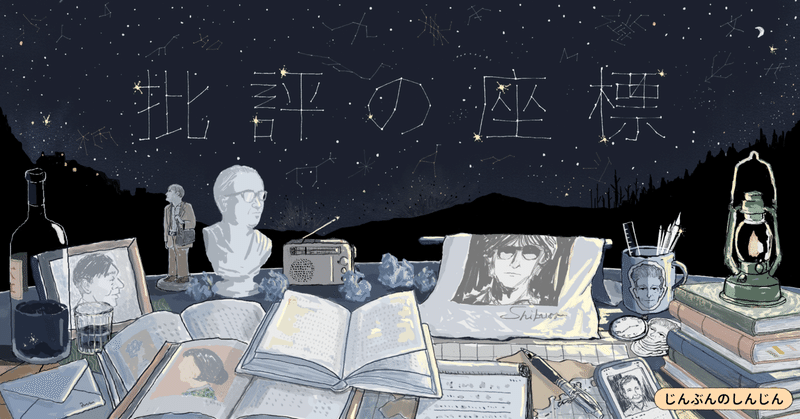
【批評の座標 第21回】悲しき革命家としての鹿島茂(つやちゃん)
19世紀のフランス文学を専門とする文芸評論家であり、古書コレクターとしても著名な鹿島茂。パリの風俗、美術と映画、ベンヤミンに吉本隆明と、多岐にわたって語る鹿島のその思考に一貫するものは何なのか。ラップミュージックをはじめとした音楽やファッション、モードなどを横断的に論じてきたつやちゃんが解き明かします。
――批評の地勢図を引き直す
悲しき革命家としての鹿島茂
つやちゃん
長いあいだ、私は早めに寝ることにしていた。ときには、蠟燭を消したとたん目がふさがり、「ああ眠るんだ」と考える暇さえないこともあった。しかし、そんなときでも、三十分もすると、もうそろそろ眠らなければならない時間だという思いが強くなり、目が覚めてしまうのだった。まだ手に持っているつもりの本をナイト・テーブルに置こうとして、蠟燭を吹き消そうとする。眠ろうとしながらも、さきほどまで読んでいた本の内容について思いを巡らすことを止めずにいると、その思いがすこし特異な様相を帯びてくる。作品に語られていたもの、つまり、教会や、四重奏や、フランソワ一世とカルル五世の抗争などに、私自身がなってしまうのだ。[1]
夢と現実が入り乱れる中うつらうつらとまどろむ、その深層の中、あるいは集団の夢の中で、ある一つの流れ――自動律のような――が生まれる。それは、私にも乗り移る。今どこにいるのだろうか。夢に巻き込まれ、どこまでも連れていかれてしまう私――眠っているのに運動しているかのような――。
*
鹿島茂(1949-)と聞いてまずイメージされるのは、彼が「具体」の人であるということだ。それはもちろん、世界でも有数の一九世紀フランス古書コレクターである事実から想起される。[2] 東京・神保町で、バルザックやユゴーらが当時のパリ風俗を描いた『Le Diable a Paris(パリの悪魔)』なる古書――木版画の押絵が描かれ、深緑色の革で装丁されていた――に出会った瞬間、その魅力に憑りつかれ収集家人生が始まってしまったというエピソードを鹿島は様々なところで語っている。
その衝撃的な遭逢以来、大量の書籍に淫し、紙に埋没し、ついには渋谷に〈NOEMA images STUDIO〉という書斎スタジオを、神保町に〈PASSAGE by ALL REVIEWS〉なる書店を立ち上げるまでに至った。デビュー作『馬車が買いたい!』は、まさにその鹿島の性質が凝縮された偏執的とも言える作品である。馬車という事例を題材に日常生活の細やかな場面ひとつひとつをありありと想像し得る次元にまで徹底的に具体として羅列し、註釈を連ねていく拡大鏡のような視力によって、一九世紀フランス文学を愉しむ下支えを作ったと言える。けれどもそれを、今で言うところのオタク気質なる烙印とともに処理したうえで、いわゆる博学インテリなどと形容して片づけてしまうのはいささか勿体ない。なぜなら鹿島は細部にこだわり存在そのものを凝視しながらも、極めて正統的な構造主義者として全体を見つめ、俯瞰的視野で数多の差異を採集してきたからである。つまりそれは、コレクターとしてその主従を逆立ちさせ、いわば差異を発見するために収集しているかのような素振りを見せる、ということなのだろうか。否、実はそういうわけでもないところが鹿島のつかめなさである。たとえば、『セーラー服とエッフェル塔』を見てみよう。
SMに、縄や紐などの道具で複雑に縛った「亀甲縛り」というジャンルがあることを知った鹿島は、欧米のSMを形作る主要な要素が「革」と「鞭」で成り立っている事実を対比させ、それらを日本の農耕文化と欧米の家畜文化という違いで説明する。いわゆる比較文化としての解説であればそれで十分かもしれない。けれども鹿島は、エロティシズムに深く関連する行為についてそういった味気ない説明に安住することへの不十分さを自覚したうえで、「SMというおよそ脳髄的なセックスを説明するのに、その上部構造(精神)を無視して下部構造(物質)のみこだわっている」と戒める。「SMとは、なによりもまず精神の動きであるという事実を確認しておかなければならない」というわけだが、だからこそもう一段階思考を深め、欧米の革や鞭によるSMを、馬と御者の支配 - 服従関係を反映したものとして捉える。
一方で、日本の亀甲縛りについては参照元が着物にあるという仮説を立ててみるものの、「亀甲縛りの縄は、着物の帯や伊達巻きとは辻褄があわない」と述べ、納得しない素振りを見せる。その後さまざま思考を彷徨った結果、最終的にたどりついたのは「米俵」であった。「女性のような円筒形の物体を力学的かつ合理的に縛る」方法は米俵にしかないこと。「縄でキリキリと締め上げられて、少し凹み、そのことで逆に丸みを帯びた」部分がエロティックであること。「縛ることで、本来はアモルフ(不定型)な米(女体)にきっちりとしたかたちを与え、モノとして客体化するという関係」であること――。[3]
「SMと米俵」というタイトルのこの論考はエッセイ調で書かれた数頁の短いものだが、大胆で軽やかな運動神経に鹿島の神髄が凝縮されている。マクロとミクロを行き来しながら国ごとのSMの違いに目を凝らし、〈関係-部分〉という両者が生み出す交通の循環に身体を投じつつも、その網目から浮き上がってくる空気を捉え、それが表象する具体にまで切り返していくアプローチ。いつも通り神田の街で古書収集に勤しんでいた際に緊縛写真集を見つけたことから始まったというこの論は、〈具体の収集→構造化→差異の発見→差異の表象による具体化〉という流れをたどっており、具体から始まり具体へ戻るという点において極めてアクロバティックだ。同様の芸当は膨大な著作の中に多く観察できるが、ベンヤミン主義者を自覚する鹿島が『『パサージュ論』熟読玩味』や『パリのパサージュ 過ぎ去った夢の痕跡』で展開した論はとりわけ重要である。
パサージュがいま、注目のスポットになっている理由、それは、過去の華やかな繁栄の記憶をとどめたまま長い時間隧道(タイム・トンネル)の中に入りこみ、そこから突如、現代に姿をあらわしたからである。過去の繁栄の時代、人々はパサージュで、未来へと向かう夢を見ていた。もちろん、一人一人は活発に活動し、目覚めていたが、その集団的な無意識の中では、人々は、自分たちの未来を投影した夢の中でまどろんでいたのである。[4]
ベンヤミンは、資本主義の黎明期に見られた集団的意識――まさに一九世紀パリのような――を「眠る巨人」、経済を「内臓感覚」、パサージュやモードなどをその「表現」としての「夢」と表象した。ベンヤミンのこうした認識について鹿島は、上部構造・下部構造というマルクス主義的な歴史的唯物論を貫きながらも視覚性・具象性を高めるために擬人的な性格の強いフロイトの夢理論を用い補強したのではないか、と推察する。と同時に、「眠る巨人」というイマジネールについて「一九世紀的な共同幻想とは異なって、個々の眠る人が集合的に集まってできあがったものではない」とし、「一九世紀のパリという巨人・巨女が眠りつづけるには夢を見ている必要があるが、その夢の供給源たる内臓、すなわち、経済はあくまで生きて活動していなければならず、理の当然として、経済を支える個人的意識は常に覚醒していることが要求され」、さらに「個人の意識が覚醒して経済を支えているからこそ、集団的意識という巨人・巨女は、それをパサージュやモードという夢に表現することで眠り続けることができる」とも述べる。
上記の通りパサージュの有するシュールレアリスム的な夢を指摘しつつ、鹿島が特に着目したのは、ベンヤミンが「眠る人」のシンボルを「衣服のひだ」に投影した箇所である。「子どもが(そして、成人した男がおぼろげな記憶の中で)、母親の衣服のすそにしがみついていたときに顔をうずめていたその古い衣服のひだのうちに見いだすもの――これこそが、本書が含んでいなければならないものなのである」という箇所を引き、「『パサージュ論』を『ひだ論』と呼んでもいっこうに差し支えない」と語る鹿島は、次のように断言する。
「眠る人」から出発したわれわれは、ようやくここにおいて「ひだ」にたどりついた。「ひだ」こそは、「眠る巨人」が「夢」として「表現」するほかなかったパサージュやモードといった原現象のシンボルにほかならない。というのも、それは「見たところどうでもいいような、今では失われたもろもろの形式」の典型だからである。[5]
「ひだ」に着目し、当時の時代背景を元に衣服の細部に目を凝らしたうえで着用している人物像までをも突き詰めていくさまは、まさしく具体へのこだわりを貫いてきた鹿島ならではの観察眼である。同時に、乳離れの遅い甘ったれの子供(ベンヤミン)が世紀末のブルジョワ女性の間で流行していた「上着付きドレス」を着た母親にまとわりつき、ドレスの上着のすそを握りしめスカート部分のギャザーに顔をうずめているときに見出した「なにものか」が何を表象しているのか紐解いていく仕草も、極めて特徴的だ。鹿島自身がデリダの「エクリチュール」の概念を参照に出しながら「本に書いてある内容よりもむしろ形のあるボディそれ自体の方が重要である」という倒錯した価値観を説明している通り[6]、それは古書収集を通してマテリアルへのフェティシズムを追求してきた彼ならではの着眼であって、「ひだ」という小さな具体性を巨大なテーマへと接続させる視点を駆使しているのである。
さて、いささか唐突かもしれないが、そのような“大きなテーマ”と“物質性の伴った具体”を接続させる身体感覚は、たとえば蓮實重彦による表層批評のような手つきを連想させもする。『監督 小津安二郎』に代表される通り、「物語」を生成する前の「行動」、はたまた「行動」を形成する前の「動作」や「身振り」や「形象」や「色彩」そのものという具体に着眼することで作品それ自体に肉薄していった蓮實だが、いわば細部の具体に対する観察が作品全体に通じていくという点においては共通しているだろう。
実は、卒論の主査をはじめとして、蓮實と鹿島は過去に師弟関係にあった。けれども当時、雑誌『エピステーメー』でのミシェル・フーコーへのインタビューやクリスチャン・メッツ著『映画と精神分析――想像的シニフィアン』(白水社)の翻訳を蓮實に依頼され進めていく中で、鹿島は自らの適性に対する違和に気づくことになる。デビュー作『馬車が買いたい!』の新版(二〇〇九年)の刊行に際して、執筆時のことを振り返りながら鹿島は次のように告白している。
すなわち、構造主義と記号学が全盛だった一九八一年に、私はクリスチャン・メッツ『映画と精神分析――想像的シニフィアン』の翻訳を同じ白水社から出したが、それによって逆に自分はこうした概念操作に向いていないことを決定的に悟ってしまい、その反動として、具体的なモノを求めて文学・歴史の大海に泳ぎ出すこととなったのである。そして、この「概念からモノへ」という内発的転換は、私が意識してか否かは別として、多くの同時代人の心の中に起こりつつあった変化とかなりの部分で同調していただろう。[7]
概念からモノへ、いわば構造から具体へという転換の中で、鹿島はエクリチュールにおいても意識の変化を見せる。当時の周囲が皆、蓮實の“宙吊り”や“運動”といった「常套句を無意識的に真似て、それをシニフィエと対置するように」なり、「その結果、みんなミニ蓮實重彦になっていってしまった」様子を批判的に受け止めながら[8]、蓮實の特徴とも言うべきシニフィアンへの固着から距離を置きはじめたのだ。いわばシニフィエとシニフィアン双方において、具体的なモノを平明なエクリチュールで語る方向へと舵を切っていったのである。
かくして、具体に始まり具体へと着地する思考の過程を、平易な語彙と装飾を排した文体で表現するという鹿島のスタイルが築かれることになるのだが、そういった態度が価値観のレベルで最も顕在化したのが『ドーダの人、小林秀雄』ではないか。ここでは、「どうだ、まいったか」の「どうだ」に虚栄心やマウンティングといった意を込めながら、小林の著作がどれも晦渋な文章や己の純度の高さを示す目的において「ドーダ」で成立している構造を暴いていく。結果、「批評とは他人の作品をダシに使ったドーダなのである」という痛烈な結論を小林にも自著にもぶつける鹿島だが、インテリによるドーダの意地の張り合いを冷静に分析する態度は、まさしくパフォーマティブな文体から距離を置いてきた鹿島ならではだろう。
そもそも鹿島は、家に一冊も本がなかったという貧乏な酒屋の息子として生まれ育ったという。古書収集に目覚めた時期も意外と遅く、三十代前半の時から始まったコレクションは、夥しい数の古書購入と幾度となく借金を重ねる生活へと転じていった。具体から始まり具体に着地するという点においてモノを操ることで思考を回転させていく鹿島だが、それはコレクターとして常に買い、読み、書き、また買い、という資本主義を回転させ続けるラットレースに身を投じ続けていることそのものにほかならない。そこでは、買うこと/読むこと/考えること/書くことがそれぞれ歯車として一体化しながら終わりなき旋回を繰り返している。
具体にまみれた自らの体験をもって歯車に身を投じる鹿島は、市場における資本主義ゲームの力学へと関心を向け、その後『小林一三 日本が生んだ偉大なる経営イノベーター』や『この人からはじまる』といった著書を記すことになる。エッセイ集『衝動買い日記』では、「買う/モノを手に入れる」ことの連続性に加えて、古書に数十万円を出すにもかかわらず電化製品に数千円を払うのも惜しむ貧乏性なアンバランスさを開示している。この鹿島の庶民感覚から提示される「具体的なモノ/平明なエクリチュール」は、大衆へとアクセスする共通の言語となり得ると同時に、蓮實が駆使していた概念言語と明確な距離を置くものにもなるだろう。具体を起点にした思考の旅を具体へと帰着させ続ける鹿島の歯車のような回転運動は、生活者の日常なるものにべったりと張りつきながら、この数十年間、ひと時も離れる素振りを見せない。
そこで見逃せないのが、鹿島の代表作の一つに数えられるであろう『吉本隆明1968』ではないか。小林多喜二『党生活者』をめぐり中野重治ら日本共産党の党員文学者と平野謙との間で起こったいわゆる「ハウスキーパー論争」において、吉本が社会常識に照らしたうえで世のインテリたちの不毛な論争をぶった切った点を、鹿島は高く評価する。曰く「マルクスやレーニンに学んだ唯物史観などではなく、むしろ、たくましい民衆の本音である」とのことだが、「大衆の原像」なるものを批評の倫理として持ち合わせていた吉本について、下層中産階級の出自を持つ人間が知的上昇を遂げて階級を離脱するときに訪れる根源的な「悲しみ」を真正面から見据えていたのではないか、とも推察するのだ。実際、鹿島は吉本の文章で個人的に一番好きだというくだり――近所のがき連中と遊んでいたある日、私塾に通うためにその輪を抜けてしまう場面――を引用し、「おそらく、吉本はこの階級離脱の瞬間の原体験の原感情をもとにして、大衆の原像を練り上げていったのだ」と想像する。[9]
同様に、冒頭での『セーラー服とエッフェル塔』の論理展開にならうならば、具体的な下部構造(物質)に長年憑りつかれてきた鹿島についてここでその上部構造(精神)を無視して論を進めるわけにはいかない。なぜなら、吉本に見出した「悲しみ」こそ、鹿島自身が持ち合わせてきたものだからである。果てしない資本主義の回転に身を投じながら吉本的な「大衆の原像」を忘れない鹿島は、たとえば『悪の引用句辞典』では「フランス文学者となったいまも私は「日本人」が「日本語」でフランス文学やフランス文化のことを語ったり書いたりするという浮ついた営為の意味を、かつての大衆たるもう一人の自分に問いかけずには一行も書くことはできないのだ」と内省する。[10] はたまた、『子供より古書が大事と思いたい』においては、古書収集という行為について次のように記すことで自身を批評にもさらす。
コレクターとは、常に「党」を開いていくことを運命づけられた悲しき永久革命者の別名にほかならない。[11]
コレクションには自動律のような意志があり、互いに無関係に存在していたアイテムが一か所に集められたとたん一種の共鳴現象を起こし、いわば「一枚岩であったはずの党の中に党内フラクションが形成される」ことでフラクションはフラクションでいることができず、一つの党として独立する。コレクションに内在する意志がコレクターに乗り移り次々に新しいコーパスを開いていくその様子を指して鹿島は「悲しき永久革命者」と形容するが、それはまさしく、もはや自らの意志を超えたところで日々古書を買うこと/読むこと/考えること/書くことを歯車として回し、特定の場所に安住することのない鹿島自身を指してもいるだろう。
収集家人生として常に「党」を開いていくこと、日常を回転させ具体から具体へ歯車をまわしていくこと、その果てしない運動性――何者かの力によって今いる地点から離れていかねばならないという半ば強制的に動き続ける状態にこそ、悲しみは宿っている。大衆主義を掲げ階級離脱の寂しさを背負い続けた吉本隆明とは異なる種類の革命家として、歯車を回し動き続けるという営みによって「具体的なモノ/平明なエクリチュール」を操作しながら延々と新たな構造を生成してきた鹿島。今いる地点に留まることはできない、あるいは運動し続けなければならない――悲しき革命は、収集家としての命が尽きるまで――否、尽きたあともその著作やコレクションの中で自動律が渦巻くことによって――永久に終わることなく続く。
[1] 鹿島茂、『「失われた時をもとめて」の完読をもとめて 「スワン家の方へ」精読』、PHP研究所、一七頁
[2] 鹿島茂、『新・増補新版 子供より古書が大事と思いたい』、青土社、一〇頁
[3] 鹿島茂、『セーラー服とエッフェル塔』、文春文庫、六~一〇頁
[4] 鹿島茂、『パリのパサージュ 過ぎ去った夢の痕跡』、中央文庫、ⅴ頁(まえがき)
[5] 鹿島茂、『『パサージュ論』熟読玩味』、青土社、一九一頁
[6] 鹿島茂、『多様性の時代を生きるための哲学』、祥伝社、三六頁
[7] 鹿島茂、『新版 馬車が買いたい!』、白水社、四頁
[8] 鹿島茂、『多様性の時代を生きるための哲学』、祥伝社、一〇二頁
[9] 鹿島茂、『新版 吉本隆明1968』、平凡社、三五八頁
[10] 鹿島茂、『悪の引用句事典――マキアヴェリ、シェイクスピア、吉本隆明かく語りき』、中公新書、二九七頁
[11] 鹿島茂、『新・増補新版 子供より古書が大事と思いたい』、青土社、二八二頁
人文書院関連書籍
その他関連書籍
著者プロフィール
つやちゃん 文筆家。音楽誌や文芸誌、ファッション誌などに寄稿。女性ラッパーの功績に光をあてた書籍『わたしはラップをやることに決めた フィメールラッパー批評原論』(DU BOOKS)が音楽本大賞2023最終候補に選出。その他、代表的な論考・エッセイに「シャネル、コラージュ、サンプリング 通俗と中毒のブランド」(『ユリイカ』2021年7月号)、「どうせ死ぬので。J-hyperpop/背徳グルメ/揺らぐ肉体[DEMO](DEAD*AT*18)」(『ユリイカ』2022年4月号)、「母音殺し、ピンポン玉のゆくえ――HipHopとTikTokの現場から」(『ユリイカ』2022年8月号)、「来たるべきフィメール/ラップ以後の可能性について」(『ユリイカ』2023年5月号)、「解体される柴田聡子――「雑感」論」(『ユリイカ』2024年3月号)、「BUCK-TICKにおけるSF的想像力――人間と機械、生と死の狭間で」(『SFマガジン』2024年4月号)など。
次回は3月前半更新予定です。鈴木亘さんが蓮實重彦を論じます。
*バナーデザイン 太田陽博(GACCOH)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
