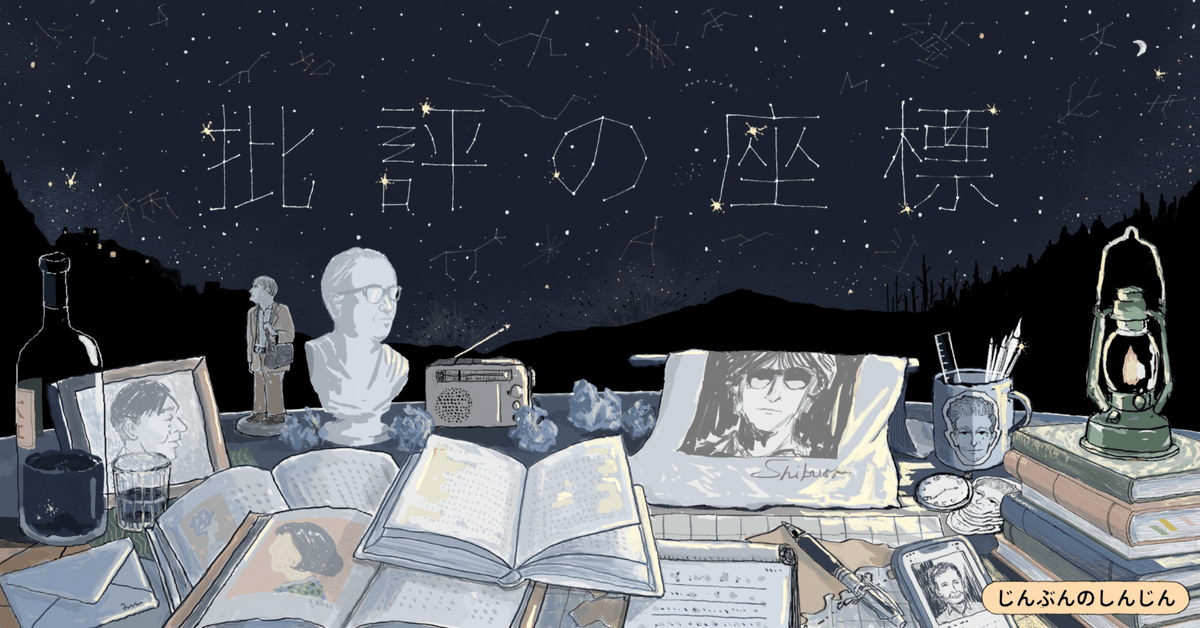
【批評の座標 第11回】セカイ創造者保田与重郎――詩・イロニー・日本(武久真士)
ドイツロマン派に親炙しながら日本の古典を論じ、近代批判を繰り広げた文芸評論家、保田与重郎。戦時下の若者に絶大な影響を与えたとされる保田を、その最大のキーワード「イロニー」から論じます。執筆者は、中原中也や三好達治などの近代詩の研究者であり、批評誌『近代体操』同人でもある武久真士です。
ーー批評の地勢図を引き直す
セカイ創造者保田与重郎
――詩・イロニー・日本
武久真士
1、「詩」と「詩的なもの」
今年(2023年)の7月に『ユリイカ』の大江健三郎特集が発売された。全650ページにおよぶこの雑誌を流し読みする中で、僕の印象に残ったのは大江の「詩」に関する話題だ。大江にとってどうやら詩とは、テロルと結びついたり散文的なリアリズムに対抗できたりするものらしい。なんだかひどくロマンチックな話じゃないだろうか。
同じようなことは三島由紀夫の小説を読むときにも感じる。三島の作品の中では、詩は美や純粋さの結晶のようなものとして語られる。三島は一時期詩人を目指していたらしいけれど、詩への屈折ゆえに詩を過剰に美化してしまうあたりは、病んだ愛だよな、と思う。
こうしたロマンチックな「詩」の観念は、それまでの詩史の流れから完全に外れたものだ。「詩」と言えば漢詩を指していた日本に西洋式のpoemが流入し、それをなんとか自国に取り入れようとしたのが明治期。当時の詩(新体詩)を読めば分かるが、このころの詩の言葉は生硬で意味が取りにくく、いかにもこなれていない感じがするものだった。そうした作品において「美」が自然なものでないのは当然で、人工的に西洋の文化を模倣しようとした時代性の典型をこの時期の詩に見ることができる。
大正に入ってようやく高村光太郎や萩原朔太郎が登場し、詩が口語で書かれるようになる。僕らが「詩」と聞いてぱっと思い浮かべるような行分け口語自由詩はおおよそこの時期に完成する。大正期の詩は基本的に抒情詩で、文字通り作者(作中主体)の情を抒べるものとして機能していた。この時期の詩においては、明治期のぎこちなさをある程度脱した自然な詩句を見出すことができる[1]。
昭和初期、モダニズムの時代に入ると「詩とは何か」ということが本格的に問われるようになる。特に『詩と詩論』の春山行夫らによる理論整備によって、作品と作者の内面とが切り離され、詩はより技術的に、理性のコントロールのもとで作られるべきだということになっていく。
もちろん距離感はあるものの、戦後詩はそうしたモダニズム詩の理念を引き継いでいる。単なる心情の表出としての詩があるのではなく、理論を踏まえた上で構築されるものとして詩があるのだという観念は、詩人たち全体に共有されたものだったと考えていい。戦争の時代、人々が「うた」の抒情に溺れ現実に対して批判的な想像力を向けられなくなったことへの反省と批判が戦後の詩を作ったのである。戦後詩は、ロマンチシズムとの戦いだった。
三島や大江におけるロマンチックな「詩」の観念は、そうした詩の歴史と逆行している。戦後文学者がロマンチックな「詩」に憧れるなんて! 小野十三郎や『荒地』が行った「うた」批判はどうなるというのだろう。
ただし、こうした詩に対するロマンチックなイメージは、なにも三島や大江だけのものではない。しばしば「自分には詩が読めないから……」と言う人がいるけれども、ここにだって詩へのロマンチシズムは潜んでいる。肩肘張らず、小説と同じ読み方を詩に適用してみればいいのである。詩作品の中には物語的なものも少なからずあるから、小説の読み方を訓練した人間ならば詩を読むこともそう難しくはないはずなのだ。
おそらく「詩の読み方がわからない」と言う人は、詩というなにか特別なジャンルがあり、それにはなにか特別な読み方が必要だと考えている。詩を神秘的に眼差している。ある特殊な技能を持った司祭だけが、天から詩の言葉を受け取り人々に伝えることができるというわけだ。もちろんそんなことはないのだけれど。
この小説ならざるもの、小説の剰余としての「詩」の問題は、日本の批評の問題でもある。中原中也と富永太郎を友人に持ちながら、小林秀雄は詩について満足に語り得なかった。まして戦後批評はどうだろう。一部の例外を除いて、詩は見事に黙殺されている。欧米の批評家がリルケやマラルメを無視することは困難だが、日本の批評家が入沢康夫や吉増剛造を素通りすることは珍しくもなんともない。
つまり戦後以降、詩は実際に詩人たちが積み上げている「詩」と、なにやら神秘的で超越的な「詩的なもの」とに分裂してしまっているのだ。どこからそんなことが起こってしまったのだろう。戦前にもある程度その気配はあったけれども、これはやはり戦後に前景化する事態だと思う。芥川龍之介の言う「詩的精神」だって、萩原朔太郎や佐藤春夫との交流を外しては考えられないではないか。
そこには複合的な背景があるのだろう。たとえば戦後における文壇と詩壇との分裂は、おそらく戦前よりも大きくなっている。しかし、戦中の読書経験も無視することはできない。戦中盛んに活動し、その上で「詩的なもの」のイメージを形成できるほどの影響力を持った文学者と言えば彼しかいない。三島も親炙した日本浪曼派、その中心である保田与重郎(1910-1981)だ。
[1]もちろんこの「自然さ」は一種の擬制である。詳しくは「詩の語りについての試論――中原中也の詩を中心に――」(『論潮』2020・7)という文章で論じたことがあるので、よかったらどうぞ。
本連載は現在書籍化を企画しており、今年11月に刊行予定です。
ぜひ続きは書籍でお楽しみください。
人文書院関連書籍
その他関連書籍
執筆者プロフィール
武久真士(たけひさ・まこと)日本文学研究者。専門は日本近代詩、特に1930年代の定型詩。具体的には、中原中也や三好達治などについて論じています。同人誌『近代体操』のメンバー。定期的にnoteを更新しているので、たくさん読んでください→
次回は10月前半更新予定です。平坂純一さんが西部邁を論じます。
*バナーデザイン 太田陽博(GACCOH)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
