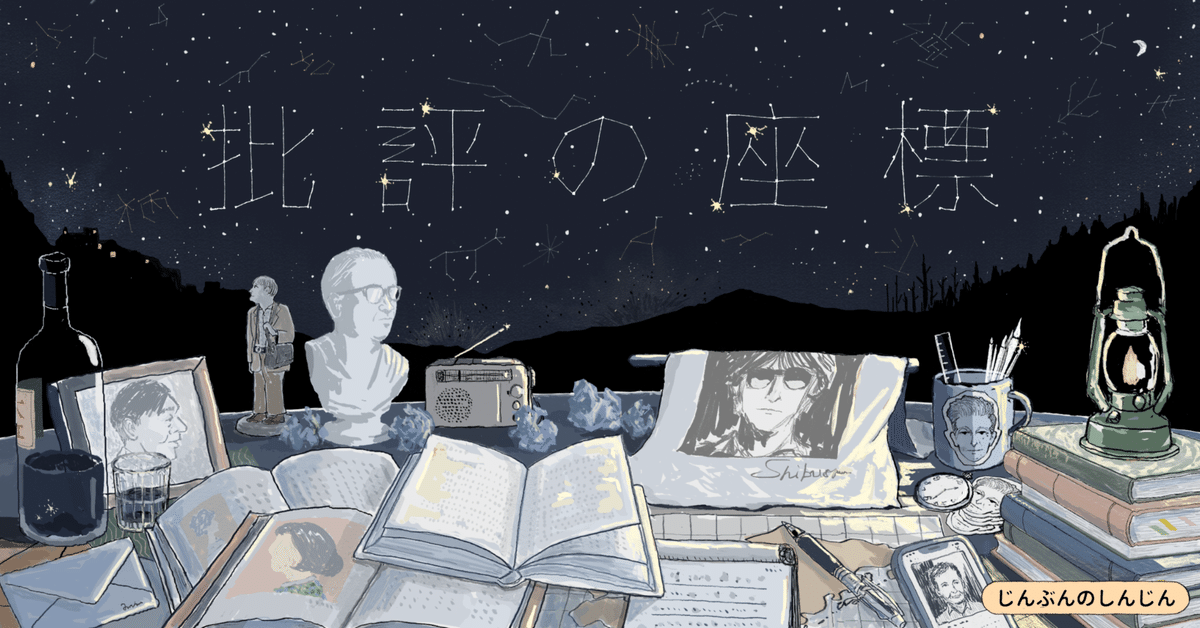
【批評の座標 第5回】「外」へと向かい自壊する不可能な運動──絓秀実『小説的強度』を読む(韻踏み夫)
近年のBLM(ブラック・ライヴズ・マター)からも垣間見えるように、ヒップホップと人種差別への抗議が連動する現代において、その批評や研究から出発し、『日本語ラップ名盤100』(イースト・プレス)を上梓した韻踏み夫。第5回では、現代史の転回点である一九六八年論の代表的な批評家・絓秀実を取り上げ、その主著『小説的強度』から、いま必要な理論的展開を描きだします。
――批評の地勢図を引き直す
「外」へと向かい自壊する不可能な運動
――絓秀実『小説的強度』を読む
韻踏み夫
「しばしば私にはヘーゲルが自明であるかのように思える。だが、この自明は担うには重い」(『有罪者』)。なぜ今日──今日においてもなお──バタイユの最良の読者たちであってさえ、ヘーゲルの自明性をいともたやすく担えるほど軽いものであるかのように考える人々の列に加えられてしまうのだろうか。(……)過小評価され軽々しく扱われたヘーゲル主義はかくして、その歴史的支配をひたすら拡大していくであろう。(……)ヘーゲルの自明性は、それがついにその全重量をもってのしかかるようなとき、かつてないほど軽く思えるのである。
1.
二〇一〇年代後半以降、絓秀実(1949-)という批評家への再評価が進んでいるかに見える。その要因は主に二つ挙げられるだろう。第一に、日本を代表する「六八年」の革命的批評家として。その評価は、絓の代表作と見なされているはずの『革命的な、あまりに革命的な』(2003)――二〇一八年に文庫化された――を筆頭に、『1968年』(2006)、共著を含めれば『LEFT ALONE 〜 持続するニューレフトの「68年革命」』(2005)、『対論 1968』(2022)などによって形作られている。次いで、絓はとりわけ二〇一〇年代以降顕著になったポリティカル・コレクトネス(PC)問題においても強く参照される批評家でもある。それは、『「超」言葉狩り宣言』(1994)や『「超」言葉狩り論争』(1995)の時期におけるジャーナリスティックな著作群によってである[2]が、同時に「華青闘告発」を大きく取り上げ、六八年の現代的帰結がPCであるとする六八年論とも密接に連関してもいる。つまり、絓は現在では、六八年と差別論の批評家として受け取られていると見てよいだろう。
しかしながら、初期――と便宜的に言っておく――の絓秀実とは他の何よりもまず、「昭和十年前後」(≒一九三〇年代)の批評家であった。デビュー作『花田清輝――砂のペルソナ』(1982)から始まり、『複製の廃墟』(1986)、『探偵のクリティック――昭和文学の臨界 絓秀実評論集 〈昭和〉のクリティック』(1988)を経て『小説的強度』(1990)に至る過程において、絓はこの、「昭和十年前後」という一時期に並々ならぬ関心を寄せ続けたのだった[3]――この点事情はきわめて複雑であるかに思われるが、ひとつだけ言っておくならば、共産党壊滅後の「昭和十年前後」の「文芸復興期」は、絓が文章を書き始めたポスト六八年の「大衆消費社会」の時代と、革命運動の退潮期という点で共通の時代性を有しているということは最低限指摘できる。
『小説的強度』は絓の最高傑作としてきわめて高い評価を受け続けてきた主著と見做しうるものであり、そこでは批評史上においても稀有な理論的達成が見られるということも疑いない。「初期」の絓は「昭和十年前後」を思考するなかで、大きく言って、「表象=代行機能の失調」(『複製の廃墟』)と「自己意識」(『探偵のクリティック』)という二つの問題に行きついていた――政治性の観点からのみ補足的に言えば、「表象=代行機能の失調」とは前衛(党)の不可能性の問題でもあり、「自己意識」とは転向の問題でもある。つまりこれらは、文学的な問題のみには収まらないものであり、ここに「後期」の絓の革命をめぐる思考との連続性を認めることは可能である。『小説的強度』はいわば、そこで得られた理論的精華を凝縮し、かつそれを縦横無尽に駆使してきわめて広大な知の領域――文学理論、哲学、経済学、政治思想、民俗学、人類学……――を横断する一冊であり、そのあまりにダイナミックで大胆な横断的記述こそ、本書の「批評的な、あまりに批評的な」魅力となっていることはたしかだ。他方、「あとがき」では、その理論的相貌に反して意外にもこれが「「時評」集として読まれれば、これに過ぎる喜びはない」[4]とも述べられている。それは、本書が書かれた同時代の状況、すなわちポストモダンの「大衆消費社会」への批判的分析という、具体性=実践性の色を強く持った書であることをも示している――実際、批評とは、理論と具体=実践のあいだで引き裂かれつつもがくことでなくてなんであろうか?このことを銘記したうえで、しかしここでは、あえてその具体性を捨象し、その理論的な側面にのみ焦点を当て、複雑かつ大胆に適用、変奏、連結される概念群の布置と運動の、ごく骨子のみを素描してみることにする。それは、その理論が、今度はわれわれの、そして未来の時代状況のただなかにおける具体性=実践性の闘争に再び移植され、用いられるべきだと考えるからである。
[1] 『エクリチュールと差異』、合田正人・谷口博史訳、法政大学出版局、二〇一三年
[2] それは近年出版されたPC論である、千葉雅也、二村ヒトシ、柴田英里『欲望会議 「超」ポリコレ宣言』(二〇一八年)、綿野恵太『「差別はいけない」とみんないうけれど。』(二〇一九年)などに引き継がれていると言える。
[3] 「昭和十年前後」という用語はもともと平野謙によるもの。それへのこだわりについて、絓自身こう述べている。「ベンヤミンの「第二帝政期」狂いには及びもつくまいが、実際に生きたわけでもない一九三〇年代を、あたかも自分の同時代であるかのように思い込んでしまう感性は、『花田清輝――砂のペルソナ』を書きつつあった時以来、日に日に強まっているようだ。一九三〇年代、あるいは平野謙の言う「昭和十年前後」における、言葉の表象(再現)機能の失調といった出来事が、現代の、大衆消費社会とも呼ばれる「複製技術時代」を生きる者にとって、他人事とは思えないのである。ベンヤミンが――あるいはバタイユやブランショが──生きた一九三〇年代が、私にとっての「第二帝政期」のように感じられる。」(『複製の廃墟』、福武書店、一九八六年、二八〇頁)
[4] 『小説的強度』、福武書店、一九九〇年
本連載は現在書籍化を企画しており、今年11月に刊行予定です。
ぜひ続きは書籍でお楽しみください。
人文書院関連書籍
その他関連書籍
執筆者プロフィール
韻踏み夫(いんふみお)ライター/批評家。94年。福岡県。著書『日本語ラップ名盤100』(イースト・プレス、2022年)。連載「耳ヲ貸スベキ――日本語ラップ批評の論点――」(2021年~2022年、文学+WEB版)、「フーズ・ワールド・イズ・ディス――ヒップホップと現代世界――」(2023年~、文学+WEB版)。論考「ライマーズ・ディライト」(『ユリイカ』2016年6月号)、「渡部直己の「弟子」としての体験を書き記す」(『対抗言論 反ヘイトのための交差路 3号』、2023年)、「ひとつではないヒップホップの性」(『ユリイカ』2023年5月号)など。
*バナーデザイン 太田陽博(GACCOH)
