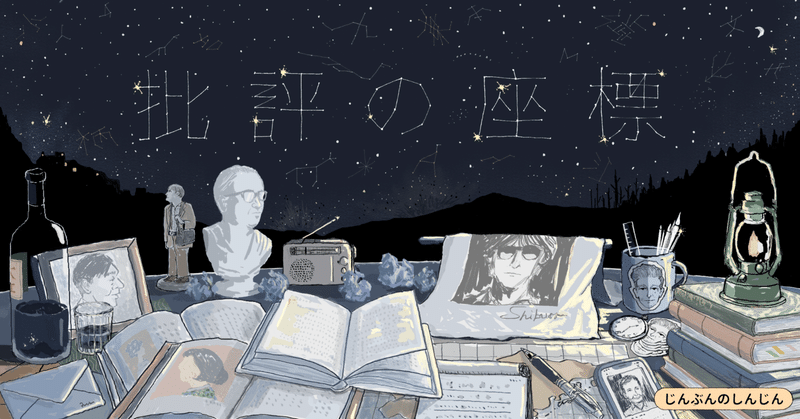
【批評の座標 第16回】「孤児」よ、「痛み」をうめいて叫べ――『鬼滅の刃』と木村敏における自己と時間の再生(角野桃花)
精神病理学の第一人者であり、人間関係の「あいだ」を探る古典的著作『自己・あいだ・時間』等で独自の哲学・人間学を展開した精神科医・木村敏。今回は木村の理論を応用して漫画『鬼滅の刃』を読み解き、「キャラ」や「成熟」と対決しながら、現代社会を生きる「痛み」を掘り下げます。執筆者は、本論考がデビュー作となる角野桃花です。
――批評の地勢図を引き直す
「孤児」よ、「痛み」をうめいて叫べ
――『鬼滅の刃』と木村敏における自己と時間の再生
角野桃花
序章.木村敏の再生――主体の獲得という扉を開くために
生まれてこのかた、「痛み」で叫ぼうとする口を世界によって塞がれている気がした。
世界は、“正しい人間”は「痛み」を感じてはいけないと私に教え諭す。この「痛み」を知ってほしいと、他者に手を伸ばそうとするなら、人間関係を円滑に進めるとかいう「キャラ」が私にまとわりつく。傷つくかもしれないから、あるいは傷つけてしまうかもしれないから、本当の自分を出してはいけない緊張感のもとで笑って脂汗を流しながら、互いの「キャラ」の手触りを言葉で確かめるのを繰り返す。
そうやって生きる中で、時間が止まっているような感覚に陥った。斎藤環が『キャラクター精神分析』で論じたように、「キャラ」は人間関係におけるコミュニケーションを通じて何度も言葉で確認されることで固定される[1]。つまり、「キャラ」からはあらゆる変化の機会が奪われている。「キャラ」を使う人間関係の空間では変化しない“いま”が茫漠と広がり、まろびでた自分の臓器を引きずって歩くように「痛み」をひとりで抱えて数十年の余生をどうにかしのいで生きていかないといけないという絶望があった。
そのような存在の目に、江藤淳の論じた「成熟」というテーマは救世主のように映った。「成熟」が可能なら、この「痛み」も過去のものになって時間の停滞も何とかできるのではないかと思った。
そして、どうやら「成熟」することは「治者」になることらしかった。すべてを受け入れる母性の領域で守られる個人が社会に踏み出して他者と遭遇し、社会と守るべき他者に責任を持つ「治者」になることが「成熟」なのだと。
しかし、それも蓋を開けたら幻想だった。提唱者の江藤淳からこれまで、大塚英志、杉田俊介など多くの論者が「成熟」について語っているが、多くは「成熟」が不可能だと自覚しつつ、社会への自らの姿勢を考えて苦しんでいた。
それに、私を取り囲んで他者と隔絶するのは母性ではなく「キャラ」だった。「成熟」するには他者と遭遇して傷つくのが必要だと知っても、「痛み」はリアルなのに「キャラ」が私にまとわりつくために世界に他者の気配はなかった。さらに、「成熟」の理論で「治者」になれるかもしれない息子とは違い、私はいつか大地のような母性を持つことになる娘だった。
だから、自分の運命を心底呪っていた。固定化された「キャラ」に支配された人間関係、他者がいなくても効率的に個人の感情を充たせる物語に溢れた世界や、その流れに乗れる人達を横目に、他者との共感を求めずにいられなかった。成長しない「キャラ」と共に永遠に「痛い」まま、ひとりぼっちで外側だけ年老いていきたくなどなかった。
その呪いを断つ可能性を見出だせたのが木村敏(1931-2021)の理論だった。木村は精神科医としての臨床経験に基づき、人間存在について現象学的な哲学探究を行った人物である。
彼は時間のあり方とは自己のあり方だと論じる。己にとって絶対的な「いま」という時間の一点が近接未来へ跳躍していくのを可能にするのは、非自己との遭遇による自己の生成の繰り返しだということだ。その非自己と遭遇する場として、木村は自他未分化の領域である自己と他者との「あいだ」を挙げている。
このような自他未分化の「あいだ」は、すでに輪郭が明瞭な「キャラ」を言葉という記号で相互に強化する空間とは全く違う。江藤淳が『成熟と喪失』で「生きつづけるためには、人は何らかの「役割」を引受けなければならない」[2]と述べたように、「成熟」のために人間を「父」や「母」、守るべき存在などと役割的に区分する江藤の理論は、どの役割にも属さない私に議論を許さない。だが、役割に拠らない自己と非自己という木村の区分なら、「成熟」のもとではあぶれ者の私にも他者との遭遇を可能にしてくれる。
自他未分化の「あいだ」から「痛み」を己のものとして拾い上げられるなら「キャラ」の世界から抜け出せる。その生き方を描いたのが吾峠呼世晴作の『鬼滅の刃』だった。主人公の竈門炭治郎が鬼にされた妹を人間に戻すため、仲間の鬼殺隊と共に圧倒的な身体能力と再生力を持つ鬼を倒す物語だ。
この鬼こそ、私が抜け出すべき「キャラ」だと確信した。鬼を最も特徴づけるのは不老不死という特性だ。鬼は人間ならば致命傷でも瞬く間に治癒できる。そして、鬼が自身の傷を治す表情からは痛みは全く感じ取れず、麻痺している様子がうかがえる。
さらに、鬼のほとんどは壮絶な過去を持つが、彼らはその記憶も痛みすらも忘却している。第10巻の第81話で堕姫が「昔のことなんか覚えちゃいないわ アタシは今鬼なんだから関係ないわよ」と開き直った通りだ。
それなのに鬼は、痛ましい過去に起因する暴力を繰り返す。猗窩座は大切な人達を妬む者たちによって彼らを毒という卑怯な手で殺され、彼らを守れなかった自責の念により、弱者は卑怯で見ているだけで虫酸が走ると言って強さをひたすら求めていく。何も与えられずに取り立てられ続けた妓夫太郎と堕姫は、幸せな他人を許さず報復していく。
鬼は傷ついてもすぐに治癒でき、過去に居直り、永遠の時間を不変の状態で麻痺したまま生きる。この様は、他者との遭遇で傷つくこともなく、時間が止まった「キャラ」の特性を捉えている。
その一方で、鬼とは対照的に人間は脆く、その人間が生きる刹那的な時間性が強調される。それは第8巻の第63話で、隊士の煉獄杏寿郎(※「煉」の『鬼滅の刃』内での正しい表記は糸偏に東。以降同様。)が猗窩座の「お前も鬼にならないか」という誘いを断るときに言った印象的なセリフ――「老いることも死ぬことも 人間という儚い生き物の美しさだ 老いるからこそ死ぬからこそ堪らなく愛おしく尊いのだ」――からよくわかる。
今、『鬼滅の刃』を通し、木村敏による時間と自己のあり方の理論をいま再生できたなら、「キャラ」が自己を覆い尽くす世界で止まった時間を動かせると思った。「痛み」でうずくまる私を「成熟」とは別の方法で前に押し出してくれる――大人にしてくれる。「成熟」の理論が目標とする、社会で責任を取る主体ではなく、隣に生きる他者を生々しく感じて躍動する時間を生きる主体になりたい。母性ではなく「キャラ」という卵の殻を破って生まれ出ることで。
その方法とは、「成熟」を前提に回復して乗り越えるべきものとして据えられる「トラウマ」とは異なり、今まさに感じている「痛み」によって絶対的で刹那的なこの一瞬を駆動するものだ。
1.木村敏と『鬼滅の刃』の刹那的な時間感覚
木村は『自己・あいだ・時間』で、統合失調症と鬱病患者の臨床経験に基づき、自己のあり方を論じているが、双方の患者が持つ異なる時間感覚と他者との関わり方の二つに着目している[3]。
統合失調症患者は、他者のいる世界でいかに自己を確立させるかに関心があり、常に未来を先取りする未来志向的な時間感覚を持つと木村は分析し、これを「アンテ・フェストゥム」つまり「前夜祭」的な時間感覚と名付けた。一方で、鬱病患者は今まで人間関係において積み上げてきた自分の固定的な役割、役割アイデンティティを維持することを重要視し、それを崩壊させる失敗を犯したとき、取り返しがつかないという「後の祭り」のような時間感覚、つまり「ポスト・フェストゥム」的な時間感覚を持つ、としている。
このように木村は、自己にとって生々しく感じられる「いま」というこの絶対的な一点が存在し、それが近接未来へ跳躍していくのを可能にするような、絶対的な一点の「いま」の前後にある「以後」と「以前」の観念を時間感覚とする。未来のとある一点に向かって直線が伸び、自動的に流れ落ちていくものとして時間を捉えていない。
この木村の時間感覚は、『鬼滅の刃』に出てくる刹那的な時間感覚と重なる。それはたとえば第7巻の第57話、人間に強制的に夢を見せる術を持つ鬼の魘夢との戦いで描かれる。魘夢の攻撃で炭治郎達は眠らされるが、炭治郎は失われた家族団欒の夢を見る。途中でそれが夢だと気づいた炭治郎は「ここに居たいなあ ずっと 振り返って戻りたいなあ 本当なら ずっとこうして暮らせていたはずなんだ ここで」とありえたかもしれない世界にしがみつく姿勢を見せる。
しかし、彼は「でももう俺は失った!! 戻ることはできない!!」と夢を振り切る。そして、彼は魘夢が見せる夢からの覚醒方法に気づく。それは夢の中で己の首を切り落とし、自害することだった。魘夢に昏倒させられ夢の世界に行くたび、炭治郎はそこで何度も自害をして現実に戻って戦い続ける。取り戻せない過去やありえたかもしれない世界線に執着するのではなく、それらを振り切って現実においてこの己が知覚できる一瞬を生きねばならないという時間感覚が描かれる。
そして木村は、このような時間は自己の生成によって発生するとしている。自己が自己であるためには、非自己との遭遇が必要不可欠だ。「人は自分ひとりだけで「自己」であることはできない」のである[4]。他者との関係の中で――木村の言葉を引用すると他者との「あいだ」において――自己は自己自身になる。非自己を意識しない人間は以下のような未分化の状態となり、時間感覚を持てない。
自己がまだ他者を抵抗として意識していないときには、世界は等質で透明な持続の底に沈んだままである。この状態では自己はまだ自己自身の存在にも気づいていない[5]。
ところが、反省的自己意識によって何かしらの対象が非自己として意識されると、自己は収斂点としてのノエマ的自己――何かを自己と同一だと認識できる拠り所となる自己[6]――に立ち返る。つまり、「有限な身体、有限な意識によって限定された有限な個別的自己」[7]のことだ。
非自己と遭遇するたびにノエマ的自己という一点に立ち返る、それを反復的に繰り返す運動とノエマ的自己は弁証法的関係にある。この反復運動によって都度立ち上がる、いわば述語的な知覚が自己として限定されたものを木村はノエシス的自己(所記的自己)とする。そして、この動的な弁証法的関係そのものが自己の正体だと述べる。
そして、この関係は自己自身の内部では完結しない。「自己自身の外部、自己と自己ならざるものとのあいだにおいて成立する」のだ[8]。そして、この動きを絶えず繰り返すことこそ時間の原形式であると指摘する。これがなければ人間は「以後」と「以前」の観念を持てない。
「いま」の瞬間における他者や事物との出会いにおいて、「つぎ」の動きを読むことによって「これまで」の自己の同一性を維持するという営みの中でのみ、時間が生まれ、歴史が成立する。[9]
つまり、時間は非自己があってこそ成立するのだ。
また、木村はノエシス的自己が自己として認識される以前の自発性、つまり自他が未分離の純粋な自発性を「ノエシス的自発性」とし、以下のようにも述べる。
ノエシス的自発性はみずからの産出するノエマ的自己によって触発されて、ノエシス的自己として自己自身を限定するが、この差異の自己限定が根源的な時間を生み出す原構造ともなる。われわれにとって時間というようなものがそもそも可能になるのは、われわれの存在がこのようにして差異の自己限定という構造をもっているからである。[10]
このように、非自己との遭遇によって時間の原形式が生まれ、同時に唯一無二の一点である自己が生成される木村の理論と、木村と同じ時間感覚を実践する『鬼滅の刃』という作品から、「キャラ」によって他者に手を伸ばす術を奪われ、「成熟」も不可能な者が止まった時間を破る生き方を見て取ることができないか。
まずは、『鬼滅の刃』に登場する子どもがいかに「成熟」とは違う「大人のなりかた」を模索しているかを見せたい。
2.「成熟」の不可能性――どうしてそんなに「成熟」にこだわっているのですか?
「成熟」の理論での「父」や「母」に属さず、「父」にもなれない立場から見ると、「成熟」というテーマへの執着は、失われた時間感覚を回復したいという願望に由来するのではないかと思う。
柄谷行人などの例外を除き「成熟」を語る論者達は、時代を下るほど「成熟」が成立しないことを前提とする。彼らは成熟の不可能性を嘆きつつ、社会への責任の取り方を考えている。
たとえば、大塚英志は『江藤淳と少女フェミニズム的戦後――サブカルチャー文学論序章』で、「大文字の歴史」と自己の間に生じる「軋み」の中で求められた仮構を江藤は否定しなかったと述べ、他者と出会う「公共」という場を生むように論壇の「成熟」を促す[11]。
あるいは、杉田俊介は『ジャパニメーションの成熟と喪失』で、主体的な責任を負わずに狭い自己世界に没入し、「成熟」できなかった男性を「オトナコドモ」と呼び、彼らができうる新しい「成熟」の仕方を提示した[12]。それは「大人」や「父」として、過去の歴史や伝統を受け継ぎつつ、批判も承知の上で、社会システムに抗って若者や子ども達に思想、制度や態度を示す道だ。それがぎりぎり可能な責任の取り方だと。
その背景には「キャラ」による時間の停滞があると思う。斎藤が定義したように「キャラ」は時間的、空間的な差異を問わずに、これとあれは同じだと伝える記号だ[13]。人間が時間の影響を受けない「キャラ」に頼って生きるならば、時間感覚が薄れるのは必然だ。時間が流れる感覚、かけがえのない現在という一点の感覚を取り戻そうと「成熟」というテーマを手放せずにいるのではないか。
というのも、『鬼滅の刃』において「キャラ」が人間を脅かすような強大な鬼として描かれているからだ。序章でも述べたように、鬼の不老不死という特性は、他者との遭遇で傷つくことも成長することもないため起きる「キャラ」による時間の停滞を捉えている。
しかし、多くの論者が「成熟」について頭を悩ませる一方で『鬼滅の刃』は、「治者」になることの不可能性を描いて「成熟」というテーマをしりぞけている。
飲んだくれで寝ているばかりの煉獄杏寿郎の父、かつて彼は鬼殺隊の中枢の「柱」であり、熱心に自分の子ども達に剣術を教えて導いていた「父」という「治者」だった。しかし、彼は何もできない自分に打ちのめされて鬼殺隊を突然やめてしまう。受け継いできた歴代の「炎柱」の手記も破き、剣術の指導もやめた。
だが、息子の煉獄杏寿郎は三巻しかない「炎の呼吸の“指南書”」を一人で読み込んで鍛錬を続け、鬼殺隊の中枢である「柱」になったのだ。
何より、主人公の炭治郎は鬼に親を殺されても、その復讐を果たすことより、妹を人間に戻すため、そして自分と同じような目に遭う人をなくすために戦っていた。炭治郎は親に置き去りにされた意識も持たなければ、親を乗り越えようという意識も持っていない。
このように『鬼滅の刃』はたった一人で「父」でも「母」でもない「大人」になろうとする子どもを描いている。『鬼滅の刃』は「父」や「母」が重大なモチーフとなる「成熟」というテーマを突き放す。このような子ども達を「孤児」と呼ばずに何と呼べばいいのだろうか。
「成熟」という幻影を傍目に、「孤児」達は「父」や「母」、ひいては社会から遠く離れた場所で、自分達なりの「大人のなりかた」を模索している。
それこそ、時間の流れを許さない「キャラ」の世界から生まれ出て、すぐ隣にいる他者に手を伸ばし、刹那的で絶対的なこの一点という時間感覚を取り戻すことだ。
この「孤児」の「大人のなりかた」を差し出すために、木村敏による時間についての論に「キャラ」を位置づけておく必要がある。
3.「キャラ」による時間の停滞――木村敏の理論において
改めて、木村敏による時間の定義を振り返っておこう。非自己が意識されるたび、自己はノエマ的自己に立ち返る。この反復的な運動とノエマ的自己は弁証法的関係にあり、これが根源的な自己、つまりノエシス的自己(所記的自己)となり、自己が近接未来へと飛び移っていく時間の原形式そのものでもあった。
このノエマ的自己とは能記的自己のことであり、つまりこれまでの自分が集積された結果、自分とはこうであると言葉にできるもののことである。役割アイデンティティとほぼ等しい記述可能な「キャラ」で人間関係を構築する時代では、このノエマ的自己を自己と認識してしまいがちだが、これは自明に与えられた絶対的な一点ではない。
「キャラ」は時間の流れを許さない。人間関係において、特に若者は「いじられキャラ」、「おたくキャラ」、「天然キャラ」といった「キャラ」を演じ分け、他者との円滑なコミュニケーションを図る[14]。その「キャラ」はコミュニケーションを通じて何度も記述されることで確認され、固定される。変化の機会は奪われており、維持されるのは再帰的な同一性のみだ。
この「キャラ」の特徴は、木村の定義した鬱病をもたらす性格、前鬱病性格に見られる。前鬱病者は多くの場合、社交的な印象を与える。しかし、彼らにとって他者とは、遭遇することで自己規定の運動を生み出す存在ではなく、自己の役割アイデンティティの構成要素にすぎない。
この他者はけっして病者の自己世界から独立して考えられる共同世界的な個人としての他者ではなく、むしろ病者の自己世界のなかで重要な位置を占めている人物、いいかえれば、病者の自己世界を構成しているもろもろの意味関連のうち、とくに重きをなしているひとつの意味対象であるにすぎない。[15]
「キャラ」の大きな特徴である、人間関係における相互記述で維持される点も、以下の前鬱病性格の記述によってしっかりと捉えられている。木村は前鬱病性格の中に「キャラ」の予兆を見て取っていた。
自己の役割が役割的に出会われた他者の存在を通じて補強され支持されるという、相互肯定的、相互依存的関係であり、しかも、この「肯定の肯定」という相互性は、役割的自己の側のみから一方的に設定された仮想的相互性であるにすぎない。[16]
そして、「キャラ」の持つ記述可能性や同一性の維持機能は、木村が述べたノエマ的自己(能記的自己)の特徴と合致する。さらに、前鬱病性格の役割アイデンティティによる自己規定とは、ノエマ的自己に自己が占拠されることでもあった。
この相互記述による自己規定が、時間の起源からかけ離れているのは言うまでもない。「キャラ」の支配する世界で他者は非自己として立ち上がることはなく、役割アイデンティティを補強するために己が所有する対象でしかない。「キャラ」は社交しながらも自閉し、のっぺりとした時空を生きる存在なのだ。
この社交性と自閉傾向が両立する矛盾について、木村は以下のように述べていた。
役割交換は、もちろん共同体の共通項に十分な顧慮を払うことを前提としなければ成立しない。或る意味では、彼らの「自己」すらも、そういった「共通項」の性格を帯びて外化されている。共有の時間と無縁な自己自身の時熟といえるようなものを、彼らは持ちえない。[17]
それでは、どうやったら時間感覚の失われた状態から「大人になる」ことができるのか。木村は前鬱病性格が築き上げた役割アイデンティティに致命的な傷がつくことで、取り返しがつかないという「ポスト・フェストゥム」的な時間感覚がもたらされる、と述べていた。私たちはその道をあえて行くしかないのか。あるいは、「成熟」の不可能性を知りながらも議論を続けるのだろうか。
いや、「大人になる」ことはできる。その絶望を打ち破る方法は『鬼滅の刃』における「孤児」の生き方に描かれている。どうかその生き様を見ていただきたく、次章で『鬼滅の刃』で描かれる「痛み」について論じたい。
4.「キャラ」、「痛み」、うめき声
「痛み」が「キャラ」の世界を破る契機になる。だが、「キャラ」と「痛み」は真逆に位置するのでは、という指摘もあるだろう。たしかに、「キャラ」は主体がそれになることで「本当の自分」を守り、苦痛を排除するための記号だ。しかし、その苦痛とは具体的にどの場面におけるものなのかは慎重に扱わなければならない。
ここで、土井隆義の『キャラ化する/される子どもたち』での詳細な定義を見てみよう[18]。土井は「キャラ」を人間関係における「外キャラ」と対自における「内キャラ」の二つに分類し、対他的場面において人間関係の潤滑剤の役割を担うのが「外キャラ」、対自的場面において「誰が誰でも構わない」という存在論的な不安をぬぐうための不変の拠り所としての役割を負うのが「内キャラ」としている[19]。
つまり、以下のことが言える。「外キャラ」は人間関係における苦痛を排除する。「内キャラ」は確固たる自分がないままに、自分の輪郭が曖昧になるような何だって構わないという相対主義にさらされる不安を取り除く。
では、逆に「なんでよりにもよって自分が」という、自分の輪郭がはっきりする固有性を帯びた「痛み」を経験したとき、「キャラ」によって生きる人間はどうなるだろう。土井が同著内で指摘するように、自分の絶対な拠り所としてトラウマを求める人が多いことを踏まえると、「内キャラ」として「痛み」が固着してしまうことは容易に想像できる。いわば「不幸キャラ」である。
この状態に陥った人間はどうなるか。言語化によって、彼らの「痛み」ですらも「不幸キャラ」というノエマ的自己の強化に使われてしまう。もちろん、「外キャラ」のために非自己と遭遇しないので、木村が定義した自己規定の反復運動そのものとしての自己は生成されない。「キャラ」というノエマ的自己単体では時間感覚が生まれない以上、ずっと「痛み」が現在“いま”のまま、過去のものにすることもできずに生きていく。
しかし、その運命から逃れる方法がある。それは言語化される前に言葉にならない声で「痛み」をうめいて表出することだ。
「キャラ」の厄介なところは記述可能性だ。つまり、言葉や語りは「キャラ」の強化に使われかねない。そして、能記的なノエマ的自己によって自己が覆いつくされるあり方をしていると、何か外界に触発されても瞬く間に言葉で記号化されてしまう。それが「キャラ」による生き方だ。
では、言葉が「キャラ」という記号に還元されるなら、言葉を使わない回路を見出すしかない。だが、言葉を使わずに他者と遭遇する手立ては「キャラ」の世界で確立するのは難しい。
ただ、「痛み」は言語を介さずに身体に突き刺さる。そして、自他の境目がない世界では「痛み」が感じられないように、「痛み」は非自己があってこそ成立するものだ。「痛み」は唯一残された他者との遭遇のサインである。
そして、木村の定義した自己のあり方を回復するために、「キャラ」で覆われた自己が経験した「痛み」を過去のものとして位置づけるには、感じたその痛みが「キャラ」の隘路に陥って記号として回収される前に、「痛い」とうめき声を上げるしかない。そのために、嬉しいとか悲しいとか言葉にされうる感情以前の情動、ノエシス的自発性に立ち返るのだ。ほぼ死に絶えた自己規定と時間の回路を生き返らせるのには、痛いときのうめき声しか活路がない。
5.「孤児」のうめき声を聞く
この自己の取り戻し方は、「孤児」が鬼と戦う『鬼滅の刃』で描かれる。
鬼を討伐する組織の鬼殺隊に入った隊士は親を亡くしたか、親に捨てられたかで文字通りの孤児として描写されることが多い。たとえ親がいても、煉獄杏寿郎の父のように機能していないことが多い。
さらに前に述べた通り、その「孤児」が戦う鬼は、他者と遭遇して傷つくこともなく、時間の原形式も生まない「キャラ」そのものだ。
その鬼は自らの不老不死性を、作品を通して人間に対し勝ち誇る。だが、鬼に対して煉獄杏寿郎が「老いることも死ぬことも 人間という儚い生き物の美しさだ 老いるからこそ死ぬからこそ堪らなく愛おしく尊いのだ」と言ったように、「孤児」は「キャラ」をしりぞける。
そして、その「孤児」は、鬼とは対照的に「痛み」にもだえる存在である。同時に、失われた身体機能や命が戻らない苛烈な不可逆性を生きる。戦いの中で「孤児」は「痛み」を感じればうめき声を繰り返しあげる。うめき声を上げながら自己を回復していく。
たとえば時透無一郎は、第14巻の第121話の戦闘中に血みどろになっている最中、鬼に双子の兄を殺され、自分も殺されかけた凄惨な過去を振り返ったあと以下のように心でつぶやく。
お館様の仰った通りだ “確固たる自分”があれば 両の足を 力一杯 踏ん張れる 自分が何者なのかわかれば 迷いも 戸惑いも 焦燥も 消え失せ 振り下ろされる刃から 逃れられる鬼はいない
「痛み」でうめくことで彼は「“確固たる自分”」を取り戻している。これは凄惨な過去を思い出したとも捉えられるが、無一郎はこの痛ましい経験を経て、定期的に記憶を失っている描写がされているのが重要だ。記憶が積み上がらないのは、ノエマ的自己が更新されていない、つまりノエマ的自己への反復運動がされていないということだ。この戦いで「“確固たる自分”」も記憶のつながりも取り戻した無一郎は、「痛み」によるうめきで自己と時間を回復できたと言える。
そして、無一郎は「あの煮え滾る怒りを思い出せ」と、ノエシス的自発性としての「痛み」をノエシス的自己として認識する、「痛み」を自分の「怒り」と認められるようになる。
また、以下のように、第1巻の第1話で冨岡義勇が炭治郎に言ったセリフも「怒り」について「原動力になる」と言っていた。
怒れ 許せないという強く純粋な怒りは 手足を動かすための揺るぎない原動力になる 脆弱な覚悟では 妹を守ることも治すことも 家族の仇を討つこともできない
このセリフが示唆するのは、「痛み」を叫ぶことで時間を駆動させて「大人になる」可能性にほかならない。
終章.「孤児」よ、「痛み」をうめいて叫べ
今回の議論では、「成熟」にこだわる大人から遠く離れた場所で「孤児」ができうる「大人のなりかた」、つまり「キャラ」によって停止した時間の流れと自己を取り戻す方法を論じた。
このしんとした他者の気配がない構造のなかで、「成熟」することもできない世界で、「孤児」は「痛み」によってうめくことを見出したのだ。このうめきによって、非自己という存在を自覚し、それによってノエマ的自己への反復運動とノエシス的自己を蘇らせるのだ。
これが「孤児」の「大人のなりかた」だ。
ただ、『鬼滅の刃』で鬼は討伐できたものの、数多くの隊士が亡くなった、「大人になれていない」という指摘もあるだろう。しかし、「痛み」を叫ぶキャラクターの死を苛烈に描くことで、虚構の世界に没入して生きてはいけないと『鬼滅の刃』は読者を押し戻し、あくまでも現実の世界で「大人になる」ように語りかけている。第16巻、第137話で鬼殺隊の当主である産屋敷が鬼の始祖である無惨に対し「この千年間 鬼殺隊は無くならなかった 可哀想な子供たちは大勢死んだが 決して無くならなかった」と語ったように、作中のキャラクターは死んでも『鬼滅の刃』の「キャラ」から抜け出す「大人のなりかた」は無効にならない。
だから「孤児」達よ、生きる世界で「痛み」でうめいて叫びちらせ。己の体が言葉で凍り付き、その手に血が通わなくなる前に、静まり返った己の世界に裂け目を入れろ。
[1] 斎藤環『キャラクター精神分析――マンガ・文学・日本人』、筑摩書房、二〇一四年、四八頁。
[2] 江藤淳『成熟と喪失――”母”の崩壊』、講談社、一九九三年、五八頁。
[3] 木村敏『自己・あいだ・時間 現象学的精神病理学』、筑摩書房、二〇〇六年、一九二頁。
[4] 木村敏『分裂病と他者』、筑摩書房、二〇〇七年、二七九頁。
[5] 木村敏『分裂病と他者』、筑摩書房、二〇〇七年、四三頁。
[6] 木村敏『分裂病と他者』、筑摩書房、二〇〇七年、一〇六、一〇七頁。
[7] 木村敏『自己・あいだ・時間 現象学的精神病理学』、筑摩書房、二〇〇六年、二四七頁。
[8] 木村敏『分裂病と他者』、筑摩書房、二〇〇七年、四四頁。
[9] 木村敏『分裂病と他者』、筑摩書房、二〇〇七年、四七頁。
[10] 木村敏『自己・あいだ・時間 現象学的精神病理学』、筑摩書房、二〇〇六年、二五二頁。
[11] 大塚英志『江藤淳と少女フェミニズム的戦後――サブカルチャー文学論序章』、筑摩書房、二〇〇一年。
[12] 杉田俊介『ジャパニメーションの成熟と喪失――宮崎駿とその子どもたち』、大月書店、二〇二一年。二五九頁。
[13] 斎藤環『キャラクター精神分析――マンガ・文学・日本人』、筑摩書房、二〇一四年、二八五頁。
[14] 斎藤環『キャラクター精神分析――マンガ・文学・日本人』、筑摩書房、二〇一四年、二三頁。
[15] 木村敏『自己・あいだ・時間 現象学的精神病理学』、筑摩書房、二〇〇六年、三五〜三六頁。
[16] 木村敏『自己・あいだ・時間 現象学的精神病理学』、筑摩書房、二〇〇六年、八九頁。
[17] 木村敏『自己・あいだ・時間 現象学的精神病理学』、筑摩書房、二〇〇六年、二三五頁。
[18] 土井隆義『キャラ化する/される子どもたち――排除型社会における新たな人間像』、岩波書店、二〇〇九年。
[19] 土井隆義『キャラ化する/される子どもたち――排除型社会における新たな人間像』、岩波書店、二〇〇九年、三三頁。
人文書院関連書籍
その他関連書籍
執筆者プロフィール
角野桃花(すみの・とうか)1996年生まれ。東京大学教養学部卒業。2021すばるクリティーク賞最終候補(「サブカルチャーの〈娘〉とその〈母〉と〈父〉――『キルラキル』を通じて)。第65回群像新人評論賞最終候補(「「ママ」をもう一度人間にするために――『約束のネバーランド』と『かか』において」)。X:@taohuasumino
次回は12月後半更新予定です。古木獠さんが山口昌男を論じます。
*バナーデザイン 太田陽博(GACCOH)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
