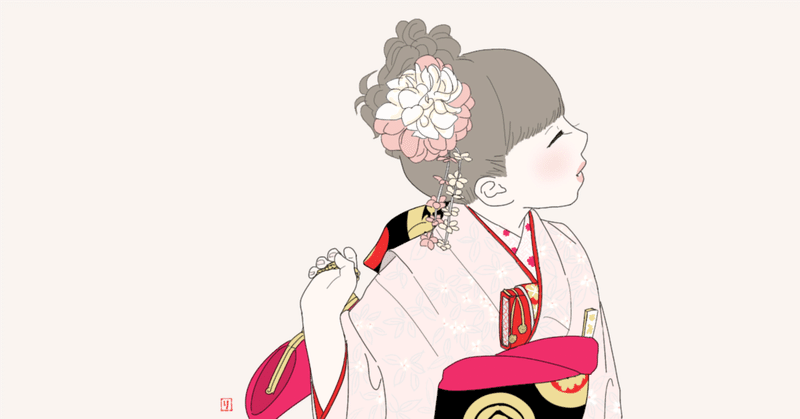
日本舞踊キャラバン公演
2023年8月よりスタートした日本舞踊キャラバン公演
全11箇所で2024年1月まで行われる。
日本舞踊キャラバン公演へようこそ!
本公演は日本の美と粋がつまった
伝統芸能「日本舞踊」の魅力を
存分にご堪能いただく企画です
第一線で活躍中の舞踊家・演奏家による
珠玉の舞台をぜひお楽しみください
すでに以下の3公演が終了している。
山形公演(8月20日)
鹿児島公演( 9月13日)
徳島公演(9月20日)
次回は11月5日富山公演がひかえている。
続いて同月23日には高知公演
3日後の26日北海道公演
12月に入って
京都公演(3日)
宮城公演(15日)
沖縄公演(24日)
年明けの1月に
山梨公演(13日)
そして最後を飾る大阪公演(28日)が行われる。
本公演の魅力は、全国各地に一流の日本舞踊家が集うこと、そして各地で活躍する舞踊家が出演する点である。
また、演目も比較的見やすい作品が揃っている。
2023年 日本舞踊 が国の重要無形文化財に指定された。
これまで多数の日本舞踊家が人間国宝に指定されてきただけに、日本舞踊として未だに指定されていなかったことに驚かされる。
ただ、重要無形文化財の仕組みを考えると、日本舞踊として指定することの難しさも否定はできない。
演劇,音楽,工芸技術,その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上または芸術上価値の高いものを「無形文化財」という。無形文化財は,人間の「わざ」そのものであり,具体的にはそのわざを体得した個人または個人の集団によって体現される。
国は,無形文化財のうち重要なものを重要無形文化財に指定し,同時に,これらのわざを高度に体現しているものを保持者または保持団体に認定し,我が国の伝統的なわざの継承を図っている。保持者等の認定には「各個認定」,「総合認定」,「保持団体認定」の3方式がとられている。
重要無形文化財の保持のため,国は,各個認定の保持者(いわゆる「人間国宝」)に対し特別助成金(年額200万円)を交付しているほか,保持団体,地方公共団体等の行う伝承者養成事業,公開事業に対しその経費の一部を助成している。このほか,国立劇場においては,能楽,文楽,歌舞伎,演芸等の芸能に関して,それぞれの後継者養成のための研修事業等を行っている。
人間国宝の仕組みから考えると、重要無形文化財の理解がしやすい。
人形浄瑠璃 文楽を例にみてみる。
まず人形浄瑠璃 文楽は
所属する機関又は団体:人形浄瑠璃文楽座
重要無形文化財(芸能)昭和30年5月12日指定
として総合認定されている。
そして、その構成員(技能保持者)として、人形浄瑠璃文楽座に所属する技芸員が認定される。
構成員として認定されるには、その団体内によって基準がある。
能楽界の場合であれば、総合認定をうけると、社団法人日本能楽会(能楽協会とは別の団体)の構成員になる。
さて、人間国宝であるが、これは重要無形文化財保持者。各個認定ということである。
文楽の場合、
人形浄瑠璃文楽 太夫
人形浄瑠璃文楽 三味線
人形浄瑠璃文楽 人形
であるが、各個認定の場合、保持者の逝去により指定が解除される場合がある。逆に同じ分野で先に認定者がいる場合は、現保持者に加えての追加認定という形になる。
日本舞踊はこれまで、歌舞伎舞踊・上方舞・京舞が各個認定されてきた。
しかし文楽と違い、日本舞踊という芸能としてそれぞれが同じ舞台に立つということは、ほぼないのである。
ここで、浮かびあがるのは、そもそも日本舞踊とは何であるかという問題である。日本舞踊には多くの流派があり、それぞれに特色がある。これは流派を問わず、各時代の名人が各個認定されていることからも明らかである。
日本舞踊は、主に江戸・東京の歌舞伎において初演された歌舞伎舞踊や、京阪において主に座敷舞として発展した京舞及び上方舞から構成された、我が国の伝統的な舞踊である。演目としては18世紀以降につくられた歌舞伎舞踊が多くの割合を占めるが、劇場振付師や舞踊師匠たちを中心に伝承されてきた点、また衣裳付の上演のみならず、本衣裳を排し、より踊り手の技芸に表現の重点をおいた、素踊りも重要な上演形態となっている点など、歌舞伎を離れた独自の歴史や芸術上の表現を有している。上演にあたっては、立方とともに、長唄、常磐津節、清元節、義太夫節、地歌など演奏を受け持つ地方も不可欠な構成要素となっており、御祝儀物と呼ばれる素踊りの演目群に代表されるように、演奏用に開曲された曲に振付を加えた演目も、主要な伝承曲となっている。
歴史的には、例えば江戸時代初期の女歌舞伎のように、我が国には女性芸能者による舞踊の系譜があったが、日本舞踊においても、歌舞伎の舞踊(所作事)、あるいは京阪の舞を歌舞伎役者や劇場振付師等から習得し、一般の子女に伝承する役割を果たした舞踊師匠には、女性が多く活躍した。そして劇場振付師、所作事に秀でた歌舞伎役者、大名家等へ出入りして歌舞伎や舞踊を見せた女性たちである御狂言師を母胎とし、西川流、藤間流、坂東流、花柳流、若柳流等の流派も誕生するようになった。京阪では井上流、山村流、吉村流等が生まれている。明治以降になると、家元・宗家や舞踊師匠のなかからは、教授活動のみならず舞踊家として劇場の舞台に立つ人々も現れ、日本舞踊はより芸術的に洗練されて現在に至る。
以上のように、日本舞踊は、芸術上特に価値が高く、芸能史上特に重要な地位を占めるものである。
(重要無形文化財の指定及び保持者の認定等)解説より
今回、日本舞踊を総合認定するに当たって、日本舞踊を支える演奏家もその構成員(日本舞踊保存会会員)とすることで、日本舞踊とはなにか?という問題にひとつの答えが出ることとなった。
無形文化財として認定されたことで、これまで、流派という単位で活動していた日本舞踊界のなかに、構成員として追加認定されるという新たなステップが誕生した。
キャラバン公演は流派をこえて、演目を出す傾向にあり、
これからの日本舞踊界は流派をこえて支え合うという形が主流になっていくと思われるが、流派の特色もぜひ大いにアピールして欲しいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
