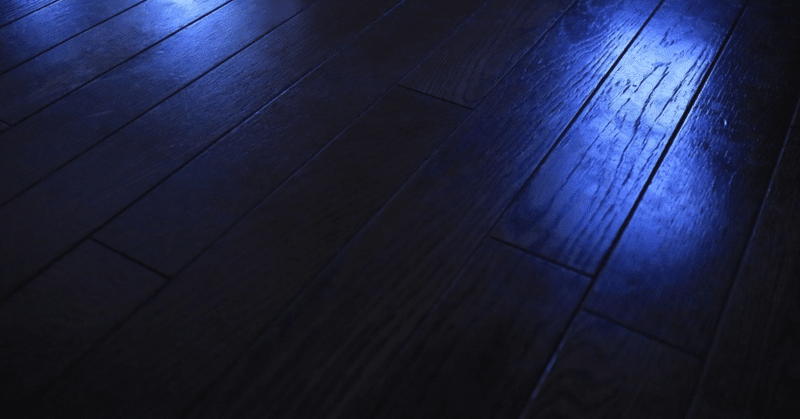
加害者と被害者の境界 ―― ゴンサロ・M・タヴァレス『エルサレム』書評
去年くらいから、アジア系住民が道端やバスの車内でいきなり突き飛ばされたり殴られたりする事件をしばしば目にするようになったせいで、カナダで生活している私は、自分が外国にいて異質な存在であり、脆くて危うい弱者になり得るのだということを意識するようになった。レイシズムは不正義だ、けしからんと怒っていられるうちは、まだ他人事だったけれども、いま被害に遭っているのは私と似たような人。被害者と自分を隔てるものが何もないところで起きる暴力には、もう恐怖しかない。
ゴンサロ・M・タヴァレス著『エルサレム』は、狂気と恐怖をテーマにした小説である。舞台は、名前の明かされないある街。早朝、まだ日が昇る前の暗闇の時間だ。主な登場人物たちはみな、それぞれの理由で街をさまよっている。エルンストは、窓から飛び降りて死のうとしていたが、そこへ電話が鳴る。ミリアは、医者にも見放された病気で激しい痛みに襲われ、教会に向かうが、夜明け前のため中に入れてもらえない。ミリアの前夫で、医者であり、今は落ちぶれてしまった学者のテオドールは、障害を抱えた十二歳の息子カースを置いて、娼婦を求め外に出る。夜中に目覚めたカースも、父を捜しに出ていく。元軍人のヒンネルクは、ある衝動にかられて銃を持って街を徘徊している。ヒンネルクに献身的な娼婦ハンナは、商売のため街に出ている。彼らが何者で、どんな事情があったのか、少しずつしか明かされないので、先が読みたくなる。
ミリアの前夫テオドールは、長年、恐怖の歴史を研究していて、彼が読んでいる本や、後に出版される彼の論文を引用するという形で、恐怖のさまざまな定義と概念が述べられる。時間を前後しながら挟まれる、登場人物たちが交差する場面は、それぞれがまるで恐怖の標本の役割を果たしているかのように、たいがい誰かがひどい目に遭っている。それも、いつも決まった誰かなのではない。被害者が別の場面では加害者になったり、加害者が被害者になっていたりする。この境目のなさが、なんとも嫌な感じがした。
「私の関心は、弱者を前にした際、強者がいかにふるまうかに尽きる」
作中のテオドールによる「著書」冒頭の一節である(第二十七章「テオドール」)。被害者を善良、加害者を邪悪と考えるのは誤りで、それは単に〈可能性〉の問題だとテオドールは論じる。他者と比べて力を持たない弱者も、力を強化したり、さらに弱い者に近づいたりすれば、強者になれるという。
ひと目で外国人とわかる顔だとか、精神の病気を抱えているとか。あるいはただ年を取っているとか、満員電車で唯一の赤ちゃん連れだとか、ツイッターで炎上したとか。理由は何でも、ちょっかい出してもこちらに反撃できないだろう、誰もとがめないだろう、ばれないだろう、ばれても問題にならないだろう、という安心感というか、「力」を感じると、人はいがいとすんなり加害におよぶのだ。特に、相手を自分と同列に考えていないときは。現実の世界にあてはまることがありすぎて、とても怖かった。
翻訳者向け書評講座
書評家の豊崎由美さんを講師にお迎えした、翻訳者向け書評講座。自分と異なる読み方を否定しない、というお言葉を大切に持ち帰りました。
上の書評にいただいた評価は「素直さはいい」。ふつうなら「とても怖かった」なんて書評で書かないそうです。とにかく作法がわからなかったので、手が届く範囲のことだけ、武器を一個で書いたらこうなってしまったのですが、手元しか見えていないと、他の書評を評価するときにも、自分の読みと合っているかどうかを中心に考えてしまい、読み方が浅くなると反省しました。
こう書くものだ、だけでなく、こう読んだほうがためになるを知って欲しい、という冒頭のお話どおり、書き方だけでなく読み方についても示唆に満ちた講座でした。
#エルサレム #ゴンサロ #タヴァレス #木下眞穂 #書評講座 #翻訳者向け書評講座
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
