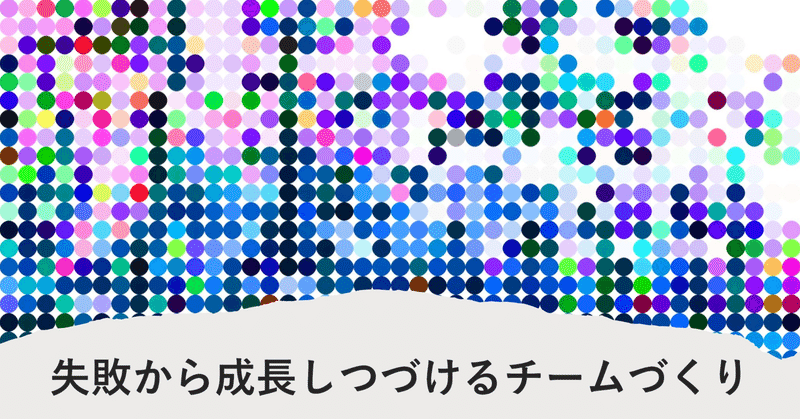
失敗から成長しつづけるチームづくり
以前に「失敗を上手に定義して振り返る」という記事を書きましたが、
それが個人に対する話であったのに対し、
今回はチーム全体に対する話になります。
↓以前の記事はコチラ
失敗をきちんと定義して共有する
どんな小さな活動であっても、その活動を行った後には結果が出てくると思います。
その結果に対して、ある人は「成功した」と言い、ある人は「失敗だった」と言う、
そんな状況になれば、チーム内で意見がぶつかってしまい、その先の大事な話すべてがSTOPしてしまい、次に進めなくなってしまう要因になります。
だからこそ、その活動を起こす前に、
「どうなることが成功で、どうなることが失敗なのか?」
という定義をあらかじめチームで決めて共有しておくことが非常に大事かと思います。
#M-1もそう
#漫才の定義とは
たとえば、
・事業を行えば、その売上が〇〇円以上得ることを目標にします!とか、
・寄附を募れば、集まった寄附額が〇〇円以上を目指します!とか、
そういった金額の多寡を基準に成功か失敗かの判断をする場合もあれば、
・寄附金の総額よりも、〇〇人以上の支援をいただけなかったら失敗と判断する、
といったような、支援者(ファン)の数を基準に成功か失敗かの判断をする場合もあります。
これはどちらが良いとか悪いとかではなく、
そのチームが大事にしていることを、チーム内でしっかりと話し合い共通認識(共通のものさし)を持って活動していくことが重要かと思います。
振り返り反省し次に活かす
私の場合は、仮説検証を繰り返す理学療法をやってきた経験からか、
ある活動をした後の結果としてデータが1つも取れなかったら失敗、とみなすことが多いです。
#リハをやっても良くならない場合もある
#行ってきた過程も大事
つまり、
ある1つのことをしたけれど、良かったのか悪かったのか、結局のところなんかよく分からなかったね、という状態になることを失敗とすることにしています。
単に、悪くなったから失敗、としているわけではなく、悪い結果として得られたのであれば、次からはそれを避けるようにすれば良いので、それはそれでとても貴重な成功につながる経験だったと捉えるようにしています。
なんか有名な実業家の人たちも同じようなことを言っていたりしますが、
めちゃくちゃ共感出来ます。
理学療法士の臨床思考過程が、この発想に繋がったと認識しています。
絶対に失敗する、ということを避ける
よく、成功するためにはどうすれば良いか?と聞かれたりしますが、
成功するかどうかはTPOによって様々なので、実際よく分からないと言うことになります。
#それが分かれば神様
#みんなやってる
しかし、その反対に、失敗しないためにはどうすれば良いか?を考えた際には、絶対にしてはいけないということがある程度共通して出てくるかと思います。
その中の1つとして、先ほどのことがあると思っていて、
チームとしてきちんと失敗を定義しておいて、いざそうなった際にはチーム全体で振り返ることが出来て、その後の対策をチーム全体で考え実行に移すことが出来る、
そういった失敗から学び、次に活かし続けることが出来るチームは、おのずと成功へ向かっていくのではないかと思います。
あとはこのサイクル。そして継続。
