
ゆるぼうvol.020 災害ボランティアってどんなことをするの(竜巻・噴火災害編)【Youth for the Resilience】
災害ボランティアってどんなことをするのシリーズのおそらくラストになる今回は、竜巻(突風・強風)や噴火により被害を受けたときのことについてご紹介します。
➖竜巻による被害について
気象庁によると、日本では、年間平均25個程度の竜巻の発生が確認されています(海上竜巻を除く)。一つの市町村でみれば90年に一度程度の極めて稀な現象です。

具体的な被害としては、屋根が飛ばされてしまったり、窓ガラスが割れ、家の中がぐちゃぐちゃになってしまったりします。
屋外にあるものも、大きなものであれば車が横転したりすることもあります。
➖竜巻災害時のボランティア活動について
竜巻災害に対して人手が求められる場面は、地震災害の時と似ている部分があるように思います。
屋内外に様々なものが散乱してしまっているので、それらを片付けたり、

雨が降ると、雨漏りしたり、雨が屋内に吹き込んできてしまうので、雨から家や家財を守るために、ブルーシートなどで雨対策をするということなどが必要になります。

➖噴火による被害について
日本には111の活火山があります。
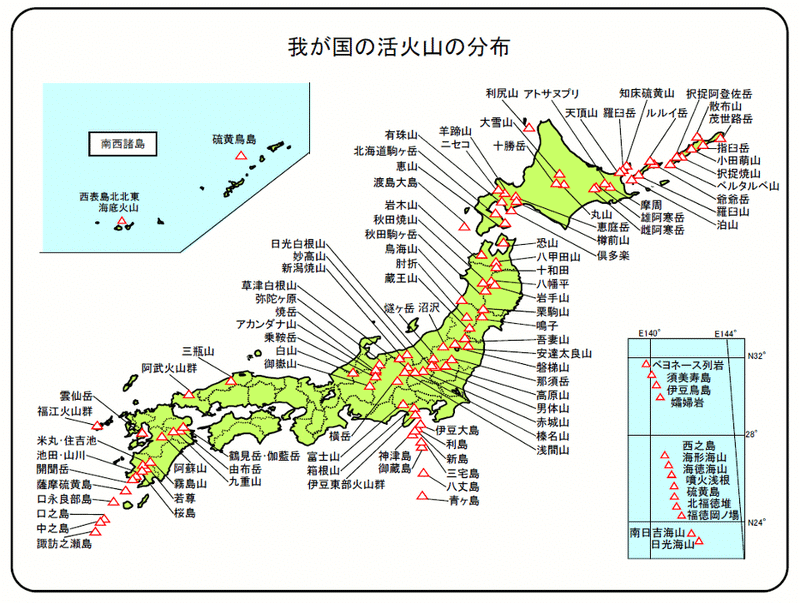
比較的近年に噴火した火山は、
・阿蘇山(熊本県)
・御嶽山(岐阜県・長野県)
・三宅島(東京都)
・有珠山(北海道)
などがあげられます。
噴火災害の被害では、噴火に伴い広範囲に火山灰が降り積もるため、その火山灰の除去に人手が必要になります。

特に、火山灰が堆積した後に、雨が降ると、火山灰が水を含み、とても重たくなり、水害の時の土砂・泥の除去のように重労働になります。

また、2000年に発生した三宅島噴火災害の時には、全島避難となり、全島民が島からの避難を余儀なくされました。
避難指示が解除されるまでに4年5か月を要し、住民が帰島される際には、島での生活を取り戻すために帰島支援が行われ、物資の運搬などもボランティアがお手伝いさせていただきました。

災害が起きたときに、ボランティアどんなことをするか、少しはイメージが付いたでしょうか?
災害時のボランティアには、これまでにご紹介していないものもたくさんありますので、また機会を見てご紹介できればと思っています。
次回は、災害ボランティアが求められる背景についてご紹介する予定です。
▶『Youth for the Resilience』とは
東日本大震災から10年となる今、私たち若者が自らの大切なものを守るための「備え」と「行動」を身につけることを目的とした「若者の災害対応力向上キャンペーン」です!
「#Y4R」
▶『ゆるぼう(ゆる防災)』とは
Y4Rキャンペーンの取り組みの一つで、 「調べれば分かるけど、そこまでじゃない話」をコンセプトに、防災・減災に関する様々なテーマについて話し合うシリーズです!
今後も「防災袋に入れておくべきものは?」「避難生活時に気をつけるべきことは?」などなどのテーマを予定しています!
▶会員向け災害対応力レクチャーのお知らせ
私達一人ひとりが取るべき避難行動は生活圏・居住環境によって異なります。
この災害対応力レクチャーでは、IVUSA職員の宮﨑が、実際にあなたが暮らす地域や居住環境で必要な災害への備え、被災時行動をレクチャーします!
希望する人は会員ページ内の災害対応力レクチャーエントリーページからエントリーをお願いいたします!
IVUSA危機対応研究所 主任研究員 深山 恭介
IVUSA17期卒。関西事務所勤務。
災害救援活動、ロジスティックス、危機対応講習を担当。 プロジェクトでは阿蘇海環境づくり活動、雪原カーニバルなかさと協働活動、インド生活支援活動を担当。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
