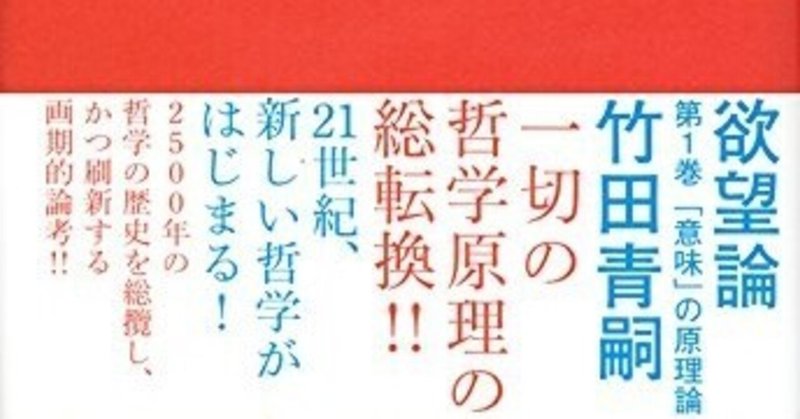
【解説】竹田青嗣『欲望論』(9)〜ポストモダン思想の根本問題
1.脱構築
現代哲学において、あいも変わらず続けられている「形而上学的独断論 VS 相対主義」の構図。
前回の言語哲学に続いて、今回はデリダの「脱構築」、およびドゥルーズの「差異」について論じていこう。
知られているように、『声と現象』において、デリダはフッサールを批判して、絶対的な「今」「ここ」などないことを主張した。
あるのはただ、「差異の運動」だけである、と。
絶対的な「今」の観念を、時間性を詳細に分析するなら「今」はそれ自体としては存在しない、というパラドクスに追い込むことに尽きる。絶対的な「今」は存在せず、「今」と呼ばれるものはじつのところ「過去」「今」「未来」といった契機の「差異の運動」でしかないことが示され、この絶対的な「差異の運動」が記号論的には「原(アルシ)=エクリチュール」と呼ばれる。
デリダのフッサール解釈はひどい誤解に基づくものだが、ここではその詳細は割愛する。
本質的な論点は、デリダの論理は、相も変わらず帰謬法を駆使した単なる相対化にすぎないということ、つまり、結局はあの「ゴルギアス・テーゼ」の枠内にあるということだ。
要するに、彼は「同一性」としての「本体」など不可能であるということを、さまざまな論理的パラドクスを駆使して帰謬論的に主張したにすぎないのだ。
しかしここには、自ら設定した「差異の運動」とか「原=エクリチュール」とかいったものも、論理的には相対化しつづけなければならなくなるというパラドクスが生じることになる。
それゆえ彼は、「差異」もまた絶対の根源ではないといったことを、ただ延々と繰り返すほかなくなってしまうのだ。
相対主義はそれが自己自身の論拠をおいつめると、“どんな主張も妥当性をもたない”へと転化し、結局、自己の主張を「相対的な正しさ」に留めるほかないからである。デリダは、「今」(同一性)を先構成するものとして「差異」(原=(アルシ)エクリチュール)を置くが、そのことでこの「純粋な差異」の概念が新しい“根源性”(根拠性)を帯びることになり、今度はこの「差異」の根源性の性格を打ち消すために、さまざまな論理的努力が要請されることになる。
これは、相対主義が自ら抱え込む、典型的なパラドクスだと言っていい。
2.ドゥルーズの「差異」
同じことはドゥルーズにも言えるが、彼の場合は、むしろ相対主義というより、その反対に「現代の形而上学」と言ったほうがふさわしい。
世界の一切は「差異」である。一切は「差異の反復」である。この「差異」は、痕跡としての、再表象としての差異ではなく、それ自身差異化する運動としての、いわば「力」(強度)としての差異化の運動である。二〇世紀の新しい寓喩−説話的世界哲学は、こうしてまず独自の仕方で世界の「根本原理」と「究極原因」(動因)を設定する。
「世界は本当はこうなっている」。そう主張するのが、形而上学的独断論だった。
ドゥルーズは、まさに独断的に、世界は「差異の反復」であるという形而上学的イメージを述べ立てるのだ。
その際、彼は己の言葉をとことん難解化、韜晦化、謎言化することに力を注ぐ。
竹田はまたも挑発的に次のように言う。
哲学の理説が普遍性の根拠についての本質理論をもたないとき、その正当性を主張するために用いられる基本的な戦略は以下である。すなわち難解化、煩瑣化、膨大化、曖昧化、韜晦化、秘教化、謎言化、神秘化、そして聖化。
ある意味できわめて独創的な装いをもった預言者哲学が登場するや、もはや理論の普遍性や正当性を問題とする動機をもたない知的伝播者たちが、その周りに蝟集して、この謎言化話法を反復しはじめる。
その難解で謎めいた哲学は、まさにそれゆえにこそ、人びとに「ここには何かすごいものがあるに違いない」と思わせ、それを解読することに精を出させて(喜びを見出させて)しまうのだ。
竹田の挑発は続く。
そこに現われるのは、伝統的「本体」に対置されたもう一つの「本体」観念にすぎない。そう見えないとすれば、ここでは、きわめて高度な難解化、晦渋化、韜晦化の謎言話法が、すなわち思考の工程に暗号をかけて解読不可能にする技法が功を奏しているからである。現代の多くの思想伝播者たちは、秘教化された預言者的哲学を歓迎する。その暗号を解読するために多くの時間を用いること自体が、一つの知的特権を形づくるからである。
あらゆるタイプの難解化、韜晦化、謎言化は、仏教哲学の時代から形而上学的独断論の常套手段だ。
このきわめて難解な哲学は、その絢爛な難解さそれ自体のゆえに、これを「解読」したいとする知的追随者たちを生む。
しかしだまされてはならない。この難解な寓喩‐説話的世界理説は、とどのつまりが検証不可能な独断論にすぎないのだ。
ドゥルーズの動機は、デリダと同じく一切の「同一性」にノーをつきつけることにある。
この「同一性」こそ、ある種の全体主義的暴力をもたらす思想であるからだ。
その動機自体は、健全なものだ。
しかし彼の哲学は、この全体主義的「同一性」の世界に対する「革命の要請」の哲学へと、最終的に変貌することになる。
それは結局、「同一性」の物語に対して、また別の物語を対抗的に提示しているだけである。
世界は、「反復としての差異」として存在すべきであったが、いたるところ「表象=再現前化」する反動力、秩序と制度を捏造する否定的力によって、その本来あるべき姿を歪曲され、抑圧されている。この表象において、ドゥルーズの反復としての「差異」の哲学は、矛盾に充ちた世界における彼岸的な救済者としての寓意力をうる。カントの形而上学の不可能性の哲学が、『実践理性批判』において「神の要請」の哲学になったように、世界の根源理説としての「差異」の哲学は、決定的な場面で「革命の要請」の哲学へと変貌する。
現世否定と革命の要請という根本動機から作り出された、形而上学的な寓喩‐説話的世界理説。これこそドゥルーズ哲学の正体にほかならないのだ。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
