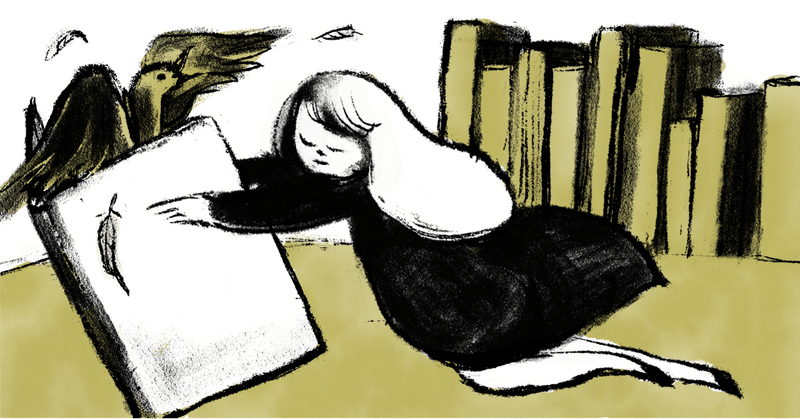
断片小説集 4
その古本屋では本を量り売りしている。白髪の眉が垂れ下がり、背中も曲がった店主は店の奥の狭いカウンターに座ったまま、客が選んだ本を秤に乗せては値決めをしていく。あらかじめ値札を貼らないのは、量るのが本の物質としての重さではないからだ。
本の重さは変化しないが、内容の重要さは時代によって変わる。目まぐるしく変化する現代社会では昨日まで価値があったものが、今日には価値が半減することもあるのだ。店主は本の題名を確認し、その日の相場に合わせて秤を調整し、本の内容の重さを量る。客に「ここ数日で下がった相場も今日が底だろうから、買うなら良いタイミングだよ」とか「この本は相場が安定してるから、この先も大きくは動かないだろうね」などと説明し、客は懐具合と相談して買うか買わないかを決める。
中には相場が乱高下するものもある。
1日の中でも価値が大きく動くような本の購入を望まれたときには、店主は大忙しだ。同業者や古書市場に電話をかけて、その時の正確な相場を割り出さなければならない。目利きと経験、それに相場を読む勘がこの商売には欠かせないのだと、店主はニヤッと笑った。
(「量り売り古書店」)
* * *
幼馴染の影山涼子との付き合いは3年ほどの短いものだった。
5歳から7歳まで、幼稚園から2年生までの3年間しかない。涼子の一家は引っ越してしまったからだ。
涼子とは幼稚園の頃から互いの家を行ったりきたりしていた。涼子一家の住まいは路地の奥に建っている古い木造アパートの2階だった。
「涼子ちゃんの家にはそんなにたくさん行っちゃいけませんよ」
母親に何度かそう言われた。
涼子の家の暮らし向きが決して楽ではないことは、幼い僕もなんとなくわかっていた。その他にもなにか自分が知らない事情があることは感じたが、それが何なのか、誰にどうやって聞けばいいのか、子供の僕にはわからなかった。
母から涼子が引っ越すと聞かされたのは夏休み前のことだ。
涼子の父親が亡くなり、九州の祖父母のところに行ってしまうから、お別れして来なさいと言われたのだった。
涼子が出発するその日のことだった。
「大人になったら会おうね」
それが涼子が車に乗り込む前、最後に言った言葉だった。
次に会ったのは四半世紀が過ぎた後、場所は長崎の葬祭場だった。涼子は黒い帯のかけられた額の中で1枚の写真になっていた。
祭壇の脇には涼子の母親、涼子とは父親違いの弟、そして涼子と瓜二つの娘がいた。涼子の娘だった。
「お母さんが君ぐらいだった頃のことは僕は良く知ってる。聞きたくなったらいつでもおじさんに連れてもらっておいで」
通夜の済んだ後、僕は涼子の娘に言った。小さな涼子はこくんと頷いた。
そんなことを言うくらいには大人になったのだな、と僕は思った。
翌日、東京に戻るためにホテルから続く坂道を下って行く途中、タクシーとすれ違った。
雨など降っていないのに、どうやってできたのか、タクシーは大きな水たまりから盛大にしぶきを上げた。僕はずぶ濡れになった。
タクシーは止まることもなく、ウインクするように一度だけウインカーを点滅させ、カーブの向こうへ消えていった。
夏の日、近所の公園の噴水で涼子と水を掛け合ったことを、僕は思い出した。
(「大人になったら会いましょう」)
* * *
ぜひサポートにご協力ください。 サポートは評価の一つですので多寡に関わらず本当に嬉しいです。サポートは創作のアイデア探しの際の交通費に充てさせていただきます。
