
40代家庭持ちが現役ゲーマーであり続けるための生存戦略
人は、ほんの些細なきっかけで、ビデオゲームから離れてしまうものです。
それまでどんなに熱心にプレイしてきた人であっても、仕事が忙しくなったり、子どもが生まれたり、そういった生活の変化の中でなんとなくゲームを触らなくなってしまい、そのまま卒業してしまうことがあります。
僕自身のことを話すと、僕は40代の社会人で、奥さんと、6歳の双子の娘の4人家族です。
忙しい生活ではありますが、なんとかゲーマーを自称できる程度にビデオゲームを遊ぶことができています。年間数十本程度の作品に触れ、こうやって定期的に文章を書けるくらいには情熱を保っています。
改めて考えてみると、これは決して自然に達成できていることではなくて、「ビデオゲームとの向き合い方」を常日頃からある程度意識的に考えているからなのかなあ、と感じています。
言い換えると、自分が現役ゲーマーであり続けるための「生存戦略」を常に頭に置いて実践しているから、と言えると思います。
もしかしたら、お読みの方のゲームライフに何か役に立つことがあるかもしれないので、今回はその「生存戦略」を3つのステップに分けて紹介したいと思います。
ステップ1:身の程を知る
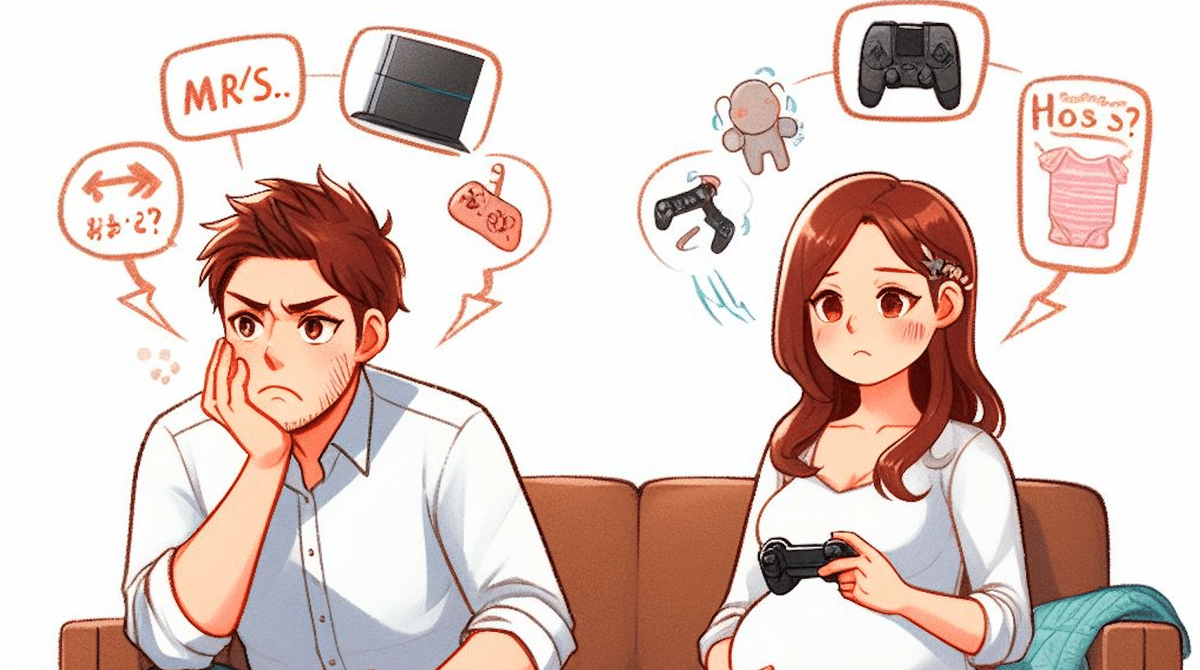
最初から身も蓋もないことを言ってしまうのですが、「もはやかつてのようにビデオゲームに没頭することはできないのだ」という現実を、まずは受け入れる必要があります。おそらく、これがもっとも大事なことだと思います。
以前なら気ままに好きな時間にゲームを遊べたかもしれません。週末に徹夜でトロコンを目指せたかもしれません。ふと思いついて、秋葉原巡りに出かけられたかもしれません。でも、もうそれは無理なのです。
かつての僕は、とても多趣味な人間でした。ゲームで遊ぶことは当時も今と変わらず好きでしたが、それ以外にも、大学時代からずっと続けてきたクラシックギターを弾き、週1〜2回はジムに通い、月に10冊本を読み、フルマラソンの大会にも出ました。それでいて、現在よりもはるかに長い時間ゲームで遊んでいました。
5時間11分でフルマラソン完走しましたー!
— Itaru Otomaru, Ph.D (@itaruotton) November 1, 2015
思いの外ちゃんと走れて、楽しめました♪
しかし、子どもたちが生まれ、生活の全てが子育てになったその時に、「もはやかつてのように色々な趣味を楽しむことはできないのだ」ということを悟ったのです。
僕は、「ビデオゲーム以外」の全ての趣味を切り捨てることにしました。クラシックギター教室を辞め、ジム通いをやめ、ジョギングの頻度を減らしました。ビデオゲームにある程度まとまった時間を確保するためには、それ以外の全てを諦める必要があったのです。
「身の程を知り、受け入れる」というのは、とても大事なことだと思います。というのも、「かつてビデオゲームに長時間費やして、やり込んで、没頭していた自分」というイメージのまま新たな生活に突入してしまうと、「かつての自分」と現在とのギャップに苦しむことになるからです。
そして、その苦しみは、自身を「ビデオゲームそのもの」から遠ざけてしまう要因となってしまうからです。
このように、自分のマインドセットを切り替えることができてはじめて、次のステップの戦略に進むことができます。
ステップ2:ゲームプレイのルーティンを作り、習慣化する
僕自身意識的に実践していて感じるのですが、ゲームをプレイする時間をきちんと決めておき、それを守るよう努力する(つまり習慣化する)ことは、プレイ時間を毎日着実に積み上げるために、とても有効です。
というのも、「暇な時間ができた時に遊ぼう」とか考えていると、日々の忙しさに押し流されてしまい、「ゲームを遊ぶこと」は簡単に途切れてしまうからです。
僕の場合、平日のゲームプレイのスケジュールは以下のような感じです。
・20:30前後〜21時過ぎまで:ゲーミングPC
・21:30ごろ〜22:45ごろまで:コンソール(PS5もしくはXbox Series X)
・23時過ぎ〜23:40ごろ:ROG Ally(ベッドの枕元で)
このように、3つのプラットフォームを切り替えながらプレイすることで、3本のゲームを同時進行しています。
上記に加えて、休日や在宅勤務日は、夕方ごろに1時間程度、子供たちの前で遊びます。(タイトルは『スプラトゥーン3』だったり『グランツーリスモ7』だったり『Litte Kitty, Big City』だったり、日によって様々です)

このように1日のゲーム時間はとても限られている(合計2時間強)ので、本来であれば、1つのタイトルに集中してクリアを目指さないといけないところです。(実際、このようなスタイルだと、1本のゲームをクリアするのに数ヶ月かかることはザラです)
それでも、僕がこうやって複数のタイトルを同時進行するのは、「ゲーム時間は少ない、でもいろんなタイトルに目移りしてしまう」という自分の気持ちと折り合いをつけるためです。
さすがにAAAタイトル3本立てとかにしてしまうと複数作同時進行は大変ですが、例えばROG Allyで遊ぶのは比較的短時間でプレイ可能なインディータイトルにしたりすることでバランスを取っています。
人によって生活のスタイルは様々ですから、僕のスタイルが全ての人におすすめできるものではないかもしれません。それでも、何かしらルーティンを作って習慣化することは、誰にとっても良いことだと思います。
そして、次のステップでは、そのようにして作り出したゲームプレイの時間の「質」をさらに高める努力をします。
ステップ3:環境に投資する
ゲーム機やPCを立ち上げるのが億劫で、それが理由でビデオゲームから離れてしまう…というのもよく聞く話です。
そういうことが起こらないように、「なるべくハードル低くビデオゲームに触れることができるようにゲームプレイ環境に投資する」というのが、本記事で紹介する戦略の最後のステップとなります。
僕の場合それは、昨年(2023年)夏に購入した『ROG Ally』でした。
コンパクトなボディながら『Starfield』が40〜50FPSで動作するスペックを持つ本機は、PCゲームをプレイするハードルを下げてくれた素晴らしい相棒です。

このカテゴリの製品としてはValveの『Steam Deck』がメジャーですが、Steam専用機である『Steam Deck』とは違い、本機はEpicやPC Game PassなどあらゆるプラットフォームのPCゲームを起動可能です。
特に、Xbox Game Passで提供されているタイトルは、XboxとPCとの間でセーブデータが同期されるので、リビングのXboxでプレイした続きを寝室のROG Allyでプレイ…といった具合に、柔軟な遊び方が可能です。
また、僕自身はまだ手に入れていないのですが、PlayStationのゲームをメインにプレイする方でしたら、『PlayStation Portal リモートプレーヤー』も、同じような理由で強力な選択肢になるでしょう。

他にも、ちょっとした空き時間は、スマホのリモートプレイを使うことで有効活用できます。僕の場合、『龍が如く 7』をXbox Game Passでプレイしていたのですが、Xbox Cloud Gamingを活用して、会社経営のパートを昼休みに進めていました。
このように、あらゆる機会をとらえてビデオゲームとの接点を持ち続け、プレイするハードルを下げること、そのことが、時間が限られている中でも充実したビデオゲームライフを送るために重要なことなのではないかと感じます。
まとめ
本記事では、40代で妻子を持つ身である僕が、充実したゲームライフを送るために心がけていること、言い換えると、「自分が現役ゲーマーであり続けるための生存戦略」を紹介しました。
この記事で紹介した内容は、僕の経験に基づくものですので、全ての人に役に立つ一般化できるようなものではないかもしれません。結局、魔法の解決法なんてものはなく、「人それぞれである」というのが本記事の結論になってしまうかもしれません。
それでも、皆様がこの記事を読んで、自分自身の「ゲームとの向き合い方」を考えるきっかけとなり、充実したゲームライフを送る助けに少しでもなるようでしたら、これに勝る喜びはありません。
(了)
2024.5.26 Itaru Otomaru
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
