
読書への苦手感を克服するまでのこと
読書は苦手でした。
今はそれなりの数の本を読むようになりましたけれど、そうなるまでにはいろいろあったように思います。
子供の頃から遡って考えてみると、嫌いではなかったはずの読書について妙な癖のようなものができてしまい、それが大人になってから違った形で作用して苦手意識を作るようになってしまった…
社会人になって本を読まなくてはならなくなった時に、癖から生まれた苦手意識を乗り越えるのにかなり試行錯誤を繰り返しました。
私の読書の仕方がどんなふうに変化し、できてしまった苦手意識がどうやって克服されたのかについて整理してみたいと思います。
本を読み始めた頃
絵本ではなく文字中心の本を最初に読んだのは小学校に入ってからだと思います。漢字の読み方が解ってきて、教科書以外で単行本の本を読んだのは小学校の2年生ぐらいからのはずです。
公立の小学校でしたけれど、夏休みの課題図書というのが学年ごとに何冊かあって、それを読んで読後感想文を書くのが夏休みの宿題になっていました。
私は小学校2年生の時から親に言われるままに欠かさず課題図書は読破して読後感想文を出しまくっていました。4年生の時には全国コンクールで入賞して賞状をもらったりしていました。
この頃の私の読書は完全没入型でした。読後感想文を書かないといけないので、物語の世界観に入りこみ登場人物の気持ちを汲み取らないといけませんでした。
ゆっくりと一字一句を追いながらも同時に行間を読み、著者の意図や登場人物の気持ちを察る読み方を訓練されたと言って良いかと思います。
両親から本を読むことをかなり口酸っぱく言われてました。今月は何冊目かとか聞かれていたように思います。本はいくらでも買うと言ってくれてましたが、実際には学校の図書館で借りて読んでいました。図書館だと借りてきて2週間で返さないといけないのでその間になんとしても読破しますし、読み終えたら感想文を書くことを求められていました。
そう、この頃は量を読めていたのだと思います。
そんなやらされ感満載の小学校の頃でしたけれど、与えられずとも自分から読みに行ったのが「シャーロック・ホームズの冒険」でした。
読みやすい「まだらの紐」や「踊る人形」のような短編から入り、4大長編である「緋色の研究」「四つの署名」「バスカビル家の犬」「恐怖の谷」を読破したことで長い小説でも苦もなく読めるようになって読書が楽しくなってきていました。
そこからは親や親戚が面白いと勧めてくれる本は素直に読んでいたと思います。平家物語、今昔物語、太閤記、信長記、徒然草など日本の古典が多かったと思います。最も素直に本を読めていた時期だったかもしれません。

知的好奇心ドライブ
小学校の高学年から中学生にかけては読む本のジャンルが劇的に変わりました。
中学受験も終えたので、親もあまり私自身への教育についてはエネルギーを割かなくなってきたのもありますが、どの本を読めとかまで細かくは言わなくなり、読みたい本を学校の図書館で借りてきて読めるようになりました。
そして私自身は、急激に理系の本に傾倒してゆきます。具体的には、ブルーバックスを読みまくっていました。
小学校高学年ぐらいからプラネタリウムに行くのが好きで、星空や果てしない宇宙に想いを馳せるのが好きでしたし、月蝕の観測とかも惑星の動きも観測したりし、望遠鏡が欲しいなとか思っているほどでした。
そしてある日プラネタリウムの併設展示で「星の一生」を知った時に、なぜガスの固まりが燃えて高エネルギーを出し続けられるのかに興味を持ったのが「理系」への興味のきっかけだったと思います。
そこから知的好奇心の赴くまま天体物理学の難しい理論を読み、さらには原子物理学も何冊も読破してミクロの世界で何が起きているのかを理解しようとしていました。「マクスウェルの悪魔」も確か中学一年ぐらいの時に読んでいますし、相対性理論も中学在学中に読みました。おそらく理論そのものはよく分かってなかったと思いますが、光速と時間の話や重力波の話などは起こる現象にものすごく興味を持っていました。
この辺りは、後になって好んで読むSF漫画とも繋がってるかもしれません。
物理学だけでなく生物学や生化学にも興味を持ちました。
脳の話や心理学。そして「生命」とは何か。生物はどこから生まれてどこに向かってゆくのか…
そんな日常から離れた壮大な話が好きだったのかもしれません。
一方で文系の本はいくら勧められても読もうともしない時期でした。
祖母が哲学書を読むことをものすごく勧めてきて、自分が学生の頃読んでいた古い本を何冊もくれたのですが、文体が古くて読みづらい上に内容が何を言ってるのか分からないので数ページ読んだだけで全く手をつけていませんでした。
この頃に哲学に傾倒していたら全く違う人間になっていたのではないかと思います。
高校から大学にかけては、クラブ活動が忙しくなってきていたことと、本を読むよりも音楽を聴く方が好きになっていたこともあり、本はほとんど読まなくなりました。代わりに漫画をかなり読みましたね。SF漫画では松本零士や手塚治虫、永井豪、石川賢をはじめとする少年漫画はもちろん、竹宮惠子、萩尾望都、大和和紀といった少女漫画も後になって名作と言われるものはほとんど読んでいたのではないかと思います。
親からは「漫画ばかり読んで!」と叱られてましたけれど。

キャリアチェンジで生まれた知識欲
大学に入ると、単位を取るために面白くもない本を何冊を読むことになります。そのような本は機械的に考え方を頭に叩き込むような読み方をしていましたので、試験で吐き出した後は内容を覚えていないですし、どんな本を読んだのかすら覚えていません。
一方で記憶に残っているのは、当時の友人から勧められたハードボイルド系の小説でした。大藪春彦とか北方謙三はたくさん読みましたね…
なんというか、自分なりの美学を構築しようとしていた時期だったんだろうと思います。主人公のストイックさ強さ、カッコよさに惹かれたのは同時自分が体育会で剣道という個人競技をやっていたからというのもあると思います。今思うとロマンスのかけらもない男臭い世界に浸っていた感じですから。
就職してからもしばらくは漫画が中心で時々小説を読むような日々が続きました。当時は営業でしたので、仕事のニーズで本を読むということはそれほどなかったもので。
再び、本を読むニーズに直面したのは、40代を迎えようかという時期でした。
人事に異動になったタイミングです。
全くベースとなる知識や勉強もなく事業部門から人事に移った私は、なんというか、勢いと気合いだけでその場でなんとかしてきたものが通用しなくなった感があり、もっと勉強しないとやばいなと(多分生まれて初めて)思ったのでした。
具体的には、人事に入って最初の仕事がL&D(Learning and Development = 人材開発担当)でしたので、様々な研修や学習の仕組みづくりを行ったのですが、その中で何人かの研修講師の引き出しの多さに圧倒されていました。
人材開発担当である以上、自身も人前に立って研修としたり教えたりする機会はかなりの数あるので、研修講師の知識の凄まじさに驚きながらも、自分もそうならないといけない、自分は知らないことが多すぎる…と危機感を感じていました。
言わば、ここにきて危機感から知識欲が芽生えたのでした。
研修講師の中でこの人は一番すごいなと思った人に相談しました。
自分は圧倒的に知識が足りない。どうすればいいですか?と。
そのかたはニコニコしながら言いました。
「本を読むと良いですよ」
やっぱそう来るかぁ… まぁ、そりゃそうだよなぁ…
「読めない」との格闘
その研修講師は大学の先生でもあったのですがとても親切な人で、しかも私のことを視点や考え方に見所があると思ってくれていたようで、実にたくさんの本を勧めてくれました。ほんと、親切でした…(笑)
全部その場でメモしていると…さらに一言。
「本は出版されても売れないと割とすぐに廃刊になってしまうんですよ。興味があるなと思ったらそうなる前に買って手元に持っておいた方が良いですよ」
この後私の部屋に膨大な数の書籍が積み上がることになりました。

カミさんからも「そんなに買って読めるのか」と白い目で見られて文句を言われ、仕事で使うからと宥めながらも溜息が出てくる状態になりました。
あれも読みたいこれも読みたい、でも読みきれない。読む前に次の本を買ってしまうから結局積読になる。
これはなんとか、サクサクと本を読める方法を身につけないと…
ここから読書の仕方の試行錯誤が始まりました。
多読したかった私が最初に興味を持ちトライしたのは速読でした。
たぶん、ビジネスパーソンが多読ニーズが出てくると真っ先に考える選択肢ではないでしょうか。私も御多分に洩れずそうなりました。
何冊か速読本を読み、実際にPhoto Readingとかはトライしました。しかし、私にとってはなんとも気持ちが悪い読書体験でした。
なんというか全然頭に入ってる気がしないのです。潜在意識的にはきっと眺めるだけで頭に入っているのでしょうけれど読んでいる手応えや感動のようなものが欲しかったのだと思います。
また、試して判ったのですが、速読はそれができる心理的状況にならないと全く頭の中に残らないですし、そうなるまでにはかなりの訓練をしないといけないようです、少なくとも私の場合はそうでした。
速読が自分に向いてないとなると結局コツコツ読んでゆくしかありません。
しかし、読む先から積読が溜まって行く状況は結構辛いものがありました。いつしか「読めない」という苦手意識ができてゆきました。
積読状態になってるからだけでなく、自分の読み方の癖のようなものが「読み進むスピード」を落としていることにも気づきました。
特に、ビジネス書は書かれている内容が抽象的で、これは一体どういうことだろうかと考えてしまうのです。書かれていない状況描写を頭の中で始めてしまうのでそこでページを捲る手が止まってしまいます。2−3分経っても内容が先に進みません。
また、時には著者との対話が頭の中で始まります。ある考え方が提示されると、
(え?それってよく分からない、こういうこと?)
(でも、それじゃこういう時はどうなの?)
と問いが次々と湧き出し、著者の意図を探りながら、
(ひょっとして、こういうことが言いたいのかな?)
とか考え出すと、これまだページを捲る手が止まります。
つまり、本を読みながら派生していろいろなことを考えてしまうので、全然読み進まない状態になるのです。おそらくこれは、前述した私自身の小学校の頃の深い読書の仕方の癖が抜けてないためなのでしょう。
やがて、「自分は本を読むのが下手だ」と思い込み、それが読書に対する苦手意識として私の中に刻まれそうになっていました。
これはかなりまずい…
ふと友人たちと駄弁っているとき、そのうちの一人が年間に50冊読んでる、と自慢げ話したので、それに食らいついて、
「え?どうやってそんなに読めるの?」
と聞いてみたら、彼は
「いや、簡単だよ。週一冊読めば年間で50冊でしょ?」
と軽く返してきました。
あ、そうか…
言われてみれば当たり前ですし、週一冊読めないから苦労してたわけですけれど、自分的には妙な肚おち感があり、自分もやってみることにしました。
2015年の年末のことでした。翌年の正月から早速始めることにしました。
完成した私なりの本の読み方
やる、と決めたら簡単には諦めない方なので、2016年は本当に毎週一冊読みました。
私の頭の中では「これは読めるようになるトレーニングなんだ」と考えるようにして、続けることで読書筋肉みたいなものを作る感覚でした。
こういう時に体育会気質のストイックさが助けてくれます。
そして、2016年は50冊を軽く超え、年末までに58冊読破することができました。
58冊読みながら、読んだ証としての読書メモを書き、それをFacebookに投稿していました。読書メモと言ってもそれほど長いものではなく、どんなことが書かれている本で自分は何を学んだのかを200文字程度でまとめていたものです。
それを友人にシェアをする習慣を作ることは自分自身に対して読書習慣を作るモチベーションにもなりましたし、自分自身の中にも本を読んだ実感を残せたので、やってみてよかったなと思っています。
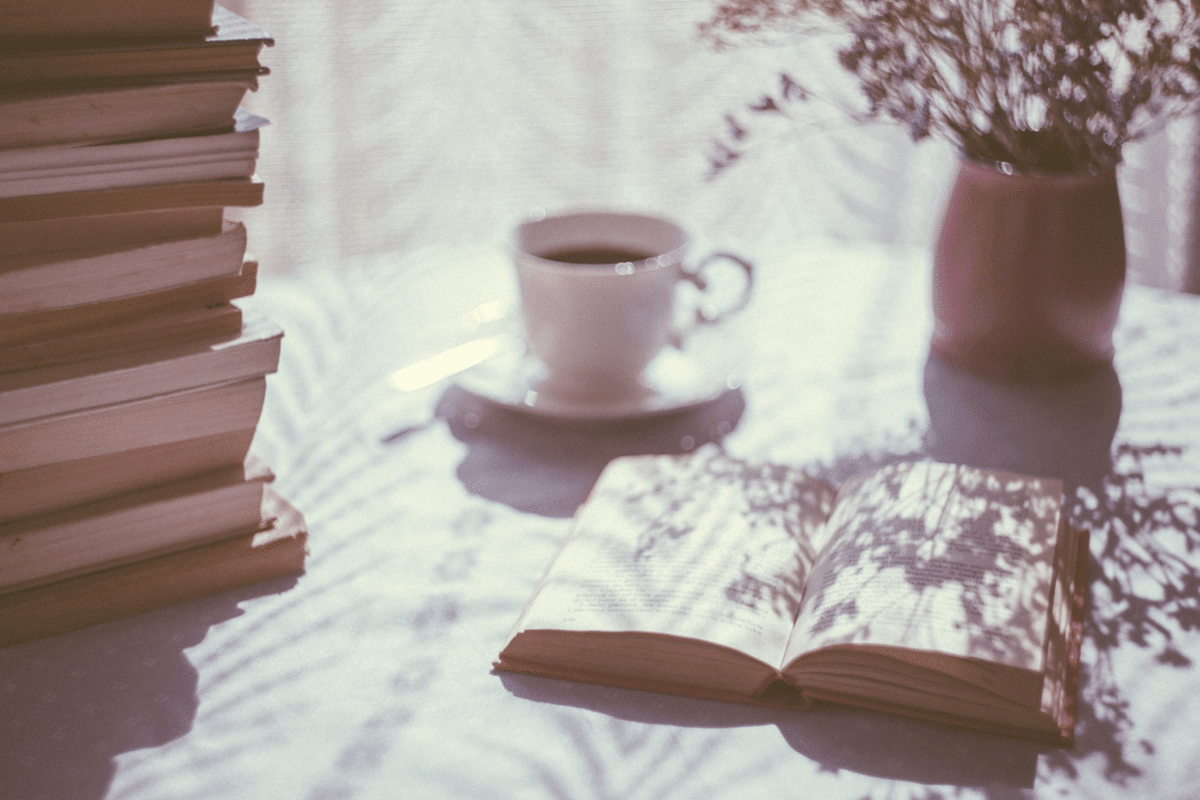
そして、私の苦手意識がどうなったのか、ですが…
正直、最後まで完全に無くなりはしなかったのですけれど、気にならなくなりました。自分なりの読み方も悪くないなと思えるようになったのです。
自分でも素直に著者の言うことを吸収していないひねくれた読み方だなとは思いますが、自分の読書の目的は本から学んだことを他の人に伝えるところにあったので、著者がなんと言っているかよりも「本に書かれていることを自分の言葉で語れること」の方が大切なのです。そのことに気づけたことは大きかったですね。
読むスピードも実は少し上がっていました。50冊以上読んでコツが掴めたと言うのがあると思います。
どんな読み方をしているのかをまとめてみましょう。
まず、「はじめに」を読む。ここはしっかり時間をかけて読みます。流し読みは決してしません。ここに著者の意図や伝えたいところ、著作の構造が書かれていますので、まずそれを理解します。
そして、自分としてはこれを知りたい、を設定します。これ大事です。
知りたい項目がたくさんあるときは書き出しておきますが、できれば2−3に絞り込んでおいた方が良いと思います。大抵の場合知りたいことの答えは繋がっていますので、細かくみて行くよりも大まかに捉えることでよしとするのです。
その上で、自分の知りたいことの答えに関係ありそうなところを探しながら読みます。逆に読みながらピンとこないところはスルーするか、「?」を書き込んでおきます。
そして、知りたいことの答えが得られたら、途中でも読了にしてしまいます。
一回で全部読もうとするのではなく、後から二度読みして理解を深めれば良いのです。そのほうが一冊の本が二度美味しいと言うことにもなりますし。
読書する勢い(スムーズに読めるように)作りも場合によっては必要ですね。これはすなわち著者の文体の癖に慣れることで可能になります。
結論を先に言ってくれる著者や、とても周りくどい言い方をする著者。人間ですから文体には著者による違いが当たり前ですがあります。
自分の思考法をそれが合わないと読んでいて違和感を感じたり、言葉選びが気になって頭に入ってこなかったりします。
と言っても、言い方変えてもらえないので、慣れるしかありません。
第1章、第2章くらいは、頭に入ってこなくても諦めて著者の文体になれることに専念したほうが良い場合はあります。慣れた後でもう一回戻ってくればいいのですから。
行単位の読み飛ばしもうまくできるようになりました。
ビジネス書は多くの場合、理論と事例の構成になっています。理論が理解できるのであれば事例は流し読みでほとんどの場合OKです。理論がよく分からない時は事例を深く読んで理解をするようにします。
そして、読みながら本を汚すようにしています。
汚すと言うのは、線をひいたり書き込んだりすると言うことです。本棚に置いておきたい本は最初に読んだ時に持った印象や学びを記録しておくと、次に手に取った時に過去自分と出会ったり、再発見があったりします。
kindleが出てきてからこれはかなりやりやすくなりました。自分がマークした箇所の一覧も作ってくれるので後からの振り返りに便利です。
最後に、印象に残った本(中にはハズレな本もありますので、全部ではありません)は必ず読後メモを残しておくようにします。
これは先に述べたように、自分の中で学びを定着させるためと人に語れるようにするためです。
どんなにたくさん本を読まなくてはならなくても、その人に合った本の読み方があると私は思います。
私はそれを見出すのにかなり時間がかかってしまった感がありますけれど、それを見つけたことで本を読むのが苦痛でなくなり(面倒だとは時々思いますけれど)楽しめるようになったこと、そしてこのように語れるようになってよかったなと思っています。
読書に関して私の目下のテーマは、どうやって読むべき本を選ぶか、です。
以下のリンク先にある別記事で要約サービスのことを書いています。
要約サービスは、読書する代わりに内容を把握するために使うのでも良いですし、どんな本かを把握し、詳しく読みたくなったら入手するための頭出しに使うのでも良いと思います。
うまく使えば、多読できなくて困っている人の助けになるのではないでしょうか。
おそらく読書において最も大切なことは、それほど力まずに肩の力を抜いて楽しみながら読む、ことなのではないでしょうか。
私の場合は週一冊のノルマを課す「修行」を経て、読書筋肉がつくと言うよりも力みが取れたと言うところが真実なのではないか、と今になって思います。
読んでくださっている貴方の読書体験が楽しく豊かなものになりますように!

最後まで読んでくださってありがとうございました ( ´ ▽ ` )/ コメント欄への感想、リクエスト、シェアによるサポートは大歓迎です。デザインの相談を希望される場合も遠慮なくお知らせくださいね!
