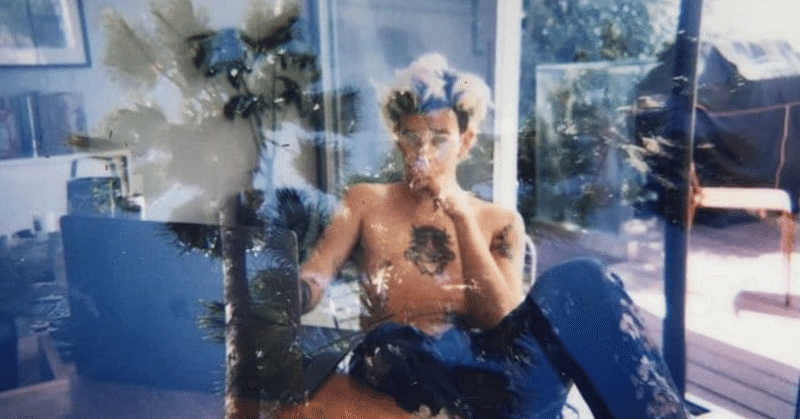
自分とは何か ⅸ
バンドを組んで、音楽に対する認識が一変した。
リードギターと一緒に曲を作ることになり数日。彼からリンクが送られてきた。それはThe 1975の“Girls”のMVで、確かなポップネスがミニマルなサウンドに乗った曲だった。それまで邦楽しか聴いてこなかった僕にとって、それは目新しいものに感じられた。英詞である、ということだけでなく、メロディパターンや展開、リズム感や音像など、何から何までだ。対して彼は、僕が慣れ親しんできた音楽には全くと言って良いほどに馴染みがなく、彼とベーシストとの音楽談義に花が咲く中、1人取り残される状況が続いた。
然し、それを否定的に捉えることはなかった。僕の耳は歌にしか興味を示さなかったから、自分が担当するパートさえ納得していれば、他は楽しければいい。強いて言えばコード感や雰囲気には何かしらの拘りがある気がしたが、何曲か作っているうちに彼のセンスに脱帽するようになった。自分の音感で間違いを是正したり、コードにテンションをかけるだけでより良いものになった。
彼の美的感覚は、芸術領域に関する興味と知識、ファッションや言葉選びなど随所に現れていて、いつしか嫉妬に近い羨望を抱くようになっていた。僕は何故音楽を聴くのだろうか。大抵、いつも他に注力しなければならないことがあり、それから逃げる為に耳を塞ぎ、口ずさむ。その為の手段でしかなかったのかもしれない。音楽自体にどんな意味があるかとか、細部にどんな表現が宿っているかとか、ジャンルとかカルチャーとか、考えることはしてこなかった。あの時部活を辞めていたら、そういうことに時間を割いたのだろうか。そもそもバスケを始めたのだって、ミニバスをしていた友達を羨んで着いて行ったに過ぎなかった。主体的に何かを選んで、そうしたかったからそれでいいと、そう思えるほどの自信を持ち合わせていなかった。
彼のお陰で、素晴らしいアーティストを沢山知ることができた。自分で作るようになったというのもあって、自然とどうやって作られているか、何をどう表現しているかに焦点が合うようになった。その中でも、The 1975は僕らにとって、神にも等しい存在だった。彼らはバンドでありながらその肩書きに囚われず、創造力を思うがままにしていた。特にその前年に発表された3rdアルバム、“a brief inquiry into online relationships”は、僕の理想そのものだった。登下校中は毎日のように聴いていたし、放課後は大抵、公園で缶チューハイやら紙タバコやらを片手に屯していて、その間も頻繁に誰かしらのiPhoneから流れていた。シンプルなのに風変わりで、散漫なのに統一されている。古いのに新しく、キャッチーなのに洗練されている。今でも、無人島に1枚だけ持っていけるとしたらこれを選ぶかもしれない。創作に対する姿勢や哲学の中心には、必ずこの作品がある。
高校生活の集大成として完成させたEP、それから3年後、去年の9月にリリースしたEP、そのどちらにも、彼らに対する憧憬とコンプレックスが詰まっている。長年に渡り、僕は彼らの音楽と、シンガーソングライターであるマシュー・ヒーリーを最上の存在として捉えていた。
彼は革命家だった。二世芸能人で、軽薄ともとれる歌モノの作り手でありながら、社会と向き合い、その写し鏡としてのアートの役割を考え続ける。それは不遇な立場から溢れ出る純真な反骨とは異なり、より大局的で、政治的な説得力を持っていた。それを可能にするのは、コンセプティブなテーマであり、ウィットに富んだアイロニーであり、様々なジャンルを統合するアイデアであり、ビジュアルアートワークであり、彼の個人的なファッションであり、そうして細部に及ぶ完璧主義であり、何より、そういった表現に対する誠実さだ。
彼の精神は不安定で、度々混乱してしまう。誤解を招く言動を繰り返してはSNSを炎上させ、その度に表現で得られた信頼を失ってしまう。それでも自分自身と、世界と戦い、究極の作品を発表する。その度に僕らは心酔する。彼は革命家だった。
僕はバンドを組んでからずっと、彼になりたかった。僕らは内気で神経質で、The 1975を通じて少しずつ価値観を共有してきた。作る曲、綴る言葉、服装、考え方、感じ方。僕が彼に近づけば、僕らも近づける気がした。
僕は彼ではないのに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
