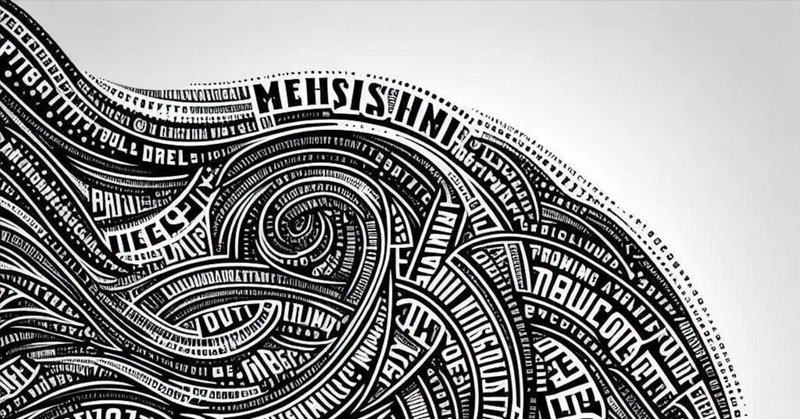
文学理論は「公式が勝手に言ってるだけ」を肯定する:脚本の人が考えていないことも考えてよい理由
(見出し画像は、Copilotが生成した「テクスト論」の画像の一部)
「公式が勝手に言ってるだけ」という言葉がある。「公式の声明」よりも「自分の解釈」を優先する姿勢のことだ。
(事例を出そうとして我が身を振り返ったが、なんの心当たりもなくて困っている。樋口円香の初恋が浅倉透だったのは事実だし)
ニコニコ大百科では、『となりのトトロ』の例が引かれている。
サツキとメイの死亡説を持ち出した人に、ジブリが否定していると言ったところ、「そんなの公式が勝手に言ってるだけやん」と返された例だ。
一般に、こうした姿勢は妄言として退けられる。
だが、世界は広い。こうした明らかに無理な姿勢を肯定する立場もある。文学研究がそれである。
文学研究では、作者の意図をなぞる立場を作品論、作者を殺す立場をテクスト論と呼んでいる。トトロの例では、ジブリが否定していると言った人は作品論の立場を、公式が勝手に言ってるだけと言った人はテクスト論の立場を取っている。
現在の近現代文学研究者で作品論の立場を取っている人はほとんどいない。彼らをレフェリーにしてレスバをすれば、「公式が勝手に言ってるだけ」と言ったほうに軍配を上げるだろう(解釈の内容の妥当性や質は問わない)。

テクスト論の前提となっているのは、フランスの哲学者ロラン・バルトの「作者の死」という論文だ。この論文は破壊力が大きすぎたので、文学研究ではストレートに作者の意図を考えることができなくなってしまった。「作者の死」というより「作者の惨殺」のほうが実情に即したタイトルだと思う。
バルトは、こう書いている。
テクストとは、一列に並んだ語から成り立ち、唯一のいわば神学的な意味(つまり、「作者=神」の《メッセージ》ということになろう)を出現させるものではない。
『物語の構造分析』花輪光訳、みすず書房(1979)所収、以下同じ
バルトは、詩人のマラルメのテクスト(作品のこと)を「作者の地位を読者に返す」ものだと褒め(p.82)、作品における作者の優位を否定する。あなたに作者認定されると殺されそうなので、返さないでほしい。
つぎの文章では、バルトが作者絶対殺すマンになった理由が明かされる。サスペンスであれば、海を背景に断崖絶壁で「仕方なかったんだ!」と叫ぶシーンである。
あるテクストにある「作者」をあてがうことは、そのテクストに歯止めをかけることであり、ある記号内容を与えることであり、エクリチュールを閉ざすことである。
崖っぷちで叫んでいるにしては冷静な口調だが、作者は「正解」をもたらしてしまうよね、というのがバルトの主張だ。
(では「作者=バルトの主張」など読み取れるのか、という議論もあり得る。これは妥当な指摘だ。だが、ややこしくなるので、ここではスルーしていただきたい)
作者の意図を神格化すると、解釈が固定され、サツキとメイが死亡しているという読解はできなくなってしまう。その意味で、「公式の見解=正解」というのは思考停止にほかならない。
「脚本の人そこまで考えてないと思うよ」という表現がミームとして流通しているが、脚本の人が考えていなくても、読者はそこまで考えてもよいのである。
作者の支配から解放された解釈は自由だ。
夏目漱石の『こゝろ』では、「私」と「先生」の奥さんがじつは結ばれているんじゃないか説まで真面目に提唱され、批判されたりされなかったりしている(小森陽一「「こころ」を生成する「心臓」」『成城国文学』1985年)。
たとえ漱石がそんなことを思って書いてなかったにせよ、そう読めてしまうのである。
そもそも、わたしも趣味で小説を書いているが、思い通りに書けることはまずない。日常会話で「うまく言葉にできないけど、しいて言うなら……」と妥協して話すのと同じ感覚で書き飛ばすし、文字のひとつひとつを完璧に制御することは不可能だ。
加えて、プロともなれば事態はもっと複雑で、編集者や読者の要望を組み入れることだってある。作品が全部「意図」で成り立っているなどというナイーブな考え方は捨てたほうがいい。
さて、いまやわたしたちは作品論者に対する武器を手にした。
今度「公式が否定してるけどね」と言われたら、胸を張ってこう言おう。
「そんなの公式が勝手に言ってるだけやん」
余談
「じゃあ、国語の授業で作者の気持ちを訊かれたのは?」と思った人もいるかもしれない。
教員が文学を専門的に学ぶわけではない小学校ならまだしも、中学・高校でそのような教え方をされることはまずないはずなので、いわゆるマンデラ効果なのではないかと思っている。
国語の問題は、基本的に解釈の前提として認めてよい部分を問うているのであって、作者の気持ちを問うているのではない。もちろん、中には悪問もあるが、「気持ち」を訊ねる問題は見たことがない。
実際、文科省が「高校生に国語を教えるときにはこうしてください」と書いている資料には、「作者」という言葉は一度しか登場しない。
その一度にしても、
創作した作品について相互に批評し合うことによって,書き手は作者という立場からは想像し得なかった読み手の受け止め方を知ることができる。
というもので、明らかに「作者の死」と文脈を共有している(この辺りは、大塚英志『文学国語入門』星海社(2020)が参考になる)。
べつに国がこう言っているからこう読めというわけではないのだが、通常の「国語の授業」で作者の意図を問われることはないはずだ。
