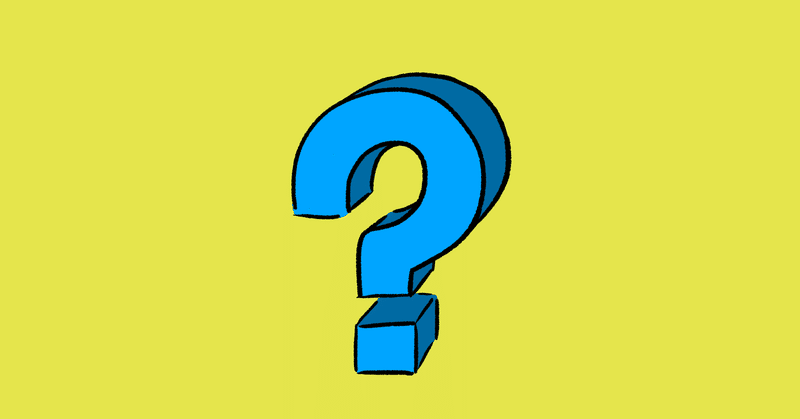
リーダーやマネージャーや人事にとって、「問い」を考えることは大切だと思う
僕はロジカルシンキングに苦手意識がありました。
元々は、「あーそれいいね、やってみようか」とすぐに言いたいタイプです。
もちろん、それで済ませられる場面ばかりではありませんので、大学時代の恩師とか、大学院時代の恩師とか、新卒で入った会社の先輩方に随分と鍛えられました。
そのおかげで少しばかりはマシになった、はずです。
ところで、「考える」という行為には、その前段に「問う」という行為があります。
今日は、この「問う」ということについて書いてみたいと思います。
「問う」ことは方向づけること
僕たちは、誰かに何かを問われたら、基本的には、その問いに対して考えようとします。
もしそれが会話の中で発せられた問いならば、問いとそれに対する回答に応じて、その後の会話が進むことになります。
つまり、「問う」という行為には、その場で紡ぎ出される思考と会話を方向づける働きがあると言ってもいいと思います。
ですので、リーダー、マネージャー、人事の皆さんにとって、どんな問いを発するのかは、とても大切な問題だと思っています。
「なぜ?」と問うことの効果と限界
仮に、自社のA営業部の長時間労働が問題になっているとします。
そんな時、「なぜ、 長時間労働が起こっているのか?」という問いが、僕たちの頭に浮かびます。
まず、「なぜ?」の問いが機能するには、「原因を特定することが可能」でなければなりません。
加えて、「特定できた原因を(比較的容易に)取り除いたり、修理したりすることが可能」であることがポイントです。
それらが担保されるならば、僕たちは、漏れなく順番に理詰めで解決することができます。
これは、問題の原因や構造を特定し、原因を取り除いたり、構造を手直しするという発想のアプローチです。
例えば、A営業部では「お客様第一」のスローガンのもと顧客の要求に常時即応することが求められており、たとえ帰宅間際であっても問い合わせがあれば応対することが常態化しているとします。
このことの原因は、スローガンを掲げていること自体にあるのか、業界や会社の根強い商慣行にあるのか、営業部長の長時間労働への意識の低さにあるのか、現状に異を唱えることができない社員の姿勢にあるのか、顧客の不合理な期待値にあるのか、その他か、それらの全てなのかなどなどを特定することが、まず容易ではありません。
仮に商慣行に原因があることが分かったとしても、変えるのにはとても時間がかかりそうですし、現実的だとも思えません。
それに、お客様を大切にするという考え方自体には良い側面もありますから、話はややこしくなります。
かように、人や組織に関わる問題は、「なぜ?」の問いですっきりと解決できない問題が多いように思います。
「ひっくり返す」と「どのようにしたら?」
一方、「なぜ?」と問うこととは全く異なる作戦が二つあります。
「なぜ?」と問うことが「問題が発生するメカニズムを修理しよう」という発想であったのに対して、これらの作戦は「新しいメカニズムを作ってみよう」という発想に基づいていることが共通点だと思います。
また、二つを組み合わせて使うことで、よりパワフルになると感じています。
一つ目の作戦は、「ひっくり返す」です。
これは、みんなが実現してみたいと思えるようなことに、問題を転換してみる作戦です。
A営業部の例であれば、「長時間労働の解決」から「お客様満足と働きやすさを両立した職場の実現」という形で、問題を捉え直してみようというわけです。
ここでは、元々の問題がきちんと解決されるとともに「目指したい姿」で捉え直しているかどうかがポイントになります。
二つ目の作戦は、「どのようにしたら?」です。
「なぜ、問題が発生しているのか?」ではなく、「どのようにしたら、目指したい姿を実現できるのだろうか?」を問う作戦です。
A営業部の例であれば、「どのようにしたら、私たちは、お客様満足と働きやすさを両立した職場を実現できるのだろうか?」と問うてみることができると思います。
この時、「私たち」を主語にすることで、「みんなで取り組もう」という雰囲気が醸し出されることが、もう一つの肝になってきます。
僕は、「なぜ、 長時間労働が起こっているのか?」よりも、「どのようにしたら、私たちは、お客様満足と働きやすさを両立した職場を実現できるのだろうか?」を考えることの方が、たぶん意欲的に取り組めます。
さて、皆さんはいかがですか?
以下は、今回の記事を書くにあたって参考にした資料です。
『なぜ、あのリーダーの職場は明るいのか?—ポジティブ・パワーを引き出す5つの思考法—』
“How might we ...”言葉で変えるIDEO流 創造的文化のつくり方 | HBR創造性vs.生産性ブログ
最後までお読みいただき、どうもありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
