
花山法皇ゆかりの地をゆく⑫〜大入集落跡、笠置山 後編〜
(前編からの続き)
設楽山荘
2024年5月3日15時15分、本日の宿泊地である設楽山荘に到着した。

国道257号沿いに設楽山荘の看板はなかったが、国道の横を流れる名倉川の小さな橋を渡り、森の中を進むとすぐに設楽山荘は見つかった。
設楽山荘は山あいの静かな民宿と言いたいところだが、国道の方からはたまにバイクの排気音が聞こえる。私もバイクに乗っているから、文句は言えないのだが。

玄関を開けると女将さんと思われる女性の方が現れて、私が名前を名乗ると、向こうも私の訪問は把握済みであったようで、部屋やプランの説明をしてくれた。
予約時にあまり意識をしていなかったが、八畳部屋を予約していたものを、今日はクラス会があり騒がしくなるとのことで十畳部屋へアップグレードしてくれたとのことだ。
私はありがとうございますと礼を述べて、部屋に入った。渡された鍵には、本来の鍵がどれであるかもわからないほど、大量のピンクのキーホルダーが付けられていた。
部屋に入ると荷物を整理して、さっそくコンビニで買って来た缶ビールを飲む。今日は登山もしたし温泉にも浸かったのだから、とりわけビールが旨い。
つまみに、道の駅アグリステーションなぐらで買っておいた、穴子の干物のようなものを食べる。
ひとり部屋でビールにつまみと満足にしていると、ドア越しに女将さんから風呂に入れと催促をされた。
本日の設楽山荘の宿泊客は、私以外に七名の団体がいるらしいが、その団体が風呂に入る前に入った方が良かろうという計らいであった。
呑みかけのビールが少し気になったが、素直に風呂に入る。
設楽山荘の風呂は、旅館ほど大きくはないが、一人で入るには十分すぎる広さで、総檜風呂が気持ちよかった。
風呂から上がっても缶ビールは冷えたままだった。風呂上りのビールを楽しんだ。

夕食は入口側に囲炉裏が切られたスペースのある、広い和室であった。
すでに七名の団体は囲炉裏を囲んで食事を始めている。
私は和室の隅の席で、一人食事を頂いた。
日本の民宿や旅館のような食事が供される宿で、一人で食事をとるというのは、すでに何回も経験しているが未だに慣れないし、きっと死ぬまで慣れないのだろうけど、日本で一人旅をする以上、こればかりは仕方ない。

この後、ジャガイモの煮っ転がしや山菜のてんぷら、ご飯や蕎麦なども出た
食事の内容は、昨今の宿にあるような、和牛や豪華な船盛の刺身といった、やたらと豪華にした食事ではなく、アユの塩焼きに馬刺しに筍の煮物に野菜の煮込みや山菜のてんぷらなど、いかにも山の中にある里の御馳走である。
大変においしくいただいた。
ほうらいせんという、この近辺の地酒もつけたが、あっさりした辛口の味が食事とよく合った。
食事をしていると、女将から今日はどこを回ったのか、明日はどこへ行くのかなどを聞かれた。
これは、別に女将が私や私の旅程に興味があるわけではなく、旅館業法施行規則に基づいて宿泊者名簿に前泊地と後泊地を記載せねばならないのに、チェックイン時に私が宿帳にそれらの記載を怠ったからに違いないのだが、女将はそれを私に咎める風でもなく、さも興味があるかのように聞いてきた。
一通りの食事が運ばれたのち、今度は主人からも挨拶があった。
GWのかき入れ時に一人で部屋を占有したのだから、宿としては疎まれことすれ感謝されるとは思えないが、こんなに歓待を受けるとはこちらが恐縮してしまう。
主人は元自衛隊員だという。食事が終わったら、バーエリアでお酒でもと言われたが、朝早かったことのもあり、食事が終わり部屋に戻ったらすぐに眠ってしまった。
岩村城址
2024年5月4日の金曜日、設楽山荘の客室で6時頃に目が覚めた。
朝は昼の暑さがウソのように肌寒かった。

風呂はまだ温まっていなかったようなので朝風呂はあきらめて、7時にバーエリアに準備された朝食をいただいた。
テレビでは、円安で輸入牛より和牛の方が安くなったので、和牛が売れているというニュースをやっていた。これが政治色の強い報道だと、円安でも円高でも、まもなく日本は終わりだのような報道になるが、朝はこの程度の軽い話題のニュースが程よい。
もちろん、円安で困っている人だってたくさんいるとは思うが、そればかりにスポットを当てても仕方ないではないか、とも思える。
食事を終え、設楽山荘を出ようとチェックアウトの手続きをしていると、主人と女将さんから、何度も「また来てくださいね」と声を掛けられる。
当たり前のあいさつなのかもしれないが、こうも言われると、また訪れたくなる。実際にこの設楽山荘は、周辺に主だった観光地があるわけでもないし、関東からも遠く、気軽に来れるものではないが、また来たい、良い宿だと思う。
7時45分、後ろ髪を引かれる思い出設楽山荘を発って、再びバイクを走らせる。
本日は、最初に岩村城址を目指すことにした。
岩村城址は鎌倉時代の1221年に築城された、日本三大山城に数えられる山城である。花山法皇と関係があるわけではないが、通り道にあるので寄ってみる。
昨日に引き続き、国道257号線を北上して恵那市方面を目指す。
岩村城址は、恵那市へ向けて国道257号から国道418号に切り替わると間もなくのところにあると思っていたが、国道418号に入っても見つからず、しばらく国道418号を走っていると、新木ノ実トンネルを越えた先に岩村城址に入るT字路と看板が突然あらわれ、危うく通り過ぎてしまうところであった。
国道418号を右折して、岩村城址へ続く山道を登り、8時25分岩村城址の駐車場に到着した。

岩村城址は上司の石垣と、駐車場横にトイレを併設した小さな建物があるだけであった。駐車場には車が10台弱とまっている。
トイレを済ませ、建物側には大した展示物は無いのを確認すると、石垣の方を見物することにした。

当然だが、昨日見た大入集落跡の石垣より、規模の大きさはもちろんだけれど、石の大きさも揃っているし、石垣の表面はなだらかに湾曲をしていて、こちらの方が高等な技術で作られたことが、私のような素人目にも明らかだ。
石垣が作られた時代が500年近く違うはずだから当たり前ではあるけれども、山中奥深い大入集落と、山上とはいえ里から近い岩村城の違いもあっただろう。石垣を作った人足の数だって、大入集落と岩村城では大きく違ったはずだ。

石垣の間に設けられた階段を登り、本丸跡まで登ってみる。
こうして、花山法皇のゆかりの地を訪れるようになって、花山法皇とはゆかりがないものの、旅のついでで何件かの城跡も訪ねたのだけれど、城跡というのはどうにも淋しい。
天守閣や本丸の館、あるいは物見櫓のような本来あるべきであった主要な建物がなく、石垣とその上にただ平らなだけの敷地があるのだから、その様子は人工物であるものの無駄の極致のような地形であるし、非日常的なシュールな景色でもあるように思える。
本丸跡から望む景色は、木々に阻まれてあまりよろしくない。
それでも、木々の間からふもとの岩村町の様子が見えた。
この景色を見ながら、少しだけ田舎の殿さま気分を味わうことにした。
さて、本丸跡からの眺めを見たら、これ以上は岩村城址でやることもないので、早々に岩村城址を後にして、再び恵那市方面へバイクを走らせた。
時刻は9時近くになっていた。この時刻になると、朝の肌寒さは無くなり、昨日と同じ、強い日差しの暑さが戻っていた。
笠置山

岐阜県恵那市にある笠置山は、本来は舟伏山という名前の山であり、確かにこの緩やかな傾斜を持つ独立峰を恵那市街地側から見ると舟をひっくり返したような形でもあるから、こちらの名前の方が良いように思える。
今の名前である笠置山の山名の由来は、花山法皇が以下の和歌を詠んだ伝承によるものとなっている。
眺めつつ 笠置の山と名付けしは これも笠置くしるしなりけり
笠置山の由来は上記の和歌によるが、さらにWikipediaによれば、京都の笠置山に似ているからとされている。これは、京都の笠置山というのは後醍醐天皇が篭城をした笠置山のことであろうか。
であれば、後醍醐天皇が生きた南北朝時代以降であれば京都府の笠置山も有名な山に違いないだろうが、花山法皇の時代に笠置山という山が、わざわざ他所の土地まできて思い出すほどの山かというと、どうにも疑わしい。
京都の笠置山は標高はわずか288mの、周囲も同じような山に囲まれた小山である。高い山が貴からずとはいえ、この恵那市の笠置山は1128mの堂々とした独立峰であり、そのような山に京都府とはいえ平安京より遠く離れた奈良の外れにある小山の名前を付けるとは、いくら法皇とは言え失礼ではないか。
というか、花山法皇がこんな無粋な和歌を本当に詠んだのだろうかという疑問がある。
そもそも、この笠置山の山名が笠置山となったのは、廃藩置県直前の明治三年。江戸時代からこの地を治めていた苗木藩によるものである。
当時の苗木藩は、溜まりに溜まった借金の返済と、尊王思想にかぶれた廃仏毀釈を強引に進めていた。
おそらく、笠置山の山名変更についても、尊王思想にかぶれた末にどうにか恵那地方と天皇家のゆかりがないものかと探した結果、どうにか見つけのが上記の和歌で、山名変更も他の政策同様、当時は薩長政権と言えばよいのか、時の政権に媚びを売るために強引に進めたものと思われる。
よくよく調べるとこの苗木藩、小藩ゆえに身動きが取りずらい面はあっただろうが、どうにも政策は最初から最後まで浅薄な印象をぬぐえない。それでも、庶民からの人気や支持はあったようだが。
中山道と飯田方面へ抜ける道のある交通の要衝であったのだから、経済面ではもっと有効な政策は取れただろうに、愚直に節約と緊縮政策ばかりを採っていたようであるし、街道から外れた山上にある苗木城を無理して維持するよりも中山道に近い場所に陣屋を構えた方が、よっぽどマシだったのではないかと思える。
おまけに、苗木城を白壁に塗れない理由を、木曽川から現れた龍が壁を赤くしたからだと、悔し紛れの大法螺を吹かすような藩である。
そのように考えると、この花山法皇の和歌についても、苗木藩による捏造を疑ってしまう。いずれにせよ、真偽は相当に怪しいと思われる。

このようによくよく調べると、どうにも笠置山と花山法皇の経緯については真偽が怪しいのだが、疑ってみても確かめようもないし、そもそもこの「花山法皇ゆかりの地をゆく」シリーズは、信憑性に関わらず伝承があれば訪れることにしているから、ここは素直に花山法皇の和歌を信じて、笠置山を訪れようと思う。

岩村城址を出たのち、恵那市街のガソリンスタンドで給油した後、中央西線の踏切を越えて、何度か道に迷いながら、9時50分、笠置山山頂近くの高根駐車場と看板のある場所までやってきた。
高根駐車場の真横には、看板や標識の類は全くないが、おそらく車道として整備しようとしたと思われる道幅の未舗装の道が、山頂に向かって伸びていた。
地図をみると、この道は正規の登山道では無いようだが、山頂まで続いているようでもある。

山頂には続いていない
この道を登ってみる。
やはり、車道として整備をしたようで、車でも登れるような斜度でつづら折りに道が設けられていたが、この道は数百メートルも歩くと、土砂崩れに遮られており、山頂には続いていなかった。
斜面を強引に登るにしても、まだ山頂らしきものは見えないし、これでは山頂までたどり着けるのかもわからない。
ここは素直に引き下がって高根駐車場まで戻り、再度バイクを走らせると、100mほど進んだ所に、正規の登山道と思われる入口が見つかった。

ここにも数台の自家用車が止められる駐車スペースがあり、1台だけ車が止まっていたので、その横にバイクを止めた。
10時10分、山頂を目指して歩きだした。
事前にGoogleMapで調べたところ、この入口から山頂までは直線距離にして200m程度であるから、大した歩きではないだろうと思っていたが、意外に山頂まではしっかりとした登山道であった。後で調べたら標高差は180mほどあるようであった。

10時30分、笠置山の山頂に到着。
山頂には、山の山頂とは思えない大きな笠置神社の奥宮の社があり、それを覆うように屋根が設けられている。
先に到着していた登山パーティの撮影が終わるのを待って、奥宮の写真を撮り、裏側の山頂と岩先からの眺めを一通り見て回る。
山頂の標識は、奥宮の立派さに比べると木に括りつけられた大分粗末なものであった。
東京都の奥多摩の主だった山頂は、10年くらい前に石造りの標識が備えられるようになったが、それに比べると簡素すぎると思われた。

山頂といえば、花山法皇は笠置山の北西側にある現在の中野地区から笠置山を眺めて、上記の和歌を詠んだといわれているのだから、笠置山の山頂が花山法皇のゆかりの地と言えないのではと気付いてしまった。
しかし、ここまで来てそんなことを言い出すのも野暮であるだろうと思いながら、登ってきた登山道を下山した。
国道19号と善立寺
笠置山のある恵那市から中津川市を越えて、木曽路に沿って設けられた国道19号を北に進んだ塩尻市にある善立寺という寺院には、花山法皇の石仏がある。
善立寺建立は1545年とのことだから、花山法皇自身が善立寺を訪れてはいないだろうけれども、善立寺公式のXには花山法皇参拝の伝説がたりがあるようだ。
伝説がたりについてはともかく、善立寺に花山法皇の石像があるのは間違いのない事実で、これは中山道にあったものを善立寺が引き取って保管しているものらしい。
花山法皇の時代に中山道はなく、現在の中津川市か恵那市から峠越えをして飯田市に入る東山道というのが主要路であったようであるから、花山法皇が通って塩尻に至る行程を歩いたとは考えにくい。
しかし、中山道の途中にある御嶽山は、平安時代にはすでに開山していて修験者が登っていたようであるから、公式の記録はないものの、花山法皇が御嶽山に登るために中山道の途中にある木曽福島まで至った可能性は大いにあり得る。
今回は、中津川から国道19号を北上して塩尻へ向かい、その善立寺を訪れてみようと思う。もちろん、目当ては花山法皇の石像である。
笠置山を下山し、中央自動車道で恵那インターから一区間だけ走り、中津川インターでおりて国道19号に入った。
国道19号は結構な交通量であった。中津川市街を抜けると渋滞は止んだが、ずっと車の列が途切れず連なっていた。
国道19号は「木曽高速」と揶揄されるほどの快走路であるのだが、これは深夜にほとんどの信号が黄色点滅の「注意して進め」となる時間帯に、中央道を避けて走る大量のトラックがいるから名付けられた名前で、昼間であれば一般国道とそうは変わらない。
そんな国道19号を北上する。中津川を出た直後は多かった交通量も、南木曽町を過ぎると徐々に減りはじめた。

12時35分、道の駅木曽福島に到着した。
位置的には御嶽山に入る入口に相当する場所だ。
今は昼時であるが、暑さのせいかあまり食欲は無い。
食堂には入らず、窓口で売られていた五平餅を10分待ちと言われたのを素直に待って、テラスで御嶽山を眺めながら食べる。

御嶽山から目を下ろすと、木曽川の向こうに御嶽教の本宮と思われる立派な宗教施設が見えた。
豪奢な建物であるし、ここから遠くなさそうなので行ってみようかと思ったが、観光客らしき人影が全く見えない。
のぼりが何本も建てられているようで、信者ではない訪問客を拒んでいる様子は無いのだが、この連休のまんなかでもあまり観光客もいないのであれば、わざわざ訪れるのも気が引けたので、まっすぐ国道19号を北上することにした。
道の駅木曽福島を出ると、一気に塩尻まで向かおうと思っていたが、走り出すと意外と疲れていると気付き、13時20分、道の駅きそむらに停まって再び休憩をとった。

やはり腹は減っていないものの、座って休息をとりたいと思い食堂に向かったが、食堂は入場の行列ができていた。
食堂での休息は諦めて、売店で紅茶のクッキーを買い、ベンチで買い食いをする。この紅茶のクッキーは、紅茶の香りが強くてうまかった。
再び、国道19号を北上する。
中津川からずっと山あいの谷を走っていたものが、景色は盆地に変わり、塩尻市街に入る。
塩尻市街地に入ると、再び渋滞に巻き込まれた。加えて、ただの渋滞としてはどうにも進みが悪い。
どうやら、高出という交差点で国道19号に沿って実際に松本方面へ左折をすると、すぐにもう一つの信号にぶつかり、左折した車は直後の信号で止まらされるために、思った以上に進まないようであった。
その高出交差点をどうにか抜けて松本方面へ引き続き国道19号を走るが、相変わらず交通量が多い。この区間の需要を考えれば片側二車線道が適当に思えるが、片側は一車線しかないのだから仕方ない。
おまけに反対側は渋滞している。善立寺からの帰りは国道19号を先ほどの高出交差点まで戻るのだから、気が重い。
それでも、国道19号を北上し、JR広丘駅が左に見えたら右折をすると、まもなく善立寺である。

14時35分、善立寺に到着。
事前に調べた情報から、それなりに大きい規模の寺院かと思っていたが、実際に訪れてみると、そこまで大きい寺院ではない。少し拍子抜けをする。
しかし、善立寺の本堂は新しく立派な造りである。

善立寺訪問の目的であった花山法皇石像は、本堂の手前にある観音堂に納められており、すぐに見つかった。
とはいえ、まずは本堂のお参りを済ませて、観音堂でも手を合わせてお賽銭を納めたあと、中を覗いてみると「花山法王」と脇に彫られた石像が、観音堂内部の棚の左隅に置かれている。


並べられている他の観音像が精緻な造りであるのに、どうにもこの花山法皇像は簡素である。
大入集落の花山神社前に置かれていた石像と、あまり変わり映えしないのも確かだし、「花山法王」の文字が彫られていなければ、ただのお地蔵さまなのだろうけど。
「花山法王」と「王」の字を使っているが、おそらく明治初期以前のものなのだろうと思われるが、実物を見てもそれ以上は何もないようにも思えた。

花山法皇については触れていない
観音堂で花山法皇像を眺めるのを終えて、周りを見回すと、善立寺の敷地の大半を占めると思われる墓地には、一般的な和形の縦長の墓石には違いないが、一般の墓地ではなかなか見られないような巨大な墓石が何体も見られた。
写真は撮らなかったが、墓地の敷地に入って眺めてみると、墓標も一枚ではなく五枚から十枚ほど建てられており、ほとんどの墓標に名前が埋まっている。
このような巨大な墓石を建てられる家が何軒もあるというのは、それなりに財力のある家が何軒もある場所なのだろうか。
思えば、長野という土地は、東京に比較的近くても、全国的な資本進出をなかなか受け入れない土地だったように思える。
長野県にマクドナルドが本格的に進出したのは、長野オリンピックの折であったし、2001年に上高地でワンシーズン住み込みで働いていた際は、松本に初めてイトーヨーカドーの大型ショッピングセンターができたと、結構大きな話題になっていたのを思い出した。
この善立寺の副住職は元エンジニアのやり手で、自分で墓地管理のExcelシステムを作り、寺院ITアドバイザーも務めるような方であるらしい。
元エンジニアの住職、寺院とIT、思いがけないが時代を考えれば当たり前のような住職と花山法皇の石像という、二つの奇妙なコントラストに何とも言えない思いを馳せながら、善立寺を後にした。
中央自動車道と甲府市街
15時前に塩尻の善立寺を出て、今回の旅で訪れるべき場所は全て訪問は全て終わった。
あとは中央自動車道を東京方面へ走って帰るだけである。
しかし、休日の中央道といえば、上りの小仏トンネル渋滞がどうしても避けられない。
小仏トンネルが渋滞する理由は諸々あるのだろうが、利用者からしてみれば理由を探ってみたところでどうしようもない。
今から中央道の登りで東京方面へ向かおうとすれば、ちょうど中央道の上り方面渋滞のピークにぶつかるのは間違いない。
そこで、今回は甲府駅前のビジネスホテルに一泊して、翌朝の渋滞が発生する前の中央道で帰ることにした。
そのため、出発の二日前にホテルの予約も済ませておいた。

15時35分、八ヶ岳PAで休憩を取る。
昼過ぎの夕方も近い時刻で、標高も高い場所にあるのだが、日差しは相変わらず強く暑い。
暑い中であったが、小腹が空いたので移動屋台で厚切りベーコンを買い食いした。

八ヶ岳PAを出ると、右手に甲斐駒ヶ岳、正面に富士山を眺めながら、甲府盆地を駆け降りるように中央道を走り、甲府昭和インターで中央道を降りた。
16時35分、甲府駅前付近で道に迷いながら、どうにか本日の宿泊地のビジネスホテルに到着した。

甲府市の市街地には、かつて働いていた会社があり、あまり良い思い出が無い。
良い思い出が無いなら、無視して目に入らないようにすればよいのだが、登山などでちょくちょく中央線特急には乗って甲府駅は通るし、通ればかつての嫌な思い出がぶり返してしまう。
いつまでも、そんな有様を繰り返しているのもバカらしいので、ここはひとつ、一度甲府市の駅前に宿泊して、思い出を上書きとまではいかなくても、少しは甲府市の印象や思い出を変えたいという思いが、今回の甲府市街の宿泊の目論見でもあった。
果たして、実際に甲府の印象が変わったかというと、結論はそこまで変わらなかった。
ホテルの自動チェックイン機でチェックインを済ませ、部屋に入るとまずはシャワーで汗を流し、甲府駅前に出てみたが特にすることも無い。

甲府駅の改札前まで行ってみたが、人でごった返していた。
甲府駅は東京方面の特急が30分に一本の割合で発着しているだけのような駅であるから、ふらりと訪れても人でごった返すことなど稀なのだけれど、GWの今日はそうでもないらしい。
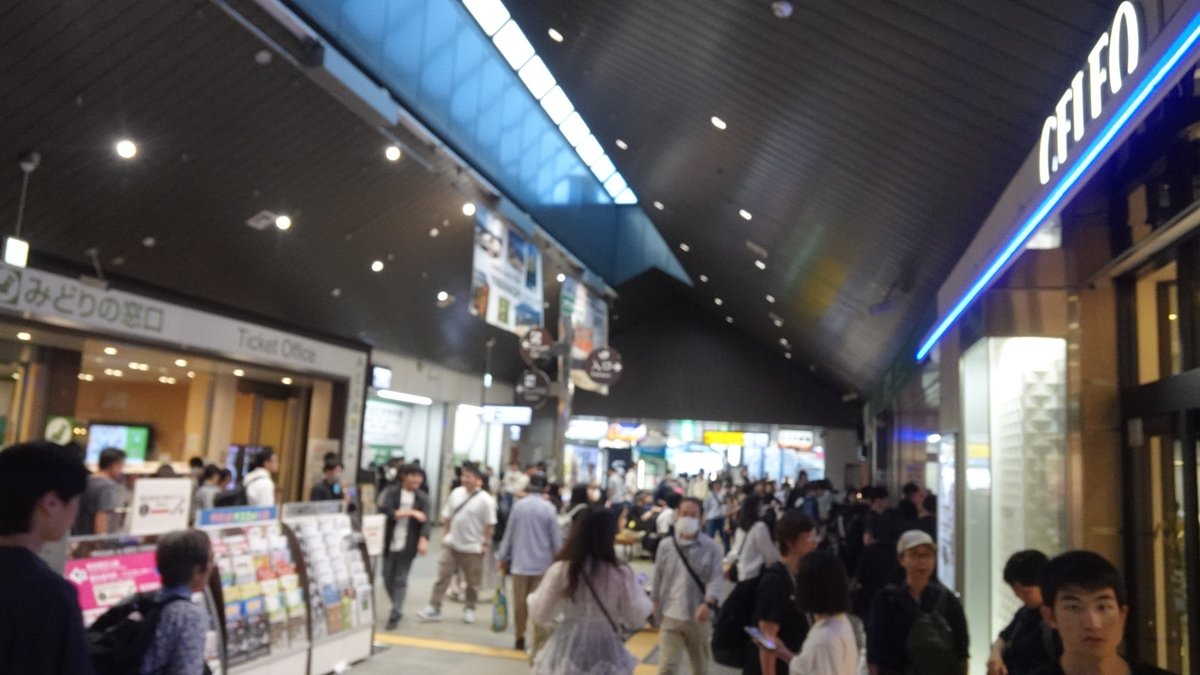
甲府駅を出て、少し早いけど夕食にするかと、駅前通りを歩いてみる。
「ほうとう」や「鳥もつ」といった甲府名物の看板を上げている居酒屋には、すでに店先で多数の客が入店を待っていた。
そういった店を避けて、安価そうな居酒屋に入る。
その居酒屋では、カウンター席でもつ煮込みや刺身をつまみに日本酒を飲んだ。
居酒屋を出ようとすると、子連れの家族が入店した。GWの家族旅行で居酒屋も無いだろうにと思ったが、この両親の行動できる範囲では精一杯なのかもしれない。
この後、他の店にも入ろうとしていたが、居酒屋を出ると思いのほか酔いが回っていることに気付き、ホテルに戻った。
ホテルに戻るとすぐに眠りについてしまった。

2024年5月5日の日曜日、このビジネスホテルの朝食は無料を謳っている。
全国展開をしているビジネスホテルであるが、安価を売りにしているせいだと思うが、追加料金を出してまでホテルで朝食を食べようという客は少ないのだろう。
一方で、朝食提供のサービスを止めてしまうと、旅館業法上のホテル扱いにならないから、食事提供自体は止めることができない。
そのための無料朝食であるから、あまり期待してはいけないのは当たり前なのだが、せめてご飯は皿盛ではなくお茶碗で食べたかったなと、しょーもない感想を抱えて、ビジネスホテルをチェックアウトし、中央道をまっすぐ走って帰ることにした。
わざわざ甲府で一泊して走る朝の中央道は、思惑通り渋滞は無かったが、さして交通量が少ないわけでもなかった。
逆に反対車線の下りは大渋滞なのかと思ったが、そこまででもなく、相模湖付近でわずかに渋滞している箇所がある程度であった。

本日はGW4連休の3日目。
甲府を朝に発って帰るのであれば、河口湖や山中湖を周って道志みちを走るなり、柳沢峠から奥多摩を通るなり、雁坂峠から秩父を抜けるなり、色々遊びどころはあるが、今日は16時に新宿で高校時代の友人との待ち合わせがある。
9時15分に八王子インターを過ぎてすぐの石川PAに到着し、トイレを済ませるとまっすぐ自宅へ帰宅した。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
