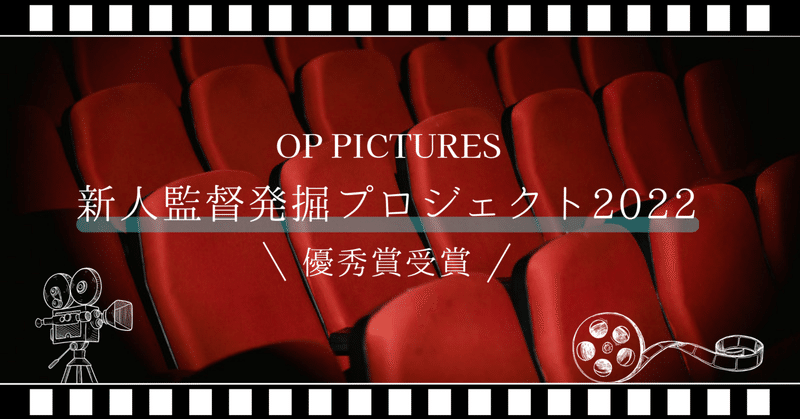
やっとピンク映画を作れるということ。

おはようございます。堂ノ本です。
遅ればせながら、皆様にお知らせがあります。
『OP PICTURES 新人監督発掘プロジェクト2022』にて、優秀賞を受賞しました。自分でも心底嬉しい結果なのですが、周りが自分の事のように喜んで、連日飲み会の日々だったのが非常に嬉しかったです。それも落ち着き、こちらにようやく書くことができます。この記事では、私の短くも長かった闘いの日々を振り返ろうと思います。
※ここからは「ですます」で書くと難しいので書き言葉でいきます。
※とても長くなってしまいました、ごめんなさい。
受賞の電話が鳴って。
まず、受賞の電話が鳴ったのは、とある昼下がりのことだった。その時は、スタジオカナリヤの自宅には、脚本担当の小林一晴くんがいた。ちょうど昼ごはんを食べていた。休日にご飯を作るのが億劫で、珍しくカップ焼きそばを食べる途中だった。この時は、新人監督発掘プロジェクトの話は、考えないようにしていて、でも確実に頭の中にあったと思う。
そんな時、東京都からの03から始まる着信。私の胸は高鳴った。OPからの電話であってくれ、と願った。けれど、期待なんてしても余計に苦しむから、精一杯抑えようとした。どうせ、どうせ、どーーーーせ、奨学金の催促やらセールスだって、心で唱えて、でも、やっぱり期待が抑えられなくて。4コールくらいして、出るか出ようか迷って、出た。
「もしもし、堂ノ本監督でお間違いないでしょうか」
嬉しかった。はい、とだけ答えたけど、答える頃には目頭が熱くなっていた。「堂ノ本監督を優秀賞に選ばせていただきました」と続き、何か答えなくちゃ、あ、あ、と声を出した瞬間、涙がこぼれそうになって、慌てて、平静を装って答えたのを覚えている。たしか笑ったふりをしながら、相手にも、小林くんにも泣いてるなんて思われたくない変な意地があって、でも興奮していたから多分バレていたと思う。で、話が続いて、何度もありがとうございます、と言ったのを覚えている。でも、どうにも鼻がつんとして、完全に涙がこぼれてしまって、「すいません」と何故か謝りながら、会話を続けた。受話器越しに相手の笑い声が聞こえて、でもその声が優しくて、あぁ一応歓迎されてるんだろうな、って思うとまた泣けてきて、そうこうしてるうちに電話を切った。
電話を切った後、やっぱり気になったのは小林くんの反応で、恥じらいがあったから泣いているなんて気づかれたくなくて、「企画、通ったよ」と一言だけ言って、部屋を出た。階段を登りながら、後ろから「よっしゃー!」という声が聞こえた。私は踊り場で止まった。止まったまま、声を聞き続けた。小林くんが、うちのたけぞう(猫)に「ホンマによかったなぁ」とそれは本当に優しい声で言ったものだから、えんえんと泣いた。
泣き声なんて聞かれたらこの後一生いじられるので、急いで階段を上って、そして上りながらまず電話したのが、彼女だった。彼女に電話をかけると、1コールくらいで出た。彼女は、「なに、なに、怖い」と言った。それは私が咽び泣いていたからで、彼女は「誰かが死んだ」と思ったらしい。私は怯える声を聞いて、「一番嬉しい時、自分は恋人に一番に伝えたくなる人間だったんだ」なんて隠れた自分の本性に気づきながら、「企画、通った」と答えた。彼女は、今にも空を飛ぶんじゃないかってくらいの甲高い声で喜んで、「よかったね」と続けた。それで私の涙は、堰を切ってこぼれ落ちて、もうどうすることもできなくなった。「よかった。本当によかった」と噛み締めた。電話を切って、ため息が出た。そこで私は、ようやく噛み締めたと思う。「本当によかった」と独り言を呟いて、煙草を吸いに外に出た。
小林くんも吸いに来た。一緒に煙草を吸って、何吸いかして、二人とも黙っていて、どっちから喋り出したのか、とにかく「よかった」と言い合った。あたりでは、発情期の野良猫がニャンニャン鳴いていて、その声を聞きながら、また「よかった」と繰り返した。
家に戻って、すぐに金田敬監督に電話をかけた。私から電話をするなんて多分初めてだったから、珍しそうな声で電話に出てくださった。
ピンク映画、やっと作れることになりました。
ホンマやっとやな。
やっとです。
うん、去年くらいに作ってもよかった。
はい、でもやっとここからです。
次は大事やぞ、もうプロですからね。
プロですか。
うん。プロや。
と続いた。2,3分で終わるかに思えた電話は、気づけば長電話になっていた。とにかく頑張ります、と終えた。そして高原秀和監督に電話。高原さんは、いつもの調子で、楽しそうに話してくれた。なんでも協力するからな、と言ってくれた。心強い味方だった。そこから、現役ピンク監督への質問という感じで、何個か気になることを聞いて、また聞きますし、お願いします、と図々しく返して終えた。
その後、帰ってきたカナリヤ結成時からのメンバー・古川くんに報告した。本当は落ちたと言って、発表まで黙っておくか、なんて小林くんと計画してたのだが、これまでの道のりを考えると顔を見た瞬間、言いたくなってしまった。いつもは驚くほどに声が小さくて、ローテンションな古川くんが、「マジで!?」と、一言だけ発して、上に上がっていった。その後すぐに降りてきて、小躍りを始めた。彼なりの感情表現が面白くて、3人で笑い合った。みんな、噛み締めていた。口々に「よかった」と呟きながら。
そして受賞の発表がTwitter上で行われ、私は想像以上の反応に尚嬉しかった。これまでご一緒した俳優の方々から温かいメッセージが届き、実際に企画を読んでもらったり、意見を聞いていた小林敏和さんや渡辺厚人さん、燃ゆる芥さんや長森要さんからお祝いの連絡が届いた。SNS上でも色んな人がメッセージをくれて、嬉しかった。みなさん、ありがとうございました。


これまでの経緯(大学時代)
思い返せば、この「新人監督発掘プロジェクト」と私の関係性は、2018年に遡る。当時、大学で『濡れたカナリヤたち』制作中だった。ピンク映画を作りたいと思っていた私は、大学でR-18相当の短編成人映画を企画していた。映像学科では、喧々諤々の雰囲気で、「そんなものを大学で撮るな」と幾人もの人に言われた。私は若干、その雰囲気に嫌になり、『新橋探偵物語』の横山翔一監督がこのコンペで受賞したことに羨望の眼差しだった。私の目標からすると、当然、目指すべき目標になり、早くこんなところじゃなくて、堂々とピンク映画を作りたい、そう思った。
それから、『やりたいふたり』の谷口恒平監督。やっぱり憧れた。やりたいふたりはすごく大きかった。『濡れたカナリヤたち』を経て、ただの憧れじゃダメだと自己嫌悪してる中でのそれだったから、羨望というより悔しさが強かった。小栗はるひ監督は、女性でのピンク映画挑戦。谷口監督とは違う魅力があって、性別なんて関係なく、悔しかった。そういえば谷口監督は、過去作品で川瀬陽太さんとやっていて、それもあって強烈に悔しさを感じたのを覚えている。少なくとも、この頃には目標というより「来る未来」として、捉え始めていた。きっと、応募資格を有していたら絶対に出していた。でもその時は、”劇場公開作品を監督している”という条件があった。私はその条件に合致していなかった。
そして卒業制作『海底悲歌』の準備に入る。一番最初に、「この作品は絶対に劇場まで持っていく」とスタッフに宣言をかました。それはやっぱり、このプロジェクトを意識したからに他ならず、あわよくば『海底悲歌』をそのままオークラに持っていく気でいた。それは結果的には成功したわけだが、とにかく、その頃、大学の先輩、鳴瀬聖人監督がピンク映画デビューした。私は、この頃実際に彼と会って会話を交わしている。「ピンクは難しいよ。ピンクもいいけど、もっと別の」という親切なアドバイスに怒り心頭だったのを覚えている。撮れたやつまでそんなこと言うんじゃねえよ、と思った。俺はそれだけがやりたいんだ、その席変われや、と思った。今となっては、同じように「ピンクに興味が」なんて学生と会ったら、同じ回答をする気がする。どうだろう。
で、色々と問題は起こったものの『海底悲歌』はオークラ劇場で上映が決まる。その時に、同時上映だったのが角屋拓海監督だった。ここでもやっぱり悔しかった。でも、この時は「次は俺だ」とバラ色の未来を見ていた。実際に、恩師・金田監督もそう話していたし、私はそう信じていた。
これまでの経緯(卒業後)
けれど、そこから私の短くも長い闘いが始まった。大学を卒業して、幾つもの企画が頓挫した。早速出そうと思った「新人監督発掘プロジェクト2021」も、応募資格の「劇場公開作品を監督している(成人映画は除く)」の文言で、出す前に撃沈。ずっと前からそういう規定だったみたいだが、私は項垂れた。戦うことさえできなかった。
最初は自主制作でピンク映画を作ろうと進めた。当然金も無く、1年目のフリーランス。地獄を見た。食うに困るくらいの勢いで、何度も親の脛を齧った。怪しい仕事もした。そんな中、当時いた佐藤くんと古川くんと3人で、毎週3つずつ企画を持ち寄って、何度も何度も会議を開いた。半年以上そんな日々が続いた。でもとにかくお金がないから、経済的な企画を、と2,30個の企画の中から2つに絞った。最終的に1つに絞って、それはホラージャンルの作品で、スタッフィングまで進んだのだが、『海底悲歌』の時にいたスタッフはみんな社会人で、難航した。いつまで経っても、進まなかった。そして、日々の貧しさからか、次第に映画の話をし合うことがなくなっていった。
そんな時、やっぱり寝ても覚めてもピンク映画がやりたい私は、官能小説を読んで、「これは」という原作に出会う。実際に作者に映像化の許諾もいただき、出版社とも話し合った。けれど、その前のホラーの企画で、我々スタジオカナリヤは仲違いじみていた。家では、ただ一人黙々と原作モノの脚本化という初めての難題にぶち当たり続け、それでも諦めちゃいけないと、眠る時間が短くなっていった。未熟な私は相談することもできず、最終的に体調を崩した。入院まで行った。結局、その企画は腹心だった佐藤くんがカナリヤ脱退となって、熱量を失った。技術的にも追いついていなかったのもあって、これは完成まで行けないと投げてしまった。
その後もVシネマの制作会社とやりとりを始め、覚えているだけで15個は長編企画を作った。先方に送ったのは、6個。どれも複数の人に意見を聞いて、かなり詳細なプロットもまとまって、好評だった。相手も好感触で、これはいけるんじゃないか、と思われたが、突如、連絡が途絶えた。企画は絞られて、企画書から初稿に向かっている段階だった。でも、途絶えた。頓挫だった。
そこから、失意の我々は、この頃にカナリヤハウスに住むようになった小林くんの卒業制作の企画へと移る。当分、全く映画に関わらなくなっていたが、重い腰を上げて、色々考え始めた。最初は成人映画の企画をして、そのまま乗っ取ってやろうと考えていた。でも、結局最後は良心が戻ってきて、小林くんがやりたかったアクション映画の制作に携わった。ここで1年が経った。実に50個以上の長編企画を考えていた。ピンク映画だけじゃなく、他のジャンルも死ぬほど考えた。思い返せば嫌になる日々だ。
その間、佐々木原保志御大の誘いもあって、大阪万博にまつわるドキュメンタリー映画を企図したり、映画だけでなく、YouTubeや音声メディアでの活動も行なった。
でもやっぱりピンク映画が撮りたい。何か変えなければと、金田監督に電話した。「助監督で現場に入らせてほしい」と相談した。ずっと助監督はやりたくないと、逃げてきた私だったが、やっぱり下積みをしないとこの現状を変えられないと思った。結果、高原秀和・石川欣監督の現場に参加することが決まった。色んなことを吸収した。実際にピンク映画の脚本を読んだのも初めてだった。昔のやつはいっぱい読んだけど、今の時代のピンク映画の脚本は初めてだった。ああこうやって作るのか、と感心した。1行1行のト書きを穴が開くほど読んだ。奈良から東京へ2週間の旅。泊まり先は、姉ちゃんが婚約を破棄して出て行く寸前の彼氏の家。なんちゅう環境だ。でも楽しかった。打ち合わせも衣裳合わせも楽しかった。個人的に辛いことが1個あって落ち込んだが、初めての商業ピンク映画製作を生で見た。高原さんも色んなところへ連れていってくれたし、スタッフの人とも話した。けれど、現場前日になってコロナで強制隔離となった。迷惑をかけた、まだ準備しかしてない、悔しい。でもそれ以上に、「何かを変えたくて、でも何も変わらなかった」と、一人で苦しんだ。帰りの新幹線は地獄だった。財布もなくして、スマホの充電も切れて、こういう時に限って雨が降って、「何してんだろ」って思った。
そんな時分に、「人手不足だから大学に戻ってこないか」と打診があった。即答で行きますと答えた。何も変化のないまま大学に戻ってきてしまった。次は仕事で戻るけど、もう一度学び直そうと心に決めた。
これまでの経緯(映像学科研究室)
大学に戻ると、学生時代に見えていなかったものが見えるようになった。学生が出してくる膨大な企画の数々や、初稿、2稿、3稿と延々と続く脚本作業、色んなレポートも読んだ。時間が空いたら、研究室に毎号送られてくる月刊シナリオ、月刊ドラマ、その他関係者たちの書籍や脚本集、卒業生の脚本、色んなものを手当たり次第に読んだ。仕事が終われば、大学の映画館で映画を見たり、一人で企画を考えるのが日課になった。そんな日々の中、学生と対峙して、意見を言う機会も増えた。ここはこうしたほうがいい、と第三者の目線から話すことで、これまで作った自分の企画にも問題を多く見つけた。何かが変わってきている、とそう思えた。
そんな中、できた企画があった。実際の事件をもとにしたピンク映画の企画で、これは絶対にいける、と思えた。大学に戻ったことで得た人脈を駆使して、製作費を出資してくれるプロデューサーを見つけた。初稿、2稿、3稿と改稿が進み、実際にスタッフィング、キャスティングに移行した。今回は、クラウドファンディングもして、もっと盛り上げていこうとなった。クラウドファンディングに向けて、色んな資料も作って、新たなスタッフも交えて、準備は順調に進んでいた。実際に撮影のスケジュールまで出ていた。「今度こそ、ようやくピンク映画が作れるんだ」と心晴れやかだった。でも、突然終わりがやってきた。出資者のガンによる他界。地獄だった。集めたスタッフを解散した。作った資料も全部捨てた。もうだめじゃん。こうも何度もつまづくと、そう思ってしまう。「映画が作りたいだけなんだ」と心の底から思った。でも言っても仕方なかった。
そして、程なく石井隆が死んだ。続いて、大森一樹が死んだ。石井隆は、私にとって大きな存在だった。石井隆がいなきゃ、私は佐々木原保志というカメラマンにのめり込まず、大阪芸大の門戸を叩かなかっただろう。大森一樹は、私のピンク映画を応援してくれた。大森一樹がいなきゃ、「こんなものを撮るな」と学内では一蹴されていたはずだ。学科長自ら賛同してくれたことで私は『濡れたカナリヤたち』『海底悲歌』を作れた。やっぱり暗い気分になった。辛いというより、”終わった”という感覚だった。
けれど、誰かが死んでも世界は回るわけで、自分がずっとできずにいることを何十人もの学生が1年間のうちに何十本と映画を完成させる。たった1本の映画を作れずに、何十という企画をゴミ箱に捨て、本棚に隠した私の前で、学生たちはいとも簡単に何十本という完成した映画を提出しにくる。楽しそうに、晴々した顔で私の前に立つ。どうにも、もどかしかった。もう解放されたい気持ちもあった。
その頃、OP PICTURESの新人監督発掘プロジェクトがあった。昨年まで闘う舞台にさえ立てなかった場所だった。でも、今回は「映画祭などでの上映歴がある」という規定に変わっていた。私は藁にもすがる想いで、再び机にしがみついた。この規定の変更は、自分を規定の中に入れるためのものなんだ、と信じた。俺が通らなきゃ、こんな業界終わりだ、と気合を入れ直した。そう思えたのは、やっぱり、学科長・大森一樹との最後の会話が私には重くのしかかっていたからだ。
「次もエロいんか? もっとやれよ、どんどん。」
ニヤニヤ笑いながら、いつものように喫煙所でしわがれた声で出た大森一樹の言葉だ。確か、秋口に入る間際だったと思う。大森さんの容態が瞬間だけ落ち着いて、久しぶりに大学に来た時のことだった。私はその時、「当たり前です。次はもっとエロいのやるんで、見ててください」と答えた。
連日連夜の打ち合わせの末、完成した企画書を、祈るようにポストに投函した。そして、そのままの足で、違う企画を考え始めた。ダメで元々、結果の発表の時に悪い方に転んでも苦しくないように、短編映画を作る、と息巻いた。学生のようにもっと楽しんで、もっと気楽に、もっと自由に映画を作ろう、とやりたかったことを挙げ連ねた。それは、苦しかった卒業後の日々が嘘かのようだった。ちなみに、その短編は今月末にインする。
※上記、短編企画は無事につい先日オールアップしました。
受賞した時の想い
だからこそ、やっぱり通ったって電話が来た時は、涙が出た。この時ばかりは、苦しかった日々にさようなら。嬉しさより、報われた安堵だった。口々につぶやいた「よかった」には、やっぱり私やカナリヤメンバーの想念の重さが込められていたと思う。私は、人生で初めて誰かからの電話で嬉し泣きをした。苦しかった以上に、報われた喜びがあった。
何度も何度も企画を読んでもらった方々からも、すぐに連絡が届いて、なんだかお祭りのようになって、受賞してすぐの毎日の飲み会を経て、やっぱり「よかった」という言葉しか出ない。でも、それが本当に幸せだと思う。
ここからが本番
けれど、大事なのはここからで。どんな映画になるのか、どんな物語になるのか、きっと苦しいこともあるわけで、私はでも、楽しみだと思う。きっと、1年前の自分じゃ、こうなっても楽しみには思えなかったと思う。でも、今の自分は楽しみに感じているのだ。
学生時代にはなかった色々なものを経て、一体どんな映画になるのか。企画の話はできないが、映画というのは、自分が今まで見てきた世界が描かれるわけで、私が愛してやまないピンク映画の伝統的な部分と、今の自分だからこその部分、その両方を取り入れられる作品に必ずなると思う。何より、『海底悲歌』以来の長編作品になるので、完成した後の自分に大きな期待を持っている。
みなさん、楽しみに待っていてください。
そして、必ず完成したら見にきてください。
少しでも私のことを応援したいなと思って下さった方、そのお気持ちだけで励みになります。その上で、少しだけ余裕のある方は、サポート頂けますと幸いです。活動の一部に利用させていただきます。
