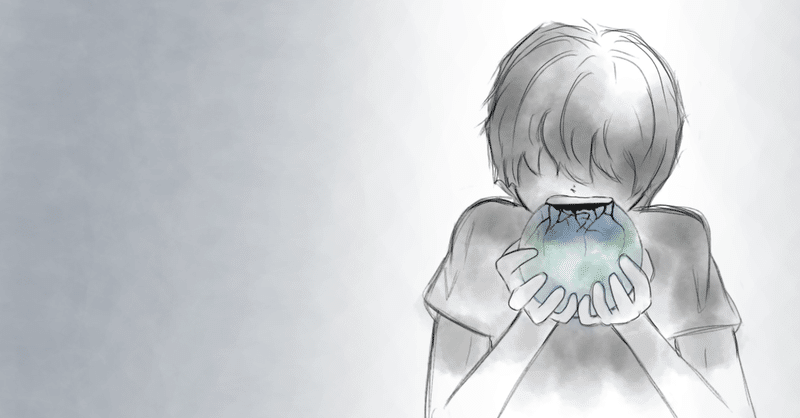
『世界は僕を拒む』①
家が貧しかった僕は、幼いころから働きに出ていた。父親の知人の高橋さんが、言わば僕の雇い主で、新聞配達から簡単な工場の作業員など様々な仕事を僕に振り分けていてくれた。学校には週三回登校できれば良いほうだった。しかし先生方が当然それを許すわけもなく何度も面談にはなったが、結局働いていることは秘密のまま何も変わらなかった。そんな話をするとあたかも苦労話に聞こえるが、僕はこの生活に満足していた。学校に閉じ込められ、いつ役に立つかも分からない勉強を延々とさせられるより、外に出て大人の話を聞いているほうがためになると思っていたし、稼いだお金はもちろん両親に渡していたが、『この年で働いている』という事実が僕にとってちょっとした誇りだったからだ。
僕が中学生に上がると生活は少しだけ変わり、学校には全くと言っていいほど行かなくなった。そこに僕の意志はなく、『中学は別に行かなくてもよいだろう』という大人たちの考えにより、平日はほとんど高橋さんと共にいた。
とある日、僕は工場でキーホルダーの袋詰めをしていた。僕は山積みの段ボールを目の前にパイプ椅子に座り黙々と作業をし、高橋さんはその隣で何かの本を読んでいた。高橋さんは高身長で吊り上がった細い目が特徴的な男性だ。口数も多いほうではないが僕が質問したことにはしっかりと答えてくれる。父親との関わりがどういったものかは知らないが、先述したように、僕が作業員で、高橋さんは雇い主であるから、高橋さんは一切、僕と同じ仕事はしない。しかし、幼いころから僕の仕事中は必ず僕を近くで見守っていてくれたから、高橋さんのことをとても優しい人だと思っていたし、信頼をしていた。
「僕、すっかり学校へ行かなくなっちゃったね」
高橋さんは持っていた本を閉じた。
「学校へ行きたいのか?」
「行きたいかって言われると、行きたくもないけど、自慢する相手がいなくなったなってたまに思うよ」
「自慢?」
「もちろん、働いていることは誰にも言ってないよ。でも、なんとなく僕は君たちと違って働いているんだぜって鼻を高くして教室にいるのが楽しかったなって」
「お前にとってこれは自慢なのか」
「そうだよ」
僕が最後に袋に詰めたそれを高橋さんに見せつけるように持ち、笑うと高橋さんは僕の頭をぐちゃぐちゃと撫でた。
「学校へ行きたくなったら言えよ」
「わかったよ」
僕が作業を再開させると、高橋さんもまた本を読み始めた。
朝9時から出勤し19時に退勤。そのあと高橋さんの家でご飯を食べ、家へ帰るのは20時頃なのだが、この頃では親が家にいない日も多くなった。初めのうちは不安もあったのだが、最近ではもう慣れてきてしまっていた。自分の分の布団を敷いて眠るだけ。ほんの少しだけ寂しいと感じていた。
翌日、仕事内容は昨日と引き続き、キーホルダーの袋詰め作業だった。高橋さんはコーヒーを片手にノートパソコンを開き仕事をしていた。
「最近、家に帰っても誰もいないんだよね」
「いつから?」
「昔から誰もいない日はたまにあったけど、ここのところはもう4日ぐらい続いてる」
「寂しくないか」
「寂しい」
僕がそう言うと高橋さんはゆっくりとコーヒーをすすり一息ついてから
「今日から家で暮らそう」
と言った。
「高橋さんの家?」
「そう」
「でも、お父さんとお母さんが帰ってきたら」
「二人には俺から連絡しておく。二人が帰ってきてお前が帰りたいというなら帰す」
「わかった」
僕がそう言うと、高橋さんはコーヒーを飲み干し、その紙コップを潰すと、ゴミ箱に投げ捨て、パソコンを勢いよく閉じた。そして立ち上がり
「じゃあ今日はもう帰るぞ」
と僕の手を取った。
「仕事は?」
「本来であれば、こんなのお前の仕事じゃない。しばらく家へ引っ越すんだ。荷造りしよう」
高橋さんは腰をかがめ、両手で僕の肩をつかみそう言った。
「ありがとう」
僕は、高橋さんの考えていることを少しもわかってはいなかったし、現状、僕がどんな立ち位置にいるのかさえも分かっていなかったのだが、高橋さんが僕に何か救いの手を差し伸べてくれているような気がした。僕は高橋さんの後を歩き、車に乗った。
【続く】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
