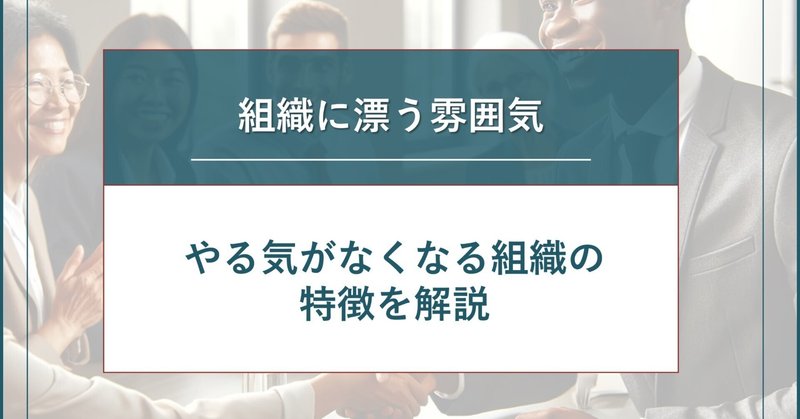
崩壊する組織に漂う雰囲気とは
事業の拡大に伴い、人も増やしていく戦略を取っている企業の経営者たちが最も苦しんでいること、それは「採用と育成」だと言います。
優秀な人材を確保したくても中々採用できない。
また採用できたとしても会社のカルチャーにフィットしない人たちもしばしば。
また、育成面に至っても中々機能する組織を作ることが難しい。など、
いくつもの課題に見舞われているケースも。
今回はこんな組織は危ない。ということで、
組織が崩壊するケースをまとめてみました。
組織の課題を客観的にまとめると

組織は本来、会社が目指すべき目的を果たすために作られた機能。なのだが、そこには組織の責任者を配置し統制を計る。
しかし、うまくいかない組織は、組織の責任者がある意味私物化してしまう。
・ 都合の悪いと判断した情報は、配下の人間には共有しない。
・ 責任者は絶対的であり、逆らうことも他の部署の文化を取り入れることも許さない。
役割であるはずの責任者というポジションが、
「偉い存在」という勘違いをつくり結果的に人も組織も支配する構造を作り出します。

その中で、個人の意見が採用されることはほぼなく、
中にいる人材は閉鎖的な環境と限られた情報の中で、考えることを放棄し疑問に思うこともなくなってしまう。
当たり前だが、この中から次期責任者や幹部候補が出てくるはずもなく、
会社の意図とは異なる人材になってしまうことが起こっている。
経営層の焦りは、現場には伝わりにくい
経営層と現場のマネージャーでは見ている視点が違うため、
責任者は意図を汲み取ることが出来ないケースも。
一方で、現場が何をしているのかを正確に把握できていない経営層が現場を信頼できない、または今の現場にフィットしたやり方ではない固定化された考えの元、組織作りに介入することでスムーズに進まないケースもある。



経営層と現場をつなぐ存在の必要性
現場を良く知り、経営層に正確にレポーティングし組織の課題を客観的に、時に批判的に意見をする存在を企業は採用するべきです。



ビジネスプロセスリエンジニアリングという考え方
正しいKPIの設計

スキルや事業に応じた組織の選択肢

組織にフィットするリーダーのあるべき姿

まとめ
1.事業の進むべき方向を会社全体で意識する。
2.経営層と現場責任者の間でずれが生じる。
3.現場責任者が組織を支配することを常に警戒する必要がある。
4.経営層は現場の意見を取り入れ批判的な考えも受け入れる必要がある。
5.全ては目指すべきKGIとコミュニケーションである。
6.客観的に組織やリーダーを見直す第3者の存在が必要。
7.スキルや能力に応じて組織の選択肢を持っておく必要がある。
8.常に改善するサイクルを作り、見直す必要がある。
irohaが最も得意とすることは、
BPR(ビジネスプロセスリエンジニアリング)として現状の課題に対して客観視点で改善サイクルを作ってきたことです。
組織に対するお悩みや人材育成に対してのご相談お待ちしております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
