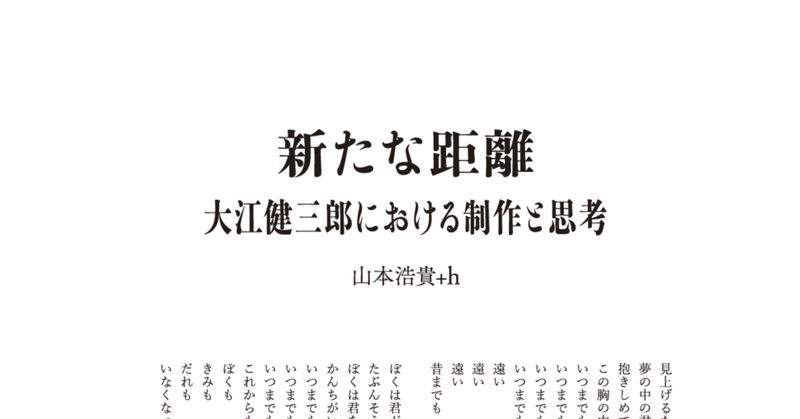
大江健三郎論を公開します
自分にとって、最も影響を受けた表現者です。
2014-5年(22-23歳)に、いぬのせなか座の立ち上げと並行して書いた大江健三郎論の全文を以下に公開します。
初出:『いぬのせなか座1号』いぬのせなか座、2015年
レイアウトと絡むところもあり、紙面PDFとなります。
見開きと単ページ、いずれも内容は同一です。
要旨は以下。
本テキストは、大江健三郎(一九三五−)の小説作品、とりわけ『水死』(二〇〇九)を、小説制作に伴う思考の問題をパフォーマティブに扱ったテキストとして分析する(ないしは相応の分析言語を制作する)。その際、大江が駆使していることで知られる「擬似私小説的手法」……書き手と語り手が混同され、過去作で組み立てられたフィクションが現実のものとして想起され、「私」の書き直しが土地や社会の巨大な神話へとゆれひろがっていくという、彼の達成したその技法を、小説という表現方法の内的性質を極端に発達させたものとして、考えていく。これは、本テキストで用いられる私が、小説という表現方法を、書くたびに生まれる言語表現主体に関する情報の、ひたすらな書き直しによって書き手自身の思考を発達させていく過程、ないしはそのような発達の技術の伝達過程として捉える立場を、かたちづくろうとしていくものであることを意味している。一方で、こうした小説への立場のかたちづくりは、小説を印刷された文字列の内に留めることなく、テキスト外の人間や、彼らを取りまく環境にまで広げて再定義していこうとする過程と、表裏一体でしかありえない。結果、この私は、従来のテキスト分析が陥りがちな、書き記された言語への過度な依存ののりこえや、非言語中心的思考へある種の反発として推し進められる傾向のある昨今の哲学・芸術理論の領域へと、小説の近辺に蓄積されてきた技術や理論を渡し開いていく営みの、双方をもまた、自らの意図として組み上げていくものでもあることになる。
Ⅰ.小説的思考。大江は、小説とはなにか、という問いへの答えを、書き記された文字列ではなく、その表現過程にこそ見ていた。《この自分は私でありながら、私じゃない。私はかれだ、父親だ。》(『水死』)という文章は、それ単体では異様だが、全体を読み進めるなかでは、複数の言語使用方法が重ねられたかたちとして知覚されるという点で、その思想を具現化している。小説は、複文がひとつの場で立ち上がるかたちでの思考からこそ成り立つものであり、そのような思考は、単文を複文たらしめる私の同一性が、印字の外に、ひとつの素材として設けられることで、そこにおいて、展開される。この際、私の同一性を折り重ねたり破砕したりする性質をもったものとして、映像機器や録音装置、絵コンテ、演劇における身体などといった、多くの非言語的性質を持ったイメージが用いられ、それ自体、語りの多層の媒質として機能する。
Ⅱ.分散と統合。印字の外に小説の表現過程があるとして、その外は、テキストを蝶番に、ふたつ、想定される。言葉の刻まれる余白(=奥)と、言葉を見つめ触れる人間(=手前)である。『水死』で語り手の前に飛来する二行の詩は、語り手と読み手を類似させながら、それの刻まれている石碑=隕石を経由して、大江の小説に頻出する概念「森のフシギ」へと到り、複数の言表行為を受け止める余白への思索を露わにするが、同時にそこで、余白に刻まれた言葉が複数の「私」をひとつに圧縮する手続きを、大江が転生と呼んでいたこともまた明らかとなる。書き記された言語に、それぞれを表現する主体の認知が保存されているという事態を、大江が「文体」と定義するとき、印刷された文字列は、書き直しや忘却に伴う認知限界などによって無数の時空間に分散させられた言語表現主体たちと、それらを囲む環境群が折りたたまれた奥行きとして、捉えられるようになる。そこでの思考は、ディープラーニングのような並列分散処理的性質を持った自発的な概念形成システムとしてありうる。
Ⅲ.分身。複数化した言語表現主体による思考は、単一の主体には収束しえないが、しかし収束しえないことをもってして最大限の思考としてしまえば、表現過程を通じての言語使用方法の変容は生じず、「私が私であること」の余白は全体主義と似通うことになる。これを大江は、表現のなかへ事後的に見出される不可視な「分身」の問題として検討する。重要なのは、「分身」概念の裏地に、「本当のこと」と呼ばれる環境内不変項(地形学的構造)の探索が縫いつけられていることである。小説を作ることで生まれた無数の私らによる環境への反復的働きかけは、多宇宙のイメージを伴いながら、現実・虚構という区分を調停するような運動を、自らの原動力として用いる。それら運動の総体をひとつに取りまとめようとする小説家は、息子と自身のふたりの年齢を掛けあわせたものに前後数十年を加えた「二百年の子供」として、私をほんのわずかだけ隣へ拡張させる。
Ⅳ.教育。転生を成功させる言葉の運用に関して、大江が「教育」という概念を記すとき、『水死』において、夏目漱石『こころ』を題材にした演劇の上演場面が、「教育」の小説的実践として浮かびあがる。それは、抽象的な言葉の配列を具体的に知覚する主体を、言語使用方法として包装し、読み手のもとへ転生させる「教育」であり、大江が小説論で盛んに取りあげる「異化」の、発展したかたちだ。そうした「異化」を十全に果たすものとして詩が定義されるが、ひるがえって小説は、詩の生じる環境、歴史の組み立てられる時間そのものを、彫刻しようとする。
Ⅴ.技術。言葉の配列を読む際、人間に類する存在を指示する言葉は、演劇的教育を介して、周囲の言葉らを自らのもとに収束させる傾向がある。この、語り手生成の回路を素材にして、遠く離れた場所にあるふたつの語り手を交通させるのが、「おかしな二人組」という技術である。これは、土地や動物らと人間とのあいだのカップリング、ないしはそれによる言語使用方法のクレオール化の可能性を、開設する。擬似私小説的手法がその拠り所としていた「私が私であること」の分散と統合は、無数の非言語表現主体ら(とりわけ言葉で自らをうまく表現できない息子)へ貸し与えられることで、私の死後に生きる「新しい人」が、環境内不変項の探索とともに制作される。こうして小説は、フィクションにも、また書き言葉にも限定されることのない、ひたすらに身振りでもって私を死後へと転生させ救出しようとする試行錯誤の思考として、あらゆる瞬間、あらゆる場所に散らばり断線した私らの内側にあってそのつどの私をゆるがす「新たな距離」と、呼び改められる。歴史のうちで、完全に消え去ったものらに向けた技術の実在を、あちらこちらに「かたち=模様」として証明しながら小説は、自らを用い、技術を探す生活、それへの参与を私らに(いつも)強いる。
自分にとって大江さんは、「いえの近くのあのあたり出身の有名な作家」であり、子どものころからなんとなくの親しみを持っていました。
『水死』発売時にふと書店で手に取り、決定的な戸惑いと揺さぶりを受けて以降、自分のなかで最大の、問うべき「小説家のモデル」でした。
一度、ご自宅でお話をうかがったことがありました。忘れ難い時間でした。
山本浩貴(いぬのせなか座)
※2023/06/29追記
上記大江健三郎論を掲載した『いぬのせなか座1号』を増刷しました。紙で読みたい方はこちらをご検討ください。
また、『ユリイカ』2023年7月臨時増刊号 総特集=大江健三郎に寄稿しました。もう少しだけ踏み込んで、追悼めく内容を書いています。良ければこちらもご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
