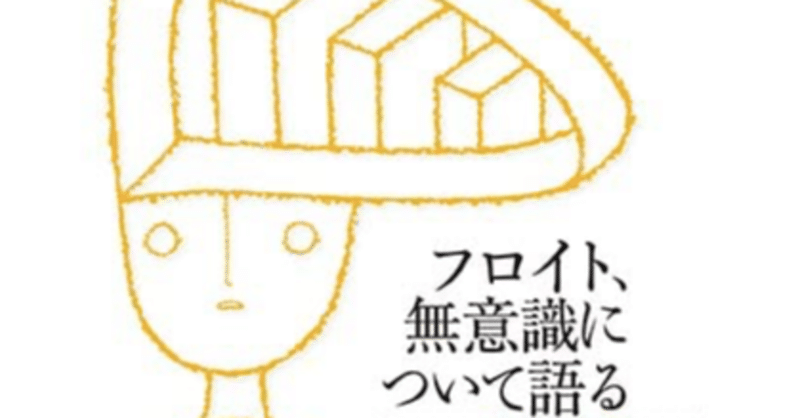
【心理学】フロイトの語る無意識について
フロイトの無意識についての本を読んだので、面白かったところや興味深い内容を紹介します。一文が長く専門用語が多い本なので、あくまで個人的に面白かったところや気になったところをまとめています。
快と不快の原則→現実原則
人は誰しも心的動作の一次過程において快を求め不快は避ける。これを快と不快の原則(快感原則)という。この不快から心の働きを撤収しようとする働きが抑圧である。
誰しも上記の原則に従い夢や空想で自らの願望をみることができるが、そのような幻覚では期待した満足を得ることはできず、失望をすることになる。
その失望による抑圧から逃れるため、心的な装置は現実への認識を実際に変える決意をする必要がある。例え不快なものであっても、何が現実のものであるのかを思い浮かべるようになった。これが現実原則である。
この現実原則というものは、どのような結果をもたらすか確かではない刹那的な快感を放棄するかわりに、将来獲得できるであろう快感を新しい方法で獲得することを目指しているのである。
※フロイトはこのことを、快と不快の原則(快感原則)→現実原則の順序が、人間の認識においては逆転していると表現しています。
宗教と科学
上記の快と不快の原則と現実原則の入れ替わりは、社会に大きな影響を及ぼしている。例えば多くの宗教で行われる「現世での快感を放棄する代わりに来世で報酬を得る」という教えは、この心的な転換が神話という形で投影されている。
様々な宗教は一貫してこの手本を見習いながら、来世での報酬を約束して現世での快感を否定しているのである。
また科学もその仕事を遂行することで知的な快感を得ることができると約束している。
※宗教も科学も、今ここで得られる快感を否定する思想や活動であるものの、実際は空想もしくは未来において期待される快感が原動力になっています。そのため人間は快と不快の原則(つまり原始的で動物的な心理原則)から逃れることはできない、ということをフロイトは語っています。
抑圧について
フロイトは心理学の研究と現場での患者の診断を通じて、あらゆる精神疾患や神経症、問題行動の根本にあるのは抑圧であると語っています。
ちなみに抑圧が発生することで、無意識と意識できる限りなく深いところのはざまに、本能的な欲動のエネルギー(リビドー)が注がれ、それにより様々な認識や行動が生まれるとフロイトは語っています。
この本では抑圧、転移、反動形成について専門的な言葉を交えて非常に難解に語られていますが、以前の私の記事で抑圧から心を守ろうとする防衛機能の種類についてまとめているので、よければ読んでみてください。
おわりに
メンタリストさん的な面白さは皆無ですが、役に立つ風の心理学ネタも大元をたどればフロイトにたどり着くわけで、読んておくと巷にはびこるキャッチーなネタに振り回されなくて済むメリットはあるかもしれません。
ちなみにフロイトのいう無意識とはどんなに意識しても到達できない深いところにあるものであり、私達が日常的に使う無意識とは意味が異なるみたいです。この記事では、個人的に読んでいて面白かったところだけを簡潔に書いてみました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
