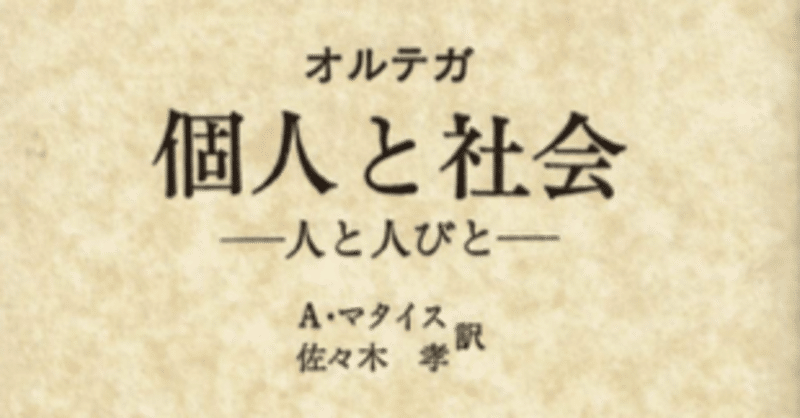
オルテガ「個人と社会-人と人びと-」まとめ
数年前に読んだ大衆の反逆がツボだったので、より内省的で思索的な表題の本を読んでみました。
その中から印象的な部分を箇条書きで51個まとめてみました。
一文が長く難解な表現が多いので、意味が変わらないようにシンプルに添削している箇所も多いです。そちらを踏まえて目を通してもらえたらと思います。
(1)人間と他の動物との違いは深い思索ができることである。しかし魚が泳ぐこと、鳥が飛ぶことに比べると、人間は生きる上で深い思索を必要とはしていない。それゆえ人間はどのような行為をしていても人間であることに絶対的な自信を持つことはできない。
(2)神話を広めんとする者はあらゆる手段を用いて人々を熱狂させ、熱狂と恐怖の中でわれを忘れさせる。人間はこのような熱狂と恐怖で深い思索能力を失い自分自身であろうとする自我を裏切る。
(3)人間が他の動物と異なる特性は自己の内部に入り込むことであるが、何らかの要因でそれが叶わなくなると自己疎外の状態になり、動物にまいもどってしまう。
(4)人間的生において、本質的には他から課されたことや前もって定められたことなどは何ひとつない。まったく自分だけの責任の下に、自分自身のために、自分自身の立ち合いのもとに選択と決定をしているのである。他人の意思に流されるという選択も、その人自身が決定しなければならない。
(5)すなわち生は他に譲り渡すことのできないものであり、各人が自分自身の生を生きなければならない。生きるという課題は誰も肩代わりすることができない。ある人が感じる歯の痛みはその人自身しか感じることができない。
(6)人間は本質的に孤独である。真実の愛と呼ばれるものは二つの孤独を交換しようとする試みにほかならない。「われ」と「なんじ」は内と外であり、多少の差はあれ異質のものなのである。
(7)生きる人間は周囲もしくは環境のなかで生きなければならない。その世界は境界線がかすんで見えるほど巨大なものであり、鉱物、植物、人間と呼ばれる様々なものではち切れんばかりに満たされている。
(8)世界はひとえに私との連関によって構成されており、良きにつけ悪しきにつけそれらに依存している。つまりあらゆるものは、私に好意か敵意を持つもの、愛撫か摩擦、へつらいか損傷、奉仕か損害なのである。
(9)人間が何かをする振りをするというのはとても興味深いことである。女性的ではないのに女性のふりをする女性、ほほえむふりをする、軽蔑するふりをする、望んでいるふりをする、愛しているふりをする。このように人間は本気でやろうとしないために何かを行うという奇妙な習性がある。
(10)人間的生とは
①原初的意味において各人の生であり、極めて個人的なものである。
②根本実在は、一定の環境の中で常に何かをしていなれけばならないということ
③環境がわれわれに対して様々な行為の可能性と存在の可能性を与える
④他に譲り渡すことはできないものであり、自分の行為を決定すること、痛みや苦しみなども同様に私が引き受けなければならないものである。
(11)世界とは要件や必要事のもつれであり、その中に人間は好むと好まざるとに関わらず織り込まれている。そして人間はこの要件の海で泳ぐべく定められており、またどうしようもなくそれらが自分にとって重要であるよう強いられている。
(12)私自身の生が根本的に孤独であるように、他者の生も根本的に孤独である。つまり他者からすれば私は他者所(よそ者)であり、我々の世界はぴったりと一致することはできない。
(13)宗教は特定の神々を天国にいる高き者として特別扱いをする。その反対に劣ったところ、つまり地獄に悪魔を位置づける。
(14)馬と関わる人間は馬に蹴られないように気をつける。このように他者が我々の行動に対して行動することが、我々の行動の構成要素になっている。
(15)好むと好まざるとにかかわらず、相互性は互いに「考慮し合う」こと、社会的なるものとしての第一の事実である。誰もが他者として、ある者として誰かの応答者として社会性のなかに現れるのである。
(16)石に何かを語りかけたり触れたりしても石の方から何か反応が来ることはない、動物は極めて限定的なレパートリーでそれらに反応をする、しかし対人間の場合にはそこに社会的事実が生まれる。
(17)人間は根本的孤独を社会的事実を踏まえて様々な相互浸透の試みを実践する。私の生を他者に与え、また他者の生をもらおうと望みつつ、われわれとしての非-孤独化を試みるのである。
(18)我々が生きるところの大多数の物は、推定的なものばかりであるばかりではなく偽りのものである。それらは人間環境の中で人が名づけたり定義したり、あるいは評価したり正当化したりするのを耳にしたものに過ぎない。
(19)つまり我々が認識しているあらゆるものは擬似的なものであり、我々は擬似物を用いて何事かを常に作り上げる擬似行為をしていることになる。それが上述の「何かをやるふりをする」という行為に繋がっている。
(20)他人の眼がある限り人は完全に裸になることはできない、他人の眼がある限り、人は自分自身の眼から自分自身を覆ってしまうのである。
(21)哲学はそうした擬似的なもの、因習的生への批判であり、それらの因習を真正なる生、仮借なき孤独という法廷の前に引き出して行わなければならない批判なのである。つまり哲学は科学ではなく、むしろ不謹慎なことである。
(22)人間は自由であることによって、その運命に対してもまた自由である。つまり自由を引き受けることも抗うこともでき、あるいはそれと同じことだが自分が運命と一致することも、運命と一致しないこともできるのである。
(23)我々は過去の中に否応なく登録されているのではなく、むしろ過去のほうが、あらゆる瞬間に、我々の未来的存在の自由な創造へと我々を投げ出すのである。
(24)我々の生的知識は浮動するものであるが、それはその知識のテーマである生や人間が、すでにそれ自体新しい可能性に常に開かれている存在だからである。
(25)もちろん我々の過去は我々の上にのしかかり、未来においてあるものより我々を傾けさせるものではあるが、しかし我々を縛りつけることもしなければ、我々を引きずることもしない。我々を固定した存在にするのは死んだときだけである。
(26)女性は男性よりも己の肉体に対して知覚的である。女性は男性よりも身体を世界と自我の間に置かれたものとして認識している。そのことにより女性は装飾、清潔、礼儀作法、女性らしいとされる繊細な身振りという発明を完成させた。
(27)世の中にはほとんど因習性という疑似-生しか生きていない人もいれば、これとは反対に自己の真正性に忠実な他者を伺いみる場合もある。この両者の間にあらゆる中間の方程式が与えられている。
(28)他者との交わりの最初の瞬間から、我々は無意識で相手の生の方程式を、つまり彼の中には因習的なものがどの程度あり、真正なるものがどの程度あるかを計量しているのである。
(29)この因習的の計りを経て、接吻するか棒で打ち合うかは不明だが、他者が汝(なんじ)となり、我と汝は我々となるのである。そのことは我を根本的孤独としての生の中ではなく共存という第二の実在の局面に生まれるのである。
(30)我々の関係が親密であるほど、一般的かつ理論的な知識よりも、直観的ならびに個別化された要因が増大する。
(31)すべての社会は同時に何らかの割合で非社会的であり、すなわち友人と敵の共存なのだ。
(32)我々がときに一枚の絵だったり、一つの成功だったり、一人の女性だったり、同じものをめぐって戦わなければならないときに起こる積極的な否定は、ときに私に自分の限界を、ときに汝の世界ならびに汝との境界線を発見させてくれる。
(33)人口密度が最大の場所、例えば極東、中国、日本などは人々は互いにあまりにもくっつきあっていて、ほとんど重なりあって生きなければならない。そうしたところでは礼儀作法や儀礼的礼式が極端に発達し、例えば日本の場合はあなたの代わりにそちら様と言ったり、私の代わりに拙者などと言われるのである。
(34)我々が法的に禁ずる、命令すると呼んでいる行動の主体は警官でもなく、市長や首相でもなく、言うなれば国家である。国家とは全てであり、社会、集団である。
(35)警官が我々の歩行を阻むのは、彼の個人的な動機から生まれるものではないし、我々に対して人間対人間として差し向けるわけでもない。この善良な警官は人間ならびに個人としては親切だったり、我々の横断を許すほうを望んでいるかもしれないが、しかし彼は自分の行為を生み出すのは自分ではないという状態にある。
(36)もし誰かが今日の午後、兜や鎧や槍を身につけ道を歩いたとしたら、今夜は精神病院か留置所で夜を明かすことになるだろう。それは慣習でも習慣でもないからである。
(37)それと同じことをもしカーニバルの日にやるとすれば、人々は彼に仮装行列の一等賞を与えることも考えられる。そうした祭で変装することは慣習であり習慣だからである。
(38)いつものことを我々がするのは、それが一般に行われていることだからである。一般に行われていることをするのは誰か、それこそが人々である。
(39)我々は多くの行いを自分の考えからではなく、とらえることの不可能な、不特定の、責任のない主体、すなわち人々、社会、習慣の考えとして話すのである。私が自分の個人的な根拠から考えたり、話したりするのではなく、そう言われていることやそう考えられていることを繰り返すほど、私の生は私のものでなくなり、私は本来の極めて個性的な人間ではなくなり、社会の名のもとに行動することになる。つまり私は社会のロボットになり、社会化されてしまうのである。
(40)多くの組織や共同体でみられる集団的魂、社会的意識というものは、手前勝手な神秘思想である。すなわち集団は確かに人間的なものではあるが、それは人間不在の人間的なもの、精神不在の人間的なもの、魂のない人間的なもの、非人間化された人間的なものであるということである。
(41)集団の中での個人は、みずからは理解していないレコード盤を載せられた蓄音器のように、あるいは自分の軌道に対しては盲である天体が回転するように行動するのである。
(42)服を着るということ、挨拶をすること、社交パーティでの握手など、多くのことが決して我々によって十分に責任ある根拠を持って考えられたものではなく、私の中から出てきたものでもなく、それが慣習であるがゆえに繰り返されているのである。
(43)挨拶という行為を避けると「しつけのなってない自惚れ屋」として周囲はその人を見るようになる。しかし群れの人間以外は危険な敵であった原始時代と違い、現代において挨拶の必要性について具体的な動機は見当たらない。つまり現代において人々の挨拶は、階段で転んだ人が「落ちる」という動作をするのと同様に、重力の必然に従って行われている。
(44)慣習とは、自然のもっとも測り知れない秘密と同じように意味もない神秘であり、我々はこの世に生をうけて以来、慣習という大海の中に沈められて生きているのであり、最も強力な実在であり、社会的環境もしくは世界なのである。
(45)慣習は設定されるにも時間がかかり、消失するにも時間がかかる。
(46)慣習は巨大な構造物を構築しながら、違いに繋ぎ合わされ、互いに根拠を持ち合うのである。その巨大な慣習の建造物こそがほかならぬ社会なのだ。
(47)慣習は、そして集団は、そうしようと思わないのに、いつも個人の生活を見張っているのだ。
(48)社会というものは、我々にありきたりのメニューを示すことによって、朝食を何にしたら良いかと頭をひねる労力を省いてくれる。この極めて単純なことこそ、社会が存続する決定的理由である。
(49)人間の中には他のどのような動物にも与えられていないような内面世界があったのである。誤りはその内面世界が合理的なものであると考えられたところにある。
(50)我々の見解のほとんど全てが、見解であるにも関わらず、なんら合理的なものではなく、言語や挨拶と同じように慣習的で、機械的で、押しつけられたものなのだ。
(51)社会的しきたりは、起源がどのようなものであれ、我々の個人的な支持不支持に関係なくそこにあるものであり、我々が考慮しなければならず、強制力を及ぼすものである。逆にいうなら、社会的しきたりとは、我々がいつでも助けを求めることのできる権威、権力としてあるものである。
上述の大衆の反逆よりもよりも読みづらく理解が難しい本ですが、大衆の反逆と同じように、特にしきたりを重視する日本人にとって有益な本だと思いました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
