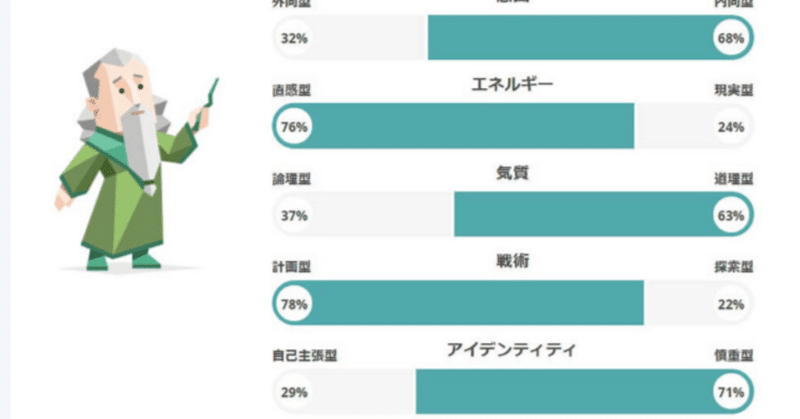
ビッグファイブ⇄MBTI(ビッグファイブ編)
ビッグファイブの特定5因子を、MBTIの知識も交えて考察してみました。
似ているところ違うところ、新しい着眼点などが見つかるきっかけに繋がればと思います。
仮説的、推論的な内容も多いので参考程度にでお願いします。
外向性
一言でいうとポジティブな事柄への反応度を表します。
MBTIでは他人や外界と関わる時間で充電されるE型(外向型)と、一人で個人的な時間を過ごすことで充電されるI型(内向型)に分けられますが、ビッグファイブの場合はこれが対人間というよりは刺激全般への意欲に置き換わります。
ここでいう刺激というのは身体的、感覚的な事柄や精神的なものを含めており、ドーパミンやアドレナリンと関連した興奮、高揚に関連するものになります。
これには大脳新皮質の一部が関わっていて、外向性が高い人ほど覚醒レベルが低いがゆえに刺激を必要としていて、外向性が低い人ほど通常時で既に覚醒しているので特に刺激を欲することがないということになります。
結果として外向性が高い人のほうが楽しい場所やイベント、名誉や賞賛、物質的もしくは精神的な報酬を得られるチャンスに意欲的になるので、世間一般的でいうポジティブな人間像に一致しやすくなります。
その反面、刺激を欲するあまり危険を省みなかったり、過度なリスク選好、アルコールやギャンブルの依存症になるリスクなども(外向性が低い人と比べると)高くなります。
ちなみに外向性が低いからネガティブということではなく、単にポジティブな事柄に対して反応するのが(外向性が高い人と比べると)面倒で、フラットで落ち着いた状態を好むということになります。
MBTIとの関係
上述の通りMBTIの外向内向とは基準が異なるのですが、ビッグファイブの外向性が高い人のほうが人との関わりを通じた刺激に楽しみを見出しやすいので、結果としてはMBTIと同じようにE型の方が外向性は平均的には高くなると思われます。
しかしMBTIでE型でも人との関わり以外においては落ち着いたライフスタイルを好む人もたくさんいますし、逆にI型でも野心家や刺激的なライフスタイルを好む人もたくさんいるでしょう。
その違いに関わるのは心理機能でいうところのSeやTeになり、主機能がI型だとしても、第二機能などでSeやTeによる影響が大きい人は、ビッグファイブでは外向性が高い人になりがちかもしれません。
これはSeが楽しさやスリルといったポジティブでアクティブな事柄を好むことと、Teが社会的な評価やステータスに好意的なイメージを抱きやすいことが理由になります。
開放性
創造性、多面的な解釈、クリエイティブな発想に関連した資質になります。
MBTIのN型と相関性が高く、N型の人は開放性が高いといって過言ではないと思います。
前述の外向性がポジティブな反応度、後述する神経症傾向がネガティブな反応度とすると、開放性が高い人はポジティブとネガティブの両面を捉えるのを好む人が多くなります。
開放性が高い人ほど革新的、芸術的、先進的な事柄を好み、開放性が低い人ほど伝統的、現実的、慣習的な事柄を好みます。
開放性が高い人の方が平均的にIQが高かったり、MBTIの場合「N型は木をみて森をみずにならず、全体的に物事をみれる」という表記があったり、好ましいこともたくさんあります。
しかし現実社会においてほとんどの労働は開放性の高さを特に必要としていないので、開放性を存分に発揮できる環境に身を置けるのは一握りなのではないでしょうか。
このあたりがネットでN型が社会不適合とネタにされたり、後述する誠実性が高い人はどの分野でも活躍しやすいという事実に繋がることになります。
MBTIとの関係
先ほど紹介した通り開放性が高い人の内容はN型の説明とほとんど同じになります。元々MBTIはN型に優しいというか甘いところがあり、N型を引き寄せやすいメソッドになっているので、この記事を読む人ならN型についての説明は不要かと思います。
MBTIにおいてはN型とS型が対極的に描かれてますが、ビッグファイブでは開放性と誠実性はトレードオフの関係になりがちです。
分かりやすい例としてはNe主機能(開放性が高い)がSi劣等(誠実性が低い)になることで、このNeとSiの関係性は脳科学的にみても正しいということになります。
ちなみにNi主機能の場合はもう少し複雑で、主機能はNだけれどSiが劣等ではないせいか誠実性がそれなりに高い場合も多く、先ほど開放性と誠実性のトレードオフ関係に当てはまらないケースも目立ちます。
MBTIの人口比率をみると、同じN型でもNJ型はNP型より少ないのが共有認識ですが、これはビッグファイブでいうと開放性が高いけど誠実性もそこそこ高いということで、つまりトレードオフに反した人の少なさが、MBTIの人口比率に反映されているのかなと思われます。
逆をいうと、同じN型でもNeユーザー(NP型)の方が、誠実性というパターンや規律に縛られず自由な発想にエネルギーを全振りできるので、多くの人が想像するような「クリエイティブな天才肌の人」のイメージに合致しやすいのではないでしょうか。
TwitterとかでYoutubeで面白いことを言って注目を集めているのも、Neユーザーの人がすごく多いですからね。
協調性
一言でいうとみんなで仲良く人道的にという特性になります。
協調性が高いほど集団主義、低いほど個人主義的な行動言動が多くなります。
愛情ホルモン、絆ホルモンと呼ばれるオキシトシンとの関連が強く、協調性が高い人ほど、いわゆる世間一般的に優しい人、思いやりがある人という人物像になりやすいです。
協調性がプラスに作用すれば仲間を大切に人に優しくとなりますし、マイナスに作用すれば出る杭を打つ、合わせない人に対して排他的な態度を取りがちになります。
逆に協調性が低い人はよくも悪くも個人主義なので、周囲の人的な状況や構造に惑わされず理性的、合理的な選択をしたり、物事を正確に捉えるという強みにも繋がります。
女性のほうが男性よりも協調性が高く、横の繋がりを意識するような脳の構造になっています。巷でよく女社会は…と語られる多くの事柄はこのことが影響しているのでしょう。
協調性の低い人のほうが会社組織で出世しているという統計があります。これは出世するほど対等な関係の人は少なくなりますので、本音で話せる人が少なくなることも影響しているのでしょう。
ただ協調性が低い人が、協調性をおろそかにしすぎた結果、あまりにもオキシトシンが欠乏した状態になり、事件やトラブルを起こしていることも巷には多いので、協調性の高低に関係なく他人をリスペクトできたほうが賢明かとは思います。
MBTIとの関係
分かりやすく協調性が高いのはFeで、協調性が低いのはTiになります。
F型は優しくてT型は厳しいという言説がネット上にはよくあります。
言いたいことは分かりますが、個人的にFiやTeは優しさ厳しさとは直接的に関係がなく、その人や状況次第になるかと思いますので、FeとTiの対比が協調性においては分かりやすいです。
※もちろん全体的にみればT型よりもF型のほうが優しさを大事にしている可能性は否めないですが...
TiユーザーがFeを強く求められることにストレスを感じるのは、みんなと和気あいあいと世間話をしながら難しい数学の問題を解いたり複雑なパズルに挑戦することが出来ないのと同じで、決して心根が冷たいというわけではなく思索が邪魔されるのがストレスになるからでしょう。
逆の立場で考えると、オキシトシンを補充したいFeユーザーが、一人で自分なりの答えを出せと孤独な境遇に置かれ続けるのと同じベクトルのストレスかも知れません。
挨拶をしっかりしよう、お客様に感謝しよう、飲み会で腹を割って語らうことが大切だという、具体的根拠はないけれどなんとなく大事にされている慣習(しきたり)が世の中にはたくさんありますが、それらを守るものを仲間として受け入れたり、反対に排除したりするのは、Fe(協調性)が大きく作用しているようです。
誠実性
一言でいうとコツコツ真面目に物事に取り組む力になります。
ウサギとカメでいうところのカメのような資質を表す指標になります。
世間一般で語られる(人柄的な意味での)誠実さと一致するわけではありませんので、誠実性が低いから信用ならない不誠実な人間ということではありません。
誠実性が高い人ほど、決めたこと、与えられた職務、その場で請負った役割に対して忠実に取り組もうとするので、いわゆるGRITする力、物事をやり遂げる力が高いです。
一般的な会社員生活、安定した結婚生活などライフスタイルの様々な面で誠実性の高さはプラスに働くことが多く、健康のために運動を続けたり、いわゆる丁寧な暮らしをして精神的な余裕も育みやすいと言われています。
その反面、アドリブ対応、予測不可能な状況、臨機応変で柔軟な対応は苦手で、これらは誠実性の低い人のほうが得意だったり、上述の開放性が高い人の方が打開策を見出せるかもしれません。
音楽で例えると、クラシックの楽団員のように与えられた役割を果たす、またそのポジションを勝ち取るために楽曲を完璧に弾きこなす努力をするのは誠実性が高い人のほうが強く、ジャズのように会場の雰囲気やメンバーと波長を合わせたり、時にはトリッキーに働きかけたりといった即興性が高い環境は誠実性が低い人の方が好まれるということになります。
MBTIとの関係
誠実性の高さと関係する内容が多いのはSi、Teで、それに比べると相関性は落ちますが関連していそうなのはFe、Seあたりになります。
またP型よりもJ型、N型よりもS型のほうが平均的に比べると誠実性が高いという予測も成り立ちます。
このあたりを整理すると、
誠実性が高くなりがちなのは
①SJ型
②SP型(個体差が大きい)
③NJ型(個体差が大きい)
④NP型
という順になります。
日本人は慣習に従う人が多い、空気を読む、管理されていることを好むと色々な分野の有識者が語っていますが、これらはMBTIでいうとSJ型がマジョリティになっていることが影響しており、つまり誠実性の高さが世論のスタンダードになっていることになります。
もちろんこのことは勤勉で真面目な日本人像を表しており強みになっていますが、誠実性の好ましくない面、MBTIでいうTeやFeを押し付けがちになるあたりが、色々な面で問題になっているのも事実だと思います。
神経症傾向
最初に紹介した外向性がポジティブな事柄への反応度だとすると、神経症傾向はネガティブな事柄への反応度となります。
脳のストレスや不安と関連のある扁桃体が強く影響しています。
ジョジョの奇妙な冒険の一巻の最初に「二人の囚人が鉄格子の窓から外を眺めた。 一人は泥を見た。一人は星を見た。」という詩が載せられてますが、ここで星を見たのは外向性が高い人で、泥を見たのが神経症傾向が高いというイメージです。
神経症傾向が高いことによるメリットは、例えば皆が素晴らしいと評価していることに悲観的な感情を抱きやすいことで集団浅慮を防げたり、不安や恐怖を糧にトラブルを避けられたりすることです。
デメリットは不安をもとに考えることで、何もしないほうが得策だという「うつのリアリズム」に陥りやすいこと、情緒安定性の低さからそれぞれの気質の負の側面が表出しやすいことが挙げられます。
MBTIとの関係
神経症傾向が高ければ「そのタイプの強みよりも弱みが周囲からみて目立ちやすい
」ということになります。エニアグラムでも退行先のタイプや健全度が下がった状態の言動行動が出やすくなるということになります。
特に○○タイプだから神経症傾向が高いとか低いとかはありません。
ただ個人的に神経症傾向が高くても自己アイデンティティに対して悲観的になる必要は全くないと思っています。
なぜならば、まず日本人は平均的に神経症傾向が高いという説があること、さらにこの時代は何をどうやっても扁桃体に高負荷がかかる構造になっているので、神経症傾向が高かろうが低かろうがさほど変わりがないからです。
神経症傾向の高低に限らず、精神面や肉体的な健康に配慮し、自分のプラス面とマイナス面を踏まえてバランスを取る方法を模索するのが大事なのかもしれません。
終わりに
記事を書いていて思ったのは、MBTIの内向感情(Fi)が、ビッグファイブ上だと完全に相関する項目が見当たらないということです。
大袈裟な言い方をすると「人間ひとりひとりの気持ちや感情は、脳科学では言い表せないものがある」という深淵なテーマに触れた気持ちになりました。
これは深掘りすると時間がかかりそうなので割愛しますが、
とりあえず次回は16タイプそれぞれをビッグファイブの五因子を用いて考察してみたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
