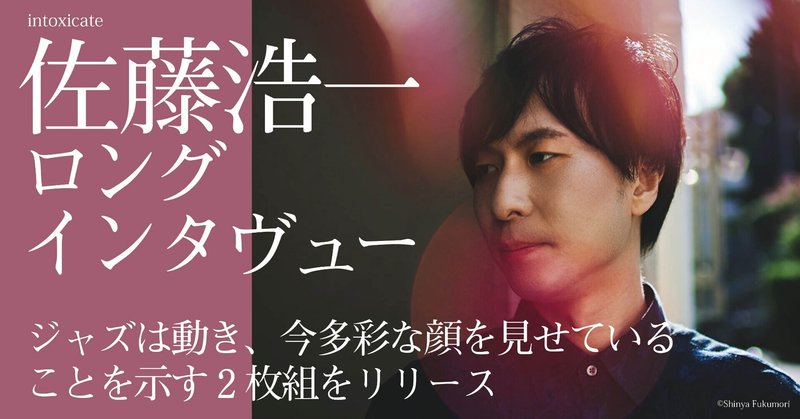
【佐藤浩一】ジャズは動き、今多彩な顔を見せていることを示す2枚組をリリース

©Shinya Fukumori
ジャズは動き、今多彩な顔を見せていることを示す2枚組をリリース
interview & text:佐藤英輔
音楽は深い。今回のピアニストの佐藤浩一に取材して、そう感じさせられてしまった。彼の3作目となるリーダー作『Embryo』は2枚組作品だが、Disc1は“ソロ・ピアノ”盤で、Disc2は弦楽器も用いるアンサンブル盤となる。両盤はともにゆったりと流れ、聞き手を包んだり、清新な風を送り出している。それら両Discは耳に優しい。ところが、その奥には旧来のジャズのあり方への疑問や、真摯な音楽への探求や挑戦があることに気づかせられる。通り一遍の行き方をするものより、一筋縄で行かない音楽のほうが面白くはないだろうか。それらは臨機応変に、流れていく感覚も聴く者に与える。そして、それこそはプロデューサー/ドラマーである福盛進也が設立した“nagalu”レーベルが抱える意図と重なるものだろう。同レーベル第2弾となる『Embryo』を出した、佐藤浩一に忌憚のない話を聞いた。
——『Embryo』はリーダー・アルバムとしては3作目になるんですよね。
「そうですね」
——そのアルバム・タイトルは胎内にいるような感覚を表しているんですか?
「はい。ソロのほうのレコーディングをしている段階で、ちょっと変わった調律をしているので、それと曲調が相まっての不思議なサウンドだな、それは赤ちゃんがお腹の中にいるみたいだなという話が出まして、それで『Embryo』(胎児という意味を持つ)と付けました」
——本作を録る以前は、ソロ・ピアノのアルバムはもっと歳を取ってから作れればと考えていたようですが、録音を終えた現在はどんな感想をお持ちですか?
「いずれは絶対に作りたいとは思っていたので、今はそれが早まって良かったと感じています。まあ、いつ死ぬか分かりませんし、こういう時代でいつ何が起こるか分かりませんし、そういう意味でも録れて良かったなと思っています」
——なぜ、わざわざソロとアンサンブルの2枚をパッケージするアルバムにしようと思ったのでしょう。
「2枚組というのは“nagalu”のコンセプトであるわけですが、レーベルを立ち上げた時点で、浩一君の作曲家という顔を主に出したいとまず思いました。浩一くんのピアノと市野さんのエレキギター、そして弦楽器を含んだアンサンブルでの小曲集というのが頭の中にまずありました。そして同時に完全にソロの世界観も見せたいという思いがあり、その両方の世界を一貫したものとして作りましょうと、提案しました」(同席していた、福盛の発言)
——まず、ソロのほうですが、そこで普通は使われない古典調律を施したピアノを弾くというアイデアはどこから来たのでしょう。
「もともとは古典調律でやることは考えておらず、別のアイデアを持っていました。普通の調律は440から442Hzの間でするんですが、それをぐっと下げた415から432 Hzあたりの質感が好きで、ベートヴェンの時代とかはそのぐらい低かったんです。それが現代に向かいどんどん上がってきていき、一時はもっと上がった時代もあったらしいんですが、今は442 Hzに落ち着いているようです。調律も時代時代によって変わっているんですね。僕の場合はその低い調律はクラシックから影響を受けたのではなくて、今活動しているポーランドのピアニストのスワヴェク・ヤスクーケ(1979年生まれ。筆者は2016年にポーランド大使館で、彼のソロ・ピアノの演奏を聴いたことがある)という人がいて、即興もして、1番の印象としてはポスト・クラシカルという感じの演奏をする人なんです。彼は432 Hzという低い調律でレコーディングしているんですよ。それだとすごい落ち着く感じがあるんですが、物理的に言うと432 Hzという低い調律の際の低いCの音が人間の胎内にいるような、リラックスできたり催眠の感覚を引き出す周波数らしいんです。それで僕も低い調律で録音したいと思い、今回調律していただいた狩野真さんに相談したんです。ヤスクーケは専用のピアノを持っていて、それでレコーディングしているんですが、普段スタジオに置いてある442 Hzで弾くことが前提になっているピアノを432 Hzに調律することは不可能なようなんです。現代の楽器はその調律で弾くように作られておらず、ピアノにも良くなく元の調律に戻せなくなってしまうようで、そのため断念しました。でも、狩野さんの方から低くはできないけど、代わりとなる面白い調律があるよと提案を受けて、それが古典調律だったわけなんです」
——それは、耳にいい人だったらすぐに分かるんですか。
「そう思います。ただ、古典調律には色々な調律があり、今回弾いたのはヴァロッティ音律というのを僕の曲に合わせて応用してくれたものなんです。僕の曲にはいろんなキーのものがありますが、一般の古典調律というのはこの曲のこのキーに対してはこの調律というふうに限定されてしまうのですが、今回やっていただいたヴァロッティ音律というのはその古典調律のなかでは割とどのキーにもフレキシブルに対応できる調律法なんです。今回、僕が録る曲のキーを狩野さんに全部渡して、どのキーの曲にも対応できるように調律してもらいました。とはいえ現在使われている12平均律に則るオールマイティな調律とは違うので、普段弾いているピアノにはない気持ち悪さと気持ちよさが存在するんです」
——では、最初は戸惑いもあったわけですか。
「戸惑いは相当ありました。普段は響きを想像しながら弾くんです。こことことを弾けばこういう響きになるというのが分かってピアノを弾いていくんですが、それがことごとく外れていく感覚なんです。違ううねり方をしたり、全然うねらなかったりとか。それがある意味即興的というか、ほんとその場のそのピアノを鳴らして初めて得る響きがあり、それは新鮮でもありました。だから、聞く人が聞けば分かるものではあると思います」
——今回ヴァロッティ調律がなされたピアノを使ったことで、自分の演奏が実際にこう変わったと口で説明できる部分はありますか?
「ペダリングが変わりました。意図的にそうした部分もあったんですが、音を伸ばすサスティーン・ペダルの使い方は、普段は一つコードが変わると踏んで、そんなに濁りを残さないように紡いでいくんです。ジャズの奏者はあまりペダルを使わない方が多いですね。使いすぎるとなんかぬめっとして良くないと、習ったこともありました。でも、僕はそういう教えに否定的だったんですよ。まあそれはともかく、今回曲によってはずっとペダルを踏みっぱなしというものもあります。それは今回の調律でどんなに伸ばしても音が濁らない曲があり、それだったらホールで音が響く感じでずっと踏みっぱなしで弾きました。ゆったりした曲ですうっとコードがつながっていくような感じで弾いた曲もあります。ペダルを踏み換える限界まで挑戦した感じがありますね。どこまで伸ばしても耐えられるか、と」
——では、レコーディングはかなりチャレンジングな作業でもあったわけですね。
「そうですね」
——短い曲から6分ぐらいの曲まで、曲の長さは様々なんですけど、楽譜はどんな感じのものだったのでしょう?
「ソロのほうの楽譜は、7、8割ぐらいの曲については書かれています。自分の曲を弾くので、完璧に書かなくても覚えているので、その場でどんどん変わっていく曲は少なかった。でも、残りの2割、3割ぐらいの曲は全く譜面のないインプロヴィゼイションの曲でした。あとは曲のアイデア自体は作っていて、スタジオに入ってその場で進也君がディレクションしてくれて、どんどん変わっていた曲もあります。テイクを重ねて、スタジオで作っていった曲もありますね」
——ソロのほうはベーゼンドルファーで、アンサンブルの方はスタンウェイを弾いています。それには理由があるんですか?
「今回使ったキング・レコードのスタジオには大きなスタジオが二つあって、違うピアノが置いてあったんです。単純に、違うピアノを使った方が面白いじゃないですか。ソロとアンサンブルのCDをそれぞれ録るんだったら、全然違うものにしたいと思ったんです。だから、ピアノも違うし、調律も違う。アンサンブルのほうは一般的な12平均律の調律で、録音したスタジオも違う。と、より違いを出したかったというのはあります。狩野さんがいうには、あのベーゼンドルファーは滅多にないいいベーゼンらしいです。ベーゼンドルファーはフルコンで88鍵のさらに下に鍵盤があるので、さらに響きがどっしりしているんです。実際に弾くことは少ないんだけど、それを鳴らしたときの地響きのような音はすごいし、今回はモノラル録音というのも大きく作用し、塊みたいに聞こえますね。それがすごい自分にとっては新鮮で、Disc1においてはそのベーゼンのパワーみたいなものにも助けられたかなあと思います」
——時に、ソロは裸になるような感覚もあるのでしょうか。
「そうですね。以前はソロでやるのが苦痛だった時もあるんですが、それが何年か経てちょっとづつソロもやるようになり快感に変わっているので、今は楽しいです」
——そして、楽に聞けますよね。本当に素直に自分の中から出てきたメロディを拾って弾いていると感じます。なんか祈りの感覚を覚える曲もありましたし、本当に素直なピアノを弾いているなと思いました。そして、いつもと異なる調律を触媒にすることで、佐藤さんのなかに新しい何かが生まれているんだろうなとも感じます。
「はい、すごい新しい感覚でした。今までにない発想を得ましたね」
——一方のアンサンブル盤の方は、これまで求めてきた路線の延長にあるものとしていいんですよね。
「そうですね。ただ、弦楽四重が入っているので、それは今まで自分の音楽に入れたことはないので、それについては初めてとなります」
——やはり、旧来のジャズとは一線を画す佇まいに満ちています。Disc2の方には1曲だけ通常のピアノ・トリオ編成で演奏される曲もありますが、それがまったく一般的なピアノ・トリオ表現になっていません。
「確かに、そうですね」
——わりと真っ当なピアニストって、ギター奏者をいれない人が多いじゃないですか。でも、佐藤さんは違いますよね。
「僕はギター好きなんですよね。ギターに弾いてもらえば僕がいなくてもいいんじゃないかと思うほどに……。前のアルバムの方が、そういう感覚は強かったですね。自分がいなくても成り立つ音楽を作り、そこに自分がいかに乗るかという感じでしたから。今回の10曲め(ギターとのデュオ曲)なんて、ギターだけでいいじゃないかと思い、僕のピアノはミュートしてもいいかなとも思いました。まあ、うっすら入れましたが」
——そういえば、Disc2はギターやチェロとのデュオ曲もあるんですよね。
「結果的にアンサンブルという言葉を分かりやすくするために付けているんですけど、あくまで曲ベースで録りました。曲が先にあって、それに合う音をイメージしたら、そういう編成になりました」
——いろんな種類の編成で録っていますが、その判断はどういう感じでしていくのでしょう。
「まさに曲が導くという、感じですね」
——そして、弦のアレンジに関しては、事前にちゃんと書いていたんですよね。
「はい、完全に譜面にしています」
——弦のアレンジはお好きだったりするんですか。
「経験はそんなに多くはないですが、やってみたいという気持ちは持っていて、将来的にはオーケストラものも書けたらと思っています。どういうものになるかは未知数ですけど、自分なりのオーケストラをやってみたいと思います」
——そういう志向もあり弦楽四重奏が入った曲がある一方、デュオによる曲もあるというのは、Disc2の聴きどころでもあるなと思います。どうにでも行ける自由をちゃんと教えてくれますし。編成のクレジットを見ながら聞いていると、いろいろと深読みしたくなります。
「そうですね。小さい編成の良さはあると思います。自分の曲なのでいかようにもできますね。それについてはアドヴァイスももらって、編成についてもアレンジに関しても、新鮮にできました」
——それと、Disc1とDisc2の両方に入っている曲も結構ありますよね。やはり、それらを聴き比べると興味深すぎです。曲がどうにでも旅立てるということを、ものすごく分かりやすく出していると思いました。
「それも、一つの狙いでしたね」
「今回の作品については、浩一くんの作るメロディが全面に出る方がよいと思い、それで提案しました。最初の楽譜とデモを送ってもらった際に、もう少しメロディを出して欲しいとお願いしました。また、曲によっては新しいセクションを設けることを提案し、曲が広がることに気を使いました」(福盛)
——なるほど、福盛さんはきっちりプロデューサーしていますね。
「自分がプロデューサーに立つと100%自分が思ったとおりというか、自分の範疇のなかでしか作れないので、そうならないにように客観的に見ることができ、しかも僕の音楽のことを分かってくれる人が間に立つことで、僕の曲が広がっていったと思います。ありがたかったです」
——『Embryo』は“nagalu”レーベルの第2弾になります。”nagalu”のコンセプトは意識したのでしょうか。
「“nagalu”の語源となる”流水不腐“というニュアンスは自分でも好きなあり方ですね。極端にいうと、僕は飽きやすい。物事が動いていたい、変わっていきたいと思うタイプなんです。そして、進也君はその100倍ぐらいそうですね。この録音では作られた部分と、その場で流れる部分の両方を持ったものにしたかったんです。その両方がバランスよくあるのがいいかなあと思ったし、ある意味、ここにはライヴ感覚もあると思います」
——すごい、風通しがいいなと思いますよね。
「はい。僕はどちらも好きなんです。作り込んでリハーサルを何回もして本番に臨むというのも好きだし、当日その場で起こったものを大事にするという面も好き。その両方が出たものになればと思いました」
——『Embryo』が商品になっての、今の率直な気持ちは?
「出来上がった時、泣きそうと思いました。というのは、自分が思い描いていたものがちゃんと形になったからです。ジャズとかクラシックとかいった垣根を超えて音楽を聴く人たちに聞いてもらえればうれしいですね」
——様式の異なる表現が、別々ではなく一緒のパッケージで出るというのがいいと思います。一つ一つだと印象が別れちゃうところ、一緒だとその人が持つ大きな世界が明解に伝わります。そして、ジャズの意味が広がってきて、今いろんな顔を見せるようになったという示唆にもなっていると思います。
「そうですね。海外の動きに追従していないものだとも思います。今もアメリカやヨーロッパの音楽に対する憧れはありますが、それをがんばってやっても二番煎じになってしまう。自分を肯定するという意味で、自分にしかできない音楽が作れたんじゃないかと思います」
——海外に向けての、今の日本人のジャズというプレゼンテーションになってもいますね。
「やはり、そこが“nagalu”のコンセプトですしね。“nagalu”から出ることは、そのことを後押ししたと思います」

『Embryo』
佐藤浩一
[nagalu NAGALU003/4]
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
