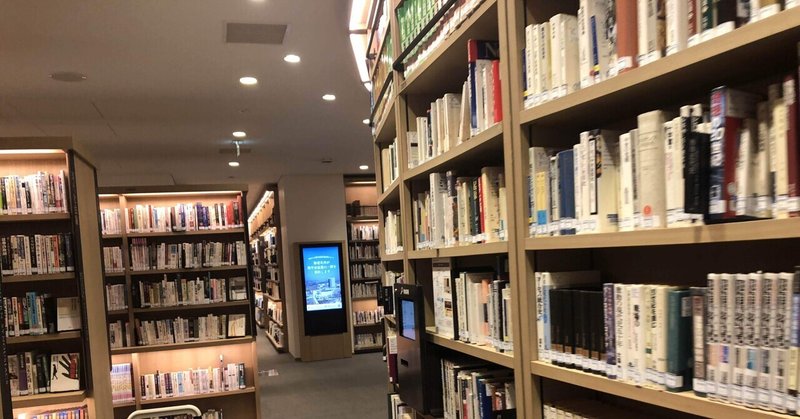
感情の合法的な味わい方
どうして物語が好きなんだろう
思えば私は、昔から物語が好きだった。
きっかけは分からない。
両親は文芸に興味がなく、家には父の趣味である車の雑誌か、母がかつて使っていたであろう料理系の雑誌しかなかった。
妹も、文芸には全く興味を示さなかった。
そんな環境で育った。
だからこそ、考えるのかもしれない。
なんで私は物語が好きなんだろう、という問いへの答えを。
小論文に書いた答え
受験生のとき、慶應義塾大学の過去問を解いた。
そのなかに、「戦禍でお腹を空かせた子どもの前で、文学は何の役に立てるのか」だったか、そんなテーマの小論文があった。
そのときに私が書いた答えはこうだ。
文学は、二つの力で人を救う。
一つは、物語のなかの登場人物と自分自身を重ね、彼らに共感し、彼らから勇気をもらえる、という力。
もう一つは、物語のなかの登場人物になりきり、つらく苦しい現実にいる自分を、ほんの一瞬でも忘れられる、という力。
文学は、お腹を満たしてはくれないし、病気も治してくれない。
でも、目の前の現実に立ち向かう勇気をくれたり、つらい「いま」から一瞬でも逃げるすべをくれたりする。
だからきっと、そこには意味がある。
少なくとも私は、文学がなかったら、憂き世に耐えかね、自ら死んでいたかもしれない。
社会人になって思うこと
社会人になって、これまでより自分自身を見つめなおす時間が増えた。
そのなかで感じるのが、私がいかに自分の感情と向き合ってこなかったか、ってことだ。
上司からよく、「あなたはいま楽しい?」と訊かれる。
私は何度問われても、その問いに答えることができず、「私、楽しいのでしょうか」と返してしまう。
自分が楽しいかどうか、分からないのだ。
なぜなら私は、「楽しい」「楽しくない」という自分の感情を、今までずっと省みてこなかったから。
私の判断基準は「楽しい」「楽しくない」ではなく、「周りから期待され、望まれている答えなのかどうか」「その選択が世間的に賞賛される選択なのかどうか」だった。
だから、自分が楽しいかどうかが、選択の判断基準に存在しなかったのだ。
合法的に感情を味わう
私にとって、自分の感情や欲求をがんじがらめにして、無意識の底に沈めることこそが「善」だった。
感情の思うがままに判断を下すことは、決して許されない「悪」だった。
だから、感情のままに、やりたいようにやる人を見ると、どこかで黒い感情が蠢くのを知っていた。
きっと自分はこんなに感情を押し殺して正しい選択をしているのにずるい、という思いが私のなかにあったんだろう。
でもその感情すら、ぐるぐる巻きにして無意識の海に沈めた。見ないふりをした。
理性は感情を制御する存在でなければならない。感情は理性に劣るものだ。
この現代に生きていながら、そんな近代の世界観に囚われている私。
私が文学を必要としたのは、だからこそだったんだと、いまになって思う。
自分の感情や欲求をがんじがらめにして無意識の底に沈めることを「善」としていた私にとって、合法的に感情を味わえる文学は、数少ない息抜きになっていたのだ。
自分の感情を素直に味わうことは、私にとって禁忌であり、違法なことだった。
私と似た世界を生きる人へ
私は、自分が別に嫌いではない。
きちんとしていて、しっかりしていて、真面目で人あたりのいい優等生。
周囲が私に対して下すそんな評価は、正直心地良く、高い中毒性を持っている。
けれど、そんな自分像を作り出すために積み重ねた選択は、自分の感情をことごとく無視したものだった。
どうするのが正しいのか、どうするのが望ましいのか。それを絶対的な物差しにした判断。
人間は、選択の積み重ねでできている。
よく自分らしさという言葉が私たちの世界を闊歩するけれど、自分らしさには明確な何かがあるわけではなくて、どんな選択をする人間かの積み重ねが、その人を形づくる。
私は、ひたすらに「周囲に望ましいとされる」と感じた選択をする子だった。それだけの話だ。
遊ぶのは宿題を済ませてから。
欲しいものは何度も悩んで、どうしても欲しいものだけ買う。
嫌いなものは先に食べる。
物事は継続する。苦しくてもすぐ辞めない。
ただ忘れないでおきたいのは、その自制的(だと自分が思っている)選択の裏には、無意識で生き埋めになっている自分がいるということ。
理想的な自分を演じるということは、理想的でない自分の首を絞めて殺す行為だ。
そのツケは、反動は、きっといつか、どこかでやってくる。ただの直感だけれど、私はそう思っている。
だからこそ、もし私と似た世界を生きる人がいるのであれば、殺された自分にも、少しでも目を向けてほしい。
ささやかに、そう祈る自分は、果たして〈どっち〉なのだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
