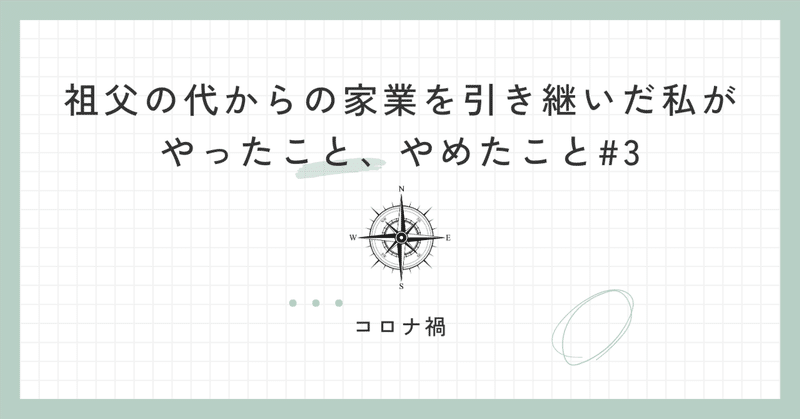
祖父の代からの家業を引き継いだ私がやったこと、やめたこと 03
コロナ禍
2020年。世間ではコロナが広がり始めていました。1月にダイヤモンド・プリンセス号で感染事例が発生し、3月にタレントの志村けんさんが急逝しました。
この頃、世間は未知のウイルスに対する恐怖に支配されたように感じました。
70歳を超える父はこれを機にテレワークに移行し出社を控えるようになりました。同様に社員に対してもテレワークを実施せなばならなくなりました。幸いなことに、ここで私が入社後に徐々に進めていた社内のIT化が功を奏しました。
私が入社した頃、会社にはCPUのついたものは電卓しかなく、紙で全てを処理している状態でした。幸い前職の職場が大企業ということもあり、PCやメールを導入し私も使用していました。
中小企業ながらも上場会社との取引もあったため、客先がそうしたものを当然と考えていることも理解していました。こうしたIT化は息子である私の役目だったでしょうし、父もその役割を期待していたと思います。まず前職で使用していたものを次々と取り入れていくようにしました。PCを購入し、ドメインを取得し、電子メールも取り入れていきました。
その後の10数年で社内の基幹情報にFilemakerというデータベースソフトを導入し、紙の管理を徐々にデータへと置き換えていきました。退勤管理や会計処理をクラウドサービスに移行した直後ぐらいに、コロナ禍が起きました。
工場は製造ですので出社する必要がありましたが、工場の社員は車通勤です。東京ほどシビアではなかったとも言えます。
本社機能は何とかテレワークで回すことができました。郵便物の処理やどうしても出社しなければいけない作業は、私自身が処理しました。私の雑務は増加しましたが(笑)、私以外の本社社員全員がテレワークとなりました。私としては打てる手は打ったと考えていました。
そして自分しか出社していない会社の事務所でこれからどうなるのだろうかと不安に苛まれていました。
コロナ禍はいつまで続くのだろうか
資金はどのくらい続くのか
どの時点で会社をたたむ判断をすべきなのか
ダメとなれば社員の次の就職先も決めねばならない、探し切れるのだろうか
そんなことばかり考えていました。
企業の存続は大命題ですが、退職金も払えない状況まで引っ張るのは現実的ではないと考えていました。社員に退職金を支払うだけの資金は残す必要がある。それがままならなくなる前に会社をたたむ決断をすべきだろう。そう考えました。
悩んでいても始まりません。手を動かすしかありませんでした。
実際に今日から一切の仕事がなくなったと仮定して、いつまで持つか計算を行いました。 当時の資金で12ヶ月を維持できる計算でした。
思ったよりも長く感じました。仕事もまだ途切れてはいませんでした。仕事の受注具合ではさらに長くできるはずです。 同じパンデミックであるスペイン風邪は終息まで3年程度でした。だとするとコロナ禍も収まるまでに3年程度はかかるかもしれない。逆に考えれば、3年間凌げば何とかなるのではないだろうか。 それでもだめになれば覚悟を決めるしかない。
それが私の想定できる限界だったと思います。それでも自分なりに先が見通せると少し気持ちも落ち着いてきます。
社員のみんなも不安に思っているはずだ。正直ベースで伝えるべきだろうと判断しました。
「明日から1件も仕事がなくなっても12ヶ月間は会社は潰れない。ダメなときには必ず先に言うから。」
と全社員に伝えました。退職者が出るかもしれないと思いました。
結果的には誰も退職することはありませんでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
