
21-1.協働を妨げる医学モデルを越えて
(特集 協働を巡る信田さよ子先生との対話)
信田さよ子(原宿カウンセリングセンター)
下山晴彦(東京大学教授/臨床心理iNEXT代表)
Clinical Psychology Magazine "iNEXT", No.21
〈参加集会型オンライン・シンポジウムのお知らせ〉
『心理職の技能として“協働”の活用に向けて』
─協働が困難な現実を越えるために─
【日程】9月20日(月曜:敬老の日)13時~16時
【申込】下記URLからの申し込み
◆臨床心理iNEXT有料会員:無料
⇒ https://select-type.com/ev/?ev=vg-WAnQI_Os
◆iNEXT有料会員以外:1,000円
⇒https://select-type.com/ev/?ev=LgYXj9MnR1w
1.はじめに
[下山]今回は,冒頭に示した「心理職の技能として“協働”の活用に向けて」と題するオンライン・シンポジウムの準備として,信田さよ子先生に“協働”を巡ってのお話をお聞きします。信田先生には,下記に示したようにシンポジウムの指定討論者としてご参加いただくことになっています。どうぞ,宜しくお願い致します。
[信田]こちらこそ宜しくお願いします。
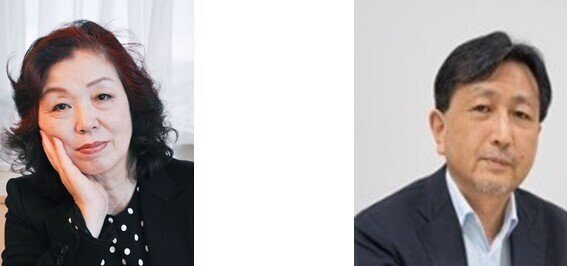
【プログラム】
■話題提供1:心理職は“協働”を技能として使いこなせるのか?
—個人モデルから関係性モデルへ転換−
・下山晴彦(東京大学)
■話題提供2:心理支援システム構築過程での協働の難しさ
—大学,高校における2つの事例からー
・窪田由紀(九州産業大学)
■話題提供3:心理支援のための臨床心理コラボレーション
—システム論からの提案—
・田中 究(関内カウンセリングオフィス)
■指定討論
信田さよ子(原宿カウンセリングセンター)
【信田先生からのメッセージ】
アディクション・アプローチがベースだった私は開業心理相談機関を長年運営し,21世紀に入ってから家族の暴力(DVや虐待など)に積極的に関わってきました。アディクションも暴力も,福祉事務所,精神保健福祉センター,弁護士,家庭裁判所,婦人相談センターなどとの協働なくして「心理支援」は不可能でした。そのような経験にもとづいて,当日は指定討論者という大役を果たしたいと思っています。

2.最初にお会いした頃の思い出
[下山]私が先生と最初にお会いしたのは20年近く前のことだったと思います。その頃の思い出として鮮明に覚えていることがあります。当時,私はロンドンで購入したポール・スミスのバッグを使っていました。そのバッグは,外からはポール・スミス製品とは分かりにくいものでした。日本では,ポール・スミスはまだあまり知られておらず,誰からも気づかれることはありませんでした。ところが,信田先生は,お会いしてすぐに「それ,ポール・スミスね」と指摘されて驚いたのを覚えています。
[信田]そうですか。私の一番早い下山さんの記憶は,東京国際大学で日本心理臨床学会※1)があって,その分科会の企画者が下山さんで,私が質問した記憶があります。帰り道東武東上線の駅の近くで偶然お会いしたとき,「こんな学会つまんないから,新しいのをやってくださいよ」と,下山さんに言った記憶があります。それに対して下山さんが「新しい学会といっても,なんか可能性ないですしね」と,諦めたような口調で言った。私も「本当にね」と言った会話をしたのを覚えています。
※1)日本心理臨床学会第23回大会(東京国際大学主催) 2004年9月
[下山]日本心理臨床学会に可能性がないことは今も変わんないような気がしますね。ところで,先生の近著『家族と国家は共謀する』※2)を読ませていただきました。この本,題名からして凄いですね。先生は,この本では,かなり大胆な主張をされていますよね。よくぞここまでお書きになられたという印象です。タイトルだけでなく,中身も凄いですね。
※2)『家族と国家は共謀するーサバイバルからレジスタンスへー』 信田さよ子(著) 株式会社KADOKAWA (角川新書 2022)
⇒https://www.kadokawa.co.jp/product/321606000181/
[信田]原宿カウンセリングセンター※3)の所長を5月いっぱいで引退して,今は顧問になったんですよ。縛りがなくなってそれで書けたっていうことはありますね。
※3)⇒ https://www.hcc-web.co.jp
[下山]今回のインタビューでは,このご著書で書かれている事柄についてもお訊きしたいと思っています。ただ,最初から家族や国家の権力の話となると,読者の中にはびっくりしてしまう方もおられると思います。そこで,まずは今回のテーマである“協働”に関連した信田先生のご経験を伺うことから始めたいと思います。

3.医師が無力なアルコール依存症の治療
[下山]以前,先生に「自分は,元々協働をすることから臨床活動をスタートした。だから,“協働”は自分にとって重要なテーマだった」と伺ったことがあります。確か先生は,最初はアルコール依存の治療に携わっておられた。そこで,依存症の治療において協働に関わる経緯を含めて,先生にとっての協働の意味をお話ください。
[信田]アルコール依存症は,元々は慢性酒精中毒と言われていた。アメリカ精神医学会は,1970年代の終わりぐらいに「アルコール依存症の治療は医者だけでは治療不可能な疾病である。つまり,コメディカルの存在なくしては治療できない」という趣旨の声明を出している。アルコール依存症は,そもそも犯罪として司法領域の問題なのか医療の問題なのか,よくわからない問題でした。だから,その治療方法は,そもそも多職種が連携していくことで成り立っていた。私はそこの中にいたということです。ところで,心理職というのは,医療の中でアイデンティティが脆弱ですよね。
[下山]非常に脆弱だと思います。
[信田]自分たちは保険医療制度の中でお金が稼げないのに,給料もらっていいのか,みたいな不全感がありますよね。ところが,依存症治療は,すでに述べたように多職種連携が当たり前だったのです。私なりに考えたのですが,医者が無力であることは,医者でない私たち心理職にも役割があることを裏側で意味していた。そういう意味で,心理職としてアイデンティティ不全に陥りながらも,出会いが依存症治療だったから救われてきた面はありましたね。
[下山]今でも,心理職がアルコール依存の治療の現場に入職することは比較的に少ないのですが,当時はさらに少なかったのではないのですか。
[信田]ほとんど無かったはずですが,勤めた精神科病院がすごく特殊な状況だったんですね。先日,NHKがコロナ禍との関連で精神科病院の特集を取り上げていました※4)。実はクラスターのかなりの部分が,閉鎖病棟で発生している。ある病院は,院長が病院名をカムアウトしましたが,他の病院は名前も出していない。精神科病院ではコロナを治療する力がないので,全て都立松沢病院に救急搬送されることになり,初めて外部の目が入った。今も精神科病院の中には,畳部屋があり,陽性者を閉じ込めて南京錠をかけるような実態がまだあるんです。
※4)ETV特集「ドキュメント 精神科病院✕新型コロナ」
https://plus.nhk.jp/watch/st/e1_2021073103678?cid=jp-M2ZWLQ6RQ
[下山]コロナ禍によって,今でも続いている精神科病院や精神科治療の闇の部分が奇しくもあからさまになったのですね。

4.医者の下で働くのは絶対に嫌だ!
[信田]私が70年代に勤めた精神科病院も,入職する2年前にアルコール依存症患者さんからの告発があり,東京都の衛生局が監査に入り,院長が退職して心機一転医療法人化されたんです。そのスタートの時期に,偶然に友人の紹介で全く状況も知らずに入職しました。
「この病院はどこでも忌み嫌われるアルコール依存症者を積極的に治療するんですよ」という新院長の姿勢のひとつとして,常勤の心理職が4人いた。上司も法務省矯正局から引き抜かれた方でしたし,今から考えればすばらしい環境でした。アルコール依存症の治療が,心理職の業界ではこんな辺境に位置するということに,病院をやめてから逆に気付いたという。変わった経過ですね。
[下山]自分で選んだというより,就職したら偶然そういうところだったのですね。結果として,そこで学ぶチャンスもあり,コメディカルが重要だということも知り,いろいろなことを経験された。
[信田]そう。最大のものは,精神科医はアルコール依存症に対しては無力ということを学んだ。つまり,薬ではアルコールを止めさせられないという,決定的なところで医者が無力であるということに立ち会った。それで「医者の下で働くのは絶対に嫌だ」という思いがむくむくと沸いたんですね。
[下山]なるほど。アルコール依存症だけでなく精神障害の治療においては,薬物療法の限界はありますね。そのような中でアルコール依存症の治療においては,その薬物療法を中心とする精神科治療の限界が如実に分かるわけですね。
[信田]そうそう。お酒やめられる薬ないから。
[下山]お酒がまずくなる薬はあるにしてもね(笑)。先生は,精神科医療の限界をアルコール依存症の治療を通して身をもって知ったということですね。それとも関連してメンタルヘルスの活動における多職種の“協働”についてテーマにしていきたいと思います。私は,多職種の協働を妨げる要因として医学モデルがあると思うのですが,いかがでしょうか。少なくとも,アルコール依存症の治療には,医療モデルが有効ではなかった。そのような状況において,どのような協働をされたんですか?
[信田]協働が先にありきではなかった。「当事者,つまりアルコール依存症の患者さんにとってどのような治療体制が必要か」ということから始まった。それが結果的に協働につながるわけです。そこでは,作業療法士,看護師,ソーシャルワーカーに加えて,かつて患者さんだったスタッフがいた。
今でいうと,リカバリングスタッフ,当事者スタッフとでも言うのでしょうか。その人々と一緒にグループをした。私は,大学ではサイコドラマ(心理劇)をとおしてグループ活動を学んでいた。その病院でも,個人の治療というよりもグループ療法を何種類もやっていました。
[下山]そのグループには作業療法士やソーシャルワーカーも参加していたのですか?
[信田]はい。そのような職種の人も参加します。当時はグループは点数化されていませんでした。今では,医者の指示によるグループ(集団療法)は点数になりますが,コメディカルに任せて保険点数をとるだけのことが多いと聞きます。断酒会の人の体験談を聞くことはたくさんあった。それはとても先進的な試みでいい勉強になりました。
[下山]当事者参加の“協働”ですね。
[信田]当事者参加というより,当事者主導ですね。つまり,「私たちはお酒のやめ方がわからないのに,この方はお酒やめられてすごいなあ」というスタンスでした。断酒会のおじさんに可愛がられたりしたんですよ(笑)。

5.権力を巡ってのチャレンジ
[下山]なるほど。そのような当事者主導の協働システムというのは,今という時代においても最先端の方法ですね。そこには,医学モデルという権威的なもの,つまり権力を越える試みがあったのだと思います。70年代は,そのようなさまざまなチャレンジが行われていたと思います。大学紛争もあった。あれも,既存の権威や権力へのチャレンジでした。
その結果,世の中が騒然としていた。心理職関連では,若手が学会主導者を批判した日本臨床心理学会の分裂があった。いろいろな混乱もあった。しかし,そこには,「権力というものをどのようにとらえ,どのように対応するのか」という本質的な問題が出てきていた。そして,その問題に対して時代を先取りしたチャレンジがなされていた。今になってそのように思います。
[信田]そうですね。あの時代のことは,いずれ誰かがお書きになればと思っています。ただ,書く前に皆さん,もう亡くなられつつあるんです。私としては,あの辺のことをちゃんと書いてほしいなと思うんですよ。
[下山]70年代の日本臨床心理学会を巡る紛争と分裂ですね。日本臨床心理学会の名古屋大会で問題が吹き出してきた。そのとき,私の大学の先輩たちもその対立に深く関わっていました。私の指導教官であった佐治守夫先生は,心理職の国家資格を目指す学会を主導する立場の一人でした。
しかし,佐治先生の後輩やお弟子さんの若手心理職の中には,学会の主導部や国家資格に反対し,主導層を批判する人も少なからずいた。私の先輩たちが国家資格化に賛成と反対に分かれて対立することになった。これは,私の出身大学だけでなく,当時の日本全体の心理職の置かれた状況でした。それは,心理職の発展を期待する者にとっては,残念な事態でした。
[信田]私はあのとき,名古屋大会の会場にいて,舞台で椅子投げたり,机を放り投げたり……。それで,私は怖くて逃げたほうでした。すごかったですよ。電気も消えちゃってね。
[下山]結局,あのときの学会の紛争や対立は,「心理職が“権力”とどのように向き合うのか」という本質的テーマが顕れたものだった。先生のご著書の「家族と国家は共謀する」も権力がテーマですので,その点で重なります。今は,公認心理師という国家資格ができているのですが,実は“資格と権力”は非常に密接に結びついている。
[信田]今の日本心理臨床学会や日本臨床心理士資格認定協会の人たちがどのように考えるのかわかりませんが,私のように70年代にあの資格の闘争を経験した世代の心理職には,資格と権力の問題にはアレルギーがあるということはすごくよく分かりますね。
[下山]私は,信田先生の世代の少し後輩に当たり,その対立に直接関わることはありませんでした。しかし,資格や権力を巡る問題には触れる機会はあり,いろいろな思いが出てきます。
[信田]当時,心理職は,国家資格を得て権力の一部になるか,そうでなければ反権力になるしかないといった発想でした。今このようなコロナ禍の時代になって,ますます権力との関係で,心理職がどのようなポジションをとるのかが問われていると思いますね。
[下山]本当にそう思います。 “協働”は,必然的に“権力”の問題とも関連してきます。この点については,後ほど改めて議論ができたらと思っています。

6.当事者を含めた協働の体制へ
[下山]ここでは,先ほどのアルコール依存症における多職種協働の話に戻りたいと思います。アルコール依存症の治療において当事者の患者さんを含めた協働をされていたとのことでした。専門職だけの協働とは異なる難しさもあると思いますが,どうでしょうか。
[信田]難しさは全然ないですね。というのは,アルコール依存症というのは,当事者がとても発言力があるんですよ。だって,あの人たち,入院中は,自分がアルコール依存症って思っていない。だから,「どうして自分がこんな所に入んなきゃいけないのか」,「入院期間はどうやって決められるのか」,「自分は他の人と違ってビールだけだから酒の害はない」などと,自己主張する人は結構多かったんですね。
[下山]なるほどね。病気だからという意識はないのですね。
[信田]アディクションの治療は,統合失調症治療中心の精神科医療と全然違うんですよ。だから,協働は,大勢いるスタッフが,いろんな方面から答えられたほうがいいに決まっている。そこでは医者も,患者さんに対して「〇〇さん,よろしく」みたいな感じで,対等にかかわる。ある意味ではものすごくプリミティブな協働となる。当事者である患者さんとの合意や,激しいだまし合いをとおした治療ということになる。だから,できる人がやるという協働ですね,当時は,そういう実践だったと思います。
[下山]それこそが最先端の協働ではないでしょうか。患者中心というのが最も本質的な協働の意味ですよね。
[信田]ただ,それが “協働”という名前を付けられて,21世紀にこんな話題になろうとは70年代当時は思ってないわけですよ。いっぽうで脳への影響が注目され始めていて,アルコール性痴呆(dementia)と呼ばれていましたので,知能検査や記銘力検査もやっていました。それ以外はグループばかりやってましたね。
[下山]やっていて手応えはすごくあったということですか。
[信田]手応えは,たぶん医者も含めて誰もないでしょ。だって,アルコール依存症の患者さんの一部は,優等生です。退院するときは「おめでとうございます」「さようなら」と皆で言って病院玄関で送り出すのだけれども,1週間後ぐらいでまた泥酔して戻ってきたりする。こういうことが,当時一杯あった。
それで,治療効果は誰も分かんない。そこはほんとに面白かったですよ。今みたいにエビデンスといった言葉もなかった。実は,今でもアディクションの治療エビデンスは曖昧だと思いますよ。
[下山]なるほど。社会がアルコール依存症の治療を必要としているので継続はしている。しかし,しっかりと治療できているのかということは,それとは別なのですね。

7.家族の支援へ
[信田]社会防衛というより,家族防衛ですね。アルコール依存症については,家族がほんとに苦しむ。東北地方では,夜中に酒を好きなだけ飲んで,泥酔したところを布団でくるみ,夜明けに病院の前に放置しておくと,出勤した病院の人が入院させてくれるという習慣があった。つい最近までそのようなことがあったと聞きます。
アルコール依存症の治療は,家族の防衛のために,本人に酒をやめてもらわないといけないわけです。家族と本人の利害の対立というのは,依存症・アディクションの現場では常識的な現実です。未だに「家族は治療協力者」なんて甘いことを言うのは,心理職くらいだけではないかと私は言いたい。
[下山]それは,先ほどのエビデンスのテーマと関わりますね。認知行動療法の有効性のエビデンスが出ているというのは,ある特定の治療しやすい環境を設定し,変数をコントロールして典型的な症状や問題行動を示す患者さんに治療をした場合の効果をみるものですね。つまり,生活場面の影響などを極力排除しての介入の効果ですね。
ところが,アルコール依存症などは,御本人だけでなく,家族などの環境などが直接,問題行動に影響を与えている。それがアルコール依存症の本質とも関わる。それが現実なわけですね。家族との対立や社会からの差別や排除などがある。そのような変数を外して効果研究をしても,そのエビデンスには意味がないということはありますね。
[信田]おっしゃる通りです。
[下山]今の話題で出たようにアルコール依存症の治療においては,家族をなんとかしてくれというニーズが強い。それを受けてということでしょうか,先生は次第にDV(Domestic Violence)や家族の問題に活動の対象を移していかれました。そのあたりの経緯もお教えいただけますか。
[信田]細かいことはさておき,80年代に入りアルコール依存症の治療はそのままやり続けました。そうすると,今度は家族というものがテーマとなってきた。アディクションの当事者は,当事者だという自覚がないのです。周りから見たらどう見ても依存なのに,本人は生きるためにアルコールが必要と信じている。自分は飲みながらでも生きられると,最後まで信じている。半ば自殺的であり,半ば信じているという非常にパラドキシカルな存在がアルコール依存症の現実なのです。
そのアルコール依存症のそばには本当に打ちひしがれ,裏切られ,暴力を振るわれている家族がいる。私は,そのような家族に対してこそ,心理職ができることがあると思っていた。当時は,自分は心理職という自覚もなかったわけですけど(笑)。ただ,少なくともそれは医者にはできないことだということはわかっていた。
[下山]心理職だからできるというのではなく,できることを考えていたら家族の支援に行き着いたということですね。それでは,次は家族やDVの問題解決に向けての活動,さらには心理職のアイデンティや社会的役割というテーマと関連して協働の可能性についてお話をお聞きしていきたいと思います。
—次号に続く−
■デザイン by 原田 優(東京大学 特任研究員)
■記録作成 by 北原祐理(東京大学 特任助教)

〈iNEXTは,臨床心理支援にたずわるすべての人を応援しています〉
Copyright(C)臨床心理iNEXT (https://cpnext.pro/)
電子マガジン「臨床心理iNEXT」は,臨床心理職のための新しいサービス臨床心理iNEXTの広報誌です。
ご購読いただける方は,ぜひ会員になっていただけると嬉しいです。
会員の方にはメールマガジンをお送りします。
臨床心理マガジン iNEXT 第21号
Clinical Psychology Magazine "iNEXT", No.21
◇編集長・発行人:下山晴彦
◇編集サポート:株式会社 遠見書房
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
