
【音楽評】『ディシプリン』キング・クリムゾン(後編)
執筆者:航路 通
こんばんは、航路通(@satodex)です。引き続きキング・クリムゾンの批評をやっていきます。
さて、前回、プログレッシブ・ロック成立の過程をお話しました。
思い出してもらうために一曲どうぞ。11分あります。しかしこれも鍛錬(ディシプリン)です。
メロトロンの物悲しいフレーズの上に、この世の終わりのようなバイオリンのフレーズが乗り、ジョン・ウェットンのダンディな声で「星のない、聖書のような暗黒」と歌われるこの曲は、プログレの世界観、ある種のダイナミズム、緩急を象徴するような曲です。
前半だけならシンフォニックな楽曲なのですが、フリップがギターを弾き始める中盤からは、張り詰めるような緊張感が漂い始めます。執拗なほど繰り返され、徐々に上がっていき耳障りなほど高音になっていくギターの音が、どこまで行ってしまうのかと不安をこれでもかと煽って、もう耐えられないというようなところで一気に解き放ち破壊的で即興的な展開を開始します。この高まって行った感情が、耐えられなくなり、破裂し、そしてテーマに回帰するという一種のカタルシスは、プログレ的な展開美であり、静と動の緩急であり、大作主義的で荘厳な世界観です。プログレを一言で説明する曲と言っても過言ではないでしょう。
僕は最後にフリップが頭のフレーズをギターで弾くとこで毎回泣きそうになります。ここに一度没入すると戻ってこれません。プログレ沼にようこそ!
この楽曲は、クリムゾンの最後のアルバム『レッド』(1974)の一番最後の曲であり、この絶望感・終末感のある楽曲がある種物語的にクリムゾンの終焉を演出していました。
さて、ここからはパンクの話をするので、BGMと思って「スターレス」を聴きながら読んでしまうと、ギャップで狂い死ぬ可能性があります。聴き終ってから読むよう、注意してください。
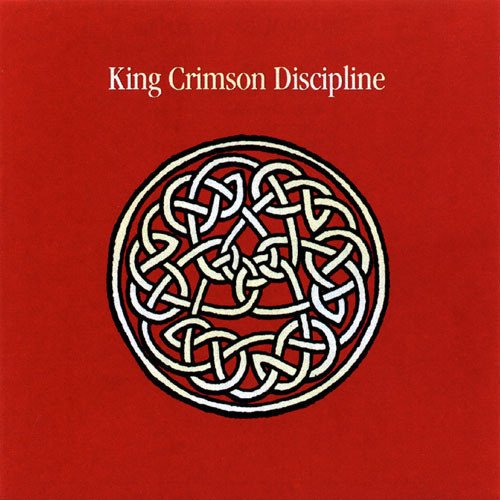
問題のアルバム『ディシプリン』(1981)が発表された当時は、プログレが衰退したのち、むしろニューウェーブの時代でした。
ニューウェーブ、パンクは、音楽的には、3コードのシンプルなロックへと回帰した音楽、とよくいわれます。70年代後半のニューウェーブの大きな潮流の発端はいわゆるロンドン・パンクで、セックス・ピストルズを代表としています。
シンプルなロックというのは確かで、ピストルズの「アナーキー・イン・ザUK」なんて、ギターを始めて三日の中学生でも弾けますからね。歌詞内容としても、低所得な若者を代弁するかのように政府や資本といったものを批判し、反社会的なメッセージを出していったパンクでしたが、これは、プログレやハードロック、あるいはフュージョンなど、複雑化した音楽に対する反抗として、しばしば語られていくことになります。シンプルで、反抗的な若者の心をがっちりと掴む、「ノレる」音楽、それがパンクでした。
パンクの持つ革新的な意味は、音楽性自体というより、その音楽性の含んでいたパフォーマティブな意味でした。パンクは、ファッションであったりとか生き方であったりとか、とにかく一つのスタイル(このスタイル全体を指してニューウェーブと言ったりもします)、すなわち一つの消費傾向、ブームになっていきます。ショートカットで逆立てた髪とか、ボロボロでラフで奇抜な格好してる人とかね。あーいうのをニューウェーブっていうんですね。
この時期に、ポップ・ミュージックが産業的にかなり成長するんですね。資本を批判したパンクが、むしろ資本として消費され、流通していくというアイロニーが、パンク・ムーブメントにはあるのです。これを自覚したのが、ある時期以降のニューウェーブ、そしてポスト・パンクだと僕は思っています。ともかく、パンクの台頭によって、ひとつの作品よりも消費物としてロックが見られるようになったと、僕は考えています。
パンクは他でもなくポップでノレる音楽なわけですから、きわめて消費物として秀逸だった。この後、パンクは色々展開していきますが、80年代に入り、いわゆるポスト・パンクになると、最新鋭のテクノロジー(電子音楽)であるとかピンク・フロイド等のプログレの雰囲気をパンクに合体させようという動きが活発になっていく。パンクが音楽としてアンチ近代、そして原始的なロックへの回帰という様相を呈していたのは本当にほんの一瞬で、プログレがロックに他ジャンルをたくさん導入したのと同じことが、ここで起きていたのだと思います。人間というのは結局シンプルなものをどこまでも複雑にしてしまう生き物なんですね。僕はプログレとポスト・パンクがそれぞれ、ロックとパンクの原義的な意味を破壊的に解釈し、別のモノへ変容させたという点で、ほとんど同じ楽しみ方をしています。
さて前置きがまたも長くなったので、『ディシプリン』を批評していきましょう。この作品は、まさにそうしたニューウェーブの真っただ中で発表されました。
ロバート・フリップは1974年『レッド』を最後にクリムゾンを解散させ、むしろパンクの世界に身を投げていきました。ソロアルバムの『エクスポージャー』(1979)がいい例で、ここではプログレ気質な前衛性が前面に出ているものの、今までとうって変わってパンク的な表現が選ばれています。今までのようなジャズやクラシカルな要素はいっさいありません。フリップ御大いわく「表現としてのポップ・ミュージックの分析」らしいです。ここでは詳細に述べませんが、『エクスポージャー』におけるフリップのテーマは、「都市の暴力」だと思っています。そしてこれは『ディシプリン』にも通じていきます。
そして、実はこの場合のパンクは、ニューヨーク・パンクと呼ばれるほうのパンクで、こちらのパンクはロンドン・パンクよりも少し前から勃興していました。アート志向で、表現としてのパンクを選んでいたと言われています。トーキング・ヘッズやテレヴィジョンがここに含まれますが、ロバート・フリップイギリス人でありながら、クリムゾンを解散させた後、こちらに没入していくこととなります。
プログレ系のミュージシャンが実際にパンクと関わっていくというのは実はけっこう珍しいんですね。70年代後半以降、音だけニューウェーブ系になるプログレバンドは数あれど、実際にパンクの原像そのものにかかわったミュージシャン、しかもそれをむしろ先鋭的な音楽表現と捉えていたのはフリップくらいだったのではないでしょうか。
そうしていくつか実験的なバンドを経験したフリップによって、再び結成されるキング・クリムゾン、そして『ディシプリン』は、当然、今までのある種ダイナミックなプログレではなく、むしろミニマルでコンパクトにまとまった、ニューウェーブ系のバンドに様変わりしていたのでした。

いままでイギリス人だけで構成されていたバンドには、エイドリアン・ブリュー(Gt,Vo)とトニー・レヴィン(Ba)という二人のアメリカ人が加入し、ドラムスには解散前と同じくビル・ブラッフォードが選ばれました。彼は「スターレス」を聴いていただけたならわかると思いますが、プログレ界・もしくはロック界でも屈指のドラマーで、手数が多いながらもシャープできっちりとしたタイム感を持っています。が、この時期には、以前のような奔放で即興的なドラミングが削げ落ち、シャープなリズムのみを追求するようなリズムワークに変わっていきます。
リズムに関して言えば、アフリカン・ビート、すなわちミニマルな反復的リズム、あるいは異なる拍子を同時に用い、そのズレから独特のリズム感をうむポリリズムの導入といった要素も、今までのクリムゾンではなかった要素です。
さて、ミニマルでニューウェーブでパンクなクリムゾン――あまり長々解説してもアレなのでここで実際に聴いてもらいましょう。
もちろんアルバム版でもいいんですが、このライブはかなり驚嘆に値する演奏を披露しています。歌詞やリズムやギターの音色などに注目してみて下さい。
とりあえず変な音が鳴りまくっているのですが、これはフリップとブリューの二人ともがギターシンセ、平たく言うと特殊なエフェクターを多用しているためです。ソロ部分ではとてもギターとは思えない音を多用しています。ロバート・フリップは、ギターの音をループするフリッパートロニクスと呼ばれる独自の機器を開発するなど、とにかく既存のギターから離れた音を追求していました。彼は盟友であるブライアン・イーノとともに、アンビエント・ミュージックにも手を出していて、そこではもはやギターに聞こえないような、延々と伸び続けループする音を披露しています。
歌詞は、英語が苦手な人でもわかるように、単なる単語の羅列です。アーギュメンツ、アグリーメンツ、アドバイス、アンサーズ…と続いた後は、バーブル、バーバル、ベンター…と、A,B,C,D,Eの頭文字をもつ、「言葉、会話」に関する単語をただ羅列し、それを「全部ただのおしゃべり、無駄なおしゃべり」と繰り返すという、極めて「無意味」を強調したものとなっています。
この曲の真骨頂はリズムセクションです。センターで歌いながら変なギターを鳴らしているピンクスーツのエイドリアン・ブリューのセンスが前面に出ていますが、よく聴いてみると後ろで座って弾いているフリップがとんでもない変態フレーズを弾いています。これはしばしば「シーケンシャル」とも形容される、特定の細かいフレーズを無機的かつ高速で繰り返すフリップのお家芸です。フリップはあまりギタリストっぽい、情念のこもったフレーズを弾きません。
また、スキンヘッドにヒゲがトレードマークであるトニー・レヴィンがスティックと呼ばれる特殊な弦楽器(主にベース的に用いられていますが、すべて指を押し付けて音を鳴らすこの楽器は、ベースとはまた違ったニュアンスの音を出します)を奏でています。
弦楽器三人の複雑なリズムの絡みとポリリズムによる差異(ずれ)の反復が緊張感を生み出していますが、結果的にはニューウェーブ的なポップさと「踊れる」ファンキーなリズムとしてまとまっているところがさらに驚異的です。
さて、ディシプリン・クリムゾンを代表する「エレファント・トーク」を聴いてわかるように、この時期のクリムゾンの音には、「ディシプリン(節制、抑制)」が効いています。確かに一見ファンキーですが、かなり計算ずくのリズムの反復がこの曲では繰り広げられています。そしてこの「抑制」は他の曲では一層顕著なものです。
テクニカルな話になるのですが、この曲では、ブリューとフリップのギターがそれぞれ別の拍子(14/8と13/8)でフレーズを弾くという、ギターによるポリリズムをテーマにしています。つまり一拍ずつずれていき、これを7回繰り返して、7/8拍ずれるのですが、最後の小節で7/8のフレーズがくっつくことで、このずれが完全に一致するという構成になっています(この箇所を解説するにあたってここを参考にしました)。
このズレと一致という緊張感を生み出すには、お互いのリズムの食い違いが無いよう、完璧にタイミングを合わせて弾かなくてはなりません(完璧に「ずれ」を生み出さなくてはなりません)。これには弾くには並大抵ではない鍛錬(ディシプリン)と技巧、精神力を必要としますし、以前のクリムゾンのダイナミズム、インプロヴィゼーションの入り込む余地はなく、ひたすら禁欲的、ストイックなリズムアプローチです。展開という意味でも、「スターレス」のように、テーマ、歌、中間部(緊張→破裂)、テーマというような展開に富んだ構成ではなく、平面的な繰り返しで構成されています。これがディシプリン、の意味だったと僕は思います。
この反復の快楽、そして「エレファント・トーク」にも見られたような無意味さ、ミニマルな表現の強調は、現代文学にも通ずると僕は思います。実際歌詞を担当したエイドリアン・ブリューはビート文学のフォロワーで、歌詞の中にもしばしばビート文学的な表現、直接的なパロディが散見されます。
このような「アメリカ」的で現代的な一種の「無味乾燥」、そしてミニマルな反復は、今までのブリティッシュ・プログレとしてのクリムゾンではありえないものでした。
フリップの関心は、このような都市の情景にあったのだと思います。

…しかしこう見ると、「フリップはプログレを捨ててニューウェーブに行ったんだ」という単純な転換として『ディシプリン』を解釈してしまうことになります。前の記事でも書いたように、僕は実は、クリムゾンのこのプログレ‐ニューウェーブという対立に「根っこで同じもの」を感じています。それについて触れてみましょう。それはまさにこれまで論じてきたリズムへの偏執、そしてフリップのスタイルにおいてなのです。
どういうことでしょうか。
先ほどの「スターレス」と「エレファント・トーク」はまったく違う曲に聞こえますが、しかしスターレスの中間部を思い出してください。あの執拗に反復される音の緊張感は初めからフリップのスタイルでした。つまり、僕はこう思っています。ディシプリン・クリムゾンはフリップにおいて、プログレ的な手法の否定ではなく、むしろ徹底だったのではないかということです。
King Crimson - 太陽と戦慄Part II
1973年の楽曲、すなわちプログレ時代の「太陽と戦慄partⅡ」です。バイオリンとギターの変拍子のユニゾンで構成されたこの曲はバルトークの影響を強く感じさせます。表面的には、ヘヴィネスやダイナミックな展開と言う意味で、ディシプリン・クリムゾンと違いますが、この平面的なメロディの乏しさ、無機的なリズムの繰り返しには、ディシプリン・クリムゾンの萌芽を感じるのです。僕はこの曲をフリップのひとつの代表曲と考えていて、無機的なリズムの反復、この反復は、実はプログレ時代から一つのテーマだったのではないか。そう感じるのです。
また11分くらいある曲なので、聴いていただかなくてもいいのですが、たとえば1974年のFractureという楽曲では、すでにシーケンシャルなプレイが登場しています。
フリップというギタリストは、徹底して無機質で平面的なフレーズと暴力的なフレーズを志向してきたギタリストであり、その点で凡百の「超絶技巧」ギタリストと一線を画しています。そのフリップのギタリストとしての個性が、むしろ今まで以上に発揮されているのが、『ディシプリン』というアルバムなのではないか、とそう考えるのです。そしてそれには、今までのイギリス人的な物語ではなく、物語を持たない無味乾燥なアメリカ人のセンスが必要だったのではないか。
言い方を変えるなら、フリップは、すべてが消費に変わっていく「ニューウェーブ」の社会に合わせた表現を考え、そこでは今まで使われていた神話的「絶望」という一種の虚構性ではなくて、物語がはぎとられたよりリアルな都市の暴力を必要とした。だからこそ手法をまるきり変えてしまったのではないか。しかしそこでの表現は、今までのフリップとは何も変わらないし、むしろ徹底しているのではないか。そう僕は考えています。だからこそ僕は、『ディシプリン』に対し、いままでのクリムゾンと徹底的に違いながら同じものであるという矛盾した感想を持っているのです。
なんとなくまとまってきました。そして長々論じてきましたが、僕としては、この『ディシプリン』というアルバムで核になっているのは、次の楽曲だと思います。貼るのは最後にします。
歌詞の内容について先に触れると、これは極めて私小説的かつ偏執狂的な内容で、「好きなものについて眺め、考えていることがやめられないこと」についてひたすら告白し、最終的に「I like it!」と叫んで終わるといった内容です。
この曲は、『ディシプリン』というアルバムにおいて、ひとつだけ「違う」曲です。なぜなら、この禁欲的で抑制されたアルバムの中で、唯一「インプロヴィゼーション」を開放している曲だからです。動画を見ればわかりますが、「エレファント・トーク」や「フレーム・バイ・フレーム」とちがい、かなり即興性があって、ブリューの歌(セリフ?)に合わせて演奏されていることがわかります。ブラッフォードも、本領発揮と言う感じで、この曲においてだけは奔放なドラミングを開放しています。
"Indiscipline"というタイトルは、そのコンセプト通り、「無規律」と訳せる単語です。"in-","im-"という接頭語は否定の意味を表します。"impossible"とか言いますね。そう考えると、タイトルが楽曲を批評する形になっていることがわかります。「ディシプリン」というアルバム、そしてコンセプトの中で、この楽曲は唯一「無規律」、無軌道な即興性を発揮しています。これは以前のクリムゾンの中での静と動の対比にも一致しますね。
しかし、この曲の批評性は、それだけではありません。これは実は一つの言葉遊びになっているのではないかと僕は考えています。
このタイトルは、inを単に前置詞としてとらえると、"in discipline"、「規律の中で」という訳が可能だからです。こうすると、まったく逆の意味になってしまいます。言葉遊びとしてはこうなります。
"Indiscipline in discipline(規律の中の無規律)"
『ディシプリン』というアルバムの中の「インディシプリン」というひとつの事態。すなわち、このタイトルは、静と動の対比が、ひとつの構築の中で同居する事態を批評的に表しているのです。あるいはクリムゾンの音楽全体に対する批評と言ってもいいでしょうし、社会的なことととらえてもいいでしょう。規律的で構造的に作られた都市、社会の中でとらえられない中心としての無規律さ、運動、空虚。そして何かに対する偏執。とにかく僕はここに、ひとつの都市批評であり、音楽批評的な意味を、このタイトルから解釈します。
さて、『ディシプリン』というアルバムは、いままでのプログレッシブ・ロックのイディオムではありえない表現を繰り広げてきましたし、そこには当時のニューウェーブ系の勃興がかなり大きく影響を与えています。そしてリーダーであるフリップはまさにそうしたニューウェーブな音楽を積極的に受容し、僕の考えでは、むしろそこに先進性、現代性を見出すことで、今までと異なる表現を模索しました。その結果、ニューヨーク・パンクに通じる道を発見し、プログレ的な手法を捨てつつ、一方ではいままでの自身のスタイルをより深める形で、「プログレッシヴ」な音楽を制作したと考えています。
「現代的」で「批評的」なかたちでの「プログレッシヴな」アルバム。僕はこのアルバムの曲を聴くと、ミニマルな反復に快楽を感じつつ、都市とか路上の冷たい乾燥を感じるのです。

「全てはどんな音楽をフォローするかによる問題であり、あの方法がダメこの方法がダメ、といいたいわけじゃない。音楽の熟練と拡張のために、音楽のスキルを使う、ということだ。ところで、どうやって速く演奏するかって? 地獄のように練習するだけだ」(1974年のロバート・フリップのインタビューより)
なんだか必要以上に長々と書いてしまいましたが、とりあえず聴いてみようと思っていただけたら幸いです。では。ありがとうございました。
『Discipline』King Crimson(1981)
1.Elephant Talk
2.Frame By Frame
3.Matte Kudasai
4.Indiscipline
5.Thela Hun Ginjeet
6.The Sheltering Sky
7.Discipline
