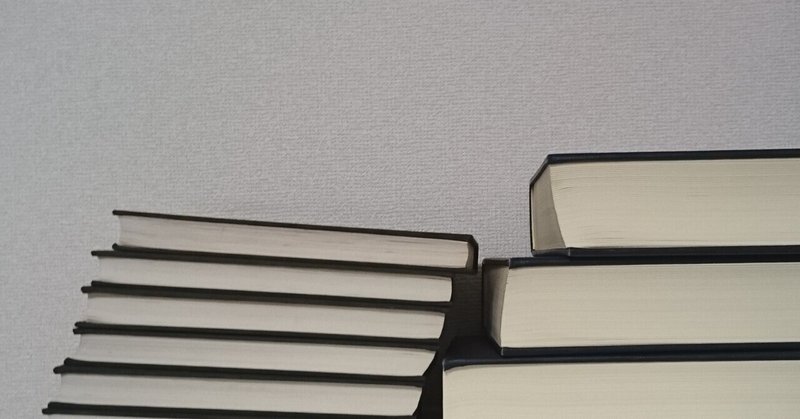
キラキラネーム可認案、意見募集開始
「戸籍法等の改正に関する中間試案」への意見募集(パブリックコメント)が始まりました。
この試案のパブリックコメントへのリンクはこちらです。
(URLは、 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080273&Mode=0 です。リンクやURLが信用できない方は「戸籍法等 改正 パブコメ」で検索してください。)
この中間試案の中で最も重大な問題は、名前の漢字の読み方がどの程度認められるかについて、現在示されている3つの案どれにおいても「海(まりん)や騎士(ないと)といった外国語読みが認められてしまう」という点です。
是非とも「字義(漢字の持つ意味)と関連があっても、外国語の読み方は認めるべきでない」という意見を、より多くの人に表明していただきたいと思っております。
なお、意見の投稿には、住所(市区町村まで)、氏名、年齢、性別、職業を記入が必要な上、どの項目に対する意見かを明示しなければいけません。これは、ヤフコメやSNSのような粗雑な放言を牽制したり、一人が何回も意見を送付することを抑制するための措置であると考えられます。ただし個人情報については省略は可であり、当然のことながらこれが公にされることはありません。
また「どの項目に対する意見か」については、「第1の2について」で伝わりますので、そうお書きください。この項目が、漢字表記と読み方に関係する箇所になります。
最も重要な主張は以上の通りです。
これを読んでくださっている皆様の意見を、直接政府に届けられるまたとない機会ですので、是非ともご活用をお願い申し上げます。〆切は今年の6/27なので、それまでに行動を起こしてください。
……さて、ここから下はもう少し詳しい内容を述べて参ります。
拙速でもいいのでキラキラネーム可認法案を抑止したい私として、上で一区切りとしましたが、できればこの後の内容も読んでくださればと思います。
改めて、当該パブコメのリンク(こちら)を掲げます。ここには「意見募集要領」、「戸籍法等の改正に関する中間試案」、「戸籍法等の改正に関する中間試案の補足説明」のPDFファイルがあり、法律的な堅苦しい文章で説明が書かれています。
上では「第1の2について」で伝わると書いてありますが、さすがに具体的内容に一切触れないのはどうかと思いますので、この中間試案そのものの全体について説明致します。
正確なところは元のPDFを見てもらうとして、中間試案のそれぞれの項目を簡潔に言えば以下のようになります。
・第1の1
名前の読み方の戸籍記載を、ひらがなにするか、カタカナにするか
・第1の2
漢字表記された名前の読み方をどの程度認めるか
・第2の1
出生や帰化などで初めて戸籍に名前が記される時、読み方も一緒に記されるというルールについて
・第2の2
既に日本の戸籍がある人物については、決められた期間内に読み方の提出を求めるが、期間内に提出がなかった場合、首長など担当者が推定で読み方を決めて戸籍に書くという制度について
・第3の1
名前の読み方を変更しようとする場合、家庭裁判所の許可を得る必要があるが、「成人になってから1年以内に届け出る場合など」に限り、家庭裁判所の許可を得なくても変更可能にするかどうか
・第3の2
名前を丸ごと変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要なことについて
この中で私が、そして世間が注目しているのが、漢字表記と読み方の関連に関わる「第1の2」という項目になります。
こちらのニュースで取り上げられているように、当該項目が国民関心の高い事柄と捉えられているのは明らかです。このように各報道記事は「戸籍に読み仮名を付けるのは是か非か」などにはまったく関心がなく、「キラキラネームに関わるこの『第1の2』項の是非」に重点を置いているのです。
ポイントとなる「第1の2」に書いてある、元の文章は下の通りです。
--------------------------------------------------------------------------------------氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの許容性及び氏名との関連性
氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの許容性及び氏名との関連性に関する審査について、次のいずれかの案によるものとする。
【甲案】戸籍法には規定を設けず、権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則による(注1)。
【乙案】権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則によるほか、氏名との関連性について、戸籍法に次のような規律を設けるものとする(注2)。氏名を平仮名(片仮名)で表記したものは、国字の音訓若しくは慣用により表音され、又は字義との関連性が認められるものとする。
【丙案】権利濫用の法理、公序良俗の法理等の法の一般原則によるほか、氏名との関連性について、戸籍法に次のような規律を設けるものとする(注2)。氏名を平仮名(片仮名)で表記したものは、次のいずれかとする。
① 国字の音訓又は慣用により表音されるもの
② 国字の音訓又は慣用により表音されるものでなくても、字義との関連性が認められるものその他法務省令で定めるものを届け出た(申し出た)場合における当該表記
(注1)【甲案】について法令に規定することも考えられる。
(注2)【乙案】又は【丙案】における「慣用」は、社会的にその氏名を平仮名(片仮名)で表記したものが使用されているという社会的慣用を意味するものである。
--------------------------------------------------------------------------------------
私は法律の専門家でなければ、法務省の官僚でもなく、法学を修めたことすらありません。なので解釈の正確性にはいまいち自信がないのですが、とりあえず意訳すると次のようになると思います。
(原文では【甲案】【乙案】【丙案】ですが、堅苦しいのでここではそれぞれ【①】【②】【③】と呼ぶことにします)
--------------------------------------------------------------------------------------【①】非道徳的・卑猥・差別的など、人の名前として明らかに常軌を逸したものは禁じる。それ以外は認める。
【②】非道徳的・卑猥・差別的など、人の名前として明らかに常軌を逸したものは禁じる。ある漢字について、辞書に載っている音読みと訓読みは認める。常識的によく使われている人名読みも認める。その他、その漢字の意味と関連がある読み方ならば認める。
【③】②の範囲に加えて、珍しい人名読みも認める。
--------------------------------------------------------------------------------------
この中で最大の問題は、原文にある「字義との関連性」、訳文にある「漢字の意味と関連がある」という箇所にあります。すなわち、漢字の意味と関係があるならば何でも――外国語でもOKじゃないかと解釈できるのが欠陥なのです。
3つの案のうち最も厳しいとされる②案ですら「字義との関連性が認められるもの」ならOKとあり、結局どの案にしても、冒頭で示したような「海(まりん)」や「騎士(ないと)」といった名前が認められてしまうことになってしまいます。
「海(まりん)とか騎士(ないと)くらい、いいじゃん。現代人ならなんとなくわかるじゃん」という反論もあるかもしれませんが、一旦こういったケースを認めるということは、結局は何でもアリになってしまう危険性を孕んでいるのです。
以前にも主張したように、日本人に馴染みの薄いアラビア語、ヒンディー語、スワヒリ語のような言語でも、英語のまったく聞いたことがないような単語でも、意味が一致していれば読み方として認めるということにもなりかねません。
なので「外国語の意味当ては一律禁じる」という規則の制定は絶対に必要であると考えています。
加えて、③案にも重大な懸念点があります。
②案より許可範囲を広げた③案を設けた理由は主に、辞書的な音読み・訓読みに載らない人名訓にあるようです。
たとえば、源頼朝の「朝(とも)」は日本人の多くが読むことができる人名訓だと思いますが、「朝」という漢字と「とも」という読みは、両者の関連を見出すことが困難であり、②案では認められないということになります。
もっと身近な例では「孝(たか)」や「昌(まさ)」も、実は漢字と読みの関連が見出せない、人名特有の用法と言えるのです。
なので、辞書的な音読み・訓読みに限定するのは、やりすぎではないかと私も思います。
しかし、外国語読みを禁じた上での③案ならば諸手を挙げて賛成できるのかと言われれば、そうではありません。
PDFの3枚目「戸籍法等の改正に関する中間試案の補足説明」には、③案を設けた理由として「名乗り訓」と「部分音訓」の存在を挙げています。
「名乗り訓」というのは上記の人名訓のことです。これを一律禁止するというのは確かにやりすぎだと思います。
ただしここで述べられている「部分音訓」が私の考える大問題であり、個人的に最も反対の意を表明したいポイントとなります。
私はてっきり、法律の専門家の集団が、日本語や漢字の立場を無視して法的な議論に終始していたと思い込んでいたのですが、このようにしっかりと「部分音訓」は意識されていました。
この「部分音訓」とは、私の言う「一部引きちぎり型」を指すものでしょう。具体的には、桜(さくら)を「桜(さ)」、渚(なぎさ)を「渚(な)」、絆(きずな)を「絆(き)」あるいは「絆(な)」、心(こころ)を「心(ここ)」あるいは「心(こ)」のように、元の読み方の一部のみを独立的に採用する手法を言います。
上記のように訓読みの一部のみが用いられることが多いですが、凌(りょう)を「凌(り)」とするような音読みの例もみられます。その事実を知った上での「部分音訓」という用語なのでしょう。
さらに驚くべきことに、「反訓」という特殊な語法まで議論が及んでいました。本議論が日本語や漢字の専門家を交えて行われた証拠とも言えるでしょう。
反訓とは、ある漢字が本来持つ意味と真逆の意味を読みとして当てはめることです。例えば「乱」と書いて「乱(おさまる)」、「苦」と書いて「苦(たのしい)」を意味させる用法は歴史上の実例として確認できるものであり、辞書に記載もされています。
日本の人名に焦点を絞っても「魯(おろか)」という漢字に、逆の意味を当てて「魯(さとし)」と読ませた例を私は知っています。
ですが、こういった読ませ方が実際に存在するからといって、じゃあこういうのも全部認めようというのはあまりに短絡的で粗末な考え方です。
過去に執着して新しいものをまったく認めようとしない態度は確かによくありません。当該「戸籍法等の改正に関する中間試案の補足説明」に記載されている議論内容にも「命名文化として、最初に誰かが名を平仮名(片仮名)で表記したものとして考えた漢字の読みが広まって一般的な名乗り訓となるところ、仮に新たな名乗り訓となり得るものが認められないことになると、これまでの命名文化・習慣が継承されないこととなるなどの指摘があった」とあります。
しかし、現代は歴史上類を見ないレベルの情報社会。新たに創出された読みの妥当性が、正当な議論・審議を経ることなく拡散され、その鮮烈さから多数の命名に用いられてしまった結果を無批判に文化として認めるべきというのは思考停止に等しいです。
簡単に言えば、この「慣習」が「悪習」である可能性が一切考慮されていないということです。守られるべき「命名文化・習慣」がむしろ破壊されていることを、参加者の誰も指摘しなかったのでしょうか。
このように主張すると、私は“古き良き”に幻想を抱いた哀れな老害と思われるかもしれません。しかし新しい命名文化の発生を一切認めないわけではありません。
昨今の男性名には、大雅(たいが)、悠河(ゆうが)、彪賀(ひゅうが)のような「が」という人名接尾語が見られます。かつて男性の人名接尾語と言えば、「雄、男、夫(お)」、「人(と)」、「也、弥、哉(や)」、「彦(ひこ)」などに限定されていました。「が」は平成後期から生まれた新しい命名文化であり、これは名づけの可能性を正当に拡大させるものとして歓迎されるべきです。
ちなみに「戸籍法等の改正に関する中間試案の補足説明」にはこうも書かれています。「氏名は、社会において個人を識別する機能を有するものであり」、読みをつける際に「社会的な混乱を防止するため、一定の制約を受ける」と。
音読み、訓読み、人名訓といった既に固定化されたものだけでも、漢字には多種多様な読み方があります。これに加えて、個人による部分音訓の創出を認めることは、社会的な混乱を招く行為に当たると考えられます。
月(るな)から生じたと思われる「月(る)」や、愛(らぶ)から生じたと思われる「愛(ら)」が含まれる人名も、私は実際に見たことがあります。
今回の中間試案では①~③案いずれにおいても、字義と関連があるから外国語読みもOK → 読み方の一部のみを使うのもOK、であり上記のような異常異様な読み方が認められてしまうことになります。
まるで難解なクイズのような個人名があふれる社会を、果たして健全と呼べるでしょうか。
ついでに、中間試案本文や「補足説明」ではまったく触れられていなかったので、法制審議会がどう考えているかは不明なのですが、「柊(とう)」、「颯(ふう)」、「輝(こう)」のような明らかな誤読も認められなくてよいと思います。
人名訓とはその通り訓読みの一種であり、音読みからなる“人名音”というものは基本的にありません。なので、上記の「柊(とう)」などを人名訓の一種と捉えるには無理があり、これを明かな誤りとして排斥することは可能でしょう。
とは言え、何が正当な慣用読み・人名訓で、何が不当な部分音訓・当て字であるかの判断は容易ではありません。例えば「隆」と書いて「ゆたか」という名前があってとしても、普通は読めません。しかし「隆」という漢字の第一義は「ゆたか」なのです。これをアリかナシか判断するのは非常に難しいです。
「補足説明」にも「字義との関連性などを戸籍窓口において審査することは困難」と書かれています。そして「一般的抽象的な規律を設け、個別に判断するのが適切」かもしれず、「戸籍窓口である市町村に対し、氏名を平仮名(片仮名)で表記したものの審査に関する明確な資料を示す必要がある」とも述べられています。
また、認められるべき慣用読みの「慣用」の基準は「不特定多数の人が読める」または「多数の人に既に使われている」のようですが、これに相当するかどうかを役所の職員が確かめることは不可能に近いです。
ただし「補足説明」には、「鈴木」と書いて「さとう」と読ませるようなものは、どの案においても「関連性が乏しく、広く誤解を招くなどの弊害を生ずる」とあります。これを下の名前で考えれば、例えば「一郎」と書いて「だいすけ」、「花子」と書いて「ゆい」、「虎上」と書いて「まさる」などは戸籍名として認められないということになるでしょう。
このような極端なケースは、戸籍窓口でも容易に判断が可能であり、おそらくは放っておいても法的な規制がかかると思われます。
部分音訓もやはり、広く誤解を招く読ませ方あるので、何らかの抑制措置は取られなければなりません。しかしこれまで述べてきた通り、法的に規制をかけるのは難しい側面もあります。
よって、行政側に資料を示すどうこう以前に、世間一般に対して部分音訓など誤解を招き社会に混乱をもたらす読みは付けるべきでないと宣伝する必要があると考えます。
長くなりましたが、まとめると今回の中間試案に求められる意見は二つ。
1.外国語読み、および音読みの誤読は法的に禁止すべき
2.部分音訓など、社会性を欠くが法的な規制が困難なものは、不適当・非推奨である旨の指針や目安を策定すべき
以上を是非とも政府に届けてください。
キラキラネーム――私が呼ぶところのダメダメネーム、もしくはメチャクチャネームと呼んでも差し支えない悪習の蔓延を、これ以上放置しておく訳にはいきません。
今回の戸籍法等改正は、社会秩序を矯め、命名文化を正す好機です。そのために、もう少し厳しいルールが必要であると、私は強く思っています。
最後に今一度、この中間試案のリンク先と意見募集期間を改めて掲げておきます。
1 意見募集期間
令和4年5月27日(金)~令和4年6月27日(月)
2 意見送付要領
パブリックコメントの意見提出フォーム、電子メール、郵送又はファクシミリのいずれかの方法により、意見募集期間の最終日必着で送付してください。御意見をいただく際には、住所(市区町村までで結構です。)氏名、年齢、性別、職業を記入の上(差し支えがあれば、一部の記載を省略してもかまいません。)、どの項目に対する意見か(例えば「第1、2(2)について」など)を必ず明示するようにしてください。
また、各項目について長文の御意見を提出される場合には、集約作業の正確性を期す必要がありますので、御意見の本文とともに、その要旨を各項目の冒頭等に付記してくださいますようお願いします。
なお、電話による御意見には対応することができません。
3 宛先
法務省民事局民事第一課
・郵送:100-8977 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
・FAX:03-3592-7961
・電子メール:minji220@i.moj.go.jp
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
