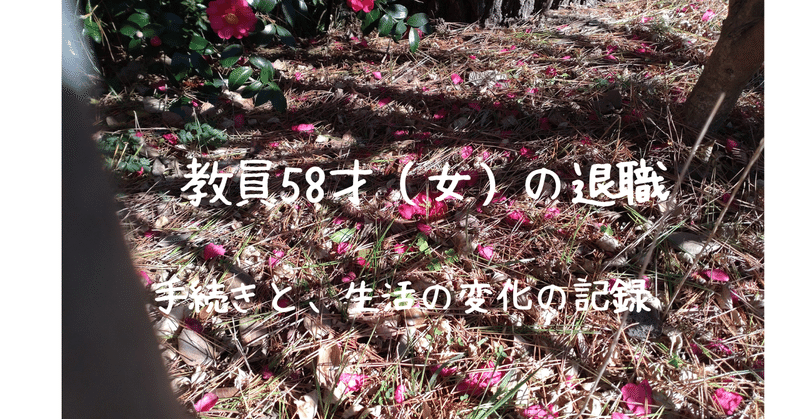
【退職】教員58才(女)の退職ー手続きと、生活の変化の記録
定年まであと3年。少し早めに教員を辞めました。
この仕事は好きでしたし、生きがいも感じていました。
にも拘らず退職することにしたきっかけは、「コロナ」と「病気」です。
新型コロナが蔓延しだした3年前、私は新しく迎える1年生の学年主任に決まりました。
彼らの入試の直前頃から、私たちがこれまで経験したことのないような、新型コロナによる混乱が始まりました。
新入生を迎えるために進めていた様々なことは、変更に次ぐ変更となっていきました。
そして、緊急事態宣言発令。入学式はできず、先生たちはみんなで必死になってオンライン授業をすすめ、5月頃から分散登校の開始。生徒たちみんなが集まれたのは6月になってからでした。
1学期中間考査できず。
春の遠足中止。
部活動の制限。
マスク、手洗い、黙食、消毒の徹底。
体育祭も文化祭も縮小。
あの頃は心身ともにみんなが限界ギリギリでしたよね。
そんな中で、2年生秋の北海道への修学旅行は、延期や変更を重ねて奇跡的に実施できました。生徒に秘密で企画した「打ち上げ花火」大会では、喜びに震えながら泣き出す生徒がたくさんいました。
2年生秋の修学旅行を終えたら、後は「大学入試」に向けた指導、そして「卒業式」で終了です。
その頃から、この2年程のコロナ対応の疲れが出たようで、体の不調が頻発するようになりました。もともとストレス耐性が低いのです。
11月頃、最近流行りの(?)帯状疱疹になり、翌年1月には皮膚ガンが見つかり手術。
そして、翌月2月には耳下腺腫瘍が見つかり3月に入院、手術。腫瘍が良性か悪性かは切ってみないとわかりません。ネットで検索すると、「悪性の場合予後は良くない。5年生存率50パーセント程度のものもある」とか「手術によって顔面マヒが残る可能性がある」など書いてあります。もしもの時のために遺言書も作りましたが…。結果、良性。
私は、ずっと、定年退職した暁には今までおろそかにしてきた「家族との日々の生活」を丁寧に送っていきたいと思っていましたが、「死」はいつ訪れるかわからないのだと実感し、定年まで待っていられない気持ちになりました。
そして、校長先生に今年度で退職したい旨をお伝えしたのでした。
最後の卒業式。「卒業式ではマスクを外すことを基本とする」という通知。
3年間、マスクを外した顔を見たことがない生徒も数多く、卒業式だというのに顔を見ても誰だかわからない子がたくさんいました。
コロナで大変だった3年間を共に過ごした生徒たちは、本当に立派に巣立ってくれました。
私は、36年の教員生活を卒業し、これからは家族との時間を笑顔で送りたいと思っています。
1 退職前後の手続き
定年退職される方には、夏ごろに「退職予定者向け共済制度・手続きガイドブック」が渡されます。その本に、詳しく書いてありますが、隅々まで読むのは割合大変でした。当然ですが、定年以外の退職者には配られませんので、自分で申請しなければいけません。
申請についての掲示物を見逃してしまっていた私は、1月頃にやっと申請して手に入れました。気になる方は学校事務室に問い合わせしてみられると良いかと思います。
基本的には、学校の事務の方が、「この書類書いてね」と渡してくださいます。学校事務のみなさま、ありがとうございます。学校の先生は事務の方のおかげで社会生活を送れているといっても過言ではない、ということがよくわかりました。
では、順にいきます。
(1)退職の意志を伝える
もちろん定年を迎えずに退職したい方の場合です。
定年退職の場合は必要ありません。私は退職する意思が固まった夏ごろに校長に伝えました。人事配置の関係があるのでできるだけ早く伝えておく方が良いと思います。
「人事に関する調書」とその後の面談の折に最終確認。そうすると、事務長さんにも伝わります。
(2)退職願を書く
必要な時期になったら、管理職から、退職願の様式を送ってきてくださいました。とても簡単な様式です。
退職願に必要事項を記入して、指定された期限内に校長に渡します。
(3)「健康保険」について決める
家族の扶養に入る
共済組合の任意継続組合員になる
国民健康保険に入る
上記3つのうちのどれかを選びます。
可能なら家族の扶養に入るのが一番お得です。
入らないならば、2の任意継続がお得です。
国民健康保険は、前年度の収入で支払額が決まるため、高額になります。
任意継続は2年間ですが、途中で辞めることもできます。
私は退職1年目は任意継続。2年目に入る前に任意継続を続ける方が安いか国民健康保険に切り替える方が安いかを市役所で確認しようと思います。
国民健康保険の掛け金は、市町村によって違いますので、それぞれ確認が必要です。(大阪府内では統一される方向だそうです)
(4)「任意継続組合員申出書」提出
上の⑶の選択によって手続きが変わりますが、私は任意継続なので、上記の書類を提出しました。こちらも事務室の方が「はい、これ書いて」と渡してくださいました。
(5)「退職所得の受給に関する申告書」「人事記録」提出
これも事務室の方から、「はい、次これ」と渡されました。1月末ごろです。「人事記録」はSSCで出力します。これまでの自分の勤務の記録が詳細に書かれています。A4で3枚もありました。育児休暇等の時期もこれを見ればわかります。(「退職所得の受給に関する申告書」に育休期間等の記入欄があります。)これらの書類をもとに、事務室の方がややこしいデータ入力をしてくださいます。ありがとうございます。
(6)退職手当の振込先口座の確認
こちらも事務の方から指示があります。2月初めぐらいまでにSSCで行います。口座を指定していないことがあるそうなので、必ず確認しましょう。ちなみに退職金のおおよその額もSSCで確認できます。
(7)互助組合の手続き
退職互助制度に加入するか、加入しないかの選択をします。互助組合から書類が送られてきますので、それに従って書類を作成して送ります。
私はこれまでもほとんど使っていないので、加入しませんでした。
そのため、「セカンドライフ支援金」「生涯福祉一時金」の申請書を提出することになります。合わせて40数万円もらいました。(生涯福祉一時金はこれまで支払ってきた分ですけどね)
(8)任意継続組合費納入(任意継続組合員を選んだ場合)
2023年の場合、3月15日までに納入すれば、3月31日には保険証が自宅に郵送されました。納入がそれよりも遅くなると、保険証が届くのも遅れていきます。一括で支払うと少しお得です。
(9)そして3月31日
共済組合員証を事務室に返却します。勤務校では事前に「持ってきてね」と連絡いただいていたので持っていきましたが、そうでないところもあると思います。
この日、帰宅すると、新しい「任意継続組合員の組合員証」、「任意継続組合員のしおり」「組合員証返納届書」が届いていました。「しおり」には今後の手続きのことや、様々な書類の様式が入っていますので、大切に保管しましょう。
「組合員証返納届出書」は、これまで使っていた保険証を返納するときに添付するものです。私は事務の方のおかげですでに返納しているので、「返納済み」とだけ書いて郵送しました。
またこのころ、「退職所得の源泉徴収票」が自宅に送られてきます。翌年2月ごろの確定申告で必要になるので、保管しておきましょう。
(10)退職手当が入金される
退職手当は、定年退職・特別退職の人は4月3日(高齢者部分休業を取っていた人は4月28日)、自己都合退職・任期付き校長は4月27日に入金されます。
(11)国民年金加入手続き
その他、60歳未満で退職する場合は、国民年金加入手続きが必要です。退職後14日以内に、手続きをします。私の居住地では、近所の市役所出張所で書類をもらって記入し、マイナンバーカードの両面をコピーしたものを添付して、年金課に郵送すれば手続き完了でした。納付書は1か月以内に自宅に送られてくるそうです。
(12)おまけ
共済組合の「長期組合員退職記念事業」というのがあり、「花のいえ」か「ホテルアウィーナ大阪」で利用できる券(1万円分)がもらえます。これは、在職中に手続きする必要があります。
長期組合員退職記念事業:公立学校共済組合大阪支部 (kouritu.or.jp)
使用期限は退職した次の年の2月中旬までです。(実は私は使わぬまま、期限が切れてしまいました😢)
2 退職後7日間の日記
【4月1日(土)】
・燃焼ごみ廃棄
ゴミ袋6袋分捨てましたが、まだまだあります。数十年間、日々食べて寝るのに精いっぱいで、たまりにたまった「いらないもの、捨てる判断を先延ばししてきたもの」をようやく処分、整理しつつあります。
・「共済組合員証返納届出書」送付
私は、昨日職場に返納したので、その旨を書いて送付します。ちなみに健康保険は、共済の任意継続を選びました。
・マーマレード作り
近所のスーパーで地元産の甘夏が売っていたので、ものすごく久しぶりにマーマレードを煮ました。近所に住む高齢の両親の家にもおすそ分け。
・家族で夕食
次男夫婦も訪れ、5人家族でにぎやかな夕食。
【4月2日(日)】
①片付け
食器棚と玄関周りを中心に。またごみが増えました。日曜日であることを忘れてしまいます。
【4月3日(月)】
①市役所出張所で「国民年金申請書」をもらう
手続きは申請書に必要事項を記入して、マイナンバーカードの両面をコピーしたもの(なければ他の身元証明書類でOK)とともに年金課に送付すれば良いとのことでした。この時期市役所本庁はものすごく混雑するので助かります。納入振込書は、1か月以内に郵送されてくるそうです。
②スーパーのチラシを見て、電動自転車で買い物に回る
これは初体験!だから楽しい。
③玉ねぎを飴色になるまで炒める
そして、カレー粉からカレーを煮る。これも初体験。だから今だけ楽しい?
④家計簿アプリを入れる
これからは収入がなくなり、預貯金から切り崩すことになります。私の性格上、収入がないのにお金を使うということに必要以上に抵抗を持ってしまいます。貧乏性です。ですから、「家計簿アプリ」上では、月々20万円収入があることにして、そこから支出するという形にしてみました。それで年金をもらうようになるまで食いつなげる計算。ずいぶん気持ちに余裕が生まれて気がします。
⑤退職金が入金される
さすがに仕事が早いです。退職したんだなあと実感。
⑥大型ごみ廃棄
6往復しました。ゴミ置き場まで100メートル程あるので、1200メートル程重くて大きい荷物を持って歩いたことになります。さすがに手足腰が痛いです。
【4月4日(火)】
①片付け
主に洗面所の物入や棚の整理。「ありすぎるもの」「足らないもの」がはっきりして生活しやすくなります。頭の中も整理されてきました。
②図書館に行く
職業柄、本を買うことだけは、貧乏性の私も自分に許してきました。その結果、本だらけ。けれども退職を機に処分しました。これからは図書館が私の蔵書と勝手に思って、近所の図書館に貸し出しカードを作ってもらいに行きました。ネットから予約もできて助かります。
地域性もあるのか、「老後の生活」についての本が多くのスペースを取って並んでいました。私だけではなく、みんな不安なのでしょう。けれども、こんなにたくさんの本が出ているということは、自分で試行錯誤をして、自分に合った老後の生活を見つけた人たちがたくさんいるということ。これからですね。
③生命保険会社に電話
退職に伴って、保険を見直します。すでに死亡保険はないに等しいものにしていますが、医療保険についても見直します。収入がなくなるので、高額の医療費がかかったとしても上限が抑えられるようになるからです。私は既往症があり、なくしてしまう決断をする勇気はなかったので、月々の支払額を抑える方向で見直します。
【4月5日(水)】
①燃焼ごみ廃棄
前回よりは少なく、4袋。まだ日常のごみの量ではありません。片づけごみがいっぱいです。
②片付け
ベランダとサッシの片づけ、掃除。何十年ぶりかにきれいになりました。
【4月6日(木)】
①片付け
冷蔵庫の掃除。賞味期限切れのもの多数。またごみを増やしてしまいました。これからはこんなことにならないはず?
【4月7日(金)】 1週間休んで思うこと
①無駄なく好きなように時間を使える。
②下痢しなくなった。毎日通勤電車でおなかが痛くなって途中下車していたのに、お薬いろいろ処方してもらっていたのに。
③お酒を飲まなくなった。毎日何かアルコールを入れないとがまんできなかったのに、飲んでないことにも気づかない。
④テレビやユーチューブをあまり見なくなった。動画に依存してたのかなあ。特に「大食い」の動画を見続けていたのに、見たいと思わなくなった。
⑤口の痛みが気にならない時間が増えている感じがする。10年以上前から、どこも悪くないのに口の中がピリピリと痛くて、もう治らないとあきらめているのですが、このところ気にならない時間が増えている気がします。特に、片付けや掃除に集中しているときはほとんど気になりません。ガムを噛んでいるとマシなので、ガムが手放せなかったのですが、この数日はほとんど減っていません。
⑥家族にもご飯を作ってあげられる。今のところはまだ楽しい。
今のところはマイナスは見当たりません。ただ、やりたいことをやっているので集中しすぎてしまい、休憩するのを忘れてしまって、結果くたくたになっていることがあります。けれどもこれは私の自閉的な習性だと思います。
もちろん収入がないのは寂しいですけど。
3 退職10日後の出来事
母より電話。「お父さんが熱出てなあ。」
よっしゃ、出動!待ってました!
仕事を気にせずヘルプ要請に応えられる、というのも今までできなかったことの一つです。
実家はすぐ近く。近くも近く、マンションの同じ棟。歩いて2分。自分の子どもたちをみてもらうために実家の近くに引っ越してきたのでした。
思えば20数年前、母は自転車の前後に孫二人を乗せて公園に行ったり、幼稚園に行きたくないと言ってぐずる孫をなだめすかしてバスに乗らせたり、学校に入学したら毎日宿題を見たり、連れて帰ってくる友だちまで世話したり、私が遅くなるとごはんまで食べさせたり。
父は、電車が好きな息子に、新大阪から京都まで新幹線に乗る体験をさせてくれたり、ラピートを見に連れて行ってくれたり、一緒に遊んでやってくれたり、USJにも連れて行ってくれたり、ハリーポッターの本が面白かったからと言って、孫のために全部の漢字にふりがなを振って渡してくれたことも。
両親とも数えたらきりがないほど、孫のために、娘の私のために、力を尽くしてくれました。
その両親が助けてほしい時に助けに行ける状況にあるというのは、これほどありがたいことはありません。
だから母ちゃん、「ごめんなー」とか、言わなくていいねんで。
父ちゃん、「帰って仕事していいで。必要な時呼ぶから」とか、気いつかわんでいいねんで。仕事ないし。
4 退職して2週間
退職して2週目の1週間を振り返りたいと思います。今週の出来事が今週起こってよかった。先週事務仕事片付けておいてよかった。
月曜日
「家の中で片付けしてばかりだと足腰弱るな」、と思い、朝ランニングをすることにしました。
ジャージを着て出発。しかし、全然走れません。
早歩きもできません。ランニング改めウォーキング。
途中の広場で高齢の方々(私よりも先輩の方々)がたくさん、整然と等間隔に広がり、ラジオ体操をしていらっしゃいます。そのうち入れていただこうかな。
火曜日
朝ウォーキング。2日続いた!
帰宅すると母から電話。父の体調が悪いとのこと。近所の実家へ向かいます。
押し車を押しながら歩く母と、ムーちゃん(こだわり強めのトイプードル)の散歩。
いつもは父が母の健康のために、犬の散歩を兼ねて母と歩いているのです。
犬の散歩をしているとおもしろいことがいろいろあります。
ムーちゃんは、真っ白のふわふわの犬に出会うと大声で吠えるのに、おとなしそうなチワワに出会うと何の反応もしません。
ムーちゃんは、あるお兄さんを見ると一目散に走り寄ります。
お兄さんは車いすを使っておられます。ムーちゃんは、お兄さんがいつもおやつをくださることを知っている。
お兄さんは、近所のワンちゃんたちの人気者。ワンちゃんたちの名前も覚えておられて、それぞれの好みに合ったおやつを準備してくださっている仏様のように優しいお兄さんです。
ムーちゃんは、うんちをすると自分のうんちを食べそうになります。食べてしまうときもあります。なんで?
いろいろおもしろいのです。
いったん自宅に戻って1時間ほど家の家事をします。
そして、母の家に行き一緒に買い物へ。ゆっくり歩きます。
いったん自宅に戻って家事をします。
夕方、母とムーちゃんの散歩第2回です。
終わると自宅に戻ります。
水曜日
ムーちゃんの散歩のあと、母の通院付き添いです。父は熱が下がらないのでお留守番。
市民病院までタクシーで行きます。検査やら診察やらが終わって、帰りにタクシーに乗ろうと思ったら、なんと母がトイレにバッグを忘れてきたらしく。
母、押し車を押して走ります!え?走る?走れるん??
バッグは無事見つかり、帰途へ。帰りに母と買い物います。
今日の夕方の犬の散歩はなし。母、バッグ事件でお疲れのため。ムーちゃんはまだ母が一緒でないと不安らしい。というか、母が私一人には任せておけないのでしょう。ムーちゃんの散歩には、母か父が必要です。
木曜日
朝、ムーちゃんと母の散歩。
母と買い物。
夕方、ムーちゃんと母の散歩。
合間にまたマーマレードづくり。(甘夏が出ていると作りたくなる)
金曜日
朝、ムーちゃんと母の散歩。
帰宅後、父の容体悪化のため、入院することになりました。タクシーで病院までいきます。
熱があるので、やはりコロナの検査から。肺炎の紹介状を持って来ていてもやっぱりそうなんですねえ。
肺のCTやレントゲンや血液検査。なんやかんやで3時間ほど待ちます。ようやく13時過ぎ入院。
私はいったん帰宅して、ご飯を食べて、忘れ物を届けにもう一度病院へ。退職前に買った電動自転車が大活躍。
ムーちゃんと母の散歩は、今日もなし。きっとムーちゃんも大変なことになっていることに気づいています。
〈今週の学び〉
① 犬のムーちゃんは、「ひと」のことが「ひと」よりよくわかっているが、自分のうんちは食べてしまう、ということ。
② 父母の保険証と診察券はあそこにある、ということ。
③ 父の身長が〇㎝、体重〇㎏、生年月日は〇〇、既往症は〇〇で、常用薬は〇〇で、〇〇のアレルギーがあって、というようなこと。(今まで知らんかった。ごめん)
④ 私はまだ役に立てる、ということ。だから、健康でいなければいけないということ。
5 退職して3週間
退職して3週目の一週間、母と犬の散歩を基本とする「日常」。あまり変化もないので、トピックスだけ振り返ってみようと思います。これからどんどんそうなっていくんだろうなあ。いいのか、悪いのか。
火曜日
大量の小型複雑ごみを出せて、ようやく断捨離第一弾終了。ベランダもゴシゴシ磨けてすっきり。
水曜日
受験生の姪っ子に「古文」を教える。まだ教えることができてよかった。なんか嬉しい。
木曜日
午前中、自分の薬を処方してもらいに、月に一度の通院。仕事を気にせず、適当な時に病院に行けるのはとても気楽。
どこも悪くないのに口の中の痛みがなくならず、もう何年も、緊張を和らげる薬を処方されています。
主治医に「調子が良いようなので、薬をやめてはいけないでしょうか?」と尋ねてみたところ、「今はバタバタしているから痛みが気にならないんじゃないかな?環境が変わったばかりの時は、薬を変えない方がいい。今の環境に慣れるまでは、飲んでいた方がいいと思いますよ。」とおっしゃいました。確かに。冷静なご判断。納得です。
金曜
昼過ぎ「ガスの点検」。団地の点検関係は、業者さんに日程を変えてもらうなど、いろいろ調整が必要でしたが、今はほぼいつでもOK。気楽です。
そのあと入院している父に面会に。コロナの時は、面会禁止でしたが、今は、「週に一回。家族のうちひとりだけ。15分以内」で面会が許されるようになりました。
見晴らしの良い、いい部屋でした。いつもどおりの気丈な父でした。欲を言えば、もうちょっとゆっくりしていられたら良かったなあ。
【時間と自由の関係について】
なんて、難しそうなテーマを書きましたが、これは、高校の現代文の教科書によく入っている評論のタイトル。内山節さんの文章の題名です。
私も国語の時間に教えていましたが、教えながらも書いてあることがピンときませんでした。
けれども、今週は、このことについて考えることがよくありました。
内容を、ものすごくざっくり、勝手な補足も付け足して書くと、
ー時間には2種類あります。それは、「時計に支配される時間」と「時計に支配されない時間」です。たとえば、昔の学校には時計がありませんでした。ほら、寺子屋なんかには時計はなかったでしょう?
ーいつ頃から学校で時計が使われるようになったのでしょうか?それは産業革命以降。労働が、時間当たりの量ではかられるようになってからなんです。経済と教育って直結していますから、学校にも時計が入ったのです。
ー学校に時計が入ると、時間割ができます。テストはぴったり時間内で行われます。1分でも遅刻したら叱られます。「時間を有効に使いなさい」とか「5分前集合!」などと言ってしつけられます。能率的に働く労働者を作るためです。
ー現代、人は時計に支配されがちです。でも本当は、時計に支配されない時間にこそ、「今を生きている」という実感を感じられるのです。
のような感じの話。
朝ドラ「らんまん」の主人公、万太郎などは、「時計の時間」に支配されずに生きている感じですかね。
私は、その「時計に支配されない時間」とか「今を生きている」などという感覚を実感したことがありません。
というか、あったかもしれませんが、思い出せません。
小・中・高校・大学とずっと時計に支配され、その後は労働者ですから。
今の社会、たいていの人がそうなのではないでしょうか。たぶん、高校生の人たちも、それまでの人生で実感したことのある人はほとんどいなかったでしょう。
この教材では、みんな想像力を働かせて理屈で考えるしかありません。
けれども、仕事を辞めた今は当たり前のようにわかります。「時計に支配されない時間」「時間を創造するということ」「今を生きているという実感」。こういうことだったのか。
時計に支配されていた時は、「あと何年生きられるんだろう」と考えていましたが、そんな風に考えることはなくなり、ただ、今生きているということだけがある感じ。
今日、買い物の帰りだったかに出会った90歳ぐらいの女性は、母によると、しばらく前に伴侶が亡くなったこともわからなくなっておられるとのこと。今の自分よりも「今」だけを生きておられるのかなあ。
6 退職して1か月
退職してそろそろ1か月が過ぎようとしています。
もう、退職後のバタバタはありません。
朝夕の、犬と母の散歩、母の買い物の付き添いと、日々の家事が日課です。3日に一回ほどの、父の病院への運び屋と。
働いている時よりは丁寧に掃除をしていますが、そのうち、「毎日やらなくても死なないしな」と思うようになる、ような気がします( ´∀` )。きっと、ピカピカなのは今だけです。写真撮っておこうかな。
雨の日は時間を持て余します。読むか書くか、それとも寝るか。昼ご飯を食べると眠くなります。
ずっと父が言っていました。「退職したら何かせなあかんぞ」と。
けれども今は、「何もしなくていいんだよ~」という悪魔のささやきに勝てません。
そんな中でも少しだけ、トピックス。

3週間ほど前に、おすそ分けしていただいた金柑を、焼酎と氷砂糖が余っていたので金柑酒にしてみました。そろそろどうかな、と思って試飲してみたら、なかなか美味しかったです。金柑酒って飲んだことがないので、これでいいのかどうかわかりませんが。
そしてもうひとつ。

実家から君子蘭をもらってきました。親戚からいただいたものを株分けして増やしたのだそうです。もう花の全盛期は終わっていて、この株も立派な花を咲かせ終わったのですが、もうひと花咲かせるつもりのようです。
私も見倣わないとな、という気持ちと、「もうええわ」、という気持ちと。
7 退職して2か月
アルバム整理
そろそろ生活が落ち着きすぎてきたので、仕方なく、見て見ぬふりをしてきた昔の写真などの整理に取りかかりました。
1枚1枚スキャンしてデータにする?
写真の量を減らしてアルバムに貼りなおす?
データ化すると、置き場所はいらなくなりますが、見返すことも無くなりそうです。それに、家族みんなでワイワイ言いながら見る、ということもしにくくなりそうです。
それで、どうしても残したい写真だけ残して、あとは廃棄する方向ですすめることにしました。
自分の写真はもう見たくもないので、さっさと捨てられます。けれども、子どもたちの写真は見入ってしまって進まないし、なかなか捨てられません。
子どもの卒園式の写真。私の両親が行ってくれています。若い両親が二人の孫を連れて、笑顔で写ってくれています。両親は今の自分の年齢と同じぐらいです。
その写真を見て、「私はどうして行かなかったんだろう」と思って不覚にも涙が出ます。休みにくい仕事があったには違いないのですが、それでも何とか行けなかったのだろうか、と心が痛みます。
勤務校の入学式の日、私は新入生の担任だったのですが、子どもが高熱を出して、入学式を休ませていただいたことがあります。
仕事を休んだことには全く後悔の気持ちが起こりません。他の先生方にご迷惑をおかけしたことは申し訳なかったのですが、「あの時に担任として入学式に出なかったこと」には全く後悔がなく、かえって笑い話にしてしまえるほどなのです。
ところが、「我が子の卒園式に行けなかったこと」は今も後悔が残り続けています。卒園式だけではなく、学習発表会も、参観も。子どもたちは忘れてしまっているのでしょうけれどね。
家族を大事にできる労働環境がないと、先生の数も増えないし、子どもの数も増えませんよね!
あら!幼稚園の先生との「連絡ノート」も出てきました。
『苦手なことでもあきらめずに、最後まで頑張っています。』とか、『〇〇さんととても仲がよくて、いつも一緒にいます。他の子どもたちに冷やかされてもニコニコ笑っています。』とか、『家であったことを毎日のようにお話しに来てくれます。』とか、うれしいことがたくさん書いてあります。
あの頃の私は、先生の連絡帳に癒されてたんだろうなぁと思います。そして、今でもうれしくて泣けてきます。保育所や幼稚園の先生って、すごい仕事だなあ。
あかんわ。もう全然すすみません。写真を見ると、その頃の自分の状況が思い出されて、感情まで揺さぶられてしまいます。
しんどい作業ではありますが、もしかすると、これからの人生を良い気持ちで生きていくためには必要な作業なのかもしれません。
結局今日は、勤めていた学校の卒業アルバム(昔は学年教員全員に配布されたので、たくさんたまっているのです)を頑丈に括ってガムテープでぐるぐる巻きにして袋に入れたのと、どんな写真がどれだけあるかざっと見て、押し入れに掃除機をかけたのとで終わり。
明日はアルバムに貼ってある写真を外しまくって時系列に並べる作業をやろうと思いますが、きっと進まないでしょう。一日1時間ぐらいに決めて、タイマーかけて、ゆっくり進めようと思います。
何回涙を流すことになるのでしょうねえ。
来た!住民税!
さて、退職後初の市民税・府民税の納付書がやってきました。納付額はウン十ウン万円です。お勤めのみなさんは、職場から市民税・府民税の書いたピラピラの紙、もらっておられますよね。あの額ですわ。
お仕事をやめられたその年の6月は、そこに書いてある額とほぼ同額の税金を納付するということですわ。
私、恥ずかしながら、あの「市民税・府民税」の紙、どこをどう見るのかさえよくわかっていませんでした。世間知らずと言われても仕方ないなあ。
「それにしても、こんなに税金払ってるのか~」と今さらながらびっくり。でも、税金からお給料もらっていたのですから、そんなことを言ってはバチが当たります。
支払いは、一括で、ゆうちょのアプリを利用して行いました。ゆうちょのアプリでの支払いは最近使えるようになったそうです。現金を出したり、窓口やATMに並んだりしなくてよいので助かります。
8 退職して3か月
退職後、消失してきたと思っていた「口の痛み」がひどくなって戻ってきました。
仕事のストレスがなくなって、痛みも無くなったのかな、と思っていたのですが。
ちょうど手術のあとに麻酔が切れていく時のような、口の中が焼けるような痛みです。
日によって朝から痛かったり、夕方以降に痛くなったりします。
内科、耳鼻科、歯科、口腔外科で検査をしてもらいましたが、どこにも異常はありません。
ネットで検索すると、「口腔灼熱症候群」というのがちょうどピッタリあてはまります。
更年期の女性に多い症状のようで、苦しんでいる人はたくさんいらっしゃるようですが、原因はわかっておらず、治療法も確立されていないようです。
朝起きた時からずっと痛いのです。口が痛いと、その周辺の首や頭や肩なども痛くなってきます。
考えてみると、仕事をしていた時も、休日は朝から痛かったのでした。
ということは、これまでの3か月ほどは、「一日中ずっと目新しい仕事をしているのと同じ感じ」だったのかもしれません。
そういえば、この3か月ほどは両親の病気やら断捨離やらで、忙しくしていました。
テンションが上がっていたために痛みを感じなくなっていたのかもしれません。
いろいろなことが落ち着いてきて、本当に毎日がお休みになってきて。
「口の痛み」が戻ってしまったのでしょう。
これからが正念場かな?
とりあえず、漢方薬を試してみようと思います。
9 退職して4か月
仕事をやめて4か月になり、「やっと」というか、「もう」というか、「残念なことに」というか、自分が教員であるという意識がなくなりました。
初めの3か月ほどは、「教員だった自分の続き」を過ごしているような感覚がありました。長い休暇中と同じような感じです。35年間、良き教員であろうと自分なりに頑張っていたのですから、急には抜けないのでしょうね。
退職して4か月になろうとする今は、仕事に行かないのが当たり前になっています。
「私、先生だったことがあったのね~」と写真なんかをみて懐かしく思いだすという感じです。高校時代の卒業アルバムを見て、「私にもこんな時代があったのね~」と思うのと同レベルです。
今、どんな生活をしているかというと…
6:00
起床。洗濯機を回す。バジル・ネギ・パイナップル・ブルーベリー・君子蘭に水やり。身支度。
6:30
朝の散歩
7:00
帰宅して朝食(パンとカフェオレとヨーグルト。たまに果物)。洗濯機を回す(2回目)
新聞をゆっくり読む。(私は「朝日」好き、夫は「日経」好きで、どちらも引かないので両方取ってます)
チラシで特売のチェック(これが大事)。洗濯物を干す
8:00
朝ドラの時間
8:15
朝のヨガ(ヨガマット敷いて。形から入るタイプです。)
8:45
長男起床。朝食を準備したり、天気やニュースの話をしたり。(長男は、「朝日」と「日経」の第一面の読み比べが好きです。)
9:30
長男出勤。(「水筒忘れてるで」「行ってらっしゃい!」を言えるのがしあわせです。)
掃除①ー毎日の掃除
(家中の掃除機かけ。5分もあれば終わります。)
掃除②ー週1ぐらいにやる掃除
(「ガラスと網戸掃除」とか、「床の拭き掃除」とか、「べランドと階段掃除」とか、「冷蔵庫掃除」とか)
晴れた日は布団を干したりシーツを洗濯したり。
10:30
スーパーに買い物(毎日行きます。たいてい特売品でその日の献立を決めます。)
11:00過ぎ
帰宅して食材の下ごしらえ
11:30頃
早めの昼ご飯
(たいてい前日の残り。ない時は納豆とごはんと漬物。たまにそうめんとか、パスタ。)
昼食後、録画していたテレビを見る。
(夫の見たいものと違うので、私が見たい番組は録画して見ます。)
13:00頃~16:00頃
ブログを書いたり本を読んだり。たまにジャムや佃煮を炊いたり。
16:00頃~
洗濯物を取り入れて片付け(夏は良く乾いていいですねえ)
夕食の準備
家族が帰ってくるまで本を読んだりテレビを見たりゲームをしたり
午後6時~7時半ぐらいに家族が帰宅するので、一緒に晩御飯を食べたり、あんなことこんなことしゃべったりします
あとは片づけて、お風呂に入って、ヨガをして、本を読んで、11時ごろには布団に入ります
以上で一日終了
仕事をしていた時並みのスピードでやってしまうと時間を持て余すので、できるだけゆ~っくりやります。
できるだけゆっくりやることで、いいこともあります。
たとえば、バジルやネギが成長していることに気が付いて喜べます。
たとえば、家や服などの汚れがなかなか落ちなくてもストレスがたまりません。かえって暇つぶしになるので喜べます。しかも頑張って綺麗になったら家族に自慢できます。
たとえば、じっくり味わって本を読めます。
たとえば、散歩や買い物の時にきれいなものを探しながら歩けます。(今は暑いですけど)
たとえば、食器を割ってしまったり包丁で指を切ったりということが減ります。(老眼や筋力の低下のため、ゼロにはなりませんが。きっとこれから老化のための失敗は増えるでしょうが、もっとゆっくり動くようにすればいいかもしれません。)
きっと今後のブログには「学校のいろんなこと」を書くことはないでしょう。また、「退職後」という感覚もそろそろなくなってきました。ただの「おばちゃんの日常」です。
10 退職して半年
気が付けば退職をして半年が過ぎていました。今日はこの半年を思い返して、「ひとり反省会」をしてみようかなと思います。
この半年でやったこと
事務手続き
退職時に必要なもろもろの手続きをしました。
目次の「退職前後の手続き」以外に、国民年金や住民税の払い込み、8月ごろの特定健康診断の申し込みなど、自宅に郵送されてくる書類に沿って行いました。
あとは、来年2月の確定申告。それから、健康保険について、「来年も共済を継続するか、それとも国民健康保険に切り替えるか」の判断をして、手続きをしないといけません。忘れそうなのでカレンダーに書いています。
お金関係見直し
今後の支出について試算して、月々いくらくらいで生活していけばよいのか、考えてみました。
4月当初は、できるだけ余裕を持っておきたいという気持ちから、お金を極力使わずに生活しようとしていましたが、それではあまりにも面白くないので、今は「上手に使いきる」方向にシフトしつつあります。けれども、この先何があるか、何歳まで生きるかわからないので、どうしても不安になります。
その他、こんなこともやりました。
生命保険の見直し(死亡保険はやめて、医療保険を少し残しました)
投資の勉強、相続の勉強(本、YouTube、ブログなどで。)
証券口座を作る(口座作るのはタダだし。経済の動きを教えてくれるので勉強になってます。
片付け
思い切って家の片づけをしました。ゴミ袋にすると50袋分ぐらいでしょうか?物が減った分収納のための家具もいらなくなり、家具も減らしました。
そうして、ひと部屋、自分のための部屋を作ってもらうことができました。(ケンカしたときなんかも便利だと思います)
一番時間がかかったのは、アルバムの整理でした。どうしてもいろいろ思い出して見入ってしまいますからねえ。
その他
ブログ開設
ベランダで再生栽培(バジルやパイナップルなど)
季節ものの料理(梅酒、山椒佃煮、バジルのいろいろ、おはぎ、栗ご飯など)
動画づくり
平日に友人とおしゃべり
近場のひとり旅
時々、両親のお手伝い
最近、エッセイ、短編小説などの公募に応募するのも趣味
こうして書き出してみると、なんと平和な充実した半年だったのか、と思います。それなのに、何となく張り合いが出ないのはなぜでしょう?きっと自分のためだけに生きているからなのでしょうね。
けれども、自分が元気でいることは家族のためになっている、とも言えるかな?そんな風に厚かましく思って、これからも楽しみを見つけて生活していこうと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
