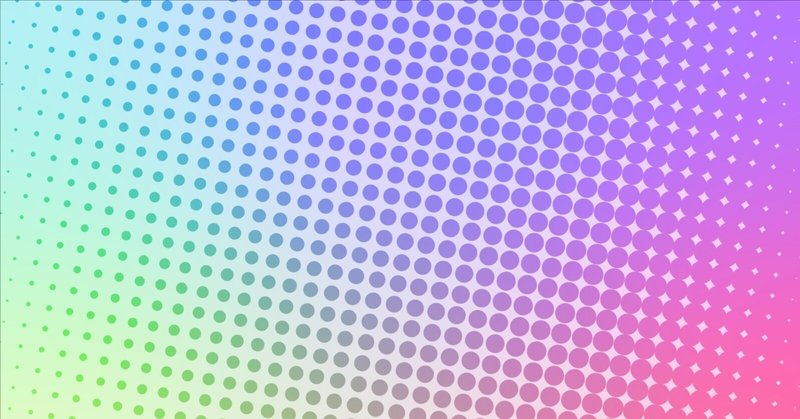
独断と偏見で選ぶ「後期」globeの(隠れた)名曲ベスト10#1 流行歌受容の臨界期仮説?
流行歌受容の臨界期仮説?
言語習得には臨界期仮説なるものがある。
言語は幼児期から思春期までに完全に習得され、それ以後に学習を開始したとしても不十分にしか習得し得ない。――
真偽は確定していないようだが、そんな気もする。
これと同じように、流行歌の受容についても〝臨界期〟があるのではないか?
つまり、ある年齢まではリアルタイムで流行している音楽に熱中でき、追いかけもするけれど、ある年齢を過ぎた途端に急速に受けつけなくなる。どうでもよくなる。
新しい楽曲は日々生産されるのに、いつの間にか懐メロに走ってしまうようになるのは、このためではないのか。
私見だが、その臨界期は20歳前後にあるような気がする。
自分の場合(1980年生まれ)、同時代的に最も親しんだ流行歌といえばglobeの楽曲だった。
ボーカルのKEIKO・ラップのMARC PANTHER・そして言わずと知れた小室哲哉からなるあのglobeである。
globeの楽曲には今でも、肌に密着してくるような〝どうしようもない愛着〟を感じる。
米津玄師の「Lemon」(2018年)やYOASOBIの「群青」(2020年)も、いいなあとは思うのだ。
けれど、globeに対して感じるような〝どうしようもない愛着〟は湧いて来ない。
今後湧くこともない。そう断言できる。
ただ、もしあの頃、自分の中の泉が涸れる前に出会っていれば、globeが米津玄師やYOASOBIに置き換わっていた可能性はある。
そういう想像はできる。
ただ、想像できるだけで、現実化することは決してない。
臨界期を過ぎているから。
馴れ初めと疎遠
私がglobeを初めて知ったのは1996年の大晦日である。
ピンポイントで特定できる。
NHKの紅白歌合戦で「Can't Stop Fallin' in Love」を唄っていた。
当時の自分はいわゆる流行歌にまったく関心が無かった。知識も欠いていた。
妹に教えられたのだ。
女性の歌と男性のラップ(語り?)の組合せ。
へぇー、こんなフォーマットがあるのか、と思った。
物珍しかった。
それで興味を持った。
そこから、過去を掘る作業が始まった。
と言っても、当時、アルバムはまだ『globe』の1枚しか出ていない。
早速TSUTAYAでレンタルしてカセットテープに録音して聴いてみた。
どの曲もよい。
グローブは野球のグローブじゃない、地球のことをグローブとも言うのだ、グローバルという語はそこから来ているのだ――ということに気づいたのも、その頃である(当時の英語力の無さ……)。
新曲が出たら必ず聴くアーティストが初めてできた。
1997年以降の自分はglobe漬けになった。
ところが……
2001年以降、自分はglobeから急速に離れた。
離れたのはglobeだけではない。
プロ野球・プロレス・流行歌……みんな離れて行った。
理由は簡単。就職したからである。
それらをフォローする時間が物理的に無くなった。
今でこそ若年労働者の低賃金が社会問題になっているが、当時はそんなことはなかった。
当たり前だと思っていた。
初めての給与明細を見たとき、愕然とした。
研修中は残業時間がつかなかったのだ。
これでは残業しなければ、やっていけないな、と思った。
若者は残業代を享受し、企業は若者の長時間労働を享受する。
そこに、バーターが成立していた。
残業代と合わせると生活が成り立つ――その前提で、ギリギリのラインに初任給が設定されていたのだと思う(現在では少子化が進んで、もうそんな非道なことをしていられない状況に変わってきているようだが……)。
時間が無い。
自然と、globeに関する情報にも疎くなる。
2002年に何とKEIKOと小室が結婚する(相手はMARCじゃないのかッ)。
2008年には小室が詐欺事件で騒動を起こす(あれだけ売れたのにカネに困っていたのかッ)。
2011年にはKEIKOがくも膜下出血で倒れる(ええッ)。
2018年には小室が不倫&引退騒動を起こす(引退するわけないだろッ)。
これらが耳に入って来た程度である。
調べてみると現在、小室とKEIKOの離婚は成立し、小室は音楽活動を再開しているらしい。
最近、テレビ東京の路線バスの番組にマークが出ているのを視て、ああ、マークはこういう番組に出るタレントになったのか、と妙な感慨を覚えたところである(「ローカル路線バス乗り継ぎ対決旅 鬼ごっこ第8弾!春休み首都圏決戦!」2023年4月5日放送)。あ、テレ東の路線バスものは大好物です)。
(次回に続く)
最後まで記事をお読み下さり、ありがとうございます。賜りましたサポートは、執筆活動の活力とするべく大切に使わせていただきます。
