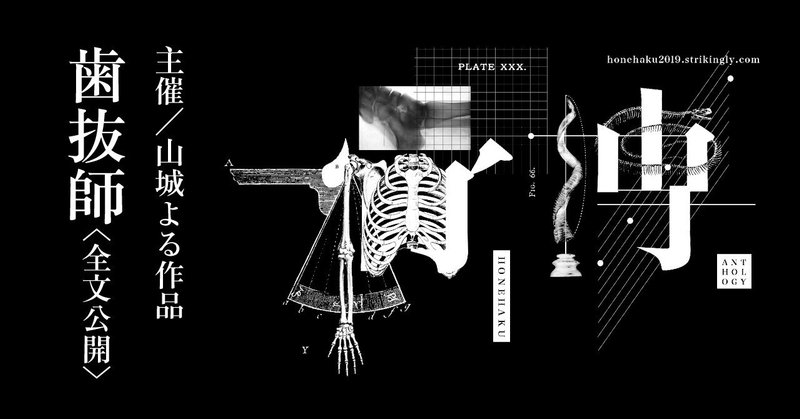
骨博【〈歯抜師〉全文公開/山城よる】
わずかな薄明に、ぼんやりと木々の形が輪郭を取り戻し始める早朝の森。辺りは冷たい靄(もや)に沈んでいる。
痩せこけた女の身が砕かれる音と絶叫が、秋の彩りに満ちかける山を劈(つんざ)き、すぐに静まり返った。
女の身は枯れ枝のようであったが、噴き出した温かい血は冷えた空気をかすかに湯気に変え、熊の毛をしとどに濡らす。強靭な熊のあぎとに掛かれば、人間の、それも女の肉体などいとも容易く砕けてしまう。熊の爪にはあまりに薄過ぎる皮膜が破られた腹部から内臓が散り、あたりに血臭が立ち込めた。
ざあっと落ち葉を蹴散らす黒い影が、夜の残滓(ざんし)をうすらと抱え、まだ暗い木々の間を縫うように駆け、ぎらと光る太く厚い刃を熊の後ろ首目掛けて叩き付けた。刃の衝撃に吼えた熊が女の肉片を放り出し反撃に出ようとした瞬間、続く二つ目の影の追撃が、毛皮の下に脂をため込み始めた皮膚、まだ致命傷に到らない熊の後ろ首──初撃で斬りつけた傷に、寸分違わず叩き付けられた。
夜と朝のあわい。人里遠く、奥深い山中における刹那の出来事であった。ずん、と絶命した熊が地を揺らして倒れ臥す。
「こんな時間に、こんな場所で、女?」
熊を仕留めた二撃のうち、一撃目を与えた男は広がる血溜まりを避けて立ち、まだ若い個体であろう大きさの熊の死骸を見下ろす。大きくため息を吐き、うんざりした様子を見せた。
この山中に彼らの棲む郷(むらざと)があるということは広く知られているものの、詳細な場所については郷の者以外には固く秘され、ゆえに、外部の者の来訪は一切ない。
死を導き、人々の弔いの身仕度を調えることを生業として、さすらう彼ら――歯抜師(しばつし)の帰る場所として相応しいよう、また、死の匂いを濃厚に常纏(じょうてん)する彼ら自身を人々が畏怖し忌避するがゆえ、その郷は山中に秘匿されていた。
郷の人間は、男衆以外は殆ど外に出ない。女子どもはせいぜい近場の林を、すぐに駆け戻れる距離で出歩く程度である。熊がうろつく薄明薄暮の時間などは腕自慢の男衆でさえ出歩くのを控える。
獣と人間が共に同じ山に棲むのだから、互いの距離を適切に保つ生活の時間がある。それは幼い子どもですら知ることだ。
「かわいそうに、こんな死に方をして」
追撃を叩き込み、熊にとどめを刺した男の方は幾分穏やかな声色で、熊の死骸のまわりに無惨にばらけている女を見下ろした。
「勝手に山に入るからだ。何処の誰だか知らんが自業自得だ」
女の身勝手な山への侵入で熊が人の血の味を覚え、それで郷が襲われてはたまらない。
痩せぎすの、冬の木立のような身体はそれでも、冬眠前の食い溜めをする熊の食糧としては食いでがあったのだろう。木の実や果物を探して徘徊するよりよっぽど効率がいい。
「人の味を知った熊は繰り返し人を襲う。気付かなければ郷人(きょうど)がやられていたかもしれんぞ」
「始末が間に合ったのだから、もういいでしょう。ここは私が見ているから、あなたは誰か呼んできて下さい」
ちっと舌打ちをし、遠々煕(とおとき)は熊の血で濡れた鉈(なた)の刃を拭って鞘にしまうと、落ち葉を蹴散らして駆けていった。
熊の身をこのまま放置するわけがない。捌いて毛皮をとればこの冬の誰かを暖めようし、肉は保存食にできる。内臓は乾燥などの加工を施せば薬材に利用でき、特に血は煮詰めて凝らせれば増血の薬になる。毎月の忌み籠もりに血を流す女たちが喜ぶはずだ。
熊は骨の一片とも余さず利用できる最大の獲物だった。狙って穫れるものではなく、また、狙うにしても強度の危険が伴うため、積極的に狩ろうとすることも滅多にない。
熊が女の身を貪るのに夢中だったからこそ、比較的容易に仕留めることができたが、幸運と呼ぶには複雑な心境で、日照雨(そばえ)は、落ち葉に半分埋もれて転がっている女の頭部を拾った。
熊の死骸と、女の血や肉片が散る場所から離れた日照雨は、背負っていた荷を解き、地面に道具を並べる。簡易な作業場として布を敷き、女の頭部を置いて緩慢に呼吸する。朝の冷たさを胸いっぱいに吸い込むと、頭の中が透明になってゆくような気がした。
恐怖に見開かれたまま絶命し、虚ろを宿した目をそっと閉じてやる。ついさっき絶叫を吐き出した口は、もう何も語らない。日照雨は女の口を開き、口角に鋏(はさみ)を入れた。すっかり青褪めた顔の、頬骨と下顎骨(したあぎと)の合わさる部分まで左右の頬を切り裂くと、慣れた手付きで顎を外す。あまり切りたくはないが、この女の口は小さく、道具が入らないので仕方がない。
並べた鋳鉄(ちゅうてつ)の道具からひとつ選び取ると、露出した歯を一本ずつ丁寧に抜き取っていった。それは力の要る作業であったが、日照雨の動作は流れるように自然で、そして早い。数多の人々に同様の処置を施してきた、玄人の手付きだった。
三十二本の歯を抜き終えると、乾燥させた香花を包んだ真綿を口に含ませ、外した顎をもとの位置に戻し、頬肉を整える。裂いた頬を縒り合わせた純白の絹糸で縫い閉じるうち、つやめく白糸は赤く染まった。
ひと通りの処置を終え、最後に血色を補う紅粉(べにこ)をはたき、色を失った唇に丁寧に紅を差してやる。
その紅は、女の一生分の働きをまとめて金に換えたとしても手が届かないほど貴重な──金属質の緑色に照る笹紅だった。青褪めた唇は血色が戻ったように赤く染まり、わずかに金色を含んで照る。仕上げの紅を差し終えると、四角い黒布である幎帽(べきぼう)の紐を後頭部で結び、顔を覆い隠した。
人間が生まれながらに持つ歯の根をすっかり抜き去った身になってようやく、弔いの──死人(しびと)にとっては旅立ちの──準備が調う。
この葬礼儀式は歯抜儀(しばつのぎ)と呼ばれるもので、死番(しつがい)山脈を中心に広がる。この女は山のどこかに郷を構える彼ら歯抜師に用があって、無縁者が踏み込んではならぬという暗黙の了解がある山に踏み込んだのかもしれなかった。あるいは飢餓のため、秋の実りを求めたか。
肉体を万全に伴わずとも、歯の根を取り払ってきちんと土に還すことができれば、この女の死も報われよう。そう考え、日照雨は更に雑布で女の頭部を包んでやった。死した後とはいえ、無惨な姿を見られたいものではないだろう。
がざっ、と音がした。瞬間身構え、まだ血に濡れたままの鉈を掴む日照雨の前に、ごろごろと何かがまろび出てきて地面にへちゃげた。それは幼い子どもだった。ようやく己の足で立てるようになった、そのくらいの年齢の。
目の見える範囲で起こった惨劇を、あまり理解していない透明な眸(ひとみ)で、赤く染まりつつある雑布に包まれた女の頭部に縋りつく。
その姿を見た日照雨は、夜と早朝のあわいを切り裂くように通り過ぎていった女の絶叫に、意味を持つ言葉が混ざっていたことを思い出す。咄嗟に走り出した遠々煕に刹那も遅れず着いていくうちにすっかり思考の外に放り投げていたそれ。
逃げて、と。そう聞こえたはず──もしかするとあの過去の日にも、日照雨の耳には同じ言葉が聞こえていたかもしれない。
幼児一人をこのような山中に放り出せば、そのうちに餓えて死ぬか怪我をして死ぬか獣に狩られて死ぬかだろうに、女は自身の最期にも我が子を危難から逃がそうとしたのだ。そんな思いがあの絶叫の瞬間にあったということに気付き、日照雨は口の中がひどく苦くなったような気がした。
「生き残って、出逢ったか……この私に」
「あ、う……あ、んまあ」
随分と小さくなった母に縋る子どもを眺め、日照雨は深く息を吐いた。遠々煕が戻ったら煩いだろう、と。
しかし彼はあれで面倒見のよい男だ。なんだかんだと御託を並べながらも、こんな小さな子どもにまで自業自得だと言って山中に置き去るようなことはすまい。
「おまえ、名はあるのかい。かあさまは死んでしまった、もういない」
「なぁ……な?」
「言葉はまだわからないか」
「はえ、きた」
子どもは突然、それだけをどこか超然と口にし、南を指した。
南風(はえ)、南の方から来たと。
「そう、南から。ならばおまえの名は今日に因み熊襲(くまそ)としよう」
「う、ま……お」
「く」
「うまお」
「くまそだよ」
じわじわと明るさが増してゆく。清涼な朝の光が、やがて山の頂を越えて射すだろう。濃い朝靄に溶けた血臭が、かすかに吹き始めた風に流されていく。血みどろの惨状もじきに落ち葉が覆い隠し、冬には雪に閉ざされ、芽吹きのころには山が飲み込んで消してしまう。
そんな風に穏やかに、ただありのまま、流れ過ぎ去るままに、この子どもの記憶からも今日の日のむごい光景はさっぱり消えてしまうといい。その方が、きっといい。
日照雨は己に向けていっぱいに伸ばされた、やわらかく、壊れそうに小さな手をそっと握った。
∴ ∴ ∴
季節は夏に近いころだというのに、熊襲は自分の手がひどく冷たいのを不思議に感じていた。緊張に手が震えている。
歯抜師見習いが着用する半幎帽――目から下、顔の下半分を覆い隠す面布の下で、そうとは悟られないよう注意深く長い息を吐く。ばくばくと跳ねる心臓の音が首の付け根のあたりでいやに響き、痛むような気がした。口も喉もからからに渇いている。
歯抜師の郷にて習い教わった通り、死人の口角から顎骨の関節までをきれいな一直線に裂くことはできた。死後数日が経つ死人の頬に鋏を入れる感触は、固く締まった土塊のように感じられた。獣の肉とはどこか異なる。
顎骨に根付いた歯を、その根ごとうまく引き抜くことができるだろうか。いや、しなければならない。失敗すれば根を取り出すために骨を砕くことになってしまう――そう考えるほどに緊張が高まり、指先の震えは激しくなった。
せっかくこんな風に、眠ってでもいるようなきれいな顔で死することができたというのに、殯(もがり)の前に必要以上に顔を壊すわけにはいかないと、熊襲は唾を飲んだ。たとえこの儀の後、誰も幎帽の下を見ることがなくてもだ。
歯は、人間が生まれ持つ肉体の中で唯一、根を持つ部位である。このことから、歯の根が死人の霊魂を此岸(しがん)にある肉体に根付かせ、離れられなくなってしまわぬようにと願い、考えるがゆえ、殯の前にすべてを抜き去る。遺族や縁者が殯屋を用意する間に、歯抜師は死人を結界内に預かり、歯抜儀を執り行う。
誰でも最初は失敗するものだからと、そばに控える師の言葉は優しい。冷たくなって震える手に、鋳鉄の歯抜具がかちりと歯に触れた感覚が伝わる。握り込み過ぎず、かといって力が入ってないのはいけない。歯が砕けぬよう、しかし確実に根の先まで抜き取れる力加減、そして角度で――。
これが熊襲の初めての実技であった。鼓動が絶え、血の通わなくなった死人の歯は、枯れ葉が自然と枝を離れる様に似て、大きな反発もなく抜けてくれた。
抜いた歯はきれいな水で磨き上げ、遺族に本数が揃っていることを確認させてから抜歯壺にしまい込む。壺は粘土を手びねりで成型し、早春の野火(のび)で焼き締めたものだ。
絹糸で頬を縫い閉じた後、紅粉をはたいて幎帽を被せ、死人の顔に触れる儀式は終わる。
死に纏わりつく負の気に極力触れぬよう、遺族や縁者は歯抜師の敷いた結界の中には入ってこない。植物を編んだ紐で隔てられたあちら側は生者の領域、歯抜師が立つこちら側は死人の領域と考えられ、地続きに、だが明確に区切られていた。
最後に顔を見せてほしいと願う女に、熊襲は幎帽を外して顔を見せてやった。土気色に沈んでいた顔は、はたいた粉の効果でほんのりと朱が差し、女がこの数日に見つめ続けた死に顔よりは幾分か生前の表情に近かろう。頬に縫い閉じた痕があったとしても。
泣き崩れ、嗚咽を漏らし始めた女に手を伸べたり声を掛けたりすることはしない。してはいけないと教わった。熊襲は半幎帽の下でぎゅっと唇を噛む。
歯抜師は、生きながら此岸を辞した者として存在する。
生者でありながら死人に寄り添うことを生業とするがゆえ、己の立つ場所をこそ彼岸(ひがん)と認識する。目の前で誰がどのように慟哭(どうこく)に臥し、死を嘆いても慰めてやることはない。それは歯抜師の仕事ではないからだ。とはいえ目の前で涙を流し悲嘆に暮れる人を見て、何とも思わないでいられるわけもない。
日照雨は初めて死人に触れた弟子の、そんな複雑な心持ちを思いつつ、静かに見守ることに徹する。半幎帽を着けてなお、顔を歪め表情を曇らせているのがわかる弟子に、まだ暫く一人前と認めてはやれないな、と小さく息を吐いた。
熊襲が初めて歯抜儀を成した死人は、出来上がった簡素な殯屋に運び込んだ。これで役目は終わりだ。抜いた歯を納めた小さな抜歯壺に布を掛け、麻紐でしっかりと封をして笈(おい)に納める。
村の長から謝礼として少しの食糧を頂戴した熊襲は、日照雨と、歯抜師の荷を運び、儀式に適切な場を定め様々な物品を手配し、寝食の準備を調えるなどといった、身の回りのあらゆる世話を専門的に行うために着いてくる灰衣衆(かいえしゅう)の二人と共に村を出た。
「熊襲、上手にできていたね。今日の手の感覚を忘れぬように。郷へ戻るまでにもう数人、行き合うことができたらいいが」
「日照雨様。先行きの灰衣衆から、この村より北へ五里ほど行ったところに死人ありと報せが」
「そう、ありがとう。ではそちらへ向かうとしよう」
死番山脈に隠れるようにある歯抜師の郷は、外の人々が思うよりずっと大きい。厳しい環境にはあるが山河の恵みが豊富に得られ、冬に餓えることも、凍えることも殆どないからだ。そのお陰だろう、他の土地に比べれば子どもの死亡率もそう高くはない。
歯抜師や灰衣衆になりたがる者は多いが、この二つの職に就くためには、広く深い知識と強靭な肉体、何事を目にしても平静を保つ精神力など、必要とされるものが多岐に亘るため、希望しても殆どの者が見習いにすらなれずに終わる難関である。
歯抜師は決まった二人一組で行動し、四人一組の灰衣衆が付き従う仕組みをとっている。灰衣衆のうち二人が歯抜師のそばにあって身辺の雑事をこなし、儀式に必要な準備などを行い、残る二人が周辺地域に人死にがないか調査に回る。
一行の行脚は、有り体にいえば死人探しの旅である。
歯抜師あるところに死があり、そして死のあるところに歯抜師がある。一年のうち最も長い夜の、濃密な夜陰(やいん)を紡いだような黒衣(こくえ)を纏う歯抜師の姿を見た者は、手で口を覆って彼らが行き過ぎるのを待つという。
死が先か歯抜師が先かという話であれば当然死が先であることは誰しもがわかっている。いつか自身も彼らの世話を受けるのだということも、人々は理解(わか)っている。とはいえ、生者でありながら彼岸に立ち、死後の人々を輪廻円環(りんねえんかん)へ導き送り出す彼らへの畏怖は、その仕事の必要性を理解していても、止められるものではなかった。
此度の外巡りが始まって三週間ほどが経っていた。
これまでは師のやり方を一番近くで見るだけだった熊襲だが、今日、初めての実技を師の前でやり遂げたという実感から、郷を出てからずっとどこかで張り詰めていた緊張の糸が、ぷつりと途切れてしまったようだった。
儀が終われば長居は無用。さっと撤収し、次の村落へ向かう道すがら、日没となる前に手頃な林の中に今夜の寝所を定めた。
一行は焚き火を囲んで寛いでいる。灰衣衆の男たちとは何度か話したことがあったが、同行するのは初めてだ。豪放な遠々煕と大らかな日照雨に専属的について歩くためだろう、さほどの時を要さずに器の大きさを感じさせる。
だが、と干し肉を齧(かじ)りながら熊襲はそっと二人を窺う。日照雨の弟子だからとて、気を許してくれているわけではないようだった。
彼らは、熊襲などにはわからない高い水準で警戒を怠らない。このあたりは夜中になるとまれに狼が出る地域だからだ。
日の出ているうちにどこかの村落に到着し、屋根など無くともいいから、獣が近付かない、普段から人の気配の強い場所で休めれば重畳(ちょうじょう)、と日照雨や灰衣衆は考えていた。
しかし今回の旅は、郷を囲む死番山脈から一度も外に出たことがない熊襲を連れている。多数の人の往来に踏み固められ、自然と草の生えなくなった道を見て「このような道は誰が手入れしているのか」と問いかけたほどだ。熊襲には見るものすべてが目新しい、何もかもが初めての旅である。
行程が遅れるのは当然であり、初めて長距離を徒歩移動する熊襲の足の遅さに合わせていては日沈前に次の村落に辿り着くことは難しいと、昼下がりにはわかっていたため一行の野営の準備は滞りなく済まされた。
歯抜師見習いは、師について実地演習を行う前にあらゆる知識を身に着け、様々な状況に対処する修練を積んでいる。郷の敷地の外山で野営のやり方も何十と繰り返してきた。すっかり緊張が解けた様子の熊襲とは相反して、灰衣衆の二人は慎重にあたりの気配に注意を払う。それもこれも、安全無事に外巡りを終えて熊襲を郷へ帰すためだ。
管理されている郷の外山で行う野営と異なり、ここには常に、牙を持つ獣が出る可能性がある。
「熊襲。どうだった、今日は」
梢が風に揺れ、どこか不穏なざわめきに満ちる林の中、のんびりとした穏やかな声が通る。日照雨のものだ。
「えっと……はい、緊張しましたけど、何とかやれました」
「祈ってやれたかな?」
「祈って……」
はっ、と熊襲は思わずといった風に口元を押さえた。
歯抜儀は、死人のこれからに備える身仕度のひとつである。
生きるうちに蓄積するとされる負の気が、歯の根を介して肉体や精神、その人であったものすべてを、此岸に根付かせてしまわないように願って行われる。
逆説的に、歯の根を抜き去るという特異な儀式には、死人の此岸への執着を、根刮(ねこそ)ぎ薙ぎ払っておくという意味も含まれていた。
此岸への未練を残さず、輪廻円環の道へ正しく旅立ってゆけるように。歯抜儀はただ歯を抜くだけではなく、死人に直接手を触れる最後の生者として、その身の奥深く、叶うなら芯や核の部分にまで届くよう、安寧なる眠りを願い、祈りを捧げるものと歯抜師は自らに定めているのだ。
だが、祈りに力はない。どれほど深く祈り、強く願い、望んだとて、死人が蘇ることは絶対にない。
無力と知るからこそ彼らは祈る。輪廻円環のその先へ、この指先の体温をわずかでも持っていけますようにと。誰の悲しみにも寄り添うことのできない自分たちの、唯一の贖罪に。
「あ、あ……おれ、歯を抜くのに必死で、すみま、せ」
「では、次はやれるね」
責める言葉はない。厳しい声色でもない。謝罪に続く言葉を切った日照雨のそれは、有無を言わさぬ強い言葉だ。できないことを許さない。熊襲はごくりとひとつ息を飲んで、はい、と答えた。謝っても、過ぎたことを改めることはできない。日照雨に謝ったところで意味もない。
「謝罪の言葉は適切に使いなさい。おまえの心を救うためにではなく。技術の方はよくできていたよ」
「はい」
深更、焚き火を背にして横になった熊襲は、日中初めて触れた死人の皮膚の固さと冷たさを思い出していた。すっかりと生命の温度を無くした顔は青く──けれど、美しいと感じた。
郷内に死人が出たときには、見習いたちを統率する、現役を退いた先達が歯抜儀を行う。見習いは見るだけだ。見ながら、熊襲は、やり方は既に習得している、外に出て行く前にやらせてくれればと何度ももどかしく思ったものだ。
しかし、今だからわかる。親類縁者である郷の仲間の最期を練習に使うわけにはいかないから、見習いは見るだけに留め置かれていたのだということを。
まだまだ子どもだ、自分は、と熊襲は自戒する。悔しい気持ちと無知への羞恥がない交ぜになって、油断するとのた打ち回ってしまいそうだった。そんな当たり前のことを理解できていなかったと、突きつけられた。
「慎重におなり。考え、慮ることが肝要だからね」
師である日照雨に口酸っぱく言われたことといえば、それだけだ。その意味に、その言葉に詰め込まれた郷一番の歯抜師の真髄に、少しだけ触れられた気がした。
山の端に金色(こんじき)の光条がしらしらと伸びている。
一夜明け、ぐっすりと眠り込んでしまっていたことを自覚し、熊襲はがばっと身を起こした。
くく、と喉を揺らす灰衣衆の男の笑い声に、頬が熱くなる。
「寝過ごしました。すみません……」
「いや、まだそう遅い時間じゃない」
だが、焚き火には新しい枯れ枝が充分に足され、なみなみと湯が沸き立っている。それだけで朝の分の薪拾いをし、水を汲んできた者がいることがわかる。目の前の男がやったことだということも。
「慣れないとな、熊襲。薪拾いも水汲みも、歯抜師の身の周りのことはすべて灰衣衆の仕事だ」
遠々煕や日照雨は、実際、多くのことを自ら行う。この二人組とここに従属する灰衣衆の間柄に垣根はなく、全員が平等でそれぞれに働き、仕事を成す。遠々煕などは山歩きのついでに食糧とするため兎や鹿を狩ってくるし、日照雨も歩きながら薬草を摘み、薪を拾うことなど茶飯事である。
その方が効率がよい、理由はそれだけだ。だが、熊襲がそうすることを良しとはしていない。
長く付き合ううちに互いのためにそうなったのと、これから歯抜師となる熊襲が最初からそうするのでは意味が異なる。灰衣衆の中には歯抜師になれなかった者もおり、心境が複雑な者がいる。そういった相手と組まなければならなくなったときに、最初から歯抜師である熊襲が下手に出てしまうのは、互いにとっていいことではない。それを皆が承知しており、日照雨は郷を出てからずっと、路傍にしゃがみ込むようなことはしていないし、本来灰衣衆の仕事とされている部分にも一切の手出しをしていない。
死人の最後に直接触れる歯抜師の手を、此岸の雑事で汚させないために灰衣衆はいるのだ。
「歯抜師の手は、彼岸に発っちまった死人のためにあるもんだ。郷で重々言われているだろうが、歯抜師は、生者でありながら彼岸に立つ者。生きるための雑事に手を出しちゃいけねえ」
「はい。ありがとうございます」
「礼も無しだ。歯抜師は歯抜儀を行う、俺たち灰衣衆はその支援を行う。それだけだ」
ただそれぞれの仕事を粛々と行うだけ。それでも関係がうまくいかず、組を改める歯抜師や灰衣衆は多い。どれほど優れようと聖人にはなれず、合う合わないがある。
だからこそ、遠々煕と日照雨の二人は特別だった。
歯抜師は二人一組。現役を退き、見習いを統率してきた先達が話し合いの末に誰と誰を組にするかを決めるが、最初からうまくいくものでないことは多い。見習いとして過ごすうちに仲がよくなっても、実際に郷を出て様々な世界に触れ、見聞きするうちに互いの粗が見えてくるものだ。野営の訓練を郷の外山で繰り返すとはいえ、それでもこれまでは郷内の別所、めいめい帰る家があるという生活基盤があった。訓練は仲間同士で見慣れぬ土地に泊まりに行くようなもので、野営そのものが生活の一部に馴染んでいたわけではない。
そんな中、見習い期間でも特に関係のなかった遠々煕と日照雨が組になった。先達らの意図を端的に表せば、余り者同士を組ませたということであったが、それがゆえなのか、思いのほかうまく噛み合ってしまったのだった。
幼児の折から豪放磊落で様々なことに突出して秀で、友だちも多く大人たちからの覚えも目出度い遠々煕と組みたがる同期は多くいたが、何がしかの下心ある者と組んでしまっては均衡が取れず、すぐに破綻してしまうだろうと踏んだのだ。
一方、日照雨の見習い期間の記録はわかりやすく良くはない。だが丁寧だった。ひとつひとつの課題をこともなげに成してしまう力においては誰よりも突出していた。彼の師となった歯抜師は特に山狩りに秀でた男で、歯抜師の外巡りから戻ってくると、日照雨を連れて山に入る。山の中で生きていく術(すべ)を文字通り叩き込んだ。それは、彼が家族を早々に亡くし、伴侶も持たなかったからこそできたことだ。
そして日照雨の方も、父は幼少期に山の事故で亡くし、母も見習いとなったころに病で亡くしていた。日照雨自身も、そう長くは生きられぬだろうと言われるほど、代々薄命が目立つ家系にあった。
そんな背景で、師と日照雨は二人で家族のようなものだった。日照雨が郷人らの無用な憐れみにさらされるのを、師がよく思っていなかったということも理由のひとつだろう。
不意に熊や狼に遭ったときにも日照雨は終始落ち着き払っていたし、そのうえ立派に獣を狩る師の援護をつとめた。日照雨の落ち着きは特異に目を瞠(みは)るべきものだった。
そして師は、日照雨が父を亡くしたときの話を郷長(さとおさ)に聞いて納得した。
秋、森できのこを採る最中、日照雨の父は彼の目の前で崖下に滑落し、そして不運なことにそこは狼の縄張りだった。日照雨は何もできずに頽(くずお)れ、ただ父が狼に喰い殺されるところを見たという。父の絶叫を聞きつけた郷の男衆に日照雨は間一髪で助け出され、涙ながら自身の目で見たものを詳細に語った。一瞬たりと忘れてなるものか、そういった気迫があった、と。
崖下から自身を見上げる父の、不運な最期をただ見ていることしかできなかった無力感と、山に潜むあらゆる危険、獣の怖さ、そういったものが文字通り心身に刻み込まれているからこその落ち着きであった。
あらゆる危険にそっと気を配る日照雨の慎重さは、ときに暴走しがちな遠々煕にある程度の落ち着きをもたらし、かといって本来の自由奔放さの邪魔もしない。
二人は実にうまく噛み合い、仲違いしているといったことがない。灰衣衆にもきちんと気を配る日照雨の人柄から、次第に複雑なものを抱えていた灰衣衆も心を許し、信頼し、惚れ込むがゆえ、彼ら二人に仕える灰衣衆でいられる自分自身に誇りを持つに到る。
この一行は、歯抜師の郷に様々な記録が残されるようになってから現在まで、灰衣衆まで含め、結成当初から一人も面子を変えていない唯一の組であると記される。
「日照雨様は?」
沸いた湯を貰い、湯(ゆ)灌(かん)をしながら、熊襲は問うた。
起きたときから焚き火の周りには灰衣衆の二人がいるだけで、師の姿はなかった。
「散歩に出ておられるよ」
「日照雨様の朝はいつもそうだ。誰より早く起きていなくなってる」
「でも、危なくないですか?」
熊などに代表される薄明薄暮性の動物だって棲む山中だ。通りに近い林の中で、絶やさず火を焚いているとはいえ、そういう生き物に行き遭うこともあるだろう。何のために歯抜師は二人一組で、四人もの灰衣衆を付き従えているのか、その根本を覆す行為のように熊襲には思えた。
一人では危ないと、そんな心配を杞憂にするかのごとく、男は声を上げて笑った。
「一人では危ないってか!」
ひとしきり笑った後、まあ確かにそうかもな、とひとりごちて頷き、男は朝餉の鍋をかき混ぜる。
「はあ~、笑って悪かったな。熊襲は……そうだよな、外巡りのときの日照雨様のことは知らないんだよな」
穏やかな気性に、落ち着き払った優しい声色で話す様。線が細く、どこか儚げにすら感じられる日照雨ではあるが、それは豪放磊落を絵に描いたような遠々煕がそばにいるから対比的にそう見えがちなだけだ。実際の日照雨は殆どのことを、大抵の場合誰より器用に何でもこなし、何なら遠々煕よりしぶといかもしれないとすら、灰衣衆は考える。
遠々煕のように弓の名手として兎や鹿を狩らずとも、きのこや山菜(やまな)、木の実果物の類を集める術に長けている。その間に狼や熊に行き遭ったとしても、うまく撒いて完璧に逃げてくる。日照雨は山と、そこに生きるものを知り尽くしているのだ。それに、狼の一頭二頭くらいなら、単身で狩ってきたこともある。何も備えず暢気に歩いているわけではない。
早朝から返り血で血塗れになって戻ってきたあの穏やかな人を見たときには、さすがに皆が仰天したものだ。遠々煕だけは「さすが!」と手を叩いて爆笑していたが。
そういった、見た目や雰囲気に反した日照雨の姿を、熊襲は知らない。当然だ、一行が郷に戻ったときにその話をしても、穏やかで優しい日照雨様がそんなわけ、と誰も信じやしないのだから。でたらめな話だ、と相手にもされない。信じられない気持ちはわかる。こればかりは現場を見ないと信じられないことだろう。見ても信じられないかもしれない。
「戻ったよ。お腹空いちゃった、ご飯できてる?」
やわらかい腐葉土が積もる林をするりと抜けてきた日照雨は、いつもの調子──熊襲にとっては見慣れない、幾分か砕けた雰囲気──で戻ってきた。散歩の収穫物は熊襲に見えぬよう巧妙に灰衣衆の男に手渡される。
「今朝採った山菜を入れりゃあすぐできますよ。もうちっと待っててつかあさいや」
「きのこある? あるなら焼いちゃおう」
さも灰衣衆の早朝仕事で収穫してきたもののように、男は受け取った袋から中身を取り出し、手早く処理をする。山菜はふつふつと煮立つ粥の鍋に放り入れられ、きのこは塩をまぶして串を打ち、火のそばに。他村から謝礼で得た砕いた米と小麦を、とろみが出るまで煮てかき回し、塩で味を調えた粥は木の椀で配られた。
「熊襲、よく眠れたかい」
「はい。寝過ぎたほどに……」
「私たちの組は、もともと朝はこれより遅いからねえ。遠々煕がひどく寝汚(いぎたな)いから……」
「そんなのでいいんですか?」
「もちろん。各組に適した動き方というものがあるだろう。厳格に朝は早く起きて動き出さなきゃいけない、なんて決めてしまったら、皆辛いでしょう」
どんなにか厳しい旅程が待っているかと身構えていただけに、熊襲は肩の力が抜けてしまった。この三週間、暗いうちに起き出しても熊襲が最後だったので、のんびり寝ても問題ないとは思ってもみなかった。
そういえば、早く起きろなどとは一言も言われていない。
「それに、死んだ人は待っていてくれるからね」
歯抜師が儀を済まさなければ、死人を殯屋に入れられない。大きな集落ならば正式な儀の手解きを受けた者がいることもあるが、まれなことだ。死人に直接触れることは負の気に触れることであり、それは、己の死を早めることと同じと認識され、皆嫌がる。
多くの村落はそれがゆえ、死人が出たときには速やかに村の敷地や山道、地道、あちこちに歯抜師を呼び寄せるため、死人有りのしるしを掲げる。
ひとところに留まらない歯抜師は、遠々煕や日照雨の一行のように手練れるほど一日の移動距離も長く、執り行う歯抜儀の数も多くなるものだ。
一行がいつも通りの面子であれば昨日のうちに、連絡のあった北へ五里進んだ先の死人のもとへと駆け付け、夜のうちに歯抜儀を執り行い、今頃はその村落の敷地のどこかで不寝番も立てずに全員がぐっすりと寝転げていたはずだ。それくらい、手練れの一行と、見習いを含めた一行の行程には差が出てしまう。
朝餉を終えた一行は野営を撤収し、次の村へ向かった。
向かったが、行き先は途中で変更することになった。目的地には昨晩のうちに別の歯抜師が到着したのだ。その報告を携えて先行きから戻った男を一行に加えると、次は今朝まで一緒にいた男が発っていった。歯抜師の一行はこうして、灰衣衆が代わる代わる先行きに発ち、あちこちの情報を集めながら移動を繰り返す。
外巡りに慣れていない若い歯抜師の一行や、組んだばかりの一行には、こういった仕組みからすれ違いが多く発生するが、長い付き合いになる日照雨の一行には関係のないことだ。
道中、日照雨はすれ違わないための指示の出し方などを熊襲に教え聞かせた。
「あれ、まだ梅が咲いてるんですね」
地道を歩く道すがら、目に付いた花に熊襲は目を丸くした。
冬の終わりの寒い時期の花だ。郷の周りに植えられた梅の花は早々に散り、今頃は青くて固い小さな若実をつけている。
「あれは李花(りか)だよ。すももの花」
「すもも……って、何ですか?」
「梅の親戚みたいな実が生る果樹のことだよ」
午前中の清涼な空気に混ざって漂う、ほんのりと甘い花の香りは、来たる夏の気配の中にも充分な春を感じさせた。
「日照雨様はあれがお好きですよね。花もですが、実の方も」
「そうそう。けど、郷の周りじゃうまく育たない」
「そうだね……ああ、熊襲。おまえがいつか歯抜師としてこのあたりを巡るときがあったなら、私があの花を好きだったと思い出してくれると嬉しい」
多くの村落では歯抜儀に対する謝礼として、土地の恵みを分けて貰える。梅よりもひと回り大きく、熟せば甘みの強いすももだが、実りの季節は短い。そのときに死人があるかもわからない。熊襲が一人前になり、仲間と共にあちこちを巡るとて、旬の短い果実を口にできる可能性はとても低いだろう。
熊襲は花の甘い香りを胸いっぱいに吸い込み、早足に歩いていく師と灰衣衆の後を追った。
いつか食べられるだろうか、と考える。食べられたらいい、という思いはすぐに打ち消した。その実に歯を立てる機会に恵まれるということは、そこに死人があるということに他ならず、願っていいことではなかった。
歯抜師見習いの仕上げとして、師と組んで外巡りができるのはこの一度こっきりだ。時間としては三箇月ほどのものだろう。
先組と後組に分けられたうちの先組、熊襲を含む見習いたちが師との旅を終えると、もう一方の師と後組の見習いたちの旅が始まり、終わり、そして秋冬を郷で越し、来年の春には一人前の歯抜師となって、己の相方となる歯抜師や灰衣衆と共に、郷がある山脈周りの近場から外巡りに慣れてゆくことになる。慣れると共に少しずつ、行ける距離を長くしてゆくのだ。
師がその手で直接行う歯抜儀を見ることは、この期間にしかできない。たった三箇月しかないのだ、と熊襲は改めて気を引き締めた。
∴ ∴ ∴
死番山脈は豊饒(ほうじょう)に満ちた山である。この中に暮らせばまず餓えて死ぬことはない、そういわれている。だがそれは同時に、熊や狼などの肉食をする獣と共生するということでもあった。誰もが一度は望みながら、しかし殆どの場合、獣の数を理由に、適応して棲める場所にはなり得ない。
特にこの死番山脈の界隈は熊や狼の生息に適しているようで、それなりに大きい歯抜師の郷にある人口よりも圧倒的多数の獣が棲む。山に生まれ、山に育ち、山に慣れた郷人でさえ年に数人が喰われて死ぬこともある。
この山の中では、人も獣の一種であると男衆は理解している。喰うか喰われるか、それは、最後は天の采配に任せるもの。こういう世界に間借りして生きているのだ。死ぬこともあれば、生き残ることもある。日常的な生死のやりとりも、生活の一部だった。
そんな環境で、郷人らは争わず、分け合って生きる。
男衆は連れ立って狩りに出掛ける。山の恵み、果実や木の実、きのこを採り、鹿や兎を狩る。ときに熊や狼に対峙する。得られた収穫は郷の皆で分け、木を伐って回る。鋳鉄や鍛冶には専従する者があり、歯抜師の道具を作る役目を担っていた。
女衆は子と畑の世話をする傍ら、紅を作り、花咲く季節には香花を摘んで乾燥させ、歯抜師の使う葬具を調える。良質な獣毛が手に入れば木を削って化粧筆を作り、春には粘土を捏ねて抜歯壺を作る。繕いや厨仕事も女衆の仕事で、女たちはいつも忙しなく働いていた。
しらしらと霞む穏やかな秋晴れに、冬の風が混じっている。越冬に備える薪拾いを終えて外山から戻った熊襲は、世話になっている夫婦に荷を預けると、午後の教えを受けるに備えて水浴びに向かった。
あの日、といわれる日のことを、熊襲は覚えていない。不運で、哀しいことがあったのだという話はぼんやり聞いているが、それだけだ。
産みの母とはそこで死別したと聞くが、詳しくは誰も語らず、熊襲も気にしなかった。今は郷人の皆が家族だった。覚えてもいない母のことを知ったところで、とうの昔に過ぎ去ったものはどうしようもない。それに、見も知らぬ母を思う暇などない。歯抜師として生きてゆくために覚えなければならないことが、まだまだあるのだ。
郷は、何に置いても歯抜師を中心にして動いている。他の地域の者が死に溜まりと呼んで忌避し、近付くことすら躊躇する死番山脈の隠れ郷にとっては、彼らが絶対的な柱であった。
歯抜師の生業がいつ頃から葬礼として定着し、ここに郷ができたのかはわからない。しかし、この死番山脈を中心に、世の人々の死を導き弔う役目を、古くからこの郷で負うてきたのは確かなことだった。
生と死の境を明確に区切り、死出の旅に送り出す身仕度を調えてやるのが歯抜師の仕事だ。彼らは様々な色を掛け合わせて作る黒か、あるいは特異に脱色された純白を身に纏う。
この二色の衣はこの郷でしか染め出せない特別な色で、ゆえに、厳しい教えを叩き込まれ、認められた者だけが名乗ることを許される歯抜師の衣にのみ使われた。
死の訪れがないかと土地土地を巡りながら、見たもの聞いたもの、口にしたものなどの様々な話を持ち帰る歯抜師は、もとより選出された優秀な者であることもあり、皆の憧れの的である。
歯抜儀と殯を弔いとする地域以外に、積極的に足を延ばす組はあまりないが、遠々熙と日照雨の組はそのひとつで、彼らの帰郷の度に郷人は沸き返り、遠い未知の世界の話を聞きたがった。
殆どはこのあたりと同様の山河の景色であったが、時折混ざる大規模な平地農耕の話や、大陸の文化を取り入れて進化してゆく都の話は人気があった。
都にまで足を伸ばすと、死人は一人分の小さな甕(かめ)や箱に入れ、あるいは身ひとつで土中に埋めるだけで弔う。歯抜儀もなければ、殯期間を終えた後の洗骨儀(せんこつのぎ)もない。
そんな話をしてやると、決まって皆顔を青くした。
死した後、歯を残したまま埋められる。死番山脈周辺一帯の人間にとっては、永遠の牢獄に閉じ込められるのと同じことだ。
土の下、一人分の小さな入れ物の中で、二度と誰の手にも触れない。歯を抜かないということは、霊魂が死した肉体の在るところに縛り付けられ、未来永劫そこから動けなくなるということだ。そんなのは嫌だ、恐ろしい、と誰もが口にする。
歯抜儀を終えた後、死人は遺族や縁者の用意した殯屋で一定期間安置される。期間そのものに決まりはなく、遺された者の悲嘆が癒えたそのころにという地域もあれば、家系や村単位できっちりと定められていることも、春夏秋冬をいくつかと数えることもあり、様々だ。
殯期間を終えると、遺族や縁者は殯屋を解体する。肉が溶け、残った骨をひとつひとつきれいに洗い揃え、骨壺に納める。そうしてやっと、ひとつの死が完全性を得る。
洗骨儀は、死人がきちんと死んだかどうか、収まっていた霊魂が肉体に根付くことなくきちんと死ねたかどうかを確かめるために行うもので、死人と生者の最後の触れ合いでもある。
負の気をため込んだ肉体は溶け消え、その人であったとわかるものは無くなり、皆が同じ容の、ただの骨となる。
それはもう誰でもない。
そして個の消滅が縁者の手で確かめられるころ、死したひとはどこかで誰彼(だれか)となってまた此岸に生まれ出でるものと信じられていた。
骨壺の扱いは、これも地域によって様々だが、決まった場所に安置する場合もあれば、一定期間を遺族や縁者が預かり祭壇に奉った後、砕いて山河に還すこともある。
死後そうして、何度も重ねて誰かの手によって丁重に弔われるからこそ、季節が移ろうように、目に見えない巡りの円環に戻ることができ、新たな肉体を得て、再び生まれくる。そうして何度となく出逢いと別れを繰り返すのだ。
弔われることなく死が完結しなければ、またいつかに出逢うことができなくなる。歯抜儀を行わない遺体は霊魂が負の気に満ちた肉体に根付き、朽ちることもなく、生まれ変わることも、無くなることもできなくなり、永遠の孤独を過ごすことになってしまうというわけだ。郷の人々は、それを怖れている。
またどこかで、今とは違った誰彼になって出逢うことがきっとあると信じるからこそ、悲しくとも、むやみに死を怖れずにいられるのだった。
∴ ∴ ∴
冬、雪入りの寸前。歯抜師たちが次々と、越冬に備え最後の外巡りを終えて郷に戻ってくるころ。
郷が震撼した。
緊急危機を報せる烽火(のろし)が上がり、先触れとして帰郷したばかりの灰衣衆の面子から、それが遠々煕と日照雨からの信号だということはすぐにわかった。
慌ただしく装備を揃えた歯抜師や灰衣衆が一斉に出て行くと、四半刻も経たぬうちに遠々煕の重傷が郷に知れ渡った。
現役歯抜師の中でも屈指に優れた知識を有し、野生動物との直接戦闘も得意とするあの遠々煕の負傷に、郷は動揺を強くした。負傷は命の危険を強く伴うものだという。
何ゆえ、と皆が思った。彼自身が野生動物のごとき鋭さで、しかし言葉を交わせば大らかで雄壮な頼りになる男だ。郷の者は皆彼を慕い、彼を頼り、また彼自身もそれに応えることを苦とせず受け入れてみせる器の大きな男だ。皆の心を掴んでいたがゆえ、衝撃は大きく凄まじいものであった。
男衆が烽火のもとに倒れていた遠々煕を認めたとき、彼の意識は既になく、詳しい状況は聞けていない。懸念されたのは彼と対を成す日照雨の安否であった。
遠々煕にはすぐさま治療が施された。一先ずの処置では手当が不充分だった傷を、既に熱されていた鉈で焼いて止血し、郷へ移送する。同時並行で男衆は歯抜師か灰衣衆を長に立てた山狩り隊を組み、総出で奥深い山中へ入っていった。
遠々煕の怪我を見れば、熊の襲撃に遭ったのだろうということは一目瞭然であった。となると、日照雨は救援のための烽火を上げたあと、その熊を追って行ったのだとわかる。
人の血肉の味を覚えた熊は何度も人を襲うようになる。その執着は実に凄まじく、郷の場所を嗅ぎ付けられては目も当てられない。放置しておけない――山が冬に閉ざされてしまう前に、仕留めておきたかった。
郷きっての歯抜師は、同時に獣狩りの匠である。遠々煕の強さ明るさに隠れ、柔和で穏やかな人柄ゆえ目立つことこそめったにないが、日照雨は、他の誰より遠々煕の隣に立つに相応しい腕を持った狩人であった。
しかしその相手は、遠々熙の片足を奪っていくほどの熊であり、いくら山を知り尽くした日照雨でも圧倒的に分が悪く、一人で狩れる獲物ではなかった。日照雨の安否は、山狩り隊がいかに早く彼に合流できるかに問われた。
熊襲は寝かされた遠々煕のそばについていた。片足を膝の上まで失った遠々煕の顔は土気色で、呼吸も殆どないに等しい。時折よく磨いた小太刀を口元に持っていき、鏡面が曇るかどうかで呼吸の有無を確認する。
郷中が不安にかき乱され、騒がしく落ち着かない。松明の灯りを絶やすことのできない、誰もが眠れない恐ろしい一夜となりそうだった。
郷を囲む高い木塀には尖らせた杭のかえしが設置され、熊の襲来に備えられた。
男衆は老人と若人、見習いたちを残して殆どが山狩りに出払い、それがまた女たちの不安を煽る。男たちのいない間に血肉を求めた熊が襲ってきたら、と不幸な想像をしてしまうのだ。
血を流し過ぎた遠々煕は汗すらかかず、虫の息で辛うじて生きている。誰もが憧れた雄壮な男の影はなくなっていた。
熊襲は膝の上で爪が皮膚を破るほど強く手を握り締めた。
今の熊襲は、力仕事に向いている。外に出ればやれることは沢山あるはずだのに、何故、座っている以外には何もできないこの場にいなければならないのか。突きつけられる無力感は焦燥となり、じりじりと心が焼かれるようだ。
熊襲──この名が、今こそ必要だと望まれたのだった。
熊襲の名は、幼児の時分に熊に襲われながらも生き残ったことに因んでつけられたものだ。言葉に、名に、何かしらの力が宿るのだとすれば、今こそ発揮してほしいと誰もが望んでいた。
遠々煕は郷の者にとってまさに太陽のような存在だ。片足を失い、二度と山を降りて歯抜師としての生業を成せず、狩人としても全く役に立たなくなったとしても、生き延びてほしい、死なないでほしい、と。そう、願われた。今このときにも郷のあちこちで、誰もが祈っていることだろう。
ゆえに熊襲も、焦燥を振り払ってただ祈った。遠々煕の意識が回復すること、日照雨と、彼の援護に出て行った男たちの無事の帰りを。強く祈った。強く。
皆の気持ちが天に届いたなら、遠々煕はきっと死なない。
女たちは朝を願う。薄明薄暮性を持つ熊は、朝方と夕方に最も活動が活発化する。夜が明けて日が昇れば、そのころには、男衆は熊を仕留めて戻ってくるはずだ。早く明けろ、早く――そう願えば願うほど、無情にも時間は長く感じられた。
夜が更けてゆく。
日照雨は身体中に土をつけ、潰した十薬の葉を噛み、人の匂いを消しながら、身を隠していた。最高潮に張り巡らせた神経で、今なら山ひとつ分の中のことなら何でもわかりそうなほど鋭く、注意深く気配を読む。
十数丈(三十~四十メートル)ほど先に、あぎとを血に濡らし、遠々煕の反撃に目を潰され、日照雨の一撃によって片足を引きずる熊がいる。木々の間を抜けていく姿を、一瞬たりと逃さぬよう注視する。
熊の口にはちぎり取られた遠々熙の足がしっかりと咥えられている。ねぐらか、安全な場所に戻ってから食すのだろう。
巨大な熊だ。郷で最も大柄な男を縦に二人並べたような体高で、数人の家族が暮らす家屋に等しいほどの大きさ。
追う立場となってようやく冷静に見つめることができたその熊は、かつてなく巨大だった。あれほどの巨体が、森で互いの姿を認めた瞬間に猛然と襲ってきたのだから、ひとたまりもないのは仕方のないことだったと思った。
腕一本が遠々煕の腹周りの太さをゆうに越え、腕の太さと同じくらいの爪は生木の幹さえ容易く折り倒すことだろう。遠々煕の足を奪ったように、易々と。
熊同士の縄張り争いのすぐ後だったのだろうか。気が立っている状態の熊に狙いを定められては、どちらかが死ぬまでやり合うしかない。
日照雨は同行の灰衣衆の頭数を揃えた六人一組でなかったことについて、幸運だったと考えた。信じられないほど大きい熊の脅威に、本能が死を悟っていたような部分もある。六人でいれば仕留められたかどうか考えたとき、答えは否だった。遠々煕が六人いれば充分に張り合えたかもしれないが、それでも分は悪い。
だが、二人なら──そう、遠々煕と自分だったから、初動が遅れることはなかった。二人ならば人死にも出ない──はずだ。自身が生き残れたらば。
あの刹那、熊の姿を認識した瞬間二人は反対方向に散り、凄まじい速さで迫り来る熊に対抗するため、狭い間隔で生えた木々の間を縫うように駆け抜けた。まず距離をとり、手頃な場所で上に逃げる算段だった。
遠々煕は弓の名手である。高い場所から獲物を狙えば十中八九確実に急所を潰すことができ、幸運に恵まれればそれだけで仕留めることもできる。
日照雨は熊から目を離さない。自分か、遠々煕か、散った二人のどちらを狙ってくるのか見定めてから、対処を考えようとしてのことだ。大抵の場合はこのためにほんの一瞬、遠々煕から動きが遅れる日照雨の方に獣は向かってくる。生存権を賭けた命のやりとり、喰うか喰われるかが決する刹那、野生動物は利がある方を取る。獣は通常、逃げ遅れている方を追うものだ。すなわち、日照雨の方を。
だがあの熊は違った。遠々煕を追っていった。指笛を鳴らし危険を報せ、日照雨は踵を返して熊を追う。日照雨には見向きもせず、熊は遠々煕を追う。縄張り争いの脅威となりそうな方を、本能で嗅ぎ取ったのかもしれなかった。
遠々煕が迎撃体勢を整えるより、熊の方が早かった。熊の身体が特異に大きいということも不利に作用した。いつもなら足りる高さよりもっと上に登らなくてはならないが、日照雨が引きつけるのに失敗し、遠々熙が直接狙われては、そんな時間を作れるわけがなかった。迎撃するには半端な高さから、しかし遠々煕は放った矢で確実に目を射ち抜いた。
だが、目を潰されながらも熊の爪は遠々煕の肉を引っ掛けた。爪は遠々煕の大腿骨を砕き、牙で臑(すね)を捉え、容易く足をちぎり取っていった。血を噴いたのはほぼ同時だったが、山を震わせる絶叫は熊からも遠々煕からも上がらなかった。
熊が咆哮すれば奪い取った足(えもの)を落とすことになり、遠々煕が叫べば正確な場所を潰れた目の熊に悟られる。蹴散らされた落ち葉が耳障りに散る音だけの、異様に静まり返った空気の中、日照雨は熊の足の腱目掛けて鉈を叩き込んだ。
逃げる熊の向かう方向を注視しながら、日照雨は片足を失った遠々煕に失血を遅らせる応急処置を施し、緊急危機を報せる烽火を焚き、遠々熙の鉈をその火に焼(く)べておく。
郷は遠くない。誰かが気付き、倒れた遠々煕の居場所に駆け付けるはずだ。そこに歯抜師がいたなら熱されたこの鉈で、すぐにも遠々熙の傷を焼いてくれるだろう。
手早く今できる処置を済ませた日照雨は熊の背を追う。
激しく荒れる吐息と呻き声に交ざって、「日照雨、」と名を呼ばう声が聞こえたが、返事をしてやれる寸間(じかん)はなかった。
最大級に嫌な気配を、二人同時に予感していた。
気をつけろ、と遠々煕は言おうとしたが、失血によって急激に冷えていく身体にまともな思考は続かず、暗くなってゆく寒々しい空を、真っ赤に染まっていく視界で仰ぎ見ることしかできなかった。
積もった落葉樹の葉ががさがさと乾いた音を大きく立てる。あまり近くまで寄るのは得策ではない、と日照雨は腰を屈めて熊を注視する。
あたりは真っ暗闇に沈み、殆ど何も見えない。数枚の葉が残るだけの寒々しい枝の向こう側に広がる星の海と、糸のように細い繊(せん)月(げつ)の乏しい光だけが頼りだった。
人間の五感の脆弱さを痛感する。今、狼が現れたらば、その鋭い嗅覚に、日照雨が纏う土と十薬のごまかしなどあってないようなものだろう。
冬眠前の厚い脂肪を纏った熊の血で、鉈は脂を吸って鈍っている。足の腱を傷付けることはできたが、歩けなくさせるには力が足りなかった。びっこを引いて逃げる熊を仕留めるだけの力は既に失われ、残る装備はあまりにも心許ない。
雪に山が閉ざされてしまう冬に備える今時期、熊肉は喉から手が出るほどに欲しい食糧ではあったが、まずは確実に仕留めることが肝要だ。どのような結果となっても。
あれほど巨大で攻撃的な熊に、人間の血の味を覚えさせてしまったのは最悪だった。手段を選べる余裕など最初からない。見失うわけにはいかない、と日照雨は遠のきそうになる意識を凄まじい集中と精神力だけでどうにか繋ぎ止めていた。
郷の男衆が装備を揃えて山中に入ってきているはずである。緊急時の山狩りは普段の倍以上の人数で動く決まりで、遠々熙の怪我を鑑みるなら、もっと多くの男手が割かれているかもしれない。
隊で動いているだろう中のひとつでいい、早急に追い付いてくれれば、という思考を、日照雨は振り払った。
助けは来ない。山は宏大で、松明の炎はさほど広くを照らしてはくれない。これほど暗くては、日照雨が辿った道に何らかの方法で目印を示したとしても、そのしるしを見つけることが難しい。奇跡的に彼らが近くまでやってきたなら、松明の灯りが見えるはずだ。そのとき大声で呼べばいい。
ひと冬充分に越せるほど、既に皮下には脂肪を、腹には食べ物を蓄えていた熊が、何故あれほど攻撃的に人の姿を認めた瞬間襲いかかってきたのかはわからないままだ。足早に山の奥へ奥へと向かう熊の足は怪我を負っている割に早く、日照雨の呼吸はひどく乱れていた。
今夜中に狩ることはできなくとも、せめてあの熊のねぐらを特定しておかなければ、来春に危難が待つことになる。
雪に閉ざされ、郷の敷地から誰も出られなくなる厳しい冬に、余計な不安を残したくなかった。
しかしそれさえ、間に合うだろうか、というのが、今の日照雨の唯一の不安要素だった。それすらも思考から振り払って、夜闇に溶ける熊の背を追う。やるべきことを今完璧に成すことが自分の役目だ、と日照雨は手持ちにある最後の十薬を噛んだ。
不快なほどつんと香る独特なえぐみと苦さをはっきりと舌で感じ取れるうちは、まだ時間は残っているはずだと信じられた。
深更、吐く息がけむるのを布で隠す日照雨は、視力が利かなくなっているのを強く自覚していた。救援はまだ遠い。当然だ、単身で、松明も持たず熊を追う日照雨を、宏大な山中に見つけられる可能性はとてつもなく低い。
濃密な闇を抱えた山森の中は危険に満ち、夜行性の獣などが動き出す時間帯となっていた。移動には更なる慎重さを求められる。そんな状況にあって、男衆が日照雨に合流できる可能性など、もはや無いといえた。
日照雨は驚異的な胆力で長時間の追跡を続けて来たが、暗闇とは関係なく、狭まった視界に限界が近いことを悟っていた。
血が、足りなかった。
熊の足を叩き切ろうと鉈を振り下ろしたあの瞬間、熊の反撃は日照雨の脇腹を抉っていた。爪は幸い内臓には達しなかったようだが、縫う必要のある大きな傷に、ろくな手当てもできないままここまできた。強く巻いた布も、下帯も下衣もすべてがじっとりと足先まで濡れ、冷え切っていた。
もう駄目か、と熊を見失うこともやむなしと追跡を中断し、烽火を上げる準備を始める。落ち葉を払い、石を集めて風避けを作り、火を点ける場所を念入りに手早く用意する。既に冬山と化しているここで、火の扱いは殊更神経を使う作業だった。失敗すれば山ごと燃してしまうかもしれないからだ。間借りして棲まわせて貰っている山々に、恩を仇で返すような真似は絶対にできない。
がちっ、がちん、と瑪瑙(めのう)に燧刃(ひうちば)を叩き付けるが、火花が出てくれない。血が足りず、凍り付いてしまったかのように固くかじかみ、力の入らない手は、この火付け道具を二つ握るだけのことに苦労していた。もう少し早く判断を下すべきだったかと焦りそうになる心情を冷徹に押さえつけ、がちんっと再度瑪瑙を叩いた。
ぞぞ、ざあっ、と落ち葉がかき回される音がする。近い。
日照雨は燧刃を落として懐に手を入れた。
狭まった視界で音のした方を見上げると、繊月を背に、立ち上がった大きな黒い影が落ち葉を蹴散らし、既にそばまで迫っていた。成年男子の腹の太さをゆうに越えた強靱な腕、腹を抉った固く鋭い爪が、圧倒的な強さで、日照雨に振りかざされた。
「……っ!」
がくん、と何もない場所に落下するような感覚で唐突に目を覚ました熊襲は、うたた寝してしまっていた、と焦って油皿を手に取り、火灯りに照らして遠々煕の様子を見た。
口元に逆刃で寄せた鋭い小太刀の刀身は、まだちゃんと曇る。息がある。ほっと落ち着いたとき、出入り口に掛けた菰の幕をばさりと払って誰か入ってきた。
「遠々煕は」
「まだ、意識は……」
「そうか」
「あ、の……日照雨様は」
灯りは弱く、男の顔が見えるほどではないが、郷長だということはいがらっぽい独特な声と衣の裾にある繍(ぬいとり)の文様でわかった。
「まだ捜索中だ。高見櫓に上れば山狩りの松明があちこちに、それは見事に眺められるぞ。あのような灯り――見たくはなかったが」
郷長の声色は苦虫を噛み潰したようだった。成果が上がれば、すなわち、どれかの隊が日照雨に合流できたのならば、その情報はすぐにも松明を使った信号で高見櫓の見張りに伝わり、ほぼ同時に郷長にも伝わるはずであった。
朝の気配が近付いてくる。濃い闇の世界が、少しずつ青い明るみに満ちてゆく早朝、誰もが胸をなで下ろす。
遠々煕は辛うじてだが生きているし、山狩りに出て行った男衆のうち誰も、怪我をして戻ってきたという報告はない。じりじりと緩慢に昇ってゆく太陽の光に感謝しながら、女衆は腹を空かせて戻ってくるだろう男衆の帰りに備え、様々な準備を始めていた。
郷に影を作る山の頂に煌々と照る太陽が達するころになり、この上なく静かに、閉ざされていた門が開いた。沈み込むような重い足取りは葬列のように、次々と山狩り隊が戻ってくる。
女衆は男らの顔色を窺っては口を閉ざし、郷は人の数に反比例して静謐に包まれていった。
腰の悪い嫗(おうな)が入ってきて、遠々煕のことは代わりに見ているからと熊襲の背を押した。
熊襲が一夜ぶりに外に出たのは、郷の中央広場に集まった灰衣衆が、四つの細い柱を打ち立てたころだった。
山狩りから戻った男衆は、女衆の作った飯にも手を着けず、その周りで粛々と働いている。
「日照雨様……! 日照雨様は?」
たかたかと駆け、灰色と野良着ばかりの男衆の中に歯抜師の中で最も濃く深い色の黒を探す。黒衣を纏う歯抜師の顔を確認しては違う、違うと間をすり抜けていく。口を閉ざし沈黙を守る人々の視線が己を見ていることに気がつくと、熊襲が胸に抱えた嫌な予感は加速度的に増していった。
「熊襲、ここだ」
地鳴りのような低い声がどすりと刺さるように届いた。
男衆の間を抜けると、広場の中央に立てられた四つの柱の外側に、小さな山のごとき熊の死骸がどっかと横たえられ、大人数での解体が始まったところだった。声の主、見知った男に近付いてゆく。遠々熙と日照雨に付き従う、灰衣衆の男。
膝が、がくがくと自分のものではないような弱さで震えていたが、熊襲は確実に、それに辿り着いた。
黒い、包みだった。
歯抜師だけが身に纏うことの許された衣の色だ。ただ黒いといっても様々な黒に染め分けられ、決められた地位によって、身に纏うことが許される黒の色合いには濃淡がある。
男が抱えたその黒は、遠々煕と同じ黒だった。
赤も青も緑も黄も全部全部深く濃く内包した、月の出ない朔の夜の闇よりも深い色。濃密な夜の森を更に凝縮したような、郷内で最も暗く美しい、真黒(しんこく)──熊襲が探し求めた黒。
郷で唯一、遠々熙と日照雨の一組だけに許されるその色を、他と見間違えるはずがない。その中には、まだらな濃淡が見受けられた。
結び目にある布端に、同色の糸でちんまりと縫い取られた雨露の文様が、日照雨その人の衣に間違いないことを示している。
熊襲の顔色がさっと蒼褪めてゆくのを、男は気の毒そうに見つめた。
「……誰も、間に合わなかった。見つけたときにには既にばらばらで……これは頭だ。持っていろ」
男は黒い包みを預けると、熊の解体に合流する。重たい包みはじっとり濡れていて、熊襲の手を赤く染めた。
日照雨は己の身に毒を帯び、喰われることで熊を死にせしめたようである、というのは後から聞いた話だ。
援護を待ってはいたようだが、合流を待ちきれず、そうせざるを得ない事由があったに違いない。それが何だったのかは不明なままだ。
何もなかったのだとすれば、あの日照雨が、施毒した熊が死ぬまでの時間を逃げ切れなかったとは考え難いのだ。
事情を知る唯一の男、遠々熙の意識はまだ戻らない。
遅い朝を待ち、ようやく松明を焚かずとも目視であたりを見回せるようになったころから、山狩り隊はひときわ活発化した。そのうちのひとつが漂う血臭に気付き、追って現場に辿り着いたとき、皆息を飲んだ。そこにあったのは、現実を疑いたくなるような、凄惨な光景だった。
ばらばらに散った血肉の池に、熊は、人だとわかる腕を齧(かじ)って咥えたまま俯せに倒れ、沈むように死んでいた。
葉をすっかり落とした枯れ木様の物淋しい木立には、人の肉体が玩具のように弄ばれたのだろうとわかる血痕もあり、ただただむごたらしい光景が広がっていた。
これがたった一人から溢れた血なのかと疑いたくなるほど、あたりの木々も地面も、一面が赤黒く染まっていた。
歯抜師と灰衣衆は濃い血臭や散った肉片を見て表情を歪めはしたが、顔色ひとつ変えず、動揺もさほど見せず帰郷のための用意をまとめ出したが、歯抜師にも灰衣衆にもなれなかった男衆には、直視できない凄惨な光景と臭気に嘔吐する者もあった。
平静を装い、血溜まりの中から肉片や骨片を集める歯抜師たちではあったが、その胸のうちには耐え難いものがあった。
肉片を拾う指先を濡らす血は、すっかり冬の気温に同化して体温を奪っていった。夜の山にひとりきりで、松明すら持たずに熊に対峙する恐怖は察するに余りある。
それなりに様々な人死には見慣れているはずだのに、こみ上げるものを堪えるのに苦労していた。これほどむごい死に様で死ぬべき男ではなかったと、全員の心は一致していた。
だが、起きるのだ。こういうことが。
深い山の中に棲むのだから当たり前だった。
熊も鹿も兎も猪も狼も、もちろん人も、すべてがひとつずつの命を生きている。その命を狩り取って喰うことがあるのだから、狩り取られて喰われることも当然ある。
そういう世界に生きていると強く自覚するからこそ、歯抜師は人間の死を見つめていられる。
そこに熱く滾る生命があったこと、日々を真剣に生きたことすべてを受け止め、弔いの気持ちに頭を垂れ、心からその死を尊く思うがゆえ、忌避され、ときに不当に罵倒され理不尽に責め立てられても平然とした顔をして自分たちは、死人と同じ彼岸に立って此岸を見つめるのだ。
穏やかで柔和な日照雨は常々、その根源的な強さから誤解を招きがちな遠々煕と仲間たちの間の摩擦を和らげていた。無駄な衝突が起こらないのは日照雨の存在あってこそ、あまりにも自然にもたらされる平穏は、遠々煕も含めた皆が彼のお陰だと認めるところであったのだ。
だからこそ、遠々煕と日照雨の二人組は郷の中でも最も特別な一組として、羨望と憧憬の的だった。その片翼の死の報は、郷に凍てつくような静寂(しじま)をもたらすには充分過ぎた。
生死の境にある遠々煕は郷長の家で安静に保たれている。誰もがせめて遠々煕だけでも生き延びてほしいと一心に願い、強く祈っていた。
「遠々煕!」
郷長の制止を振り切り、遠々煕は砂地に転がり出た。片足を無くしたせいで肉体の均衡は失われ、うまく歩くどころか立つことさえままならない。肩と頬から地面に突っ伏し、土気色の顔で、無様な姿をさらしてもその眸に宿る光の強さは爛々と輝く。
その眸が探し求めているものを、熊襲はすぐに悟った。がくがくと情けなく震え、立っているのがやっとの足を叱咤して、地面を這いずって来ようとする遠々煕のそばに歩んでいく。
熊襲は一歩一歩を踏みしめる。両の腕でしっかと抱いた包みは、日照雨の頭だ。二貫くらいの重さだろう。遠々煕や日照雨のように上背のない熊襲の腕の中に、ぎゅっと抱えてしまえるほどの大きさになってしまった。
支えようとする仲間の腕を苛立った勢いのままはねのける遠々煕が、自身の力で這いずってゆくのを、郷人たちは息を詰まらせて見守るしかない。沈痛な悲哀が横臥していた。その手が覚束ない足取りに届いたとき、熊襲は膝から崩れ落ちた。
鉄臭い真黒の包みを、縋るようにかき抱く熊襲の身体ごと、遠々煕は日照雨を手繰り寄せる。
友だった。友を超えて分離した己の半身であった。あらゆる場所を共に旅し、歯抜師として肩を並べ、各地で死を看取り、手ずから弔い、ときに背中合わせに獣を狩り、山河の美しさに言葉を無くしたりしながら、様々な地域を共に歩いた。
日照雨は山野に生い茂る草木の中に薬草を見つけるのが得意で、彼が背負う笈には歯抜師としての道具より薬草の類の方が沢山入っていた。何より平穏を愛す男だった。
腕に抱えた日照雨ごと遠々煕の両腕に閉じ込められた熊襲は、郷で最も強い男の、骨張った腕の弱々しさに驚いた。体温も冷たく感じるほど低く、顔色も壮絶に悪い。それでも、遠々煕は日照雨を強く抱き締めていた。
遠々熙の胸にある万感の想いが、漣(さざなみ)のように打ち寄せ、重なって人々の間に伝っていった。足の一本でも凄まじい喪失だというのに、日照雨は首と片方の腕、それから足一本しかまともに残っていないのだ。他の部位も集められはしたが、多くは熊の腹の中だと報告があった。
浅く短く繰り返される遠々煕の呼吸を間近に感じながら、熊襲は張り詰めていた緊張が途端によれていくのを感じた。心がくしゃくしゃに縮れ、冷えていったかと思えば焼けるような熱さで痛みが伴う。
日照雨は遠々煕の半身だった。その半身を失って、これからこの男はどうなるのだろう。師と仰いだ男を失った己もまた、どうなってゆくのだろう。考えないようにしていた不安が途端に噴き出し、どうしようもなく堪えきれない感情が涙となって目から溢れ出た。胸の中心を強く圧迫されるような、体温と同じくらいの温度の泥を腑に詰め込まれたような感じがして、息が詰まった。嗚咽が漏れ、呼吸が乱れる。
熊襲の引き攣る啜り泣きが呼び水となって、女衆、子どもたち、歯抜師と灰衣衆を除いた男衆が次々と泣き出していく。
穏やかな青空が心地のよい晴れの下、郷は悲哀の気に満ちる。
様々な嗚咽が響き渡り、その日一日絶えることがなかった。
∴ ∴ ∴
涙を流すな。
それは、歯抜師や灰衣衆を目指す者に最初に教え込まれることだ。ことあるごとに言葉で伝えられ、夢に見るほど言い聞かせられる。どんな死を目前にしても、そのそばで誰がどのように死人を悼み、嘆き悲しみ慟哭しても、平然としていろと教えられるのだ。それができなくては歯抜師や灰衣衆の見習いにすらなれない。
死人の、死出の旅の身仕度はそう難しいものではない。地域によって少しずつの差違はあるが死番山脈の周辺では概ね、歯抜儀を行い、真新しいものか着慣れた衣を着せつけ、建てた殯屋に安置し、血肉が朽ちるのを待つだけだ。
歯抜師は二人一組で各地を巡り、遺された人々による弔いの場を調え、歯を抜き去るという特異な過程を担当する。
人々は死を日常の終着点と考える。死は、日々の生活において少しずつ肉体に溜まっていく負の気が、肉の器の限界を越えたときにに訪れるものと理解していた。巡りゆく季節に芽を出し、茎を伸べ、花を咲かせては散らす植物と同様のものだと、肉体を見つめているのだった。
負の気に満ちた肉体が朽ちるのを、自然による浄化と考える。それがゆえ、人が肉体の中に唯一持つ歯の根が、死後の肉体を此岸に根付かせてしまわぬように、歯抜師という職能者が現れたのだと伝わる。
歯抜儀は死出の旅に必要不可欠で、最も重要な過程として貴ばれ、しかし、口とはいえ死人の体内に満ちる負の気に直接触れる役目でもあることから、人々とのやりとりは灰衣衆を挟んで行われた。
物ひとつやりとりするのにも、まずは地面や卓子(たくし)に置かれ、灰衣衆が取って歯抜師に渡す。逆も然り。そういうことが重要視されないのは、歯抜師の郷内だけだ。
日照雨が仕留めた熊は毛皮にされた。肉には毒が巡り、人が食べられるものではなくなっていたが、獣狩りに使う罠餌に加工するという。内臓と血は昼夜を徹し何日もかけて行う長時間の加熱を経ることで毒性が消えるため薬材にできる。残った骨もそのうち何かに加工されるだろう。
熊の腹からは日照雨のものと思しき肉片や骨が取り出されたが、明らかに他の動物のものだとわかるものと混ざっており分別は諦めざるを得なかった。
死んだ熊が咥えていた腕一本と、少し離れた場所に落ちていた足が一本。熊の周りで拾い集められたいくばくかのかけらと、それから辛うじて無事だった頭だけで弔いは行われ、歯抜儀は遠々煕が執った。
郷の中央広場に設けられた結界は、日照雨の死を嘆く人垣で更に厚く閉ざされ、その中で、遠々煕は長く共に過ごした相方の歯を丁寧に抜き取っていった。
歯抜師は、原則の二人一組で儀を執り行う。日照雨を失った遠々煕に道具を手渡す役目には、特別に熊襲がつくことを許された。情けなく泣き腫らした顔は見習いだけが身に着ける半幎帽でごまかし、震える手を押さえつける。
冬目前の気温に馴染み、凍てつく鋳鉄の道具は、持ち慣れたものであるはずだのにひどく重たく感じられた。
遠々煕は無表情だった。明るく、表情豊かに大声で笑う男から一切の表情が抜け落ちていた。遠々熙は首だけとなった日照雨を熊襲ごと抱き締めたあのときにでさえ、涙一滴零していない。
半身を失ってなお涙など見せぬ男だからこそ、郷の皆の尊崇を受けるに値しているのかもしれなかった。
それを責めるような囁きがわずかにあったようだが、すぐに打ち消されていった。
歯抜師も、灰衣衆も誰一人、泣いてなどない。郷の者たちは美しい黒と灰を纏う彼らを思い、更に深い悲嘆に暮れた。彼らはその職務がゆえ、仲間のために泣くこともできないのだ。
悲哀に沈む心があっても、それに打ち震え涙することがないからこそ、他人の死に直接手で触れ、導く立場にあることを許されている。郷の同朋、歯抜師の仲間、そして家族、ときに己が血を分けた我が子の死を前にしたときも、彼らが涙を見せることはない。
死人の世である彼岸に立つ者として誇りかに胸を張り、歯抜師たちは死出の旅に向かう日照雨の支度が調えられてゆく様を見つめた。
遠々煕の手で進められる儀は、郷人の殆どがその場に集まっているというのに、気味が悪いほど静まりかえっている。
血の抜けきった顔を清め、髪が含んだ血を水できれいに流してやる。弄ばれるうちに引きちぎれたのだろう無惨な髪を切って整え、濡れ髪のまま、彼が生前好んでしていたように似せて編んでやる。ついぞこの髪に触れることはなかったが、彼が髪を編むのを眺めるのが好きだった。
「とときさま……」
弱々しい声が耳に入る。少女が結界の外側から花を差し出していた。目もくれない遠々煕の代わり、灰衣衆の男が受け取り、花は道具を並べた卓子の端に、白布を敷いて置かれた。
頬に鋏を入れ、口を開かせて歯を抜いていく。欠けや汚れのない青白い歯が練達した手によって取り払われ、完全な姿で並べられて行った。
その最中。次の行程で必要な、縒り合わせた純白の絹糸を針穴に通そうとした熊襲は、視界が水っぽくぼやけるのをぎゅっと目を瞑って何とか阻止する。呼吸を整え、目頭の熱さが引いてから目を開けると、遠々煕は既に花を含ませた真綿を噛ませて口を閉じるところまで進めていた。
頬を縫い綴じ、紅粉をはたけば終わってしまう。
日照雨の歯抜儀は、立つことができない遠々熙のために急造りで誂えられた低い台で行われている。首だけがあって、目を閉じている日照雨の表情は微笑んでいるようにさえ見えた。
いつも通りの穏やかな表情。遠々熙は、その美しい顔(かんばせ)を見つめていた。
遠々煕や日照雨ほどの歯抜師ともなれば、口角から顎の付け根まで深く頬を裂かずとも、歯抜儀を施すことができる。相方の顔を極力傷付けたくないといった気持ちもあっただろう。口角から入れられた鋏は最小限に済まされ、縫い綴じる必要がないくらいだった。しかし、儀は決まった手順で進められるもの。熊襲は急いで針穴に糸を通した。
準備が済んだのを気配で感じ取った遠々煕が伸ばした手に、熊襲から針が渡った。遠々煕の視線は、日照雨から一瞬たりと離れない。
かつては日照雨が遠々煕のために立った場所に、今自分がいるのだと気付き、熊襲は苦しさを覚えた。視線の先に遠々熙がいる、日照雨の場所に自分が立っているということが、熊襲の心をざわめかせた。
熊襲が初めての外巡りで郷外に出るとき、歯抜師は二人一組の原則に則って日照雨と二人だった。遠々煕と日照雨が共にいる姿を郷内で見かけることはあまりなかったが、互いに気の置けない仲であることは一見してわかる。針を持ち、日照雨の頬に触れる遠々煕の手はこの上なく優しく、そして丁重だった。
本来なら触れてはならないものに触れるような敬虔(けいけん)さが、指先から滲むような手付きで、頬の裂傷が縫い綴じられた。
口端にちょんちょんと紅を差したような小さな綴じが済まされ、針を抜いて余った糸は唇の間から口の中にそっと隠す。
編んだ髪に少女が手向けた花を飾り、青褪めた肌に粉をはたく。
「紅を取れ、熊襲」
儀は幎帽を被せるのみを残し、彼ら二人だけが纏う特別な黒衣と揃いの布で急ぎ誂えられた幎帽を手に持っていた熊襲は、予想だにせぬ指示に戸惑いながらも、漆器に入った笹紅の器と筆を手渡した。
つるりと秀でた日照雨の額に、遠々熙のものであることを示す光条の文様を描きしるす。歯抜師のみに与えられる固有の紋を交えるとき、それは、組の解散を意味していた。
金属質の緑に照る文様が乾いたのを確かめると、幎帽を被せて紐を結ぶ。無数に繰り返してきた、慣れた動作だ。
名残を惜しむようなこともない。日照雨は死に、遠々煕は自身の手で彼を死出の旅に送り出す準備を終えた。
別れはくる。先延ばしにはできない。
彼は常々、死を覚悟していた。今この次の瞬間に死ぬかもしれないと、刹那刹那の時間を慈しみ、惜しむように生きていた。いつ死んだとしても、どんな状況でどんな風に死んでも、何の後悔もないように。
日照雨の死に顔には、そんな覚悟の違いを思い知らされる。いくら彼岸に立っているとされる歯抜師であっても、彼のように死を当然のものとして受け入れ生きていくことは難しい。
偉大な男だった。他に己の半身たる者はなかった。眠ってでもいるような日照雨が受け入れた死。遠々煕はそれを、まるで自分のもののように感じ、誇らしささえ覚えた。
だが、正直なところ、先に死ぬのは己だと思っていた。己の歯抜儀を日照雨がやるものと、どこかで信じて疑わなかった。
予定が狂ってしまったな、と遠々煕は嘆息する。
静かに凪いだ心を感じ取るうち、いつだったか二人で眺めた海の景色をつらつらと思い出した。
初めて海岸に立ったときには黒々とうねる宏大な海に圧倒され、暫く動けなくなって茫然と眺めたのだったか。砂浜の歩きにくさに笑い、打ち寄せる波を舐めてみたりもした。薄くて固い、きれいな色形をした骨の欠片のようなものを拾って、郷の女子どもの土産にして──走馬燈のように過去の思い出が脳裡に閃き、そして通り過ぎていった。
日照雨の顔は幎帽に覆われ、閉ざされた。もう誰の目にも死に顔は映らず、じき殯屋で長くはない眠りにつく。
遠々熙は、丁寧に集められた日照雨の身体をまとめて入れてある箱にそっと首を入れようとして、思わず笑ってしまいそうになるのを息を止めてなんとか堪えた。
まるで日照雨のもののような顔で箱に納まっているその足は、あの熊にちぎり取られた己のものだった。
そうか、足一本なら、日照雨と共に朽ち果てることができるのかと思案する。今更この足は自分のものだと言い出しても周りが困惑するだけか、と判断した遠々熙は何も言わず、ゆっくりと止めていた息を吐き出し、首を納めた。
日照雨が納められた箱は歩けない遠々熙の代わり、熊襲と灰衣衆が殯屋に安置する。
結界の周りを厚く覆っていた人垣は波が引くように割れ、その向こうに運ばれてゆく相方を思い、遠々煕は一人で空を仰いだ。
筆で刷いたような薄い雲がかかる、透き通った冬の青空がどこまでも遠く広がっている。
運ばれる日照雨について郷人たちは結界を離れていった。
遠々煕は空を仰いで倒れる。青い小鳥が飛び交い、森へ向かってゆくのを眺め――そして、深く息を吐くと、最期の視界を静かに閉ざした。
眠りに就くよりも静かに人生の幕を閉じた遠々熙に、戯(そば)えるような片時雨が降りかかったことは、誰も知らない。
∴ ∴ ∴
湿気を含んだ夏の風が、穏やかに枝垂李(しだり)の頬を撫でてゆく。彼の手には、鶏卵ほどの大きさのすももが握られていた。
村落を三つほど巡り、四人分の歯抜儀を執り行った夜だった。
そこで謝礼の代わりにと差し出されたすももの実はまだ熟していないらしく、実は固く締まっている。常温で数日おいてから食べるものだと教わったが、いつの日にか師の話に聞いたものが手元にあるということが嬉しく、白くけむるような質感で赤紫色のつるりとした表皮を指先で撫でる。
あれは確か、自分がまだ見習いのころ。春の終わり、夏の気配が少しずつ増してくる季節のことだ。
師と組んで行う、たった一度、三箇月だけの外巡り。あのとき巡った場所が、このあたりなのかはわからない。土地勘も何もないまま、師と、師に付き従う灰衣衆について行くのがやっとの研鑽の日々。
そして確か、歯抜儀を初めて任せて貰えた日だった、と思い出す。祈ってやれたか、と師は問うた。遠く過ぎ去った過去の美しい一日。
あの翌日、歩く道すがらに梅のような花が咲いており、時期はずれだと自分が言ったのだ。しかしそれは梅ではなくすももの花であると、そして師の好きな花であると聞いた。果実も好物であるが、歯抜師の郷の近くでは育たず、なかなか口にする機会には恵まれないと言っていた。
枝垂李は口元が緩むのを感じ取った。致し方あるまい。一体あれから、あの日から、どれほどの月日が過ぎ去っていったことか。こんなに経ってようやく、あの日師が好きだと言ったものを手にしているのだ。
早く食べてみたい。己の半生もそれなりに長く積み重なり、省みる価値もでてきたと思うころになってやっと、あの日師が好きだと言ったものを口にする機会を得たのだ。
師と、その相方。彼らのことは忘れもしない。忘れられようはずがない。歯抜師として名を馳せたあの二人組のことは、今でも頻繁に話に上っている。
その度にわずかばかりの悔しさと、そして誇らしさを枝垂李は胸に抱く。彼らと共にあった日々の記憶は薄れることなく、年を重ねるごとに懐かしさで一層深く刻まれていった。
師が死した冬。師の相方は歯抜儀を成すと、後を追うように死に、枝垂李と今の相方は二人して同日に師を失った。
周りの同期が言祝ぎに師から貰う名を内示に受けたと嬉しそうに話す冬を、枝垂李は寂しさと孤独を友にして過ごした。
弟子を三人立派に育て上げ、師が没した年齢を倍にできるほど生きてきた今はただ、あの日々を懐かしく思う。
見習い期間を終えた翌年春、暖かくうららかな美しい日に、一人前の歯抜師として郷に認められる日がやってきた。
郷長の隣、師が立つはずだった場所には灰衣衆の男が立っていた。持っていた竹簡を郷長に差し出す。
そこには、枝垂李の師とその相方の連名で、それぞれの弟子に与える名が明記してあった。日々のうちに自らに何かあったときにのためにと備え、灰衣衆に預けておいたものが、役目を果たしてしまったのだ。
師らの死から、半年近くの時間を経てもたらされた竹簡。
書き記されていた見慣れた師の字に、思わず涙が出たのは仕方がないといえよう。
師はかつて好きだと語ったものの名を与えてくれた。
あの日の感動を、枝垂李が同様に自身の弟子に与えてやれたかどうかはかなり怪しいが、努力はしたつもりだ。
何にせよ偉大過ぎたのだ、師ら二人は。
凄惨ではあったがあまりにも勇ましく、そして美しく散っていった二人。
彼らがひと時に続いて死した後から今まで、もう随分と長い時間が、季節が、何度となく繰り返し過ぎ去ったというのに、歯抜師たちは未だに弟子が一人前となるときの、言祝ぎとして与えてやるその名に、煕や雨の字を用いる。
偉大な二人の歯抜師に肖(あやか)って。
「枝垂李様、嬉しそうですね」
灰衣衆の男が話しかけてくる。
師の好物を、まさか現役最後の外巡りとなるこの旅で得られようとは思ってもみなかったのだ。見てわかるほど嬉しそうにするのも、今宵くらいは許されたい。
「そういえば、父から聞いたことがありますよ。日照雨様は獣肉より木の実や果実を好んで召し上がる方だったと」
「ああ……」
誰かと話すと、いつかの日々が次々と脳裡に甦る。
長い時間が過ぎたせいか、過去の日々は美化されている。
師の背を越えることは、この歯抜師人生ではできなかった。唯一越えたと思ってよさそうなのは、弟子を三人育て上げたことくらいだろう。だがこれは普通に生き長らえることができたという幸運に恵まれただけのことで、己の力ではないと、枝垂李は思う。
師も、あのとき不運に遭って死にさえしなければ、今頃、数名の弟子を育て上げていたに違いない。
「召し上がるのでしたら剥きますよ、それ」
「いや、構わん。このまま食べてみるよ」
追熟を待って食べるものだと聞いたが、待っていられるはずがなかった。
枝垂李は衣の袖で表皮を拭い、ぷちりとすももに歯を立てた。
「すっぺ」
枝を垂らすほど、李(すもも)の実が豊かに稔るように。
そう願われた名で、ようやっと口にすることができたすももの味にぎゅっと口を窄め、枝垂李は仲間と共に笑い転げる。
びいびいと日中煩く鳴く蝉も、すっかり眠りについた夏の夜、高い昊(そら)に緑色に照る星炎の明かりが絶えず瞬いていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
