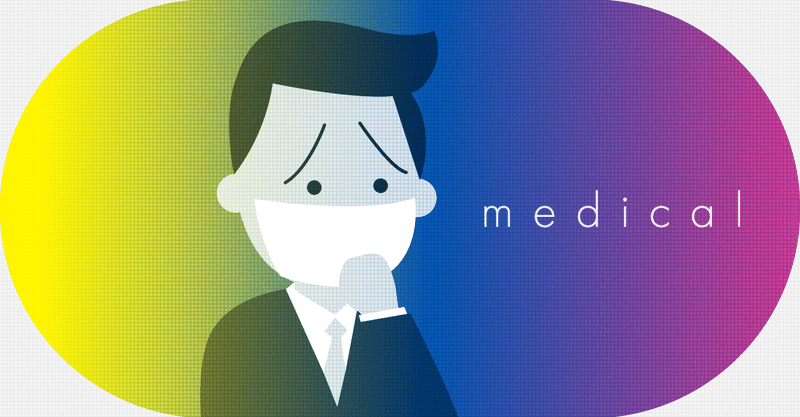
感染症と興行
およそ100年前、1918年から1920年にかけて、世界中でスペイン風邪と呼ばれるインフルエンザが猛威を振るいました。
世界中で2千万~4千万の人が亡くなったと言われています。
1918年の10月頃から日本でも流行が始まり12月には一端落ち着くもの、翌年の1919年10月から再び流行、1920年の1月に流行はピークに達し、日本全国で約40万人の死者を出しました。
当時、ウイルスというものは認知されていませんでした。(そもそも顕微鏡がなかった)
それでも、人から人へ感染するということはわかっており対策が取られました。
当時、政府が推奨した予防対策ですが
〇人と話すときは4尺(1,2メートル)離れる
〇マスクをする
〇咳が出る時は袖などでおさえる
〇学校は全て休校
〇劇場は立ち入り禁止
〇不要不急の集会の自粛
〇旅行も自粛
現在と全く一緒です。(というより、この100年前の対策を今回も参考にしたのでしょう)
イベント自粛が相次ぎ、芸能は瀕死の状態になっていますが、100年前の感染が2年間にわたって続いたのだとしたら、どうやって芸能は復活したのでしょうか?
ネットは当然ですが、テレビも無かった時代です。
そんな時、一つ思い出したことがありました。
福岡には玄洋社という政治結社がありました。
右翼の元締めだとか、日本最後の秘密結社だとか、いろいろ誤解されている団体です(玄洋社については、いずれ書いていくつもりです)
この玄洋社のメンバーの一人、末永節という人は郷土芸能の支援や興行のプロデュースをてがけていました。
西洋文化が席巻するのを見て、日本の芸能を守らなければと活動していたと聞いていたのですが。
その支援時期と、スペイン風邪の流行後は重なるのかもしれません。
だとしたら、興行の自粛が相次いでいた芸能団体を、玄洋社が支援していたのかもしれません。
そういう視点はなかったので、調べてみようかと思います。
文化を大切にし支援する地元企業や有力者の方は、今でも存在します。
本当にありがたいことです。
感染症に文化芸能が負けるわけにはいきません。
このスペイン風邪では、皇族の竹田宮恒久王(評論家、竹田恒泰の曾祖父)軍人の西郷寅太郎(西郷隆盛の長男)、劇作家の島村抱月等が亡くなっています。
志村けんさんのご冥福をお祈りします。
ドリフの舞台は、多くのことを教えてくれました。
サポートして頂けると、クリエイター冥利につきます。でも、決して無理はなさらないでください。
