
別にライブじゃなくてもいいーー真夏に観た小林私と“ミュージシャンの応援のしかた”について
■ライブに行く理由を考えなければいけない
今程ライブに行く明確な理由を考えなければいけない時代は後にも先にもない気がする。
「推しを生で見てみたい」「生の歌声やバンドサウンドを体感してみたい!」「ライブハウスが好き」……そもそもライブなんて、そんな感じの簡単な理由で気軽に足を運んでも構わない場のはずだった。でも、正直今はそう気軽には行けない、色々な事情を抱えているひとがきっと増えてしまったんじゃないかと思う。
最近やっと緊急事態宣言が解除された。最早日常の一部のようになってしまった緊急事態宣言。だからそれが解除されたところで、日常に訪れる変化はほぼない。哀しい程に真面目な僕達はこれからも、手洗いうがいを徹底して手指消毒に励み、なるべく小顔に見えるお洒落な不織布マスクを買い求めておっかなびっくりライブハウスへ行く。
最近は不穏な音楽フェスが某所で行われたこともあり、より一層音楽シーンへの風当たりが強くなったような気さえする。おっかなびっくりでもライブに行けるなら贅沢なぐらいだ。職業柄、だとか、家族に反対されて、だとか、色々な理由からもう何ヶ月も、1年以上もライブに行けていないひとだってきっと少なくない。
かく言う僕も、決して行きたいライブにすべて行けているわけではなかったりする。あくまでも個人的には、行ける範囲でライブに行き続けたいと考えてはいるのだが、東京住まいで、且つ自宅に引きこもって仕事ができるフリーライターという仕事柄、日頃の感染リスクを抑えることが出来るために比較的ライブに足を運ぶことへの抵抗感が少ない、というだけであって、感染状況や自分の体調を鑑みて敬遠してしまったり、配信で済ませた公演も幾つもある。
正直悔しい。でも、推しの音楽を鑑賞するのも、推しを応援するのも、必ずしも“ライブじゃなくてもいい”とも思っているのだ。今日はそんな話がしたいと思ってキーを叩いている。
その前にまず、僕が「それでもライブに(行ける範囲では)行き続けたい!」と思っている理由について聞いてほしい。
■真夏の小林私弾き語りワンマンライブに行った
真夏、8月の18日に友人と連れ立ってシンガーソングライター・小林私の弾き語りワンマンライブに行った。彼のライブに行くのはこれで4回目。最近はテレビに出たりタイアップが決まったりと目覚ましい活躍を見せている彼だから、(彼のリスナーならご存知の通りの)あのヒトの好いオタクで変わり者のクラスメイト、みたいなリスナーとの距離感の取り方が変わらないうちに観られるだけライブで観ておきたいと思っていたりする。ほら、本人に変わる気がなくても、周りの大きいオトナがそれを許さない場合もあるじゃないですか。
この日の会場は恵比寿のリキッドルーム。
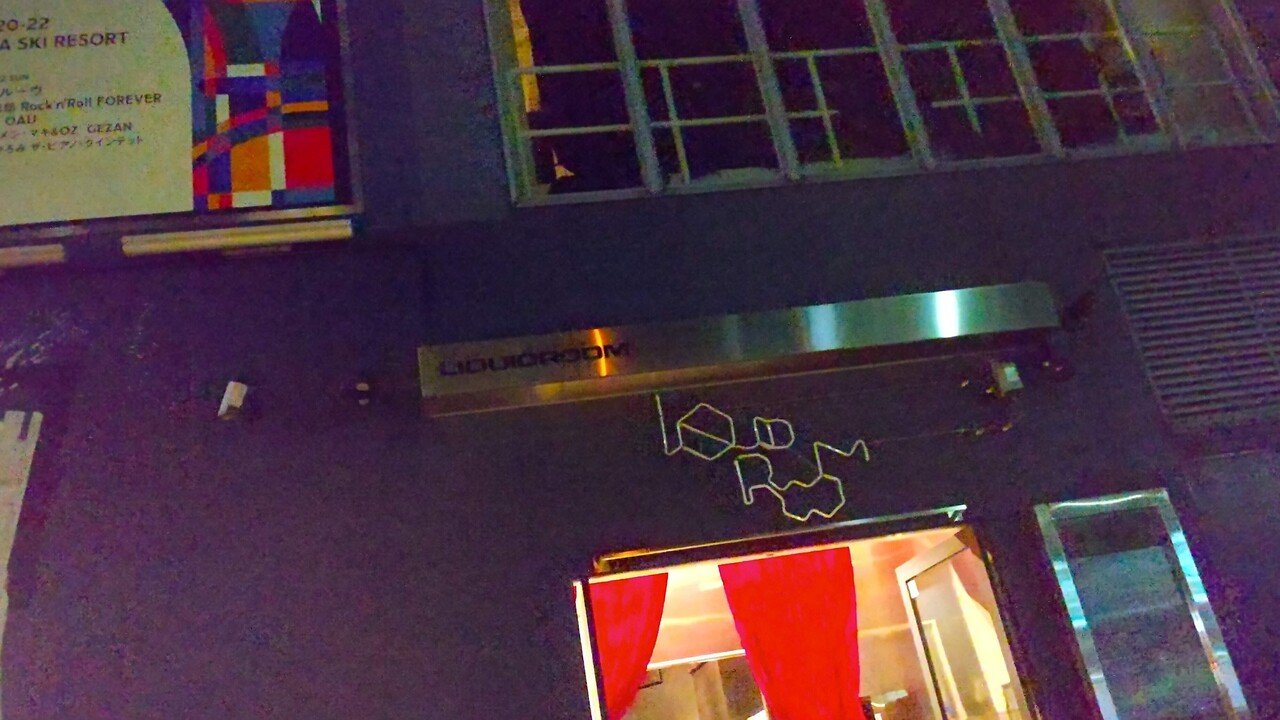
こじゃれた外装にカフェが併設された武骨ながらスタイリッシュなインテリア。大きすぎず小さすぎず、有名バンドから小林のように売り出し中の若手注目株まで幅広いミュージシャンがその板を踏んできた、都内でも人気のハコだ。友人と僕はいちおう密状態を避けるためにフロアの後ろの方の、スタンドテーブルのような柵のあるスペースに陣取っていた。因みに会場に入る前に僕はカオマンガイ、友人はガパオライスとグリーンカレーのセットを平らげている。勿論料理を食べている時以外はマスクは必須だけれど、そうやって友人と額を突き合わせて駄弁りながら開演までの時間を潰すのも、実際にライブハウスに足を運ぶ時の楽しみのひとつだったりする。いわゆる“ぼっち参戦”の時だって、普段あまり行かない土地で宛てもなく歩き回ってイイ感じの飯屋に入ってみたり雑貨屋に入ってみたりする。これはあくまでも僕の場合だが、ライブに行く理由はライブそのものだけにあらず、なのだ。

(おいしかったです)
フロアで流れるSEは小林が作詞において影響を受けたと公言する面影ラッキーホール。暗転したステージに何の前触れもなく姿を現した小林は、なんでも客の前に立ちたくなさ過ぎて、直前まで楽屋のソファでひっくり返っていたという。そんなことを悪びれもせず客に向かって話す小林。だいぶくたびれてきたオキニの赤いアロハシャツとGパン、足を怪我してもやめないサンダル履き姿でアコギを抱え、元気いっぱいに名乗りを上げる。
「小林私です、今日はよろしくお願いしま~す!!!」
ひとつに縛った長い髪に中性的な容姿、毎度思うが一見すると、オンナ手玉に取って生活していそうな絵に描いたようなアンニュイなバンドマン、という感じのルックスなのに、ひとたび口を開くと元気なオタクの好青年なの本当にずるい。しかも以前まで――それこそ今年の春の初めてバンドセットを背負ってワンマンライブをした頃辺りには、まだへっぴり腰でオドオドと入場してきていたというのに、何の構えもなく“満を持した”感じもなく、やおら姿を現すその登場のしかたも気づいたらかなりナチュラルで、全く肩に力が入っておらず一周回って堂々としていさえする。こういう細かい変化にも、逐一会場に足を運んで生で観た方が気づきやすい。
「僕のライブでは別に手挙げたり拳振り上げたりしなくてもいいんですよ、どんなノリ方してもいいです」と寛容さを示して来たかと思いきや、「何故なら皆さんの顔、ひとりたりとも見えてないから」とすぐさま落としてくる小林。人見知りの彼らしい物言いだけれど、有名ミュージシャンが伝家の宝刀として振り翳す、どんなに大きな会場の遠くのお客の顔でも「見えている」というような発言を茶化して、「後方~!!!見えてないぞ~!!!」「あんなん見えるわけないですやん、うそうそ」と笑い始めた時は流石に消されるぞ! と思った。誰にとは言わんが。
しかし彼の場合はそれでも良いのだ、とも思う。何故なら歌が上手い、表現力がある、ソングライティングスキルが高いといったテクニック以前に、歌っている時の彼はとにかく無邪気で楽しそうだからだ。それはライブだけでなく日頃YouTubeで行われている生配信を観ていても思うことなのだけれど、技術があるだとかサービス精神があるだとか、一般的にプロの歌い手として求められる基本事項以前に、その表現自体を楽しんでいてくれた方が観ているこっちだって気分が良いに決まっている。
伏せられたまつ毛、感情の込められまくったくしゃくしゃの顔、大きく開けられた口、振り乱されて風になびく伸びた前髪。小林自身が誰よりも楽しんで歌っている姿は観ていてとても痛快で、別にオーディエンスなんぞ見えてなくてもいい、と思わされる。どうせ普段の生配信では、こっちの顔なぞ彼には見えていないのだし。
「今まで2回しか成功したことがない」と豪語し、この時も結局歌詞を忘れて最後まで歌いきれなかった『泪』、テレビでも披露されたにも関わらず毎回アレンジが少しずつ変わる最新曲『後付』、突然繰り出される地元の友達(※一般人)の名前やテレビ出演が決まった際学生時代に茶道を習っていた先生が母校の裏のパン屋さんに番組名などの貼り紙をしてくれた話……改めて思い返すと、小林のライブほど曲とMCの間に境界線がないライブはないような気がする。初めて彼のライブを観た時は、その一度聴いたら忘れられない異形のようなハスキーボイスと空気をも切り裂くような声量に圧倒されて、MCの内輪ウケ甚だしいユルさとのギャップに風邪を引きそうになったものだが、こうして改めてギター1本を抱えて歌い喋る彼と向き合ってみると、彼にとっては歌うことも喋ることも主義主張の出力という意味では同じことなのだろうな、と感じられた。
やはりライブというある種フォーマルな場であることから、お喋りからは“頑張っている”空気は感じられるが、喋ってたかと思えば突然歌い出し、歌い終わったかと思いきや全く脈絡のないお喋りに移行する、そのシームレスさは日頃の生配信の時と何ら変わりない。彼自身がライブの場数を踏んで度胸がつき、より自然に振る舞えるようになったというのもあるかもしれないが、僕が当初そのギャップに風邪引きそうだったのは単純に彼の持つ独特のグルーヴに順応出来ていなかっただけのような気もしてくる。MCとパフォーマンスで完全にテンションを切り替えてくるほかのライブミュージシャンとは違って、小林私は歌うように喋り、喋るように歌い、飄々とした憎まれ口と二十億光年の孤独をその口から同じテンションで紡ぎ出す。人類は小林私に順応するために特別なスイッチを脳内に設ける必要がある。
■小林「考えてる事は日々変わるから、その日の気持ちを切り取って残しておきたい」
終演が近づいたタイミングで、小林は急に饒舌になった。「楽屋でやれ」という感じのお喋りの内容に変わりはないのだけれど、まるであんなに「立ちたくない」「楽屋のソファで寝てた」と豪語していたはずの舞台の上から、立ち去るのが名残惜しいようだった。
「終わり頃になると勿体なくなっちゃうんですよね。で、ずっと喋っちゃう」と小林は言った。やはりライブを終わらせるのが惜しいようだった。初めてバンドセットを背負ってワンマンをやった時などはいくら外出自粛が叫ばれていた時期とはいえ、たったの1時間という破格の短さで切り上げたというのに。
「昔は喋るのも歌うのも好きじゃなかった」と言い、小林はあっけらかんと笑う。「今も直前まで嫌ですからね。ライブが中止になると“休み”だと思っちゃう。でも、みんなの前に出ると楽しくなっちゃうんですよね。だから勿体なくて、ずっと喋っちゃう」
この日の個人的なハイライトは、『飛日』『香日』『恵日』の3曲を続けて演奏した件だ。独特なタイトルが多い彼の曲の中でも、“日”という漢字は意味ありげに使用されることが多く、この時のMCでは彼自身もそのことに触れていた。
曲のタイトルに“日”の文字を入れることについて小林は、「考えている事は日々変わるから、その日の気持ちを切り取って残しておきたいと思っている」と話した。その“日”に思っていたこと、感じていたこと、その瞬間を切り取った曲であることを示すために、タイトルに“日”を入れるのだという。
「5年とか10年とか、時間が経った時に、同じ事考えてたら気持ち悪いでしょ。だから、変わっていてほしいなという祈りでもあります」
表情がわからないぐらいの真っ赤な照明の中で歌う小林の影は、埼玉のイオンのヴィレッジヴァンガードで初めて目にしたあの時と比べものにならない程、芯が太くなったように見えた。「美少女のようだ」とたびたび喩えられる(僕も正直そう思っている)第一印象を忘れる程に、浮世離れした印象は薄く、“小林私”という人格にとても頼もしさを感じた。これは、ほかのバンドなどを見ていて感じる“ミュージシャン”としての頼もしさ=仕事人としての頼もしさ、とは少し違う気がする。いちリスナー如きがおこがましいけれど、彼が確実に、人間として成長していることが手に取るように感じられた、気がするのだ。
掠れても構わず繰り出されるファルセットに、地から這い上がるようなロー。本人も以前生配信で言っていたように、歌の先生なんかからしてみたら褒められた歌い方ではないのかもしれない。ちょっと前まではお節介にも喉が心配になったりもしたけれど、その歌い方が今の小林そのものであるのならばそれこそが正しいような気さえする。
小林のメインフィールドは必ずしもライブハウスではない。先にも話したように、彼は頻繁に生配信を行う。そしてその時の、歌と喋りの境目の曖昧さはライブにもそのまま引き継がれている。だから別に、彼のリスナー皆がライブに行く必要性はないだろうし、彼自身もそう思っていそうだ。
それでも僕が今、彼を出来る限りライブで観ておきたいと思っているのは、さっきまで書き綴ってきたような、彼自身の細かい変化をこの目で観られる限り観ておきたいからだ。
この時の公演はオンラインでの配信も行われていたから、正直それでも良かったかもしれない。でもやっぱり、平面の液晶の中で0と1の情報に置き換えられた姿では、著しい人間の変化には気づきにくい。「演奏が上手くなった」だとか、「声が良く出るようになった」だとか、単純な技術的な部分にしか気づけない可能性が非常に高い。彼自身が言うように、日々変わりゆく彼のその“日”を、出来る限り多く記憶しておきたいと思う。
勿論、理由はそれだけではない。あの歌声が不意に鼓膜を揺らした時の、脳味噌の芯がビリビリ痺れるような、全ての感覚を放り出して地の果てに引きずり込まれるような感覚は、実際にその“場”に身を置かないと感じられないから、というのもある。こればっかりはどんなにYouTubeの弾き語り動画を観たって、生配信で管を巻いたって、テレビで衝撃の出会いを果たしたって得られない感覚だ。彼という歌い手に対して「可愛い顔してるくせにすげえハスキーボイスだな!!!」 としか思った事がないひとも少なくないんじゃないだろうか。いや、そのギャップだけでも充分魅力的な歌い手ではあるのだけれど。
これを読んでくれている奇特なひとびとにとっては当たり前のことかもしれないけれど、音楽はなにも耳や目だけで楽しむ芸術ではない。脳味噌全体を使うものだし、なんなら心臓や胃にだって響いて溜まる。歌声もルックスもインパクトが強くて、ある意味“わかりやすい”異才であるところの小林だからこそ、このライブでしか感じられない感覚を知らずに、「ええ声やないか(面白ツイッタラーor美少女顔のくせに!)」程度で留まり続けてしまうリスナーが無数にいるのかもしれないと思うと、なんだか勿体ないな、と思ってしまう。
■別にライブに本質がなくてもいい
とはいえ、だ。
ここまで僕は、小林に限らずどんなミュージシャンにも言えるような、今この状況でも行ける範囲で/充分な感染対策はとったうえでライブに行きたいと思う理由を小林のライブに行った際の雑感を通して長々と書き綴ってきたわけだが、別にミュージシャンの本質は必ずしもライブになくてもいいし、リスナーも必ずしもライブに行かなくていいと思っている。
この考えはもともと僕の中にあったものではなくて、この2年余りの間の、思う存分ライブに行けないようなご時世になってしまったことや、ライブに必ずしも本質がない、小林のようなニュータイプのミュージシャンを知ったことで思い至ったものだ。それまでの僕はどちらかというと正反対の、生々しいライブの場で真価を発揮するミュージシャンこそが至高、と思うタイプのオタクだった。過去形で書いてはいるが、正直今でもその気持ちの方が強い。動員数、物販の売れ行き、目に見えてわかるお客さんの増減を目にしてシビアに傷つきながら、それでも諦めずに自分自身が信じた表現を埃っぽいハコの中でぶちかまし続けたバンドマンの姿に勝手に人類としての理想形を見ている。
でも別に、そんなロマンはライブハウスにしかないわけではない。確かにライブハウスでがむしゃらに闘うバンドマンからしか得られない栄養素はあるが、そうじゃないミュージシャンだって等しく尊いに決まっている。
コロナ禍は皮肉にも、音楽を表現する“場”を拡張した。それ以前からネット配信などを使って表現する配信者やVtuber(今はヴァーチャルアーティスト、とも言うのだろうか)などのミュージシャンも存在はしていたが、自由に県境や国境を越えられない今という状況が、そのスタイルをより一般的に、より面白いものに拡大していったのは事実だ。それまではCDの売上とライブの動員でしか測れなかったそのミュージシャンの収入や人気が、楽曲の再生数やDL数、配信の視聴者数や動画の再生数などでも測れるようになった。
僕はご覧の通りライブハウスという場が好きだし、さっきまで長尺をとって書いてきたような理由からライブに足を運び続けているぐらい、昭和の刑事ドラマに登場する熱血警察官並に現場至上主義なわけだが、それはそれとして“場”の拡張は素敵な事なんじゃないかと思っている。ライブハウスという限られた場所でしか得られなかった、CD屋という限定的な場所でしか得られなかった、そんな感覚を、完全に同質のものでは決してないけれど、どこにいても誰といても勿論ひとりぼっちでも体験出来るのはとても理にかなっている。
リスナー側だって、必ずしもライブに行けるわけではない。今でこそライブ礼賛みたいな文章ばかり書いて時にお金を頂けることもある僕だが、学生時代のジリ貧状態な頃にはライブのチケットを入手するどころか原価でCDを買うことすら出来ず、ずっとブックオフに通って推しバンドの音源を探していた。あの頃、サブスクサービスがあったらDL数や再生数に貢献して推しバンドの知名度や収入にもっと確実に貢献出来たのにな、と思う。あの頃格安の配信ライブが行われていたなら、少ない小遣いでもチケットを買えて自分の部屋からでもライブハウスの空気を感じる事が出来たのにな、と思う。
でもあの頃、僕はお金を自由に使えなかった分、言葉を紡ぐ事を覚えた。好きな音楽やそれを表現するひと達の魅力を伝えようと頑張って紡いだ拙い言葉は少しずつ伝播して、友人やSNSのフォロワーが僕の好きな音楽に一緒になって熱狂してくれるようになった。その頃僕が発した拙い言葉達が、回り回って彼等の音楽を広め、あまり品の良い言い方ではないが彼等の懐をも温めたかもしれないと思えば、あの頃の無力感も癒えるというものだ。
ライブは最高だ。好きなミュージシャンのライブには、行ける範囲で積極的に行った方が良いに決まっている。でも、別に行けなくても良い。ミュージシャンを応援する方法も、音楽を楽しむ方法も、法律に触れたり誰かに迷惑をかけたりしていない限り、別にどんなやり方でも良いのだ。
ミュージシャンにとっても、“ミュージシャンたるものライブハウスでお客を沸かせてこそ!”という考え方は、いまどき時代遅れなんだろう。ワンマンライブもやったことのない新人のミュージシャンが、突然彗星の如くストリーミングランキングを荒らしてMステに出演したとて、別にもう珍しい話ではないわけだし。
歓声を上げられないライブ、ライブハウスを知らない新人ミュージシャン、昨年まではそんな音楽の現状を少し淋しく思ったりもしたけれど、この現状を“制約があってウザい”と思うよりも“表現の仕方も楽しみ方も幅が広がった”と思った方が、人生楽しいに決まっている。ライブバンドへのロマンはどんな現実に対しても譲りたくはないけれど、ヘンな執着は捨てるに限る。
しかしそれにしても、たとえライブハウスで歓声を発しても良いご時世に戻ったとて、小林私の現場でコールアンドレスポンスが起こることは絶対にない気がする。まあ、ライブの楽しみ方なんて“別にどんなやり方でも良い”わけだから、それもまた一興だ。
本日は東阪ワンマンライブ「一つの例を挙げるなら貝の剥き身の展示かな」at恵比寿リキッドルームでした!ソールドアウトの会場、そして配信でご覧頂いた皆様ありがとうございました✊
— easy revenge records (@easyrevenge_jp) August 18, 2021
次回は9/12大阪梅田クアトロでのワンマンライブでお会いしましょう!!
photo by @kawado_photo pic.twitter.com/FYhyVR2OBI
(ところで最後までこの謎のツアータイトルの意味わからんかったな、知らん地元のともだちの話だけじゃなくて解説してくれよ……別にいいけど。)
かねてより構想しておりました本やZINEの制作、そして日々のおやつ代などに活かしたいと思います。ライターとしてのお仕事の依頼などもTwitterのDMより頂けますと、光の魔法であなたを照らします。 →https://twitter.com/igaigausagi
