
探究授業案8「ゼロから作る物理の問題」 vol.908
高3の授業では演習が多くなるため、自然と探究的な学習が難しくなるように感じています。
ましてや受験生は本番に向けて問題演習を増やしていきたい時期、正直受験に関係ないと分かるとやる気をなくす生徒も多くいるわけです。
それも空気の作り方次第なのでしょうが、そういった少しピリッとした空気の中でも、これが確かに大事なんだと実感を持った上で探究学習を進めていきたいものです。
今日書く授業案はそんな受験生向けの探究的な活動になるかなとも思います。
ゼロスタートで作問

正直いきなり問題を作れと言われても、出だしが難しいのは当然です。
でも、まずはこのどうすればいいのか状態を体験してもらうことに意味があるのではないかと思います。
というのも、そもそも何も元の問題がなかったり想像もできない問題というのは物理においてもあり得ないからです。
大体の場合、日常の中にある現象を切り取って問題にしているか、それともすでにある問題を複雑化させたり独自性を加えて問題を改変したりしているだけなのです。
つまり初めましての問題など1問もなく、大体の問題にはその問題を解けるだけの糸口を誰でも備えているという実感を持って欲しいのです。
だからこそあえて、ゼロスタートでの問題作問を開始させる意味があるのではと思います。
組み合わせと条件付けと
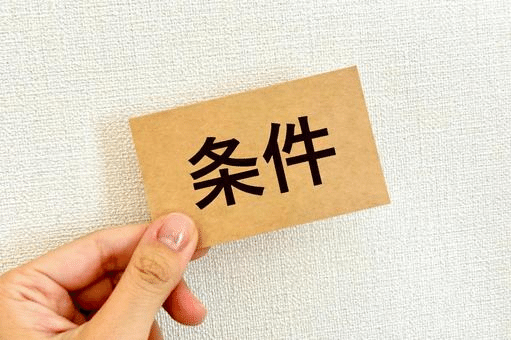
何もない状態で策問ができるのであれば御の字。
そのままそれを進めることで十分な力がついていきます。
ゼロスタートが難しい場合には複数の入試問題を見せて、そこから問題を作成していくという過程を取ります。
その際に、入試問題はいわば完成されている問題なので、そこで設定されている条件を減らしたり増やしたり、変えたりとする中でオリジナル問題を作成していくように舵を切ります。
物理の問題は初期条件から条件がどんどんと付与されていき、それらをどの公式で導き出していくのかというのを解き明かしていく学問です。
少なくとも高校物理はですが。
その条件付けをあえて自分ですることで作問者視点を持ってもらい、初見の問題にも対応できる力を身につけさせるのではないかと思っています。
誰もが納得できる解答を

そして最後には模範解答作りです。
これは自分の中で作り上げた問題を整理して解き明かす、いわば論理的思考の利用になるのかなと思います。
頭の中だけにある解法を万人が受け止めやすいように変換することで改めてその知識が自分のものに変わっていきます。
このように複数の視点を持つことが私は理科にとっては重要なことだと感じているのです。
今回のように問題そのものの改変を行い前提を疑ってかかるラテラルシンキング、今の条件での問題の成立具合を確かめながら疑い自ら条件を付与していくクリティカルシンキング、複数の視点を持って問題を見るパラレルシンキング、そしてそれらを系統だって模範解答を作るロジカルシンキング。
まだ実際にやっていない授業ではありますが、どのような形なるのか見てみたいものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
