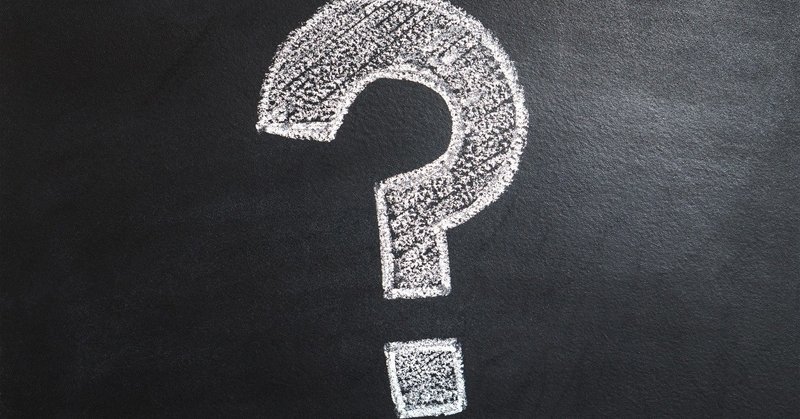
兵頭先生!中医学がムズカシイのですが……
東洋医学の根本である中医基礎学について、そのシステマィックな考え方を講義形式で分かりやすく解説した『中医学の仕組みがわかる基礎講義』。
著者の兵頭明先生に、本書の特徴やその活用法について、お話をうかがいました!

学会発表でもおなじみの兵頭氏に聞きました(写真は全日本鍼灸学会愛知大会、撮影:編集部)
――兵頭先生はこれまで多くの学生を指導してきた立場ですが、東洋医学の基礎で挫折してしまう学生も多いそうですね。なぜでしょうか?
兵頭 東洋医学概論や中医基礎学の冒頭はたいてい陰陽五行論から始まります。東洋医学を基礎づける哲学を知ることはもちろん大切なのですが、東洋「医学」を学びたいと意欲に燃える初学者がその深遠さに面食らっていきなりつまずいてしまうことも少なくないからです。
その代わり、まず気・血・津液・精といった生理物質や蔵象理論といった東洋医学の生理学的側面から入っていき、病因、病理・病態、そして病証へと進んだほうが、ずっと理解しやすいんですよね。

――本書でも、あえて陰陽五行論は避けて、生理学的側面を入口とした構成となっていますね。
兵頭 本書は、筆者が鍼灸専門学校の1年生を対象に行った講義をもとに構成しています。つまり、東洋医学や中医学のことを全く知らない人でも分かりやすく、その基礎的な考え方を理解できるように工夫されています。
実はこの講義と同じようなセミナーを自治医科大学にて、「医師のための中医学セミナー」と題して全20回。さまざまな診療科の先生が受講してくださり、なかには手術を終えてすぐ受講しに来られた先生もいたほどに好評でした。ですので、鍼灸学校の学生はもちろんですが、広く医療従事者や医療系の学生にも手に取っていただきたいです。
すべての医療職種が西洋医学の考え方を共有しているように、鍼灸師と医師、歯科医師、コ・メディカルが東洋医学というもう一つの理論的基盤を共有することによって、東洋医学をベースにした医療連携も可能になると考えます。
東洋医学について全く知らない人でも理解できるという本書の性質から、東西両医学の共通理解・相互理解の一助になると考えています。

――他にどんな方に本書を読んでもらいたいですか?
兵頭 すでに免許をお持ちの治療家にとっては、中医鍼灸をはじめとした伝統鍼灸を学ぶ最初の一歩となるでしょう。中医学は『黄帝内経』をはじめとした古典をベースに、時代を下るにつれてさまざまな流派(各家学説)の成立と淘汰を繰り返しています。
この膨大かつ変転する体系のなかで、ゆるぎない1本の太い幹となっているのが本書で解説している中医基礎学です。
これは言うなれば、内経医学から現代に至るエッセンス、つまり仕組みをまとめたものであり、東洋医学に携わる者がいつでも参照できるものであり、さまざまな古典に分け入っていくための出発点になるはずです。

-------------------------------------------------------
第1章 - 東洋医学の人体観
第2章 - 気・血・津液・精・神
第3章 - 蔵象理論
第4章 - 六腑の生理
第5章 - 3つの病因
第6章 - 病因から病態へ
第7章 - 代表的な病証29選
-------------------------------------------------------
兵頭明(ひょうどう・あきら)1982年、北京中医薬大学卒業。1984年、明治鍼灸柔道整復専門学校(現・明治東洋医学院専門学校)卒業。同年より学校法人後藤学園に勤務。天津中医薬大学客員教授、筑波大学理療科教員養成施設非常勤講師。(一社)老人病研究会常務理事、(一社)日本中医学会理事。
-------------------------------------------------------
(了)
東洋医学の専門出版社・医道の日本社のページです。鍼灸、あん摩マッサージ、手技療法、ヨガ、コンディショニングなど「身体を呼び覚ます」プロに向けて情報発信していきます。よろしくお願いします!
