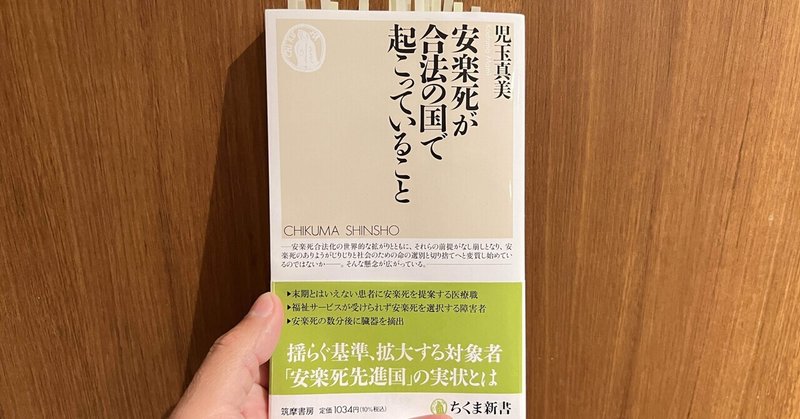
『安楽死が合法の国で起こっていること』児玉真美、筑摩書房、2023
この本は、ただ「安楽死が合法の国で起こっていること」をルポルタージュとして紹介するような本ではありません。
安楽死が合法となっている国で起こっている、本書で使われている言葉を使えば「すべり坂」のように、人の命が、そして死が軽く扱われてゆく傾向が、日本でも更に急な傾斜で「崖」のように激しくなっていくのではないか、という警告の書です。
安楽死といえば、「死ぬ権利」について取り沙汰されることが多い話題だと思います。しかし本書では、「死ぬ権利」が本当に当事者(例えば、終末期の患者、病気や事故などで植物状態に陥った患者、重症心身障害者、心の病を抱えた人たちなどなど)の希望に沿ったものと言えるのか、実際には医療従事者や政治によって医療による自死に誘導されているのではないか、と警告しています。
臓器移植が求める「死の前倒し」や、コロナ禍で露わになった医療崩壊におけるトリアージの問題、重い障害を持つ患者とその家族の問題など、一見安楽死とどう直接関係があるのか、と疑問に思えるような問題が、次々とつながってゆき、実は私たちは本当に「自分の死を死ぬ」権利を掴んでいるのだろうか? と問いかけられます。
医療や政治、マスコミの誘導で、私たちは無意識のうちに、高齢者や障害者など、「社会に役立たない者」は生きる意味がない、とか、QOLが著しく下がってしまえば生きる意味がない、といった観念を植えつけられつつあります。
そういった観念の延長線上に、たとえば相模原障害者殺傷事件を生み出すような思考が成り立ってしまうのでしょう。
「人生100年時代です」とか、「平均寿命より健康寿命が大事です」といった美しい言葉の裏には、認知症になったり、寝たきりになってしまったら生きている意味がありませんよというメッセージが言外に含まれてはいないでしょうか。
そのことと、「老人は切腹したらいい」というような有名人の発言がもてはやされる状況は、表裏一体のものではないか、と筆者は考えます。
そこには、「社会の役に立たない(何らかの利益を生み出さない)者はこの世から退場すべき」という価値観があるのです。
もっと言うと、そのような人間は、社会のコストを食うだけの「お荷物」的な存在として扱われているのです。そこにあるのは、健常者による、高齢者や障害者に対する強烈な差別意識です。
本書を読むうちに私たちは、安楽死という方法で、社会に有用でなくなった人間を個体として葬り、少なくともその臓器だけでも提供させて、社会のために役立てさせるという、徹底した功利主義が世界の医療を動かしている実態を知らされます。
そして、そのために、安楽死があたかも「自分の意志」であるかのように誘導されたり、偽装されたりする手口も明らかになります。
一体、これはナチスによる大量殺人とどう違うのかと、戦慄さえ覚えます。
著者はご自身が、重い障害を持つ子の親として生きてきた当事者であり、医療の世界でいかに障害者が差別され、虐待されているかを身にしみて体験してこられた方です。
また、患者を介護する家族が、ひょっとしたら介護される患者に手をかける可能性も否定しない。そういうことを勇気をもって告白される方です。
それだけに、安楽死を推進するこの世の底流にある、障害者とその家族に対する差別意識を、非常に敏感に見抜いておられます。
そして、例えば重症心身障害者の「自由意志」や「本人の希望」を勝手に作り出す、あるいは意識のない者としてみなす、すなわち人間ではなくなっているとみなすことの危険性についても警鐘を鳴らしています。
それでは、このような「すべり坂」または「崖」のように、どんどんと安楽死が乱用されてゆく世界の中で、何が希望となりうるのか。
それは、非常にシンプルだけど、難しい結論です。そして難しいけれども、シンプルな問いかけです。
それは痛み苦しむ人と共に生き、寄り添い、可能な限りその痛み苦しみを自分のこととして引き受けようとする思い、またその痛み苦しみを取り去るために、できる限りのことをしようとする強い意志が、周囲の人間にあるか、という問いかけです。
そして、直接に医療や介護を経験しない人にとっても、いつかはやってくる死について考えるときに、「安楽死」や「尊厳死」といった言葉を、もっと背景事情も見すえて、慎重に熟慮すべきではないかとも、本書は問いかけています。
私はキリスト者ですが、キリスト者として、この問題をどのように捉えるべきなのか考えてみました。
聖書に「人は神のかたちに造られた」という言葉があります。この言葉を、人間は理性を与えられた、と解釈していた人びとがかつていたように思います。神とは理性であり、神に似ているとは、理性があるということであると。
しかし、これは理性のない人間、つまり意識のない人間、認知症になった人間などを「人間らしくなくなった者」として排除する発想であることに、本書を読むと改めて気付かされます。
一方で聖書には、神が「わたしはある(いる)」という者だ、と名乗る場面があります。ただ存在している者だ、それが神だ、ということです。これと先ほどの「神に似た者」という言葉を並べて考えれば、「神に似ている」とは、すなわち「ただ存在している」ということ。ただ存在しているだけで、その人は神のように尊いのだ、という考えが導き出せないでしょうか。
だからどうするのか、どう考えて、どう判断するのか。それはわかりません。しかし、「安楽」死という美名のもとに、人の命が社会に有用かどうかで切り捨てられてゆく時代に、私たちが拠って立つべきなのは、人はそこに存在しているだけで尊いのだ、という理念ではないかと思えるのですが、いかがでしょうか。
この殺伐とした、ある意味で殺人的な方向に向かってゆく世の中で、著者が「愛と祈り」について触れていることには、読者として大きな救いと慰めを見出しました。
よろしければサポートをお願いいたします。
