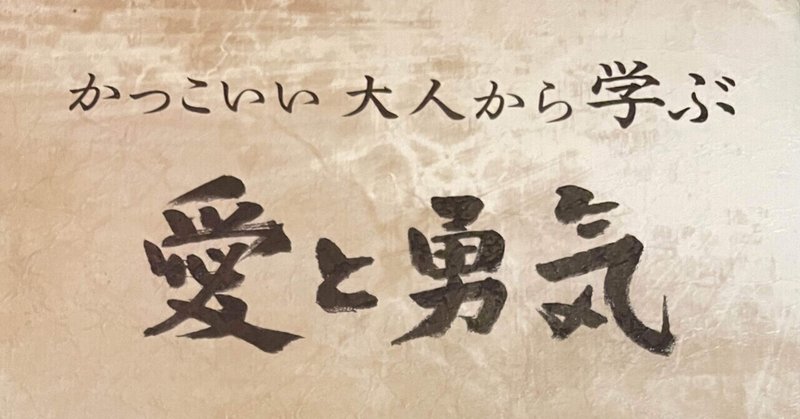
[人生のバイブル]かつて大阪堺の地で1代で納税額トップの会社を創業した方が書いた本をまとめてみました。(前半)
こんにちは。お久しぶりです。
今回、私のバイブルを紹介させていただきます。
この本は成功者の哲学が詰まっております。
誰が見てもかっこいい大人ってこうだな〜!
と思える人間像、心の在り方が書かれております。
迷った時はこの本を読んだら、
必ず正しい道へと導いてくれる気がいたします。
この本の著者は深江今朝夫と言いまして、
EH株式会社の創業者でございます。
20歳の頃、大阪堺の地で起業し、
関西でトップの納税額を収める人物にまで
上り詰めました。
現在は天国に行ってしまいましたが、
生き方がかっこよく、
様々な業界とコネクションがあり、誰もが尊敬し
並々ならぬ人であったことは話に聞きます。
「若いうちにたくさん汗をかきなさい。そう出なければ、歳をとった時、流さなかった汗が涙となって流すことになりますよ」
「苦労が辛いのではない、夢がないから辛いのだ」などの格言を多く残されておりますので、それを含めて今回は長々と紹介させていただきます。
もしかしたら、有料記事にするかもしれません。
では。
「かっこいい大人」とは、
人から尊敬されている人間です。
家族ならば子供から父親母親が尊敬されている、
会社では部下から尊敬されている先輩上司はかっこいい大人だと思います。
人として大切な考え方や精神が優れている人間だからこそ、多くの人から尊敬されています。
立場がそうさせているのではないと思います。
尊敬している人からは、叱られても聴く耳が持てると思います。
戦後70年以上が経ち、今日まで経済成長を迎えられているのは、日本人の誇れる精神でさまざまな出来事を乗り越えてきているからにほかなりません。
我々が持つべき責任は、
その日本人の誇れる精神を後世まで引き継ぎ、
これからも日本が経済的に豊かでいられるようにすることだと思います。
しかし、経済的に豊かになったはずのこの国で、不登校、いじめ、無差別犯罪、家庭内暴力など悲しい事件
が跡をたちません。
それは、戦前の「修身」の授業もなくなり
教育勅語の教えもなくなり、本当の意味での「かっこいい大人」が少なくなってしまっているのも大きな原因です。
我慢は良くない、自由で平等、個性が大切なのだから好きなことをなんでもやっていいという風潮や勘違いが普通にあるように思います。
大人になっていく段階で、子どもたちは大切なことを教えてもらう機会が少なくなっています。
大人になった時に、たとえ学校の成績が優秀だった人でも精神的に軟弱で、目標や夢を持てない人間になってしまっている人も少なくありません。
また、大きな意味での愛についても、恋愛の愛だけでなく家族を愛する心、仲間を愛する心が必要だと思っております。
人間教育「徳育」はどんな世界でも大事な基礎です。
「日本一お客様を大切にできる人・企業」になるためには、社員教育ではなく、徳育、人間教育によって人格を磨くことが大切だと痛感しております。
それは偉人や身近に尊敬できる先輩たちから、
かっこいい愛と勇気を学ぶことだと思います。
以下の要点をぜひメモにとって
生活に活かして頂けたらと思います。
①環境で人が育つ
人は環境で育ちます。
一流になりたければ、一流の環境に身を置くこと。
どなたに対しても、「明るく楽しく元気よく」
気持ちよく笑顔を添えて挨拶ができる環境で育てば、
自然と明るく楽しく元気な人間に育ちます。
先輩から後輩に挨拶をする。上司から部下に挨拶をする。このような挨拶が習慣になっていれば、
いつの間にか、挨拶が当たり前になるのです。
人が育つ環境をいかに築くかは、
先輩の言動にかかっています。
家庭でも食卓を囲んだ時、家族が感謝を言葉にしながら食事をしている環境なら、子供は「かっこいい大人」の列に並んでいると思います。
普段から愛のある言葉や感謝を言葉にしている家庭であれば子供から「お父さん、お母さん、ありがとう」といってもらえるでしょう。
このような環境で育った子供は、
大人になった時にも育ちの良さに好感度が高く、
人から可愛がって貰えると思います。
社会環境でも同じことが言えると思います。
若い人は会社の知名度や規模だけで育つのではなく自分を育てる環境に縁があったかどうかです。
仕事さえできれば全て良しというわけではなく、
人としてのバランスが大切です。社会で人間として成長できる環境に出会えれば理想的です。
人は出会いと環境で人生が大きく変わります
②偉人伝
自分が将来どんな大人になりたいのかを考えるならば、
歴史に名を残している偉人たちの人生をバイブルにすべきです。
過酷な運命にも負けず、人のために世のために努力した偉人。ありがたいことに、偉人たちは、考えたことや歩んだ道を格言や伝記に残してくださいました。
どんなふうにチャンスをつかんだのか。
どんな努力をして夢を叶えたのか。
どのように逆境を乗り越えたのか。
なぜかっこいい生涯だったのか。
経験を重ねて考え抜いた偉人たちの軌跡は、
人類の「財産」です。
③かっこいい大人
かっこいい大人とは、礼儀があり所作が美しく、清潔感があり、長幼の序を重んじ、家族を大切にし、それが実現できる経済力をもった大人でした。
そのような人達は皆、カッコよく、「謙虚」でした。
努力を惜しまず前向きに取り組む姿勢がかっこいい。
常識、礼儀、気遣い、愛情を持って、後輩に対して優しい先輩はかっこいい。誠意があって、忠誠の心を持ち、問題を冷静に対処する強い心がある人はかっこいい。
ぜひとも、かっこいい大人を目指して欲しいです。
④礼儀
礼儀は、相手を敬う心の表現です。
人間関係をスムーズにする大切なもの。古来人間が築いてきた知恵です。
礼儀をわきまえた人間として認めてもらえれば、
相手は安心してお付き合いしてくださるでしょうし、
心も開いてくれるでしょう。
最初からできてなくても社会に出てマナーの良い先輩に囲まれた環境ならば自然に身につきます。
マナーの悪いグループの中にいると、
マナーの悪いことがあまり気になりません。
マナーの悪い人は、相手を敬う謙虚さがないように見えるので、能力や心まで誤解されがちです。
節度がなく、だらしがないという印象を持たれるのでは
人生ではマイナスだと思います。
「正式な場面になったらちゃんとやる」と思っていても日頃からできていない人は急に自然体ではできません。
そして、礼儀は形だけでなく心が伴わないと慇懃無礼な品のないたてまえになってしまいます。
⑤家族
家族という環境は「絆」を育てる基本となります。
子供は生まれた時から無償の愛を経験し、成長するにつれて、様々な困難があると思います。それでも家族の土台に愛があれば一緒に乗り越えることができるかもしれません。
あなたが生まれた時、あなたは泣いていて
周りの人達は笑っていたでしょう。
だからあなたが死ぬ時は、あなたが笑っていて
周りの人達は泣いている
そんな人生を送りましょう。
⑥教養
「教養がある人」とは、
単に知識がある人ではないそうです。
辞書には「人間性と知性を磨き高めた人」とあります。
博識で芸術や歴史に造詣が深くとも、それが人格に結びついていなければ教養とは言わないのです。
アメリカの大学ではまず4年間、教養についての教育を受け、卒業後に専門の勉強をするそうです。
それを日本では、リベラルアーツと呼ばれております。
教養を身につけるということは、思いやりの心を養うということです。
古典を紐解くことも歴史に学ぶことも茶の湯に触れることも、文化を知ることは、人の心を培うためなのです。
視野が広くなることで「思いやりの心」が行動として
発揮できるようになります。
かつてかっこいいと思った教養ある大人たちは、あらゆる物事に広い心をもって対処されておりました。
色々な知識があるので問題の解決に際して心に余裕があるのです。
寛大な心は、人々を受け入れる器の大きさにも匹敵します。自分の人生を豊かな人間関係で充実させるためには教養が必要です。
知識は手段だと思います。知識は道具です。
プライドの高い人間には、教養がつきにくいです。
謙虚さが、自分自身をより豊かにします。
世界に通じる知識や教養が、
現代の私たちに問われていると思います。
⑦責任を持てる人
アメリカインディアンの子育ては、大人の真似をさせることから始めたそうです。学校に行かなくてもしつけをされなくても、周囲にいる大人たちの行動を真似するだけで、一人前の責任ある大人になれるというものです。
一方、大人は子供に真似される存在として、
考え方や行動に大きな責任があります。
そのため、インディアン社会には
「責任感がある強い人こそ本物の力ある人物」
という教えが根付いているようです。
彼らにとって立派な人物とは、権力ではなく、
責任をもてる人ということです。
学歴、容姿、若さは時折、もてはやされますが
そんな価値観の先に本当に立派な人物像はあるのでしょうか?
東大出身でも、嫌なことから逃げ出し、
約束を守らない人はどうでしょう?
尊敬されるべきは責任をもてる人だと思います。
責任を負える人間は強い心を持っています。
例えば、自分がまだまだ業務になれないときに、
こんな先輩がいたらどうでしょう?
君ができなくても、全部俺のせいだから。
俺がなんとかしてあげるから、困ったことや分からないことがあったら、なんでも言ってね。
ここは、こうしてこうするんだよ?わかる??
部下が別の人に怒られていたとしても、
「すみません。自分が教育してないのが悪いです。
こいつは悪くありません。次から必ず繰り返さないように私がこいつの面倒みますから。こいつはやってくれますよ」
こんな先輩であれば、この先輩のためなら
何でもしたい!困った時にこの先輩のために
力になりたいと思えると思います。
逆に、なんでこんなこともできないの?
出来て当たり前のことじゃない?
もう君には頼まないわ、君を信じた俺が馬鹿だった。
何もしなくていいから、報告だけちょうだいね。
部下ができないのは、全部部下のせい。
できない部下をどうやったら、できるように育てられるか?教育の責任を放棄しているように思えます。
こんな責任感のない先輩はどうでしょうか??
物事の全ては自分次第だと本心から思えるかです。
生い立ちや時代や運のせいにしない。
どんな状況であれ、
自分の信念を貫き、信じ、力を尽くし約束を守り、
最後までやり遂げます。
途中で投げ出すことは、責任ある人の行動ではなく
かっこ悪い人のすることです。
責任ある人は皆から信頼されます。
本物の大人になりましょう。
⑧先知後行
知っているとやっているは大きく違います。
この大切な教えが先知後行です。
「知識を習得したら、その後、実行せよ」という朱子学の教えで、儒教の経書「大学」に書かれています。
『大学』は社会のリーダーとなる優れた人物を育てるために書かれた実学書です。
学校の試験は「知っている」「覚えている」ことで採点されました。
日本の教育では、知っている、覚えることが得意な人が成績を残せます。
ですが、社会では「知っている」ことを源に、
考える力、想像力を行動に移す「実行力」が
もっと大切です。
結果が全てだとよく言われると思います。
⑨徳と得
大阪府堺市には、仁徳天皇陵があります。
仁徳というお名前には、「他を慈しみ愛する徳」という意味があるそうです。
仁徳天皇は、皇居から街並みをご覧になると、
当時、生活が苦しくて炊くものがないのではないか
ということに気づき、3年間にわたって免税したそうです。
そして、それだけでなく、天皇ご自身も倹約されて衣も新調されず、宮殿の屋根が破れても替えず部屋の中から星が見えたと言われております。
経済がよくなった6年後に、民は慈悲深い天皇を聖帝と崇め、皆で宮殿の修理をし感謝をしたと言います。
「徳」が大切です。徳を積む、徳がある、徳が高い
昔の日本では、誰もが徳を大切にしてきました。
徳よりも得を優先する人が増えれば、世の中は殺伐としてしまうでしょう。
※この本の著者深江今朝夫は、
20歳の頃に大阪堺の地でeh株式会社を創業しました。そして、会社が大成功して、
年商500億円超の企業にまでなりました。
ですが、御歳65歳を迎えるまで
ご自身は、
三国ヶ丘にある6畳間の激狭アパートに住み、
社長業を営んでおられました。
社員とその社員の家族が豊かになれるように
社員の人生がよりよくすることが社長である自分の責務と常に仰っていたようです。
⑩感性を磨く
坂本龍馬は、西郷隆盛に会った印象をきかれて
「鐘」にたとえたそうです。
「小さく突けば小さく鳴り、大きく突けば、
大きく鳴るような男だ」と。
感性の表現は品格となって現れると思います。
龍馬の比喩は、多く人物に会ってきた経験から培った豊かな教養が感じられます。
感性の9割は知識や体験の蓄積だと言われております。
教養によって感性は磨かれます。しかし、知識だけの教養があっても感じることが習慣になっていなければ、
頭でっかちの人で終わってしまうと思います。
感性は、日々の暮らしの中で養うものです。
些細なことでも関心のあるものを見つけたならば、
深く考え、深く聴き、深く読む。人の心も想像力を使いながら理屈だけでなく心で聴くようにする。
これを習慣にして、いかに多くの経験、
行動をし自分のものにするのかが大切です。
人間は一生のうちに全て経験することは難しいです。
しかし、人から学んだり書物から勉強し、まるで経験をしたかのような感性を身につけることができます。
人は経験と知識。違う物差しでは理解できない(浄土宗)
⑪武士のこころ
日本の資本主義の父とも言われている渋沢栄一は、
論語と算盤の著者としても有名です。
その中で士魂商才が大切なんだと書かれております。
昔、菅原道真は和魂漢才の重要性について説いていました。和魂漢才とは、日本人の精神をもって、中国伝来の学問を理解し、自分のものにすることです。
渋沢栄一は、それも大事だけれども、
武士のこころをもって、お金儲けをできるようになることが1番なんだということを説いております。
昔、儒教の影響でお金儲けは
悪という考えがありました。
論語とは、お金儲けにおいては、
役に立たないけれども人として大切なこと。
算盤は、役に立つが、世間的には嫌われているもの。
資本主義社会においては、この一見相反するものを、
合一し、身につけることが大切なんだということだそうです。
15代将軍徳川慶喜の時代、
武士は特権階級の最上位の集団で、戦う集団でもありました。卑怯なことを嫌い、臆病者は武士として非常に恥ずかしいことだと武士は皆肝に銘じておりました。
恥知らずという言葉がありますが、
これを破廉恥というそうです。
恥を恥と思わないで不明不徳の行いをすることは
破廉恥なことです。
しかし、元々は廉恥という言葉の方がよく使われていたそうです。
廉恥とは、心が清らかで恥を知る心
と広辞苑にございます。
廉恥が破れるから破廉恥なのだそうです。
忠誠、忠義、廉恥が武士の魂であり、勇気のないことは
武士の恥でした。
義を見てせざるは勇無きなり(論語)
人の上に立つ人間が実践すべき言動だと思います。
⑫忠義
忠義とは主君に真心を尽くすことだそうです。
漢字の意味で言うと、忠は真心、義は正しい道。
誤解されがちですが、主君に絶対服従で仕えるという意味ではございません。事と次第によっては忠義があるからこそ主君に諌言することができたのです。
中国の春秋時代、孔子は血の繋がりのある一族を大事にするように説きました。ですが、戦国時代になり、国が大きくなると、肉親だけを大事にするのでは社会が成立しなくなったそうです。
そこで弟子の孟子は、主君を父と思い、主君の妻を母と思い、主君の同僚を叔父と思い、先輩を兄と思い、後輩を弟と思うことで、血の繋がりがなくても、本当の家族のように思いやりを持って接するように伝えてきました。
血脈がなくても、
親兄弟のように尽くす真心が忠義です。
現代においても家族組織、
会社組織に必要な考え方や心構えが
忠義の心だと思います。
⑬愛嬌
「女は愛嬌、男は度胸」と言いますが、性別によらず
愛嬌のある人は誰からも好感度が高いです。
愛嬌がある人は、
周囲を幸せな気持ちにする人だと思います。
明るいところに人は集まり、楽しそうなら好奇心が湧きます。そして元気は人から人へと伝わります。
お客様を大切にできる人間または組織として当然の資質だと思います。明るく楽しくありたいと思うならば、女性も男性も愛嬌からスタートすると良いと思います。
経営の神様と言われた松下幸之助さんは、
「人の上に立つ人間には愛嬌がなくてはならない。人が近づきやすい表情でなければ、知恵も集まってこない」
とおっしゃっていたそうです。
愛嬌は人間的魅力のひとつです。
慕われるリーダーにこそ不可欠なものです。
愛嬌のある人には、人が集まり、人が集まるところには知恵が集まる。政治家でも愛嬌が大切だと、松下政経塾の創設時にも力説されたと伝えられております。
⑭リーダーは上機嫌で
フランスの哲学者アランは、
上機嫌こそ他人への最大の贈り物だと言っております。
周囲を明るく幸せにしたかったら、まず自分が上機嫌でいることが大切だということです。
会社でもそうだと思います。
不機嫌な上司がいたら誰も楽しく働けませんし、
相談もしにくく、プロジェクトは上手く行きにくいと思います。
そのようなリーダーの元には、真実の情報は集まらず、職場が暗くなり、上手くいく仕事さえもうまくいかなくなります。しかもご機嫌取りの部下たちを育ててしまうことになります。
幸福だから笑うのではない、むしろ笑うから幸福なのだ(アラン)
上機嫌を繰り返しているうちに、困ったことが起きても乗り越える気力が自然と湧いてきます。
上機嫌が癖になって自分が強くなっていくのです。
上機嫌な人の周りに人は集まります。
これはリーダーにとって最高の資質だと思います。
皆、明るくたくましい上機嫌なリーダーを
求めています。
⑮自分との約束
世界でもっとも成功を収めたと言われる民族は
ユダヤ人だと言われております。
世界の名だたる企業の多くがユダヤ人が創業していたりします。
そんなユダヤ人には、神との約束があるそうです。
たとえば、生活習慣の根底に「十戒」があり、
6日働いたら一日は祈りのために休むとか、父母や祖先を敬いなさい、嘘の証言をしてはならないなどがあります。
神との約束ですから必ず守らなければなりません。
人が見ているとか見ていないとかは問題ではなく、
これを守っているために彼らの信条は揺るがず、約束を守るつよい精神力が養われているのだと思います。
だからこそ成功者が多いのではないでしょうか。
私達も約束をすることがあります。
まずは人との約束を誠実に守ります。
誠実な人は真心で相手のことを考えるので約束を果たします。
しかし、相手をいい加減に考えている人は
約束を破ります。
こういう人とは信頼関係を結ぶことが
難しいと思います。
約束のもうひとつとは、自分との約束です。
自信とは、自分との約束を果たせた時に
身につくものです。
小さくてもいいので、自分の約束を果たせば果たすほど
どんどん自信がついてきます。
そして、いつの日か大きいことや難しい約束もできるようになるのです。
一旦ここで区切ります。
続きは後半で綴ります!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
