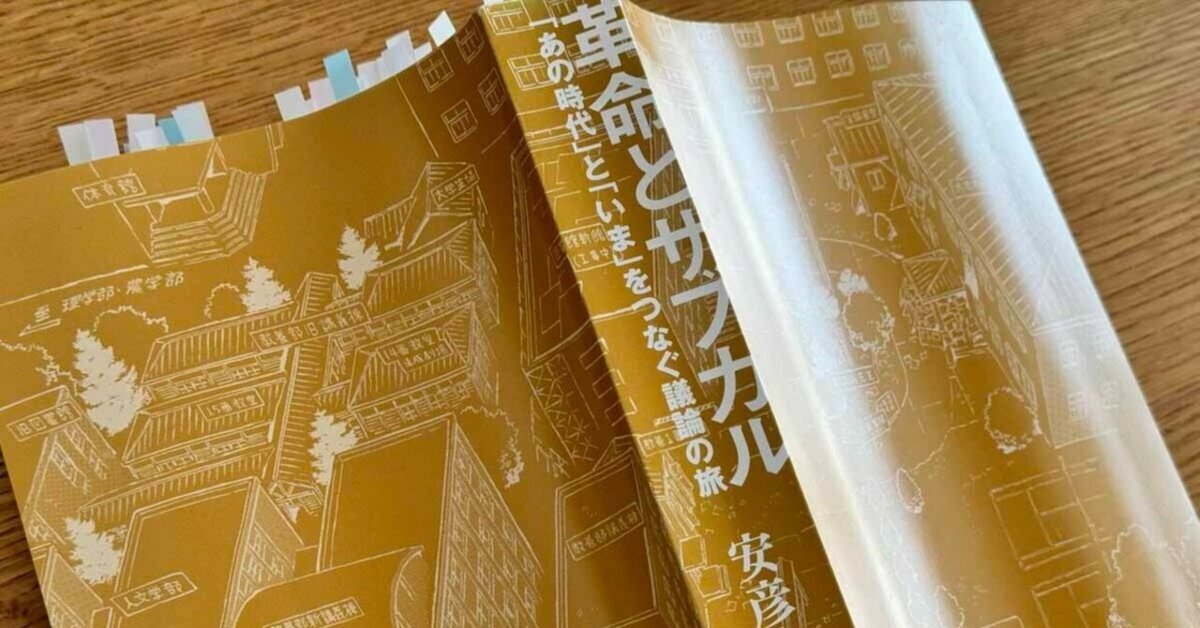
『革命とサブカル』安彦良和、言視社
ぼくはあまりアニメやマンガには詳しくはないのですが、さすがに安彦さんの名前ぐらいは分かっていて、『虹色のトロツキー』などの題名を聞けば、世代的にも「昔は全共闘でやっていたんだろうな」ぐらいの推測はつきましたが、あまり知らない弘前大学ということもあり、どのぐらいやっていたのか見当はつきませんでした。しかし、本書を紹介をたまたま読んだら仲間に赤軍派から連赤に行って逮捕された植垣康博さん、青砥幹夫さんもいたというのには驚きました。田中清玄も弘前大(旧制弘前高校)出身だったということを知り、本州最北の国立大学には、そうした伝統みたいなものもあるのかな、と。
70年代の政治闘争に集まった若者は潮を引くように消え、向かった先はサブカルだった、というのは、余りサブカルに浸ってこなかったぼくには新鮮でした。なんだ、そんな当たり前のことと思われる方も多いでしょうが、安彦さん自身《しつけの厳しい親に対してわざと悪ぶって見せていたような当時の新左翼のお行儀の悪さが、後に隆盛をみせるサブカルチャーの直接的な源ではないかと思うようになったのは、じつは比較的最近のことだ》(p.367)としています。全共闘運動末期とオタクたちは《コミュニケーション力が失われ、あるいは自らそれを放棄し、特有な言語と興味、関心のタコツボの中に各々が入り込みいたずらにイラだって他者に攻撃的になるような行き止まり感》(p.369)も似ている、と。
というより、いまからみれば《覆面で顔を隠すという匿名性、大衆団交に見るコミュニケーションの断念。パフォーマンス化した演説。冗談や偽悪的ポーズもとり入れた劇場型の派手な行動。現実から非現実へと、軽々は飛翔してゆく空論と大言壮語》といった全共闘運動のモチーフはサブカルとして顕れたんだ、と。
しかし、そうした考察もさることながら、弘前大学の学友だった連合赤軍事件の当事者二人だけでなく、他の新左翼セクトに行った友人たち、演劇などに流れた人たちなどの、なんと正直な人生が語られていることか…と感心します。
あと、面白かったのはジブリに対する評価。キネ旬の高畑さん追悼号で確か安彦さんは、良かったのはTVシリーズの時期だけで、その後のジブリ映画はあまり感心しないみたいな追悼文を載せていたと思うのですが、その背景は民青臭さが嫌いだったんだな、と。《「良いものは良い!」と公認された宮崎アニメが、彼の出自である日共的臭みをその豊かな才能で上手に包みかくして、圧倒的な国民映画としての不動の位置を確立したりもしていた》と評価していたのには驚きました。
同じように臭みを消して山田洋次が国民映画を作ったように、日共的なエセ良心に対する日本人の人気は根強いのかな、とも思いました。《吉野源三郎さんがいけないというのでは なくて、時代がそうだったわけです。良識的、良心的であることが、基本的に左翼的であったわけ ですよ。そう考えるしかなかった時代のものだけど、それがいまリバイバルで売れるということが、 ちょっとまずい》というのが、全共闘的サブカルチャーからみたジブリ的世界なのかも。
面白かったので、その前の自伝『原点』も購入しました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
