
【人間はどのように家畜になったのか】自己家畜化
こんにちは。いつもお越しくださる方も、初めての方もご訪問ありがとうございます。
今回はwikipedia英語版「自己家畜化」の記事を翻訳をします。
翻訳は主にChatGPT、補完的にDeepLやGoogle翻訳などを活用しています。翻訳のプロではありませんので、誤訳などを上手く訂正できていないと思います。
英語をはじめとする外国語には一般の日本人が全く知らない情報が数多くあります。「海外の常識を日本人の常識に」を使命に、特に歴史的流れを掴めるようにすることを第一優先課題としています。
また、当サイトで掲載されている翻訳記事は、私自身の見解や意見を代表するものではありません。
自己家畜化
自己家畜化という科学的仮説は、家畜化された動物と同様に、人類の間で人為的選択の過程があったことを示唆しています。この仮説によれば、ホミニゼーション(※人類の進化、「ヒト化」「人類化」とも)の過程で、協力的で社会的な行動を示す個体が好まれ、それによって集団全体の利益を最適化するために人類自身によって行われた選択があったとされています。この過程で、従順さ、言語能力、感情の知能が強化されたとされています。この仮説は、これがホモ・サピエンスをネアンデルタール人やホモ・エレクトスから区別する要因であると提唱しています。

仮説の起源と現状
一般的に、家畜化された動物は非家畜化されたものと比較して(例えば、カニス・ファミリアリス[いわゆるイヌ]とその親戚であるカニス・ルプス[いわゆるオオカミ]の場合などのように)共通する特性を持っています。これらの特性には、従順で遊び好きであり、攻撃的な行動が少なく、顕著な幼形成熟が見られることが含まれます。これにより、体が小さく、わずかに小さな脳と頭蓋骨、短い歯と鼻を持つことがよくあります。
これらの類似点を最初に科学的に観察したのは、自然学者、人類学者、医師のヨハン・フリードリッヒ・ブルーメンバッハであり、1800年頃でした。『人類の自然変異に関して』(De generis humani varietate nativa)という論文の著者であり、彼は人間も家畜化された可能性があるという仮説を提唱しました。

数年後、チャールズ・ダーウィンは進化論を用いてこのトピックに取り組み、動物における人為選択の過程を考慮していました。しかし、人間の家畜化の概念を純粋に科学的な観点から説明することができなかったため(誰が人間を家畜化したのかという問題は宗教的または神学的な観点からしか答えられなかった)、結局その仮説を退けました。

20世紀にドミトリ・ベリャーエフの研究は、家畜化の過程で動物の行動(アドレナリンの低レベルの観察)と毛色(色素の変化)の両方に同時に変化が起こることを示す重要な提案となりました。ギンギツネの研究を通じて、アドレナリンとメラニンという生化学的な経路が共有され、この経路が人為選択の過程で変化することが示されました。


2014年、ベルリンのフンボルト大学のアダム・ウィルキンス、マサチューセッツ州ハーバード大学のリチャード・ランガム、ウィーン大学のテクムセフ・フィッチら科学者たちは、これらの変化の共通起源が脊椎動物の独特の幹細胞である神経堤細胞にあると提案しました。これらの細胞は胚期に異なる部位に移動し、副腎皮質(アドレナリンの産生を通じて恐怖とストレス反応を管理する)、メラノサイト(皮膚や毛色のメラニンの生成を担当する)および顎を同時に形成します。これらの細胞の欠如が、すべての家畜化された動物の共通特性(従順さ、頭蓋および顎の縮小、色素の変化)を説明することができます。

リサーチチームの3人のメンバーのうち、霊長類学者のリチャード・ランガムがこれらの研究結果を人類に適用し、「人類は自己選択の過程を通じて自らを『家畜化』した」と主張しました(この提案は彼が『善性のパラドクス:人類進化における美徳と暴力の奇妙な関係』で詳述しています)。

2019年7月、バルセロナの海洋科学研究所のチームは、DNAの特定の遺伝子のメチル化を通じて、神経堤細胞の減少を引き起こす後成学的および遺伝的変化を記述しました。その後、バルセロナ大学の別の研究チームが、BAZ1B遺伝子が神経堤細胞の挙動を制御することを発見しました。ネアンデルタール人のゲノムと比較して、BAZ1Bは過去のヒト族には見られない多数の突然変異を持つ遺伝子と関連しています。この研究に関与した研究者の一人、セドリック・ボックスは次のように述べています。

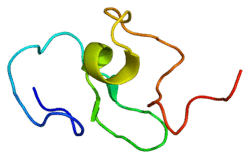
「これにより、BAZ1B遺伝子の遺伝子ネットワークが、私たちの顔がネアンデルタール人などの既に絶滅した他の祖先と異なる理由の重要な要因であると考えています。大まかに言えば、神経堤細胞に基づく自己家畜化の仮説が初めて実験的に裏付けられました。」
ヒト科
クラークとヘンネバーグは、人類の進化初期において、自己家畜化を通じてより幼形成熟の頭蓋が生じたと主張しています。この主張は、アルディピテクスとさまざまな年齢のチンパンジーの頭蓋を比較することに基づいています。その結果、アルディピテクスは幼年および若年の個体群とクラスター化されました。この種の雄における思春期の成長スパートの欠如とそれに伴う攻撃的な犬歯の装甲の成長は、アルディピテクスが自己家畜化を通じて幼形成熟の頭蓋を進化させた証拠とされました。著者たちは、ボノボとの比較を通じて次のように述べています。

「もちろん、アルディピテクス・ラミドゥスはボノボとは大きく異なり、ボノボは機能的な犬歯研磨複合体を保持しています。しかしながら、アルディピテクス・ラミドゥスがチンパンジーに比べて性的二形性が低く、幼形成熟の形態を共有していることは、ボノボに見られる発達と社会的適応が初期人類の社会および性的心理学の将来の再構築に役立つ可能性があることを示唆しています。実際、母性ケアの増加、雌の配偶者選択、および自己家畜化への傾向は、ボノボよりもアルディピテクス・ラミドゥスでより強く、洗練されていたかもしれません。」
さらなる研究により、アルディピテクスが幼形成熟の頭蓋基底の角度、大孔位置、および音声管の寸法を持っていたことが確認されました。これは社会行動の変化の証拠だけでなく、初期のヒト科の音声能力の可能性の早期の出現と解釈されました。もしこの論文が正しいとすれば、人間の社会行動だけでなく、言語能力もまた、自己家畜化の過程を通じて幼形成熟の頭蓋形態形成を経て進化したことになります。
人類の自己家畜化の最も包括的な事例は、後になってネアンデルタール人やデニソワ人といった頑丈な人類から解剖学的に現代的な人類への移行を説明するものです。これは約4万年から2万5000年前に起こり、この急速な幼形成熟は、進化的利益を持たない変数に基づく交配相手の文化的選択の結果として説明されています。その変数には、知覚された魅力、顔の対称性、若さ、特定の体の比率、肌の色調、髪の毛が含まれており、どれも他の動物種には役割を果たしません。これは意図せぬ自己家畜化であり、女性の性的なイメージが導入された同じタイミングで、当時人類が占めていた4つの大陸で同時に発生しました。これは、頭蓋形態学、骨格構造の変化、脳容量の減少、遊び心豊かで探索的な行動の確立、および数千の有害な状態、症候群、障害、疾患の発生をもたらしましたが、当時の頑丈な人類には存在しないとされています。
もちろん、これらの特定の見解は、各世界地域に存在する適応した骨格化石から示される、現代の人類集団がそれぞれの地域における適応した旧人類から進化したとする多地域進化論の観点に基づいています。しかし、これらの見解は、遺伝的証拠が支持するアフリカ単一起源説を裏付け、わずかな交配や遺伝子の導入を示すことで大部分が反証されています。しかしながら、アフリカ内でのみ、例えば、初期の人類(特にホモ・ハイデルベルゲンシスからホモ・サピエンスへの移行中)における完全な自己家畜化が開かれた可能性です。これは、各地域の旧人類(例えばネアンデルタール人、デニソワ人)が、世界中に広がるにつれて自己家畜化されたホモ・サピエンスによって主に置き換えられたことを意味します。この可能性は、自己家畜化が現代人類の成功と他の系統の絶滅に寄与したという考えを示唆しています。

自己家畜化の概念は、初期の社会ダーウィニズムでも使用されました。精神医学者マーティン・ブリューネの記事「人類の自己家畜化について」によれば、これは人間が生物学的に「完璧」になることができるという考えから発展しています。自己家畜化のアイデアはまた、社会正義の概念と関連しています。
現代人
身体的解剖学
化石記録の年代付けに基づき、考古学者たちは自己家畜化がおそらく30万年以上前の更新世に起こったと結論付けています。化石記録を使用して、ホモ・サピエンスを前サピエンスの祖先と比較した考古学者たちは、動物での自己家畜化の結果として現れる多くの特徴的な表現型特性を観察しました。これには、性的二形性の減少、歯のサイズの小ささ、頭蓋の縮小、体サイズの小ささが含まれます。ホモ・サピエンスの化石はまた、眉突起の平坦化と顔の短縮も示しています。
リチャード・ランガムはこの研究をさらに発展させ、ボノボとチンパンジーが人間の攻撃性の発達を明らかにする方法について取り上げました。学界では、自己家畜化の仮説についての矛盾について懸念を示しており、人間が責任を持って行っている暴力的な行為の深さを考えると、人間が潜在的に家畜化される可能性は論理的ではないと指摘しています。このパラドックスを調和させるため、ランガムは自己家畜化が二種類の異なる攻撃性、つまり積極的攻撃性と反応的攻撃性の結果であると仮定しました。
積極的攻撃性はチンパンジーでよく見られるもので、目標を達成するために計画された攻撃と定義されます。一般に、人間はグループ内での攻撃性が低い傾向があります。反応的攻撃性は、怒りとより密接に関連しており、脅威に対する即座の反応として特徴付けられます。これは人間における「バーでの喧嘩」に相当します。自己家畜化されたボノボの行動と一致して、人間は反応性攻撃性の傾向が高くありません。これは自己家畜化の仮説を支持するさらなる証拠となり、その中心的な特徴は反応的攻撃性の減少です。
人口密度仮説
人口密度仮説は、現代人類に観察される反応的攻撃性の低下を説明しようとします。高い人口密度の期間中、社会的ネットワークを通じて限られた資源(食料など)への信頼性のあるアクセスが増えるため、仲間に対するより高い寛容さが促進される可能性があります。ホモ・サピエンスは約30万年前にこのような高い社会的寛容度を示し始め、もしこの仮説が成り立つならば、これはより大きな人口サイズと関連付けられるでしょう。しかしながら、最近の遺伝学的データはこの仮説を否定しています。実際、ホモ・サピエンスは約20万年前に人口が減少したことが分かっています。
言語に基づく陰謀
言語に基づく陰謀は、反応的攻撃性が現代人類で選択的に進化した理由を説明し、それが自己家畜化につながったとされている、最も説得力のある理論です。ホモ・サピエンスは、ネアンデルタール人を含む先行種よりも優れた言語の能力を発展させたと推測されています。高度な言語能力は、初期の狩猟採集社会の中で権力欲の強い個人を制御し抑制するための手段となりました。他者との共有した意図を言語を通じて簡単に伝えることで、支配を試みる者は死刑の対象とされました。言語によって、部下たちは協力し、支配者の支配の試みを阻む計画を立てることができました。時間と共に、これが反応的攻撃性に対する選択圧となりました。
批判
人類に適用されるこの理論への批判は、我々と他の大型類との間の多くの違いが、脳の発達が停止し、幼少期の特徴が成人期に保存された結果ではなく、逆に脳の発達が加速し、延長された結果であるとする点です。これは、人類の進化における重要な変化を説明するために他のプロセスが必要であることを示唆しています。ランガムは、人間の自己家畜化が最近の200万年間にわたる原始人類から現代人類への進化の文脈で適用可能であり、したがって人間と他の現存する類人猿種との違いが人間の自己家畜化を否定するものではないと主張しています。
コメント
リチャード・ランガムには『悪魔のようなオスたち:類人猿と人間の暴力の起源』という著作があります。ゴリラ、チンパンジー、ボノボにおけるオスの暴力の意味を論じたもののようです。ランガムはオスの暴力は進化論的に望ましくないとし、道徳的に非難されるべきものと論じています。
共通するテーマを扱っているスティーヴン・ピンカーの『人間の本性のよりよい天使たち:なぜ暴力は衰退したのか』なども興味深いですね。

関連記事
最後に
最後までお付き合いいただきありがとうございました。もし記事を読んで面白かったなと思った方はスキをクリックしていただけますと励みになります。
今度も引き続き読んでみたいなと感じましたらフォローも是非お願いします。何かご感想・ご要望などありましたら気軽にコメントお願いいたします。
Twitterの方も興味がありましたら覗いてみてください。https://twitter.com/Fant_Mch
今回はここまでになります。またのご訪問をお待ちしております。
それでは良い一日をお過ごしください。
今後の活動のためにご支援いただけますと助かります。 もし一連の活動にご関心がありましたらサポートのご協力お願いします。
